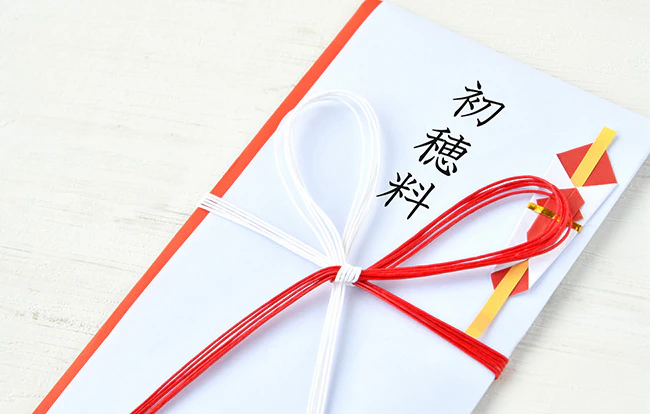一周忌法要とは、故人が亡くなってから満1年目の命日に行われる法要です。年忌法要のなかで最も重要とされています。この記事では、一周忌の意味と流れ、一周忌法要の際に遺族が準備すべきもの、および出席者のマナーについて解説します。
<この記事の要点>
・一周忌法要とは、亡くなってから1年目の命日に行われる重要な法要
・準備には会場や僧侶の手配、出席者への案内・お布施やお供えの用意が含まれる
・一般的に施主および親族は喪服、参列者は喪服または略式喪服を着用する
こんな人におすすめ
一周忌法要とは何か知りたい方
一周忌法要の流れを知りたい方
一周忌法要以降の法要の種類を知りたい方
一周忌とは
一周忌法要とは、亡くなってから1年目の命日に行われる法要です。年忌法要のなかで最も重要とされています。
一周忌法要には、遺族や親族、友人、知人など故人と親しかった人が参列します。僧侶の読経の後、焼香・食事(お斎:おとき)をするのが一般的です。
命日が平日に当たっていて仕事や学校で都合が悪い場合には、日にちをずらすこともできます。ただし、その際は、命日の後ではなく前倒しをするのがならわしです。
一周忌などの年忌法要について
一周忌などの年忌法要には次のようなものがあります。
| 法要の名称 | 行う時期 | 法要の一般的な内容 |
| 一周忌 | 満1年 | 遺族・親族と友人・知人が参列し、僧侶による読経の後焼香・食事をする |
| 三回忌 | 満2年 | 遺族・親族と友人・知人が参列し、僧侶による読経の後焼香・食事をする |
| 七回忌 | 満6年 | 遺族・親族で供養する |
| 十三回忌 | 満12年 | 遺族だけで供養する |
| 三十三回忌 | 満32年 | 遺族だけで供養する |
一周忌法要の流れ
一周忌法要の流れは、次のようになるのが一般的です。
| 1. 僧侶の入場 | 僧侶は祭壇の前に座ります。祭壇を中心とし、右側が施主・遺族および親族の席、左側が近親者・友人および知人の席です。祭壇に近い上座には、故人と縁が深かった人が座ります。 |
| 2. 施主による挨拶 | 開始の挨拶を簡潔に行います。 |
| 3. 僧侶の読経 | |
| 4.焼香 | 最初は施主、その後は上座に座っている人から焼香します。 |
| 5. 僧侶の法話 | |
| 6. 墓参り | 墓地が近い場合のみ行われる。 |
| 7. 施主の挨拶 | 箸木(はしのき)終了の挨拶を簡潔に行います。 |
| 8. 食事(お斎) |
一周忌を行う際に遺族が準備すること
法要を行うには、会場やお坊さんの手配、出席者への案内など、1カ月程度の準備期間が必要です。下記の8つの手順に沿って事前に決めておきましょう。
1. 日程を決める
一周忌法要を行う際には、最初に日程を決めます。一周忌は満1年目の命日ですが、平日に当たる場合は前倒しをして土日祝日に行います。日程は、出席する親族などにも確認のうえ決めましょう。
2. 会場を決める
一周忌法要の会場を、自宅にするのか、それともお寺やホテルなどの場所を借りて行うのかを決めます。
3. お寺へ連絡する
お寺とお付き合いのある方
菩提寺(ぼだいじ)とは、先祖代々のお墓のあるお寺のことです。菩提寺がある場合には、菩提寺に連絡をして、読経の依頼を行いましょう。
お寺とお付き合いが無い方
菩提寺が無い場合には、知人縁故からお寺を紹介してもらう方法や、葬儀の際にお世話になったお寺に相談する方法があります。
その他最近では、インターネット上でお坊さん手配サービスを利用される方も増えています。
自宅はもちろん、手配したお坊さんのお寺での法要も行えるので、菩提寺がない方には便利です。
お寺の都合によっては希望日に添えない場合もあるため、1ヵ月~2週間前を目安に寺院手配の予約をすることをお勧めします。 
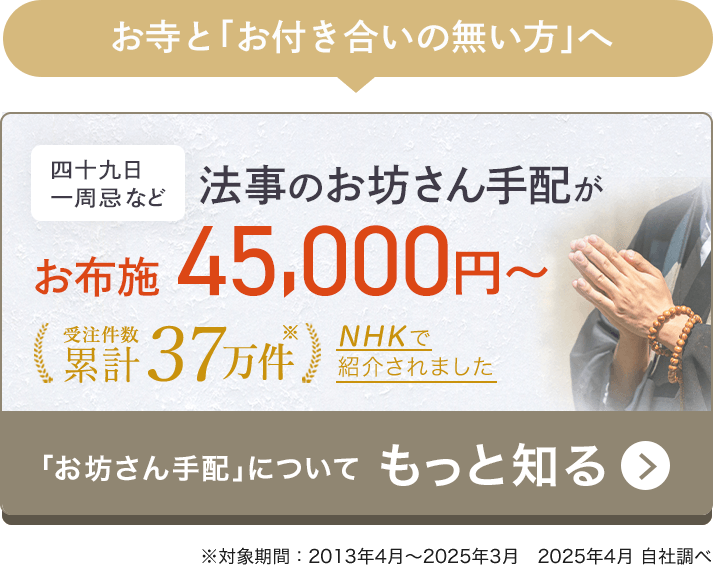
4. 食事の手配
必要に応じて仕出し料理や料理店などを予約します。予約の際は、法事で利用することを伝え、伊勢海老や鯛などのおめでたい献立にならないように注意しましょう。
5. 出席者へ案内をする
出席者への案内は、遺族・親族だけなど小規模で行う場合は電話で連絡すればよいでしょう。会社関係で執り行うなど規模が大きい場合には、案内状を作成して送ります。
6. 引出物を手配する
一周忌法要の引出物は、出席者が持参する香典へのお返しの意味もあります。金額の相場は2,000円~1万円が一般的です。品物は、石鹸や洗剤、タオル、食品などの日用品のほか、カタログギフトを用いるのもいいでしょう。
のしの表書きは「粗供養」「志」などとし、水引は黒白か銀の結び切りを用います。法要の後に食事の席を設けない場合には、折り詰めの料理と酒の小瓶を用意し、引出物といっしょに出席者にお渡しします。
7. お布施を用意する
僧侶にお渡しするお礼は、お布施(お経料)、お車代のほか、僧侶がお斎を辞退した場合には御膳料を用意します。それぞれの金額の目安は次の通りです。
お布施:3万円程度
お車代:5,000円~1万円
御膳料:5,000円~2万円
お金を入れる袋は、半紙の中包みに入れたうえで、奉書紙で慶事の上包みの折り方をするのが最もていねいな形ですが、市販の白封筒でもかまいません。ただし、郵便番号欄のない無地のものを選びましょう。表書きは、薄墨ではなく普通の黒の墨で書きます。直接手渡しするのではなく、小さなお盆などに載せてお渡しするとていねいです。
法事・法要のお布施について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
8. 供花・お供えを手配する
供花やお供えは、遺族や親族・参列者が前日までに手配します。お供えは、お線香のほかに、出席者が分けられるものを選ぶことも一般的になっています。果物やお花のほか、故人が好きだった場合にはお酒やビールなどでもいいでしょう。
一周忌に出席する場合のマナー
一周忌法要に出席する場合のマナーについて見ていきましょう。
出欠の連絡
法要の連絡が電話できた場合には、その場で返答するか、検討のうえ改めて電話して返答しましょう。案内状を受け取った場合には、返信はがきや往復はがきの返信部分を指定の期日までに送ります。
服装
一周忌法要の服装は、施主および親族は喪服を着用するのが一般的です。参列者として招かれた場合には、喪服または略式喪服を着用し、ネクタイは黒を選びましょう。
学生は制服、制服がない場合には、白いブラウスあるいはシャツに、黒・紺あるいはグレーのスカートやズボンが基本です。
法要・法要の服装について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
香典
一周忌法要に出席する際には香典を用意します。お香典袋の水引きは、黒白よりも双銀や藍銀、黃白の結び切りのものを用いるのが一般的です。表書きは、下の表のようにします。
| 様式 | 表書き |
| 仏式 | 御仏前・御佛前・御供物料など |
| 神式 | 御神前・御玉串料など |
| キリスト教式 | 御花料など |
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。


よくある質問
一周忌とはどんな法要?
一周忌法要後の年忌法要にはどんな種類があるの?
一周忌を行う際に遺族が準備することは?
一周忌法要はどんな流れで行われるの?
一周忌法要に出席する際のマナーは?
東京や一部の地域では7月、ほかの地域では8月にお盆を迎えることが多いようです。ホゥ。