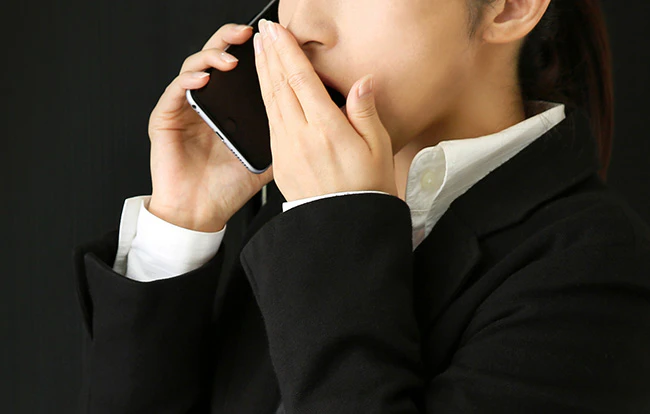今、身寄りがない高齢者の単身世帯は増加の一途をたどっています。孤独死のような事態になりかねない独り暮らし。
どのようにすれば安心して老後の生活をおくることができるでしょうか。
<この記事の要点>
・65歳以上一人暮らし高齢者は孤独死のリスクが高まっており、身寄りのないことによる不安がある
・身寄りのない方の葬儀は地域の人々との交流や相続財産管理人によって行われることがある
・生前に葬儀の契約や生前整理、遺言書の作成を検討しておく
こんな人におすすめ
身寄りがなく不安な方
葬儀の生前契約をお考えの方
身寄りのない方の葬儀について知りたい方
身寄りがないことによる不安
身寄りのない方で、自分が亡くなった時のことを心配されている方はたくさんいらっしゃると思います。
65歳以上の一人暮らし高齢者の増加は男女ともに顕著です。昭和55(1980)年には男性約19万人、女性約69万人でしたが、平成27(2015)年には男性約192万人、女性約400万人となっています。
※内閣府 平成29年版高齢社会白書(全体版)より
「家で独りのときに亡くなったら、誰が見つけてくれるのだろう」「長い間発見されないで遺体がひどく傷んでしまうのではないか」また「葬儀を行ってもらえないのでは」「財産はどうなるのだろう」と不安は募るばかりではないでしょうか。そのような不安を解消するために、生前からできることはないか、いろいろな角度から考えていきましょう。
身寄りのない方が亡くなった場合の葬儀・葬式や納骨について
身寄りのない単身世帯の方が亡くなった場合、地域の人たちとつながりがあり、日常的に交流していれば、誰かが早期に見つけてくれ、葬儀を行ってくれることもあります。このように遺族でない人が葬儀を行った時には、故人の相続財産管理人が管理している財産から、葬儀の費用を返還してもらえるそうです。
一方、亡くなった高齢者が地域に密着しておらず、何らかのコミュニティにも参加していない場合は、死後の発見に時間がかかることがあり、葬儀は死亡地の市町村長が行うことになります。身寄りのない故人の遺骨や遺品はほとんど引き取り手がないため、しばらく(5年ほど)保管されて、その後遺骨は無縁塚に埋葬されるのです。
元気なうちに決めておくことができる、葬儀の生前契約
葬儀を行うとなると、家族には金銭的負担のほか、傷心のなか葬儀の手配を進めなければいけないという心身的負担もかかるため、「元気なうちに身の周りの整理をしておきたい…」とお考えになる方も多いのではないでしょうか。
葬儀の生前契約をすれば、残された家族の負担を軽減することができ、ご自身の希望に合わせた葬儀をすることもできます。また、葬儀費用を事前に把握することができるので、亡くなった後に遺族が費用面で頭を悩ませる心配もありません。
<関連記事>
生前契約で希望の葬儀を。安心して任せられる生前契約とは
小さなお葬式で葬儀場をさがす
元気なうちにやっておくべきこと
周囲の人と関わりを持っておく
一緒に暮らす家族がいない場合、周りの人との関わりが命綱になる場合も多々あります。例えば、具合が悪くなって倒れてしまった時に、たまたま訪ねてきた近所の人に発見されて大事に至らずにすんだといったこともあります。
そこで、困った時に気兼ねなく頼れるように、日頃から周囲の人とコミュニケーションをとっておくことが大切になります。知り合いとのおしゃべりは気分転換にもなり、「明日は何をしよう。何を話そう。」という意欲も生まれます。
また、隣近所やボランティア活動、公民館でのサークル活動、市民大学講座、料理教室など人が集まる場所に継続的に顔を出してみるのもよいと思います。
行政のサービスについて調べておく
一人で抱えていてはどうにもならないことは、地域の行政を頼りにしてみてはいかがでしょうか。関わりやすい機関としては地域包括支援センターが挙げられます。
地域包括支援センターでは、高齢者からの様々な相談を受け、その解決のために必要な制度やサービス、機関を提案したり、近年増加している詐欺や虐待などから高齢者を守る取り組みを行ったりしています。さらに、高齢者がなるべく快適に生活できるように、地域にネットワークを形成して、多岐にわたる相談にも無料で対応しています。
高齢者自身でなくても、身内や親しい人に不安がある方はまず連絡をとってみるとよいでしょう。
任意後見制度を利用する
今はまだ元気で財産の管理を自分でできると思っていても、加齢に伴い誰でも正しい判断ができなくなってくるものです。そうならないうちに、先々の財産管理や高齢者自身のケアを任せたい時には任意後見制度を利用することができます。
この制度は、高齢者自身と後に任意後見人になる任意後見受任者との契約をもって成立しますが、実際に任意後見人になるには、高齢者本人の判断能力が落ちて、任意後見人受任者が家庭裁判所に後見開始の申し立てをしてからになります。
任意後見人が財産を適切に管理することで、高齢者を貧困や詐欺、悪徳商法などから守ることができるのです。
葬儀の事前準備
身寄りのない方が亡くなった場合の葬儀について、生前に葬儀社と契約できるプランがあります。
自分の死後にどのような葬儀をしたいかを葬儀社と相談および契約をして、料金は弁護士や信託会社が管理するという方法です。菩提寺がある場合にはそちらへの納骨を依頼し住職に契約のことを伝えておけば、滞りなく葬儀が行われるでしょう。
「小さなお葬式」では、事前に準備を始められたいという方からの相談も受け付けており、身寄りがない方に適した、直葬(ちょくそう)の葬儀プランをご用意しています。 直葬とは、通夜式や告別式などの儀式を省き、火葬のみを少人数で行う形式の葬儀です。

とにかく費用を抑えたい方、無宗教のためお坊さんをお呼びする予定がない方には、仏具などを省いたプランもございます。詳しくは下記のページをご覧ください。

生前整理
身寄りのない方が、やはり元気なうちにやっておきたいことの一つに、生前整理があります。自分の死後に見られたくないものは思い切って処分し、本当に必要なもの、大切なものだけを残すようにしましょう。
身の回りがすっきりして、空いたスペースで何か新しいことを始める意欲がわくかもしれません。一人では難しいと思ったら、専門の業者や葬儀社に頼むことができます。
また、土地や家など財産に関する生前整理は、税理士や行政書士が相談にのってくれるでしょう。
生前整理について、詳しい記事がありますので参考にご覧ください。
<関連記事>
生前整理とは?今すぐできる生前整理のやり方・進め方
遺言書とエンディングノート(終活ノート)の作成
エンディングノートとは、死に備えて自分の希望を書き込んでおくノートのことで、遺言書は、財産分与についての遺言者の希望が法的手続きに則って作られた書類のことです。身寄りのない人が亡くなった場合は相続人がいないことが多く、遺言書やエンディングノートは不要に思えます。
しかし、例えばアパートで一人暮らしをしていたら、その部屋の整理は大家さんがしなくてはなりません。大家さんに迷惑をかけないためにも、エンディングノートには希望や依頼内容を書いておきましょう。誰に実行してもらうかは、遺言書で指定することになります。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



香典の郵送は、現金を不祝儀袋に入れ、現金書留用の封筒でなるべく早く送ります。ホゥ。