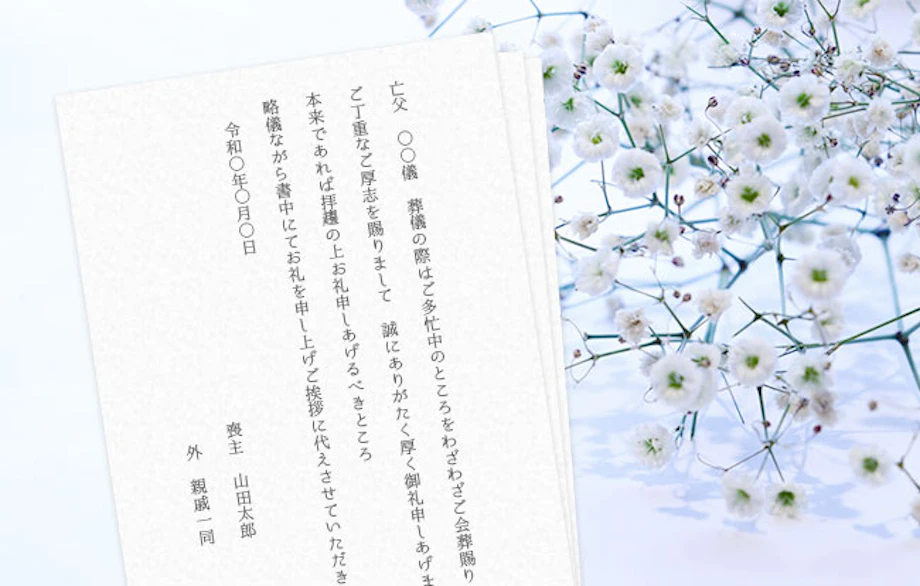身内に不幸があり葬儀を行った際は挨拶状を書く必要があります。一言で挨拶状といっても送る相手や場面によって内容が違うので「どう書けばいいかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
改まった手紙では日常で使わないような言葉や慣用句も出てきます。相手に失礼な印象を与えないためにも正しい使い方を理解しておくことは大切です。
この記事では葬儀の挨拶状の書き方とマナーを解説した上で、実際に使える例文をご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、挨拶状を書くときの参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・挨拶状には、葬儀の前に出す「案内状」と葬儀が終了した後に出す「お礼状」の2種類がある
・挨拶状に時候の挨拶や句読点は不要
・挨拶状を送るタイミングは葬儀形式によって異なる
こんな人におすすめ
葬儀の挨拶状とは何か知りたい方
葬儀に必要な挨拶状の書き方を知りたい方
葬儀の挨拶状のマナー・例文を知りたい方
葬儀の挨拶状とは
葬儀で書く手紙には様々な種類がありますが、葬儀の前に出す「案内状」と、葬儀が終了した後に出す「お礼状」の2種類に大きく分けられます。葬儀の案内状は亡くなったことを知らせる通知と葬儀の日時・場所・葬儀の形式を書くものです。通夜の会葬者にお渡しする会葬礼状は案内状に含まれます。
お礼状はおもてなしを受けたときに感謝の気持ちを伝える手紙です。葬儀に限らず、冠婚葬祭のあらゆるシーンで用いられます。基本的に前文から書き出し、丁重にお礼の言葉を述べましょう。葬儀のお礼状は参列してくださったことへのお礼や、香典・弔電といった心遣いに感謝していることを書きます。
どんな挨拶状を書くにしても書き方には一定のルールがあります。手紙は相手の顔が見えないため文面で印象が決まります。形式を踏まえて丁寧に書くことを心がけましょう。
葬儀に必要な挨拶状の書き方
手紙には普段の会話では使わない表現や形式があります。葬儀の挨拶状でも書き方のルールがあるのです。一見難しそうですが覚えてしまえば案内状でもお礼状でも応用できます。いざというときに書き方に困らないよう、この機会に理解しておきましょう。
なお、挨拶状は修正テープや二重線を引いて訂正するのはマナー違反です。書き損じたらもう一度最初から書き直します。書き終えたら誤字・脱字がないかチェックしましょう。
まずは葬儀での挨拶状の書き方を解説します。
挨拶状に句読点は含めない
挨拶状を書くときは「、」「。」といった句読点を書きません。文章の区切りは空白や改行を使って表現します。理由としては諸説ありますが、一説には毛筆で書いていたときの名残と言われています。昔は手紙を書く時は巻き紙に毛筆で書いていました。毛筆では句読点は用いませんので現代でも書き方のルールとして残ったというわけです。
他にも文中に「、」や「。」を入れると文章が途切れるためという説もあります。「葬儀が途切れず滞りなく無事終わるように」という意味で句読点を使わないとも言われています。
季節の挨拶は必要ない
一般的に手紙を書くときは本題の前に「早春の候」「〇〇の日が続いておりますが」といった季節を表す「時候の挨拶」を書きます。手紙を書くときの慣例として用いられていますが、葬儀の挨拶状では必要ありません。いきなり内容から書き始めます。
「挨拶を書かないのは失礼ではないのか」と思う方もいるかもしれません。しかし葬儀の挨拶状では挨拶を省くことで「驚きや悲しみのあまり挨拶をすることも忘れてしまった」ということを表します。
正しい敬語を使用する
葬儀の挨拶状では独特の表現があり、故人のことは「亡母 〇〇儀」「故 〇〇儀」といった書き方をします。この「儀」という言葉は添え字で読み方はありません。「〇〇に関する」という意味で故人に対する謙譲表現です。
そのほかにも気を付けることがあります。普段手紙を書くときには頭語と結語を書きますが、葬儀の挨拶状では書かなくても大丈夫です。頭語とは「拝啓」「前略」といった手紙の書き出しに用いる言葉です。それぞれ「敬具」「謹白」といった結語で締めくくります。書いても問題ないですが、頭語と結語の片方だけにならないよう1セットで使用しましょう。
宗教や宗派に合わせた言葉を使用する
宗教や宗派によってはタブーとされる言葉があるため注意しましょう。キリスト教では「死は悲しむべきものではなく天に召されたことを祝福すべき」という考え方があります。ですので「ご愁傷様」「残念」というお悔やみの言葉は使いません。
「死」という言葉も宗教によって言い方が違います。キリスト教では「帰天」「昇天」、神式では「帰幽」と表現します。また、神式の信者の方には仏教用語を使用しないように気を付けましょう。
葬儀の挨拶状のマナー
ここまでは挨拶状の書き方を解説しました。もう1つ知っておいて頂きたいのは葬儀の挨拶状は「いつ」「どのタイミングで」出すかということです。最近は家族葬が増えたため、一般の方の参列をご遠慮いただくケースも増えています。
次に、身内のみで葬儀を行った際にお礼状が必要なのか、挨拶状はいつ渡すのかについて解説します。
家族葬や密葬の場合もお礼状は必要
家族葬や密葬を行う場合は「故人が亡くなったこと」「身内のみで葬儀を行ったこと」「参列をご遠慮いただいたことに対するお詫び」の3点を書いた挨拶状を渡します。
基本的に家族葬や密葬では葬儀を行ったことを周囲の人は知りません。何かの折に亡くなったことを知りますが「葬儀に参列したかった」「どうして教えてくれなかったのか」とトラブルになることも考えられます。葬儀の後に良好な関係を続けるためにも、身内のみで葬儀を行った場合でも挨拶状を書きましょう。
葬儀を知らせなかった相手にもお礼状を出す
葬儀前に渡す挨拶状には「ぜひ会葬してください」という意味が含まれます。故人との付き合いの深さによってはかえって負担を感じさせる可能性があるので報せるのを控える相手もいるでしょう。しかし葬儀のことをずっと知らせないのは失礼に当たりますので、葬儀の後にお礼状を出します。書く内容は「故人の名前」「亡くなった日」「続柄」の3点です。
お礼状を受け取った方が弔問に訪れることもありますので、辞退する場合はそのことも記載しておくと良いでしょう。
お礼状は手書きでも印刷でも問題はない
印刷したものをお渡ししても失礼にはあたりません。以前は挨拶状を書くときは毛筆で手書きしていました。しかしすべての方に手書きで準備するとなると相当な時間が掛かってしまいます。丁寧な手紙を出すことも大切ではありますが、葬儀が終わったことをいち早く伝えるのもマナーです。
挨拶状の印刷は自分でする方法と葬儀社に用意してもらう方法があります。手書きのときは万年筆か毛筆で書き、ボールペンは使わないようにしましょう。
使ってはいけない言葉の使用は避ける
挨拶状を書くときには「忌み言葉」を使わないように気を付けましょう。「重ねがさね」「くれぐれも」「たびたび」といった同じ言葉を繰り返す言葉は不幸が再び訪れることを連想させます。
「死ぬ」「悲しむ」のような直接的な表現も避けてください。「死」は「逝去」「永眠」といった別の表現に言い換えましょう。「悲しむ」は「傷心」「哀惜」「哀愁」と表します。このように葬儀の挨拶状では悲しみを助長する言葉は避け、婉曲な表現をするようにしましょう。
挨拶状は速やかに届ける
葬儀の前に送る案内状も葬儀の後に送るお礼状も速やかに届けることが大切です。案内状は早く届かないと葬儀に間に合わない可能性があります。日程がわかり次第すぐに手配しましょう。
家族葬で周囲の方へ知らせていなかった場合は葬儀が終わったらすぐにお礼状を用意します。「〇日以内にお礼状を出す」と明確なルールはありませんが、できるだけ早く出すのがマナーです。
なお、香典を頂いた方へのお礼状は忌明けに出します。宗教によって忌明けまでの日数が異なりますので注意が必要です。
葬儀の挨拶状の例文
挨拶状は知らせる内容や相手によって文面を変える必要があります。どの挨拶状でも礼を尽くして丁寧な表現をするのがマナーです。ユニークな書き方をする必要はなく、ルールを守り形式に沿って書きましょう。
以下で葬儀の挨拶状の例文をご紹介しますが、横書きで見やすいよう適宜改行を入れながら書いています。実際に挨拶状を書くときは縦書きです。挨拶状の文面にお困りの方は〇の部分を差し替えて参考にしてください。
訃報を伝える挨拶の例文
母〇〇儀 かねてより病気療養中でしたが 〇月〇日未明永眠いたしました
ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに 謹んでご通知申し上げます
通夜および告別式は仏式により 次のとおり執り行います
通夜 〇月〇日 午後〇時より
告別式 〇月〇日 午前〇時より
場所 〇〇市〇〇町1-2-3
令和〇年〇月〇日
喪主 〇〇
外 親戚一同
時候の挨拶や頭語・結語は省いています。故人の名前・亡くなった日・葬儀の形式と日時・場所を簡潔にまとめます。
会葬に対するお礼を伝える例文
故〇〇儀葬儀に際しましては 御多用中にもかかわりませず御会葬を賜り
又ご丁寧なるご厚志をいただき誠に有難うございました
早速お伺い致しご挨拶申し上げるべき処 略儀ながら書面にて御礼申し上げます
令和〇年〇月〇日
喪主 〇〇
外 親戚一同
葬儀に参列していただいた方にお礼を伝える例文です。会葬礼状だと上記の例文になります。後日お渡しする場合は生前故人がお世話になったことを伝える文章を入れても良いでしょう。
お悔やみ状に対するお礼を伝える例文
この度は 亡父〇〇の逝去に際しましてご懇篤なるご弔意のお手紙と過分なるご香料を賜り 深く感謝申し上げます
〇〇様には御多用にもかかわらず幾度も父のお見舞いにお越しいただき 誠に有難く感謝の気持ちでいっぱいです
温かいお心遣いをいただき おかげをもちまして葬儀も滞りなく相営むことができました
亡父が生前賜りましたご芳志に心より厚く感謝いたしますとともに 今後とも変わらぬご厚誼を宜しくお願い申し上げます
まずは略儀ながら書面をもちまして御礼申し上げます
令和〇〇年 〇月〇日
お悔やみ状のほかに香典や供物を頂いていたら、そのことに対するお礼も書きます。故人が生前お世話になったことに対する感謝の気持ちも書くと良いでしょう。
喪中はがきでお礼を伝える例文
ご丁重なお年始状をいただきありがとうございます
年始から恐縮ではございますが 昨年〇月〇日祖父〇〇が天寿を全うし永眠いたしました
葬儀につきましては 故人の遺志により身内のみで相すませましたことを合わせてお知らせ申し上げます
服喪中につき 年頭のご挨拶を控えさせていただきましたが ご連絡が遅れました不手際を深くお詫び申し上げます
皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます
令和〇年〇月〇日
◯◯県〇〇市〇〇町1-2-3(差出人住所)
◯◯(差出人氏名)
年賀状を頂いた方に対するお礼と故人が亡くなったことを伝える例文です。今回は家族葬で葬儀をお知らせしていなかった方への通知ですが、葬儀に参列していただいた方の場合は存命中にお世話になったことへのお礼の言葉を入れます。
弔辞や弔電を頂いた場合にお礼を伝える例文
このたびは 母〇〇の葬儀に際し お心のこもった弔辞を賜り誠に有難うございました
ご弔意のお言葉謹んでお受けいたし 霊前に供えさせていただきました
亡母が生前賜りましたご芳志に心より厚く感謝いたしますとともに 今後とも変わらぬご厚誼を宜しくお願い申し上げます
本来なら拝眉の上ご挨拶申し上げるべきところ 略儀ながら書中にて御礼申し上げます
令和〇〇年〇月〇日
〇〇太郎(差出人氏名)
〇〇様
最後は日付・差出人氏名・宛名の順番で書きます。
香典返しの挨拶状の例文
先般 亡父〇〇の葬儀に際しましては 御多用の中霊前へのご厚志を賜り誠に有難くお礼申し上げます
ささやかではございますが 供養の印に心ばかりの品をお贈りさせていただきます
どうぞご受納下さいますようお願い申し上げます
本来なら拝眉の上ご挨拶申し上げるべきところ 略儀ながら書中にてお礼申し上げます
令和〇年〇月〇日
〇〇(差出人氏名)
まずは香典を頂いたことに対するお礼の言葉を書きます。特にお世話になった方へお渡しするなら締めの文章の前に葬儀が無事終わったことや故人が生前お世話になったことに対するお礼を書くのも良いでしょう。
忌明けの挨拶状の例文
亡母 〇〇儀 葬儀に際しましてはご丁寧なご弔慰をいただき 誠に有難く深く感謝申し上げます
おかげをもちまして納骨法要を滞りなく相すませました
早速拝眉の上親しくお礼申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもってお礼のご挨拶を申し上げます
令和〇年〇月〇日
◯◯県〇〇市〇〇町1-2-3(差出人住所)
〇〇(差出人氏名)
忌明けの挨拶状では葬儀の際にお世話になったお礼を伝えてから法要が無事終わったことを書きます。挨拶状で報告を済ませるので「本来なら直接会ってお礼を言うべきですが」というニュアンスの一言を添えておくと丁寧な印象です。
法事の案内の例文
拝啓 長かった梅雨も明け 夏本番を迎えましたが ますますご清祥のこととお慶び申し上げます
さて このたび左記日程によりまして 亡母〇〇の〇〇の法要を相営みたく存じます
御多用中誠に恐縮ではございますが 生前お世話になりました皆様のご来席を賜りたくご案内申し上げます 敬具
記
一、 日時 〇月〇日 午前〇時より
一、 場所 〇〇寺 〇〇市〇〇町1-2-2
一、 電話番号 1234-5678-0000
なお、当日は平服でお越しください
令和〇年〇月
◯◯県〇〇市〇〇町1-2-3(差出人住所)
〇〇(差出人氏名)
お手数ではございますが〇月〇日までに返信くださいますようお願い申し上げます
法要の案内では季節に合った挨拶を入れることを忘れないようにしましょう。また、法要での服装や出欠の期限についても明示しておきます。
社葬の挨拶状の例文
社葬は事前に準備に時間がかかるため、その前に身内だけで密葬と火葬を済ませるケースが多いです。
弊社取締役社長〇〇儀
〇〇のため〇月〇日永眠いたしました
ここに生前のご厚誼を深謝するとともに 謹んでご通知申し上げます
葬儀は近親者のみにて〇月〇日に相すませました
追って本葬儀は社葬をもって左記のとおり執り行います
なお 誠に勝手ながら御供花御供物の儀は固くご辞退申し上げます
記
一、 日時〇月〇日(〇曜日)
葬儀 午後〇時~〇時
告別式午後〇時~〇時
二、場所〇〇葬儀場
東京都〇〇区〇〇1-1-1
令和〇年〇月〇日
〇〇株式会社 葬儀委員長 〇〇太郎
副葬儀委員長 〇〇次郎
喪主 〇〇一郎
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
今回は葬儀の挨拶状の書き方とマナー、それぞれの場面に応じた例文をご紹介しました。葬儀の挨拶状は「死」に関する出来事を記すため、受け取った方が不快な気持ちにならないよう言葉遣いに気を付けることが大切です。しかし、葬儀の挨拶状を書き慣れていない方も多いと思いますので、いざ書くとなるとどのように書いていいか戸惑うこともあるでしょう。
そんなときはぜひ「小さなお葬式」へご相談下さい。挨拶状のご用意はもちろん、葬儀に関するあらゆるお悩みを真摯にお伺いし対応させていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



お彼岸の時期は年に2回で、春分の日、秋分の日の頃だと覚えておくとよいでしょう。ホゥ。