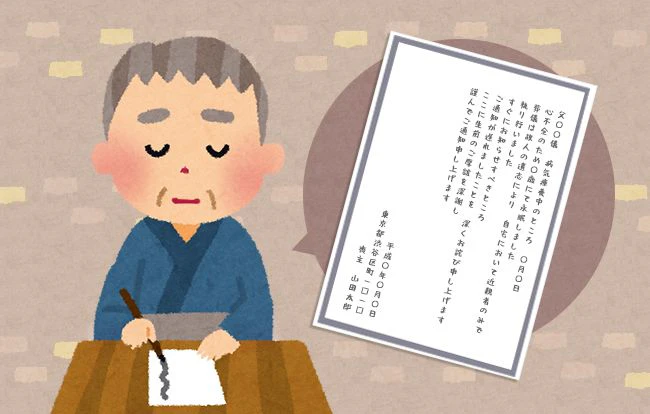身内が亡くなった場合は仕事や学校を休んで葬儀に出席することになります。しかし、人の死は予期せぬタイミングで訪れるものなので、当然前もって休みを頂くことなどはできません。
急な訃報を受けた際には、いかに迅速に忌引き休暇の連絡を勤め先や学校に連絡できるかが重要になってきます。今回は、急な忌引き連絡をしなくてはいけないときのマナーや注意点についてまとめています。
<この記事の要点>
・忌引き休暇の連絡は、深夜や早朝など電話が難しい時間帯に限りメールを利用してもよい
・メールには、故人の名前、故人との関係性、葬儀の日程と場所を簡潔に記載する
・メールで一報を入れた後に電話で最終確認の連絡を取る
こんな人におすすめ
深夜や早朝に身内に不幸があった方
忌引きをメールで伝える際の例文を知りたい方
忌引き休暇も連絡に対する返信方法を知りたい方
忌引き休暇の連絡はメールでしても良いものなのか
人の死は突然訪れるものなので、訃報が入るのは必ずしも職場や学校にいるときということはありません。深夜や早朝など、電話をするべきではない時間帯に訃報が舞い込んで来ることも少なくないでしょう。
そのようなときには、無礼にならない時間帯まで待って電話で忌引き連絡を入れるのではなく、メールでまず訃報を知らせるのが望ましいです。特に勤め先の上司には早く連絡を入れることで業務への支障を最小限に抑えることができ、同僚への負担を軽減することに繋がります。
忌引きのメールで伝える内容は?
忌引きメールは冗長な文面や感情的な内容にならないように注意し、伝えるべきことを簡潔に伝えることが大切になってきます。
忌引きメールで必ず記さなくてはいけない内容とは、「故人の名前」、「故人との関係性」、「通夜や告別式などの葬儀の日程」、「葬儀が執り行われる場所」です。もし、忌引き連絡を入れる時点で葬儀の様式まで分かっているようであれば併せて伝えましょう。
忌引き休暇のためにメールを送る場合のマナー
忌引き休暇を取得するためには、方々に忌引きで休む旨を伝える必要があります。忌引き休暇を取得したい旨をまず上司に連絡し、次いで業務の引き継ぎについて同僚や部下も含めて相談します。クライアントとのアポイントメントがある場合は予定変更を申し出なくてはならないケースもあるでしょう。
忌引き休暇を上司に申し出たことで安心せず、業務が円滑に回っていくよう同僚やクライアントに連絡を入れることを忘れないようにしましょう。
忌引き連絡はなるべく早く行う
故人の訃報を受け取ったらできるだけすぐに上司に忌引き連絡を入れましょう。一昔前は、メールという便利なものはなく、電話でしか連絡を取ることができなかったため、時間帯によっては電話ができずに訃報連絡も遅くなってしまうケースが多々ありました。
今の時代はメールという便利なツールがあるので、これをしっかり利用して早急に忌引き連絡を入れるようにしましょう。忌引き連絡を早く伝えれば伝えるほど、上司や同僚も自分が休む間の仕事をいかに分担して回していくか考える時間ができ、スムーズに引き継ぎができるようになります。
急な訃報を受けて頭の中は故人への想いや葬儀のことでいっぱいかもしれませんが、業務に支障を出さないようにテキパキ動くことも大切だということを念頭に入れておきましょう。
連絡の際に業務の引き継ぎを行う
忌引き連絡を入れた際に、業務の引き継ぎも行っておくと安心です。現在自分が担当している案件、提出締め切りのある書類の作成、クライアントとの共同作業など全ての仕事を上司や部下と共有しておく必要があります。
自分の担当していた仕事を代理として担ってくれる同僚が分かっているのであれば、直接コンタクトを取って引き継ぎを進める必要もあるでしょう。誰がどの仕事を担ってくれても良いように、自分が担当していた仕事の整理は普段から極力しておくのが望ましいといえます。
時間があれば誰でもわかるように紙やデータでまとめておいて、できる限り同僚や上司に仕事の負担をかけない工夫をしておきましょう。場合によっては発注先など社外の担当者に連絡をする必要もあります。やりとりしている先が多いと抜け漏れがありがちです。リスト化して連絡忘れを防ぎ、あとでトラブルにならないように注意しましょう。
会社の取引先には休暇の理由を伝える
商談を進めている最中など、忌引きの際にクライアントに一報入れる必要が出ることもあります。忌引きは急な休みとなってしまうので、クライアントとしても寝耳に水の話で対応に困ってしまう場合があるでしょう。それ故、ただ「休みます」と伝えるのではなく、なぜ急に休まなくてはいけないのか理由をしっかり伝える必要があります。
身内の不幸でやむなく忌引き休暇を取らざるを得ないということであれば、クライアントも納得しますが、「急に休みを取ることになりまして」と理由も言わずに休みを取られては信用を失うことにもなりかねません。
件名で忌引きであることが分かるようにする
忌引き連絡をメールで入れる際に大切になってくるのが件名です。どんなビジネスメールでも件名に気を遣うものですが、忌引きメールの場合も同じようにわかりやすい件名を考えるようにして下さい。
メールは多い時で一日に100通以上受け取ることがあります。その中で特に重要そうなメールから確認していくことが多いですが、重要か否かの判断材料は件名にあることが多いからです。「忌引き休暇の取得について」などといった件名が付いていれば、これは大事なメールに違いないとすぐに開いてもらえるでしょう。
一方で、「私事ですが」などの曖昧な件名ではいつまでもメールを確認してもらえない可能性もあります。見てもらえなければ、重要な業務引き継ぎ連絡も記したメールであったとしても意味を成しません。件名を読んだだけで忌引きについてのメールであるということが瞬時に分かるようにしておくことが肝心です。
忌引きメールの例文
忌引きメールには書くべき項目が基本的に決まっていますが、急な訃報を受けて気が動転し、正しく内容を伝えられないという事態に陥らないとも限りません。そんな時に参考にすると良い忌引きメールの例文をここに集めました。勤め先に送る忌引きメール、取引先に送る忌引きメール、学校に送る忌引きメールの3例を挙げています。
勤め先に送る場合の例文
件名:忌引き休暇の取得について
本文:○○部 ○○○○様(部長)
お疲れ様です。
大変恐縮なのですが、○月○日に私の○○(関係性)が永眠いたしました。
つきましては、○月○日から○月○日まで忌引き休暇の取得をお願いしたく、ここに届け出いたします。
期間:令和○月○日から○月○日
内容:葬儀の準備、片づけのため
葬儀日程:○月○日(通夜)、○月○日(告別式)
葬儀を執り行う場所:○○
無礼を承知でメールにて、取り急ぎご連絡いたしました。
尚、忌引き休暇中のご連絡は、私の携帯(○○○-○○○○-○○○○)まで頂けますと幸いです。
お手数おかけいたしますが、何卒宜しくお願いいたします。
○○部 ○○○○(自分の名前)
取引先に送る場合の例文
件名:アポイントメント延期のお願い
本文:株式会社○○ ○○部○○課○○○○様
平素より大変お世話になっております、○○社の○○でございます。
○月○日に予定しておりました○○に関する打ち合わせを延期していただきたく、ご連絡させていただきました。
私事で大変恐縮なのですが、身内に不幸がありましたため、打ち合わせの予定を変更していただきたく存じます。
急なご連絡となってしまいましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
私の不在時に何かありました際には、弊社の○○(○○○-○○○○-○○○○)が私の代わりに対応させていただきますので、何卒宜しくお願いいたします。
尚、○月○日から○月○日までの間の私への連絡は、○○○-○○○○-○○○○まで頂けますと助かります。
お手数おかけいたしますが、何卒宜しくお願いいたします。
株式会社○○ ○○○○(自分の名前)
学校に送る場合の例文
件名:ゼミ欠席のご連絡 [忌引き]
本文:○○教授
○○学部○○学科○年○組 ○○○○○○(学籍番号) ○○○○(氏名)
○○教授のゼミを受けております○○です。
○月○日に私の○○(関係性)が永眠いたしましたため、急遽○月○日○時限目のゼミ授業を欠席させていただきたく、ご連絡差し上げました。
無礼を承知で取り急ぎメールにてご連絡させていただきます。
後日改めて欠席届を出させていただきますので、何卒宜しくお願いいたします。
令和○年○月○日 ○○(氏名)
忌引き休暇の連絡に対する返信のポイント
忌引きメールを受け取った側はどういった対応をすれば良いのか悩まれる方もいますが、まずは、お悔やみの言葉と共に返信をするのが望ましいです。ここでは忌引き休暇の連絡に対する返信において注意すべき表現や押さえておきたいマナーについてまとめています。
お悔やみの言葉を使う
忌引きメールを受け取った際には、その内容をしっかりと確認した上で、お悔やみの言葉と共に返信メールを出すのが望ましいです。お悔やみの言葉とは故人の死を悼み、悲しみの気持ちと共に遺族など遺された人々に対して述べる言葉です。近しい間柄の人であれば、悲しみを和らげるために慰めの言葉を添えるのも良いでしょう。
いずれの場合も相手の心情を察し、無機質な返信にならないよう心がけることが何よりも大切です。
特に身近な大切な人を亡くしてしまった上司や同僚、部下に対しては、しっかりとお悔やみの言葉を述べ、「会社(仕事)のことは気にしなくて良いから、今はそちらのことに集中してください」といった気遣いを見せることで、相手の心の負担を軽減してあげましょう。
絵文字や顔文字は使わない
忌引きメールは絵文字や顔文字などが含まれない、ビジネスマナーに沿った文章で送られてくることが一般的です。返信する際にも形式やマナーに則った丁寧な文面を心がけましょう。
カジュアルな絵文字や顔文字で書かれたメールは、故人の死を悼んでいるといった雰囲気は伝わりづらく、悲しみに暮れる遺族の心に寄り添っているとは言えません。仕事のメールと同じく、忌引きメールも相手に失礼のないように絵文字や顔文字を使用しないようにしましょう。
忙しい相手のことを考えて簡潔な内容にするのも重要なポイントです。もし、同僚が古くからの友人など親しい関係だという場合には、後ほどプライベートなメールや直接会って話すことで思いやりのある言葉をかけてあげてください。会社でのやり取りはあくまでビジネスマナーに則ったやり方を心掛けましょう。
死や苦を連想させる言葉は使わない
忌引きメールに返信する際、気を付けなくてはいけない言葉があることを押さえておきましょう。まず、「死」や「苦」を連想させる言葉や数字(4、9)はできるだけ使わないようにします。
また、「重ね重ね」、「今後も」、「これからも」、「まだまだ」などの繰り返し言葉、連続言葉は、「今後も不幸が重なる」ことを連想させるため使用は極力控えるようにします。
「お亡くなりになった」「生きていた頃」といった生死に関する直接的な表現も嫌がられることがあります。それぞれ「ご逝去」「ご生前」のように言い回しを婉曲にしましょう。何も考えずに返信を打ってしまうと、うっかりこうした避けるべき表現が入ってしまう可能性もあるので、くれぐれも気をつけるようにしましょう。
電話での連絡もあわせて行う
訃報を受けたのちに、メールにてすぐに忌引き連絡を入れるのはとても大切なことです。深夜や早朝、休日であっても迅速に連絡ができ、あとで内容を見返すこともできます。一方でメールは、送った時間と相手が開いて読む時間との間にタイムラグが生じる場合があります。
特に忌引きで仕事を休んでいる間にすぐに片づけて欲しい仕事などを誰かに依頼している場合、その業務の引き継ぎ連絡メールを相手が読んでいなかったら大変なことになってしまいます。
「万が一メールが届いていなかったら」、「相手がメールに気づかなかったら」という可能性も念頭に入れ、メールを送った後でも一度電話を入れて、全ての確認をするのが望ましいでしょう。
忌引き休暇に関わる伝達ミスは職場に大きな影響を与えかねません。自分が休んでいる間にトラブルを起こさないようにするためにも、メールで一報を入れた後に電話で最終確認の連絡を取ることを心掛けましょう
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
急な訃報を受けた後にまずすべきことは職場や学校への連絡や忌引きの申請です。その際は、「○○が亡くなったので、忌引きが欲しい」といった簡易的すぎる内容では不十分です。
「誰が、いつ亡くなったか」「自分とはどんな関係か」「いつどこで葬儀が執り行われるのか」「自分は喪主か否か」といった内容を含めてしっかり伝えなくてはなりません。
社会人としてのマナーに欠くことなく、仕事に支障が出ないよう配慮しながら、関係各所にきっちりと忌引き連絡を入れるようにしましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



葬儀費用は相続税から控除することが可能です。ホゥ。