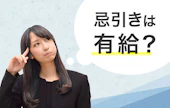家族や親族に不幸があると忌引きを取って会社を休みます。叔父や叔母は両親の兄妹ですから、生前お世話になっていた方も多いと思います。しかし、叔父・叔母は3親等に該当するため場合によっては忌引きが認められないことはご存知でしょうか。
また、忌引きができる場合は会社の方に引継ぎをして必要な証明書を準備します。マナーを守って対応し、できるだけ周囲の方に迷惑を掛けないようにしましょう。
今回は叔父や叔母の葬儀で忌引きする際のポイントや注意点を解説します。忌引きに際してわからないことがあったときの対応もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただき参考にしてください。
<この記事の要点>
・忌引き休暇を取得する際は、会社の就業規則を確認して業務の引継ぎをしっかりと行う
・叔父・叔母が亡くなった際の忌引き日数は1日であることが多い
・会社によっては、死亡診断書のコピーなど葬儀があったことを証明する書類が必要
こんな人におすすめ
叔父や叔母の葬儀の際の忌引きについて知りたい方
叔父や叔母の葬儀で忌引きする際のポイントを知りたい方
叔父や叔母の葬儀で忌引きする際の注意点を知りたい方
叔父や叔母の葬儀で忌引きする際のポイント
忌引きの日数は会社によって異なります。まずは叔父や叔母の葬儀で忌引きができるか就業規則を確認してみましょう。忌引きの制度がなければ有給休暇が取得できることがあります。忌引きをする際は会社の方に業務の引継ぎをしっかり行い、必要な書類があれば忌引き明けまでに準備が必要です。
ここでは叔父や叔母の葬儀で忌引きする際のポイントを詳しく解説します。
忌引きの日数
多くの場合、叔父・叔母が亡くなった際の忌引き日数は1日です。一般的には亡くなった方と自分との続柄によって日数が決まります。日本では親族との血縁関係を表す時に「〇親等」という言い方をします。考え方は自分と配偶者を0として、関係が1つ遠くなるたびに1を足します。
この考え方だと叔父・叔母は3親等に該当します。配偶者の叔父・叔母(義叔父・義叔母)も同じく3親等です。しかし遠方で葬儀があると1日では帰って来られないこともあります。会社に相談すれば日数を延ばしてもらえたり、併せて有給休暇を取得したりできる可能性があります。
会社の規定
実は会社に「忌引き休暇」の制度がなくても違法にはなりません。法律で定められた休日は「法定休日」と「年次有給休暇」の2つです。忌引き休暇は福利厚生の1つであり、制度を設けるかどうかは会社が自由に決められます。
会社によっては「2親等以上は忌引きを認めない」としていることもあり、雇用形態によって取得できる日数が違うこともあるのです。
基本的には就業規則で決まっていて、雇用契約書に書かれていることがほとんどです。「忌引き休暇」あるいは「慶弔休暇」があれば休める日数、休んだ間の賃金の扱いが書かれているはずですから、もし書かれていなければ会社の総務課や上司に聞いてみましょう。
業務の引継ぎをしっかりと行う
忌引き休暇を取得する際は上司に連絡をするのがマナーです。それと同時に業務の引継ぎも忘れないようにしましょう。引継ぎの連絡は口頭で伝え、漏れがないように書面やメールでも伝えておきます。
業務のことでトラブルが起こると連絡が必要です。上司と同僚には「緊急連絡先」を伝えておきましょう。休んでいる間に取引先との打ち合わせがあれば、事情を伝えて日程変更を打診します。社内に代理で対応してくれる方がいればその方の連絡先も伝えます。
忌引き中のため、会社の方は小さなトラブルでは連絡してこないことが考えられます。休暇中は葬儀の準備もあり何かと忙しいものです。しかし、自分からこまめに連絡を取って業務が滞りなく進んでいるか確認しましょう。
叔父や叔母の葬儀をどこで行うかを伝える
葬儀の日時と場所がわかったら会社に報告しましょう。会社によっては社内で代表者を選んで葬儀に参列する場合や、規定で香典を用意することがあります。忌引きを申請する時点で決まっていなければ「わかり次第報告します」と一言申し添えておきましょう。
最近は身内のみで葬儀を行う「家族葬」が増えています。一般的に家族葬はお招きする方以外には日時や場所を知らせません。会社へも手続き上必要なければ日時や場所は知らせなくて良いでしょう。会社の方には「家族葬を行うこと」「香典や弔問をお断りするか」をはっきり伝えておきます。
忌引きする際に必要な書類を用意する
会社によっては葬儀があったことを証明する書類が必要になります。有効とされるのは「会葬礼状」「死亡診断書」「埋葬許可証」「葬儀会社の施行証明書」です。必要な書類は会社によって違います。就業規則に書かれているか一度確認してみましょう。
会葬礼状とは通夜の参列者に即日返しに添えるお礼状のことです。通夜の日時や亡くなった方の名前が書かれています。死亡診断書や埋葬許可証は原本を提出するのでコピーで構いません。
証明書は忌引き明けに提出するため、休暇中に用意しておきましょう。証明書の提出がなければ「欠勤」扱いとされることもあります。
叔父や叔母の葬儀で忌引きする際の注意点
忌引きの連絡は基本的に口頭で伝えます。深夜や祝日であればメールを入れ、翌日できるだけ早い時間に電話をしましょう。電話にしてもメールにしても内容を長々と話さないように注意します。
また、忌引き明けの準備も忘れてはいけません。提出する書類は大切に保管し、香典返しや菓子折りを準備しておきましょう。ここからは叔父や叔母の葬儀で忌引きをする際の注意点を解説します。
忌引きの連絡は簡潔に分かりやすく伝えることが大切
忌引きの連絡時は必要な情報を簡潔にまとめましょう。口頭で伝えるときは、長々と話すと相手が内容を覚えられず伝達漏れにつながります。業務中なら仕事を遮って電話をしているため、早めに切るのがマナーです。
伝える内容は「叔父・叔母がいつ亡くなったか」「忌引きで休む日数」、一般葬であれば「葬儀の場所・日時」、業務連絡用の「緊急連絡先」の4点です。忌引きの連絡は電話とメールの両方で行いましょう。メールでも前置きや挨拶はなるべく短くして、本文は用件のみを簡潔に書いて送ります。件名は一目見ただけで「忌引きに関する連絡」とわかるようにするのが大切です。
必要な書類を紛失しないように保管する
会社に提出する証明書は再発行ができないものもあります。紛失しないように大切に保管しましょう。死亡診断書は役所に提出すると返却されず再発行はできません。必要であればコピーを取っておいてください。火葬許可証は火葬場で印を押してもらうことで埋葬許可証として使用できます。
火葬許可証もしくは埋葬許可証を紛失しても再発行が可能です。申請は遺族以外が行っても大丈夫ですが、死亡届を一緒に提出する必要があります。まずは死亡届を用意しないといけない上に受け取りが後日になることもあるでしょう。会社の提出期限に間に合わない可能性がありますので、なくさないように気を付けましょう。
葬儀の後に出社したときは会社の人にお礼を伝える
叔父や叔母の葬儀で休むのは仕方のないことです。しかし、休みの間に周囲の方が仕事をフォローしたり業務を引き継いだりしてくれています。忌引き明けに出勤したら、まずは直属の上司にお礼を言いましょう。そのあと同僚や部下にもお礼を言って回るのがマナーです。
香典を頂いた方にはお礼を言うときに香典返しを渡します。そのほかにも弔電や供花を頂いていれば菓子折りを渡すと良いでしょう。香典や弔電、供花を頂いていたにも関わらず出勤時にお礼をしないのはマナー違反です。誰から頂いたか休みの間に把握して、香典返しや菓子折りを準備しておきましょう。
忌引きという嘘をつかない
人によっては何らかの事情や予定があって会社を休みたいこともあるでしょう。しかし、忌引きと嘘をついてはいけません。忌引きの連絡は自己申告だけなので周囲の方にはわからないかもしれません。しかし証明書の提出が必要になると会社にばれる可能性があります。
嘘をついたことがわかると会社からの信用を失いかねません。昇進や昇給に影響するだけでなく、会社に居づらくなることも考えられます。また後日本当に不幸があり、忌引きを申請しても「また嘘をついているのではないか」と疑いの目で見られることでしょう。今後の人間関係を考えると嘘をつくのは得策ではありません。
叔父や叔母の葬儀で忌引きをする際に分からないことがあった場合の対策
ここまで叔父・叔母の葬儀で忌引きするときのポイントや注意点を解説してきました。会社によって規定は異なりますので疑問に思うこともあるでしょう。自己判断せず、上司や同僚に聞いてみましょう。
会社の方に聞きにくいことは葬儀業者に相談するのもおすすめです。葬儀業者はプロですから、忌引きで必要なものについても親切に教えてくれます。ここでは忌引きに関してわからないことがあった際、誰に相談すればいいかご紹介します。
会社の上司や同僚に忌引きについて聞く
忌引き休暇の概要は会社の就業規則に書いてあります。しかし、上司や同僚に聞かないとわからない情報もあるでしょう。葬儀の準備があり忌引き休暇の日数内で戻って来られない場合、会社に相談すれば日数を延長できることもあります。また、忌引き明けの挨拶回りも会社の慣習があればそちらに従いましょう。
就業規則で判断できないことは上司や同僚に聞きましょう。「休む上にわからないことを聞くと迷惑なのでは」と思う方もいるかもしれません。わからないからといって自己判断で誤った行動をすると、かえって周囲に迷惑を掛ける可能性があります。
葬儀業者に必要なものについて相談する
葬儀業者は葬儀全般のあらゆる相談を受け付けています。忌引きで休んだときに必要な書類や香典返しといった葬儀特有のことは知らない方も多いのではないでしょうか。会社の方に聞きにくいことがあれば葬儀業者に相談してみるのもおすすめです。
会社に提出する「葬儀の施行証明書」は葬儀業者に言うと用意してもらえます。そのほかの証明書についても、わからないことがあれば教えてもらえるので安心してください。
香典返しは自分で準備する以外に、葬儀業者に依頼することも可能です。忌引き休暇中に香典返しを準備して1人1人に挨拶状を書くのは大変です。葬儀業者に手配をお願いすれば挨拶状や外熨斗も付けられます。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
叔父・叔母の葬儀で忌引きする際はまず会社で忌引き休暇が認められるか確認し、忌引きで休む場合は業務の引継ぎをきちんと行いましょう。
提出する書類は休暇中に用意して、紛失しないように大切に保管しておきます。忌引き明けは周囲の方へお礼を言うのがマナーです。
しっかりとマナーを理解して、忌引きの際は安心して供養してあげられるようにしましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



墓じまいとは、先祖供養の続け方を考えた際の選択肢の一つです。ホゥ。