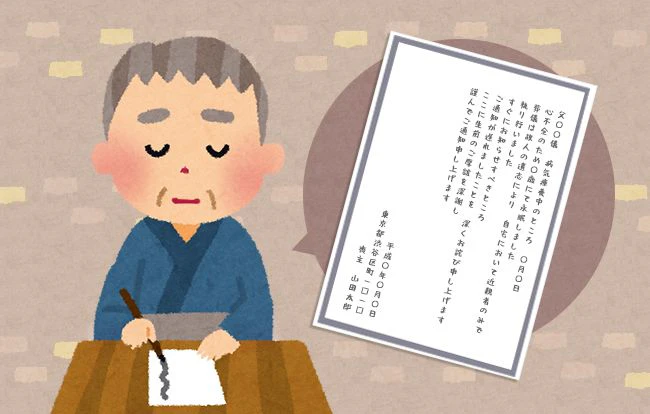埋葬とは、遺体や遺骨を地中に葬ることです。埋葬にはいくつかの種類がありますが、具体的な埋葬方法がわからない方も多いかもしれません。
そこでこの記事では、埋葬の種類や必要な手続き、埋葬でもらえる給付金について紹介します。
<この記事の要点>
・代表的な埋葬方法には墓に埋葬する、納骨堂を利用する、永代供養を活用するなどがある
・火葬や納骨をするときは、火葬許可証が必要である
・国民健康保険や健康保険組合に加入していれば、葬祭費や埋葬料が支給される
こんな人におすすめ
埋葬許可証について知りたい方
埋葬許可証と火葬許可証の違いが気になる方
埋葬許可証を紛失してしまった場合の対応を知りたい方
埋葬とは
埋葬と聞いても具体的なイメージが湧かない方もいるでしょう。埋葬を知るには歴史や法的解釈、安置方法を理解する必要があります。ここでは埋葬に関する基本的な情報を紹介します。
埋葬の歴史
江戸時代までの日本では、土葬と火葬の両墓制でした。しかし、明治3年に全ての寺院墓地が国有地となり、明治5年には法律によって自葬祭が禁止されました。これにより、葬儀は全て神主や僧侶によって行われることになりました。
明治初期は仏教の排斥と神道の推奨から火葬禁止令が出され、火葬が行われなくなりました。しかし、火葬再開を望む声が多かったことに加え、土葬用の土地が枯渇してきたことから、火葬禁止令は2年で撤回されることとなります。その後は衛生的な観点から火葬の有用性を認め、火葬が義務化されるようになりました。
<関連記事>
昔の葬儀はどんな内容だった?縄文から大正まで全ての時代を振り返る
埋葬の法的解釈
昭和23年に土葬、埋葬を不備なく執り行うための「墓地、埋葬等に関する法律」が制定されました。故人を火葬して骨壺に納めている場合は、該当の区域以外には埋葬できません。
また、自身が所有する土地に埋葬することも法律で禁止されています。ただし、火葬された遺骨を自宅に安置することは違法になりません。
埋葬と納骨の違い
遺体や遺骨をお墓に納めることを「埋葬」と総称します。「納骨」も「埋葬」とほぼ同義で、遺体を火葬して骨壺に遺骨を納めた状態でお墓や霊園、納骨堂に安置することを指します。
現在の日本では火葬の割合が99%を超えており、故人を遺骨として骨壺に納めることが一般的です。
埋葬の種類
葬儀や死に対する考え方が多様化している現代社会には、さまざまな埋葬の種類があります。ここからは、代表的な埋葬方法を紹介します。
墓に埋葬する
伝統的な埋葬方法はお墓に遺骨を納める方法です。先祖代々のお墓か、墓石を新しく建ててから墓石の下にある骨壺を収容するカロートに遺骨を収めます。
先祖代々のお墓の場合は、墓石に戒名が刻まれるのが特徴です。受け継がれてきた歴史や縁を感じられるでしょう。
<関連記事>
墓石に戒名彫りを行うときの流れと注意点
納骨堂を利用する
納骨堂とは、個人や家族など、さまざまな単位ごとに遺骨を収納できるスペースのことです。広い敷地を必要としないため、アクセスのよい都市部に建てられることが多い傾向にあります。屋内型なので、天候を気にせずにお参りできるのもメリットのひとつです。積極的に利用する方も増えてきています。
<関連記事>
納骨堂の概要やメリットは?都道府県別の相場を解説!
永代供養を活用する
永代供養とは、寺院や霊園に納骨し、遺族に代わって管理・供養してもらうことです。寺院や霊園が永代に渡って供養してくれるため、お墓を継承する必要がありません。お墓用の土地や墓石を準備する必要がないので、費用負担を軽減することもできます。
<関連記事>
永代供養とは?そのメリット・デメリット
小さなお葬式で葬儀場をさがす
埋葬に必要な手続き
日本では火葬が一般的と考えられています。一方で、火葬や埋葬に必要な手続きを理解している方は少ないかもしれません。ここからは、火葬からお墓に埋葬するまでの流れを解説します。
「埋葬許可証」の本来の意味
火葬や納骨をする際は、許可が必要で「火葬許可証」という許可証が必要です。遺骨をお墓に納めることを「埋葬」と認識されている方が多いですが、「埋葬」の本来の意味は「遺体を土の中に埋めること」であり、埋葬許可証は、土葬の許可を証明するものです。
日本でも、一部の地域では土葬が認められており、その場合、死亡届とともに役所に提出する書類は、「死体火葬・埋葬許可交付申請書」となっているのです。
多くのインターネット上の情報や、葬儀の手順を解説する書籍の中でも、「火葬許可証に火葬済の印が押されたものが埋葬許可証になる」と記されていますが、正確には、火葬許可証が埋葬許可証に変化することはありません。
火葬許可証に印が押されたものは、あくまで「火葬執行証明済の火葬許可証」でしかないのです。
火葬した遺骨をお墓に納めるときの手続き
火葬が終わり、遺骨を骨壺に納める「骨上げ」を行うと、火葬執行済の印が押された火葬許可証が渡されます。
押印済の火葬許可証は、納骨するまで必ず遺骨とともに自宅で保管しておきましょう。納骨は、四十九日の忌明けの法要と併せて行われることが一般的です。失くさずに保管し、納骨のときに遺骨と一緒に墓地に持参しましょう。
納骨のタイミングは、四十九日法要と同時でなくても構いません。納骨するにはお墓の準備も必要になるため、一周忌や三回忌などの年忌法要のときに行うのがおすすめです。
納骨の日取りは、お付き合いのあるお寺である「菩提寺(ぼだいじ)」と相談してきめます。日程がきまったら石材屋に連絡して、墓石の下の遺骨を納めるカロートを開けてもらう作業の依頼をします。亡くなった方の名前や墓誌の彫刻を希望する場合は、あわせて依頼しましょう。
火葬許可証を紛失したときや分骨するときの手続き
火葬許可証を失くした場合は、火葬許可証を発行してもらった自治体に申し出ましょう。5年以内であれば、本人確認書類と印鑑を持参することで再発行が可能です。
ただし、遺骨を2箇所以上に埋葬する場合は、その数だけ押印済の火葬許可証が必要になります。火葬する時点で分骨すると決めている場合は、事前に火葬場まで申し出ましょう。必要な枚数分の書類を発行してもらうのがおすすめです。
埋葬する際にもらえる給付金
埋葬をする際に支給される給付金があります。これは「葬祭費」や「埋葬料」と呼ばれる給付金のことです。ここからは、埋葬をする際にもらえる給付金をそれぞれ紹介します。
葬祭費
葬祭費とは、国民健康保険から支給されるお金です。故人が加入していた国民健康保険を管轄する市区町村によって葬祭費の支給金額は変動します。
支給金額は自治体により異なりますが、区部であれば7万円、市町村部ならば1万円~7万円ほどです。支給申請ができるのは、亡くなった国民健康保険の加入者の葬祭を行った人である点に注意しましょう。
埋葬料
埋葬料の申請方法は、故人が加入していた健康保険の種類によって変わります。埋葬料の支給金額はどの健康保険組合でも一律5万円です。
しかし、加入している健康保険によっては、組合独自の付加給付を上乗せして支給される場合もあります。埋葬料を申請できる人は、亡くなった被保険者と生計維持関係にある埋葬を行った人です。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
明治時代を境に、衛生的な観点から日本では火葬が義務化されました。現在の日本では火葬の割合が99%を超えており、故人を遺骨として骨壺に納めることが多いでしょう。しかし、埋葬方法の多様化に伴い、納骨堂や永代供養、樹木葬などの自然葬を選択する方も増えています。
埋葬する際は、「葬祭費」や「埋葬料」という給付金を申請できます。申請方法や支給金額は自治体によって異なるので、しっかりと調べてから申請するとよいでしょう。
死亡後の手続きや埋葬方法について不安がある場合は、小さなお葬式までご相談ください。専門のスタッフが24時間365日、ご対応いたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



訃報は、死亡確定後、なるべく早く届けることが大切です。ホゥ。