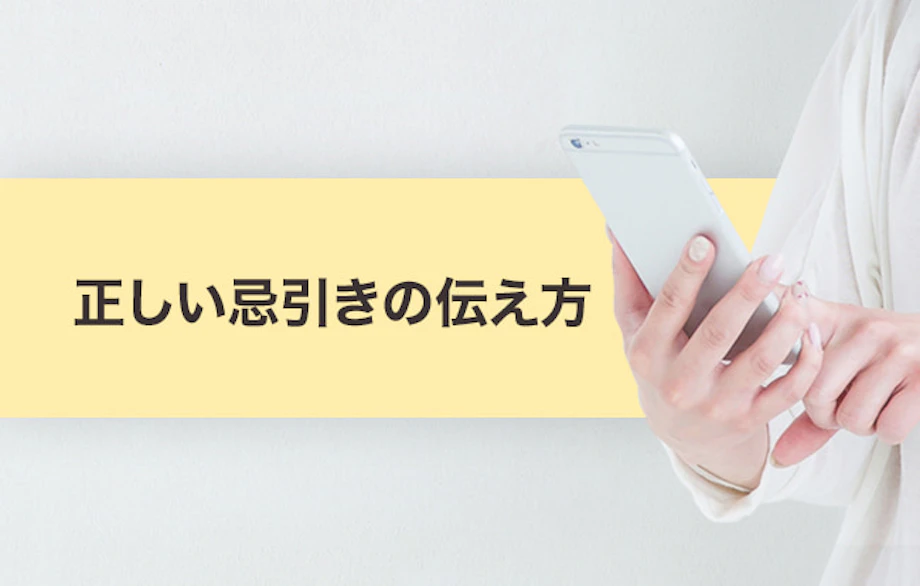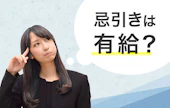身内に不幸があった際、「忌引きのため休みます」とまずは会社や学校に伝えなければなりません。しかし忌引きは有給休暇のような法律による休暇ではなく、あくまで慣習的に行われているものです。
法律で規定されているわけではないので、何親等まで認められるのか、日数はどうなるかなどは会社や学校によって異なり、分かりにくい方もいるのではないでしょうか。ここでは、取得する際にすべき連絡の方法など、注意すべきポイントについてご説明していきます。
<この記事の要点>
・忌引きは法律で定められた休暇ではなく、会社や学校によって取得日数や適用範囲が異なる
・忌引きを取得する際は会社や学校の規定を確認し、上司や担任に早めに連絡する
・忌引き休暇制度がない場合は有給休暇を使用する
こんな人におすすめ
忌引きとは何かを知りたい方
忌引きを理由に休暇をとる場合のポイントを知りたい方
忌引きをメールで連絡する場合の例文を知りたい方
忌引きについて
神道では、死は「畏(おそ)れ忌(い)みはばかるもの」とされています。死は穢(けが)れであり、その死の穢れのある人、すなわち亡くなった人の近しい家族や親族はしばらく行動を慎むべきというのが「忌中」であり、「忌引き」はその「忌」に、学校や会社にいかず休暇をとることを意味します。
忌引きには「休む」という意味が含まれている
どれくらいの期間を忌中、つまり行動をつつしむべき期間とするかは、国内でも地方によって、また時代によっても変化しています。
忌中にせよ忌引きにせよ、日本古来の神道にもとづいた慣習です。何日間くらいの休暇を取得できるか、どこまでの親等の親族に認められるのか、これらはあくまで学校や会社の習慣や規約や規定によるものであり、はっきりと共通した決まりがあるわけではありません。まずは、この点を認識しておきましょう。
忌引きには「休む」という意味が含まれている
どれくらいの期間を忌中、つまり行動をつつしむべき期間とするかは、国内でも地方によって、また時代によっても変化しています。
忌中にせよ忌引きにせよ、日本古来の神道にもとづいた慣習です。何日間くらいの休暇を取得できるか、どこまでの親等の親族に認められるのか、これらはあくまで学校や会社の習慣や規約や規定によるものであり、はっきりと共通した決まりがあるわけではありません。まずは、この点を認識しておきましょう。
忌引きと公休の違い
公休とは土曜日や日曜日のことを指します。お店であれば定休日も含まれ、もともと学校や会社で定められている休みの日のことです。規約や規定にもとづいた忌引きとは性質が異なります。
よく疑問に思われるのが「忌引きの日数に公休は含まれるのか」という点です。忌引きの期間が3日間で、開始するのが金曜日から3日間、土日はもともと公休というケースを考えてみます。
この場合、休暇が3日間なので公休をのぞいた金・月・火の3日間が休みになるというわけではありません。この場合は金・土・日となり、実質、会社を休むことになるのは金曜日の1日だけになります。法律で定められた休日である有給とは違った忌引きの大きな特徴といえるでしょう。
忌引きの日数について
忌引きは学校や会社により異なってくるとはいっても、実際に取得できる忌引きの日数や期間について、一般的な期間や日数は定められています。もちろん、最終的には規約や規定の現物で確認することが大切です。
忌引きの日数は間柄によって決まる
忌引き期間は、子や兄弟姉妹、祖父祖母は3〜5日間、両親や配偶者で1週間〜10日間が一般的です。くり返しになりますが、これらの日数は法律で定められているわけではなく、あくまで各会社の規定や慣習によって決まります。会社であれば就業規則などに、学校であれば生徒手帳に規約が記載されている場合が多いです。
亡くなった当日または翌日から数える
いつから忌引きに該当するかは会社や学校によって異なってくるので、担任の先生や上司に連絡する際にはこの点を事前によく確認しておきましょう。
また土日や定休日など、もともとの休日をはさんだ場合を数えるかどうかも会社や学校で変わるので、事前に確認しておきましょう。
忌引きを理由に休暇を取る場合のポイント
忌引きを取得する際の流れについてご説明します。まずは学校や会社でどのように規定されているのかの確認と、担当の先生や会社の上司などにしっかり確認することが大切です。また、故人が亡くなったあと、できるだけすみやかに連絡することも重要です。
できるだけ早く忌引きの連絡をする
身内に不幸があり学校や会社を休むことになった場合は、できるだけ早く学校や会社に連絡しましょう。電話、もしくは時間帯や先生・上司との関係によってはメールやSMSでも良いでしょう。電話であれば問題ありませんが、メールやSMSの場合は、返信など何らかのレスポンスによって相手がそれを読んだかどうかの確認は怠らないようにしてください。
その意味でも、最初の連絡はできれば電話の方が良いでしょう。電話や口頭で連絡がとれた場合も、メールやSMSでも一報を入れておいた方が、文面と時間の記録が残るのでよりおすすめです。
故人との間柄を伝える
第一報の連絡の際には、故人と自分との間柄(続柄)は必ず伝えるようにします。故人との間柄により日数も変化するためです。
連絡した時間帯や相手の状態によっては、その場で規約や規定を調べ、休暇の取得日数やいつ取得するかといった話に進展することもあるでしょう。その場合は必要な書類や、それをいつ用意するか・いつまでに持参すれば良いかなど、できるだけ具体的な話を進めておいた方が後にスムーズに事が進みやすくなります。
就業規則・生徒手帳を確認する
多くの場合、会社であれば就業規則に忌引きについての決まりごとが掲載されています。学校の場合は生徒手帳です。生徒手帳であればすぐ確認できる場合も多いでしょうから、できれば第一報の際に確認しておきましょう。
就業規則の場合、特に故人が突然亡くなった場合は、すぐ確認状況ではないことがほとんどです。事前に会社に赴けるのであれば、申請前にできるだけ就業規則を確認しておきましょう。
欠席届などの必要書類がないか確認する
連絡だけではなく、学校であれば欠席届、会社であれば申請書を提出することが多いでしょう。学校であれば公欠(公認欠席)届となることがほとんどです。いずれの場合も、亡くなった方とその方との間柄、葬儀の日時を記載することになります。
特に会社の場合注意しなければならないのが、証明書類の提出を求められることがあるという点です。従来ですと、葬儀の会葬礼状を提出することが多かったものの、最近は葬儀の小型化にともない、会葬令状を作成しないことも珍しくありません。その場合、死亡診断書や火葬許可証を求められる場合があります。
忌引き明けの挨拶も行うこと
忌引き休暇の後、はじめて登校・出勤する際には忌引き明けのあいさつを行いましょう。休暇取得をさせていただいたことへの感謝と、葬儀をつつがなく行った報告などを述べておきます。
会社の場合、香典をいただいていた場合は忌引き明けに香典を返したり、菓子折りを持参空いたりすることがほとんどです。ただし会社からの香典の場合、香典返しは不要というケースも少なくありません。
近年は個人でも香典返しは不要という方もいますので、事前に確認しておきましょう。
忌引きをメールで連絡する場合の例文
第一報として、メールやSMSで連絡する際の例文を見ていきましょう。
基本的には故人が亡くなったことと、故人との続柄や、取得したい日数を具体的に記述するようにします。葬儀の日時が未定の場合は、その旨も記載しておきます。担当の先生にしても上司の方にしても、連絡を受けた側は書類を確認したり、学校や会社へ手続きしたりしなければなりません。必要事項をすみやかに伝えることが重要です。
会社へ連絡する場合
件名:忌引き休暇取得のお願い
(上司名)
お疲れ様です、◯◯です。
母が本日死去し、忌引きを取得したくご連絡さしあげました。
故人:(故人名)
忌引き休暇期間:◯月◯日~◯日
葬儀日程:未定
休暇中のご連絡先は〇〇(電話番号など)になります。
葬儀など詳細が決まり次第、再度ご連絡さしあげます。
何卒よろしくお願いいたします。
(署名)
上司との関係にもよりますが、基本的にはビジネスメールの一環であるという意識で書くようにしましょう。
学校へ連絡する場合
件名:忌引きによる欠席のご連絡について
(担任名など)
◯年◯組の◯◯の母です。
母が本日死去し、下記の日数を忌引きにより欠席したくご連絡します。
故人:(故人名)
忌引き期間:◯月◯日~◯日
葬儀日程:未定
葬儀などの詳細が決まり次第、再度ご連絡します。
私あてにご連絡の際は〇〇(電話番号など)までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
(署名)
会社の場合とほぼ変わりませんが、ビジネスメールほど硬くなる必要はないでしょう。
その他忌引きについて知っておきたいこと
忌引きの取得や申請についてご説明してきましたが、基本的には必要な事項を関係する方に伝えた上で、必要な手続きを進めていくことが大事であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。特に、第一報は故人が亡くなったあとですみやかに伝えることが重要です。
このほか、忌引きに関して注意すべき点について何点かご説明しておきます。
忌引きと公休が重なった場合
忌引きが公休日、つまり週末や祝日・お店の定休日などのもともとの会社や学校の休日と重なった場合は、公休の日も忌引きの日数に含まれることが多いですが、なかには含まれないこともあるので注意しましょう。
忌引きはあくまで風習・慣習による休暇であり、有給休暇のような労働者の権利としての休暇ではありません。週末などで忌引きの取得期間がすべて公休と重なった場合は、普通は忌引きによる休暇はなしとなります。
忌引き中は有給となるのか
忌引きを取得しても、有給の日数がその分減るわけではありません。有給は労働基準法という法律で定められた休暇ですから、忌引きを理由に減らすことはできないためです。
ただしなんらかの事情で会社の規定による日数では足りなかったり、亡くなった方との間柄によって忌引きそのものの取得が認められなかったりした場合は、忌引きに加えて有給を取得するというケースは十分考えられます。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
葬儀にまつわることは、何かと注意点が多いものです。株式会社ユニクエストでは、低価格・高品質でご提供する「小さなお葬式」をはじめ、納骨方法やお墓の場所までトータルにご提案する「OHAKO」など葬儀に関するさまざまなサービスを全国でご提供しています。
葬儀に関することでお困りの際には、お気軽にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
忌引き休暇を取りたいときはなんて説明すればいいの?
親が亡くなったときは何日間休めるの?
忌引きと公休は何が違うの?
忌引きは有給休暇になるの?
忌引き休暇を取るときに気をつけることは?
メールで忌引きの連絡をしてもいい?

故人が年金受給者の場合は、すぐに年金受給停止の手続きが必要になります。ホゥ。