「お彼岸」という言葉は知っていても、具体的に何をする日かわからない方もいるのではないでしょうか。夏や秋になると「お彼岸」という言葉をよく耳にします。お彼岸の時期が来る前に、具体的な日にちを把握して準備をしましょう。
そこでこの記事では、お彼岸の時期ややるべきこと、マナーについて解説します。知識がないと恥ずかしいことや失礼な行動をしてしまうかもしれません。この記事を読んで、お彼岸の知識を深めましょう。
<この記事の要点>
・お彼岸の時期には仏壇・仏具を掃除し、お墓参りに行く
・お彼岸の時期は春分の日と秋分の日の前後7日間
・お寺で行われる彼岸会に参加する場合は、お布施を用意するのがマナー
こんな人におすすめ
お彼岸の知識について調べている方
お彼岸期間中に何をするのか知りたい方
お彼岸とお盆の違いが知りたい方
お彼岸とは?
お彼岸は、仏教の極楽浄土の考え方に由来しています。「彼岸」という言葉の意味は、「あの世にいる仏様の世界」や「悟りの境地に達した世界」です。われわれが暮らしているこの世は「此岸(しがん)」といいます。此岸から彼岸へ近づくために善行を積み、先祖に感謝する期間がお彼岸です。
仏教を由来とした日本独自の解釈がありますが、現在は行事として定着しています。お彼岸の時期は、春分の日と秋分の日の前後です。四十九日後にはじめて行う場合は「初彼岸」といいます。
時期になったら、まず仏壇に手を合わせましょう。そのあとに家族でお墓参りに行ったり、お寺の法要に参加したりします。これらすべてが先祖に感謝をし、故人をしのぶために行う行事です。
お彼岸では何をするの?
お彼岸で何をするか、事前に確認しておきましょう。これから紹介するのは、お彼岸の一般的な流れです。
各家庭の事情や宗派、地域により、内容に異なる部分があるかもしれません。しかしお彼岸でやるべきことの基本を把握するには、以下の内容をおさえておけば大丈夫でしょう。
仏壇・仏具をきれいにする
特別にしなければならないことはありませんが、先祖のためにもいつもより丁寧に掃除するとよいでしょう。お彼岸になると親戚や遠くに住む家族がお参りに来ることもあります。ホコリをかぶったような状態では気持ちよくお参りできません。仏壇と仏具を掃除して、なるべくきれいな状態にしておきましょう。
はじめに、掃除をすることを先祖にお断りをしてお参りをします。外した仏具を戻せるように現状の写真を撮る場合もお断りをしましょう。掃除は上から下へと行います。水拭きや洗剤の使用は、カビが発生する原因になるため厳禁です。傷をつけないように柔らかいタオルなどで、軽く乾拭きをしましょう。
お墓参りに行く
先祖供養としてお墓参りをします。墓地に着いたら、先祖や故人に挨拶をしてからお墓まわりの掃除や墓石などの掃除をしましょう。墓石は水をかけながら、たわしやブラシで洗います。水鉢や香立てなどもすべてきれいにしたら、最後にタオルで水気を拭き取りましょう。
きれいになった状態で「墓石に打ち水」「お供え」「焼香」「合掌礼拝」の順に行います。合掌礼拝は、墓石よりも姿勢を低くするのが礼儀です。最後にお供えものを下げ、線香の火に注意しながらきれいに片づけて帰りましょう。
お供え物をする
お彼岸にはお供えものの準備も忘れないようにしましょう。春のお彼岸には「ぼたもち」、秋のお彼岸には「おはぎ」を作る習慣があります。2つの違いの詳細は後述していますが、「ぼたもち」と「おはぎ」は同じ食べ物です。仏壇やお墓に供えたり、家族で食べたりします。
ぼたもちやおはぎは定番ですが、違うものを供えても構いません。故人の好きなものを供えるとよいでしょう。故人が好きだったお花やお菓子・果物・お酒・ジュースなどを供えることもあります。ただし、生ものやにおいの強いものは避けましょう。
先祖や家族のことを考える期間に
お彼岸をきっかけに、遠くに住む家族に会うこともあります。めったに会えない家族がいるなら、先祖や家族のことを考える特別な期間になることでしょう。先祖や終活について考える期間にすると有意義です。
普段から顔を合わせている家族でも、終活の話をしたくてもできずに悩んでいる方もいるのではないでしょうか。本当は家族が終活についてどう思っているのか気になっていても、話題にするきっかけがありません。お彼岸のタイミングなら、自然に終活の話題を出すこともできるでしょう。
お彼岸の時期
お彼岸の時期は年に2回あります。春分の日の前後と秋分の日の前後です。期間が7日間ずつあるため、いつお墓参りに行くべきなのか迷う方もいることでしょう。お彼岸は具体的にどの期間を指すのか、いつお墓参りに行くとよいのかを解説します。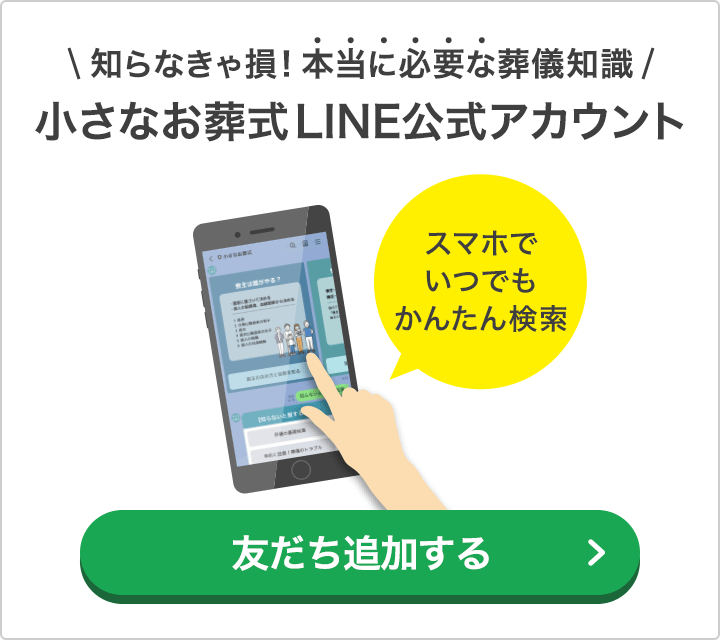
春分の日・秋分の日の前後7日間
お彼岸の期間は春分の日と秋分の日を中日として、前後3日ずつの計7日間ずつです。春分の日と秋分の日は、前年2月1日に官報によって公表されます。3月または9月の何日になるかは、公表されるまでわかりません。
(参考:『国立天文台 暦要項』)
春も秋も7日間ずつありますが、最初の日を「彼岸入り」最後の日を「彼岸明け」といいます。また、春のお彼岸を「春彼岸」秋のお彼岸を「秋彼岸」と呼ぶこともあり、家族や親戚との会話で出てくることがあるかもしれません。知識として覚えておくとよいでしょう。
春彼岸も秋彼岸も、先祖を供養してお墓参りなどをするという流れは同じです。ぼたもちやおはぎのようにお供えものの違いはありますが、やるべきことに違いはありません。
お墓参りは中日でなくてもよい
春分の日・秋分の日となる中日にお墓参りに行く方の数が多いのは、祝日で足を運びやすいからです。実際は7日間のうち、いつ行っても構いません。7日間のうちにお墓参りにいけないときは、自宅にある仏壇に線香を供えて手を合わせるだけでも大丈夫です。
地域や家庭により、中日は先祖が自宅に帰ってくる日だという考え方もあります。中日は自宅の仏壇にお参りをするのか、お墓参りに行くのかは家庭によって習慣がさまざまです。地域や各家庭の考え方に合わせましょう。
お彼岸に行われる彼岸会とは?
お寺では、お彼岸の時期に「彼岸会」を行います。多くのお寺で行われていますが、参加するべきか悩んでいる方もいることでしょう。次に彼岸会についての詳細を解説します。参加するべきか、お布施はいくらが目安かなど、彼岸会について知っておくとよいことをまとめました。参加する場合は、服装のマナーについても把握しておきましょう。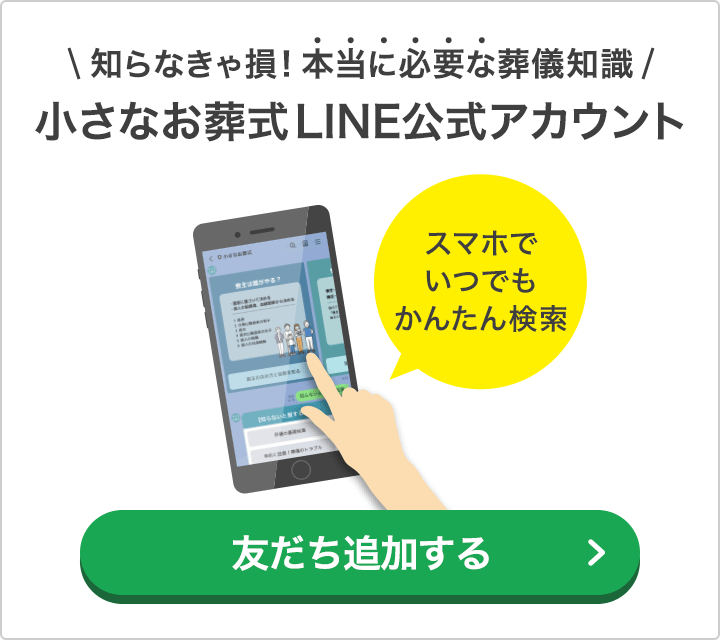
祖先の霊をなぐさめる法要「彼岸会」
先祖の霊をなぐさめるために、多くのお寺で行われている合同供養のことを彼岸会といいます。お寺の檀家(だんか)、お寺の墓地にお墓を持つ方が参加するのが一般的です。合同供養ではなく、住職が檀家の家でお彼岸供養をすることもあります。いずれにしても、彼岸会に参加する際にはお布施を用意しましょう。
お寺の彼岸会に参加する際には、お布施を3,000円~1万円ほど包みます。個別で行う場合はお布施が高くなり、3万円~5万円ほど包むのが一般的です。距離が遠い場合、お車代として別途3,000円~5,000円ほど包むこともあります。お布施の金額はあくまでも目安です。各家庭やお寺との関係性により差が出ることも、頭の片隅に入れておきましょう。
お寺で行う彼岸会の法要は、春と夏のお彼岸の期間中はつねに行われています。場所はお寺の本堂で行われることがほとんどです。場合により霊園が主催して法要会館などで行うこともあります。
参加するときの服装
一周忌までは礼服がマナーだとされていますが、13回忌以降は礼服を着ていなくても問題はありません。礼服を着る必要はありませんが、清潔感のある落ち着いた色合いの服装を選ぶとよいでしょう。黒・紺・濃いグレーの服がおすすめです。
墓地は厳粛な場所なので、肌の露出が多いタンクトップやサンダル、派手な服などは避けましょう。毛皮や本革ジャケット、アニマル柄なども殺傷を連想させることから、マナーとしてよくありません。暑い日に帽子を着用して墓地に行くのは構いませんが、お参りのときは外すのがマナーです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
お彼岸で何をするべきかをご紹介してきました。春と秋にお彼岸がありますが、やるべきことはほとんど同じです。ただし地域によってお墓参りに行く日、マナー、お供えものなどが異なります。まずは近しい親族などに確認するとよいでしょう。
お彼岸について親族に確認することが難しいのであれば、「小さなお葬式」の無料電話相談をご利用ください。「小さなお葬式」では葬儀のご相談に限らず法要やお墓のこと、終活のことなどさまざまなご相談を受けつけています。お彼岸のタイミングでご家族と終活の話をしたい方も、お気軽にご相談ください。


よくある質問
お彼岸とお盆の違いは?
ぼたもちとおはぎは同じもの?
お墓に水をかけるのはなぜ?
お花は菊じゃないとダメ?
午後にお墓参りしてはいけないって本当?
初七日とは故人の命日から7日目に行われる法要のことです。ホゥ。






























