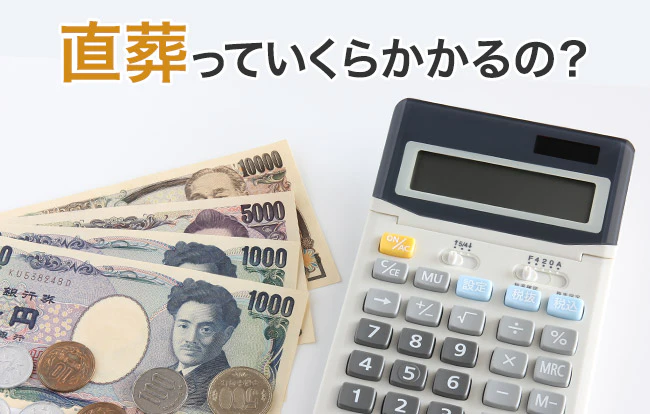真言宗は日本で主流となっている仏教の宗派のひとつです。真言宗を信仰している方や菩提寺にしている方の中には、寺院に渡すお布施の相場が気になっているという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、真言宗の葬儀を執り行う際に渡すお布施の相場についてご紹介します。寺院にお布施をいくら捧げればいいのか分からない方やお布施の内訳にはどのようなものがあるのか気になっている方は要チェックです。最後まで読めば、真言宗のお布施について詳しくわかるでしょう。
<この記事の要点>
・真言宗の葬儀のお布施の相場は50万円から100万円
・お布施の内訳は、戒名料・読経料・御車料・御膳料の4種類
・地域ごとのお布施の相場は、北海道地方で約30万円、関東地方で約55万円、九州地方で約35万円
こんな人におすすめ
真言宗の葬儀のお布施の相場を知りたい方
真言宗の葬儀のお布施を安く抑える方法を知りたい方
真言宗の葬儀のお布施のマナーについて知りたい方
真言宗の葬儀のお布施の相場は50万円~100万円
真言宗の葬儀を執り行う場合、寺院に捧げるお布施の相場は合計50万円~100万円がひとつの目安になります。金額に大きな幅がありますが、同じ真言宗でも寺院や僧侶によって異なる場合があるためです。
お布施の金額を左右する大きな要素は、戒名料といえるでしょう。戒名料を含むお布施の内容については後述するので、あらかじめチェックすることをおすすめします。
真言宗の葬儀のお布施の相場|4種類の内訳を紹介
真言宗の葬儀の際に、寺院に捧げるお布施の相場をさらに詳しく見ていきましょう。お布施の内訳は主に「戒名料」「読経料」「御車料」「御膳料」の4種類に分けられます。ここでは、それぞれの内容と相場について解説します。お布施の内容が不透明だと感じている方や詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
戒名料の相場は30万円~80万円
お布施の中で最も金額の幅が広いのが「戒名料」です。戒名料は、仏弟子になった証として故人に戒名を授けてもらうために捧げます。
戒名にはランクがあり、高いランクのものを授かる場合は捧げるお布施の金額も高くなります。戒名のランクと戒名料の相場は以下のとおりです。
・院大居士、院清大姉: 100万円~
・院居士、院大姉:90万円~100万円
・院信士、院信女:80万円~100万円
・居士、大姉:50万円~70万円
・信士、信女:30万円~50万円
ランクの高い戒名になると100万円以上の戒名料を支払う必要があるため、お布施の総額も高くなります。一般的によく使われる位号である「信士、信女」や「居士、大姉」なら比較的安く済みます。
読経料の相場は約20万円
「読経料」とは、葬儀の場で僧侶に読経していただいたお礼として捧げるお布施です。真言宗の読経料の相場は、20万円~25万円程度といわれています。
ただし、地域や寺院、僧侶によって読経料に差があるため、注意が必要です。いくらかかるか心配な方は、葬儀社や寺院に問い合わせてもよいでしょう。読経料は読経の対価ではなく感謝の気持ちとされています。心から進んで捧げる気持ちを示すことが大切です。
御車料の相場は1万円前後
「御車料」とは、僧侶に葬儀式場に出向いていただいたことに対するお礼として捧げます。交通費にあたるものと考えてよいでしょう。御車料の相場は1万円前後です。多くの場合、戒名料と読経料はお布施としてまとめて渡しますが、御車料は別途渡します。
僧侶が訪問してくれたことに対するお礼という性質上、寺院で葬儀を行う場合や僧侶を送迎する場合は、御車料を捧げる必要はありません。
御膳料の相場は1万円前後
「御膳料」とは、葬儀の際に僧侶に対して用意する食事の代わりとして捧げるお布施です。本来、葬儀が終了した後には「お斎」と呼ばれる会食の場を設けます。お斎を省略する場合に、代わりとして渡す金銭が御膳料です。
御膳料の相場は1万円前後ですが、ほかのお布施と同様、寺院や葬儀の規模によって異なります。相場は参考程度と考えて、感謝の気持ちを表すことが重要といえるでしょう。
真言宗の葬儀のお布施の相場は地域によっても異なる
葬儀の際に捧げるお布施の相場は、地域によって差があります。地域ごとの相場をご紹介するので、あらかじめチェックしておきましょう。
北海道地方:30万円前後
東北地方:50万円前後
関東地方北部:50万円~55万円
関東地方南部:55万円前後
北陸地方:40万円~45万円
中部地方:60万円前後
近畿地方:45万円~50万円
中国地方:30万円~35万円
四国地方:30万円~35万円
九州地方:35万円前後
地域によって相場には20万円以上の差があることが分かります。お布施の金額で迷ったときには自分の住んでいる地域の相場を参考にしましょう。なお、この金額は真言宗独自のものではなく、仏教形式の葬儀であれば宗派を問わず共通する相場です。
真言宗の葬儀のお布施を安く抑える方法
経済的な理由でお布施を安く抑えたいと考えている方もいるのではないでしょうか。ここでは、真言宗の葬儀を執り行う際にお布施を安く抑える方法について解説します。菩提寺がある場合とない場合に分けて見ていくので、状況に合わせてチェックしましょう。
菩提寺がある場合の倹約方法
菩提寺がある方は直接僧侶にお願いしてみるとよいでしょう。葬儀の打ち合わせの際に、お布施が用意できない理由や具体的な金額を伝えます。普段から付き合いがあれば、快く承諾してくれるでしょう。ただし、十分なお布施が用意できないときは読経の内容が省略される場合があります。
菩提寺がある場合、お布施を節約する手段が少ないのがデメリットです。正直にお願いすれば考慮してくれる可能性があるので、まずは寺院に相談することをおすすめします。
菩提寺がない場合の倹約方法
菩提寺がない場合、菩提寺がある場合に比べて大きくお布施を節約できる可能性があります。特におすすめなのは、葬儀社に寺院を紹介してもらう方法です。葬儀社と提携している寺院はお布施が安い傾向があるため、葬儀社に相談することをおすすめします。宗派にこだわりがないなら、浄土真宗の寺院に依頼するとお布施が比較的安く済みます。
真言宗の葬儀にこだわりたい場合でも葬儀社と提携している寺院に依頼すれば、多くの場合、お布施を安くできます。なるべくお布施を安くしたいと考えている方は、ぜひ葬儀社に相談しましょう。
真言宗の葬儀のお布施のマナー
真言宗の葬儀でお布施を捧げるときには守るべきマナーがあります。お布施に関するマナーは学ぶ機会が少ないため、葬儀の場で迷う方も多いでしょう。ここでは、お布施の包み方や封筒の書き方、渡し方について解説します。事前に確認しておけば、知らないうちにマナー違反になることを防げます。
お布施の書き方
お布施を白封筒や奉書紙に包んだ場合、表書きのみを書きましょう。まずは、中央より上に「お布施」、中央より下には喪主の氏名をフルネームで書きます。
お布施用の封筒を使う場合、表書きに加えて中袋にも必要事項を記入します。表書きは白封筒や奉書紙を利用するときと同様です。中袋には住所や金額を書く欄が設けられているので、記入欄に従って必要事項を書きます。金額は「金参拾萬円也」といった旧字体を用います。
筆記用具には毛筆や筆ペンを使用し、薄墨ではなく通常の墨を使うのがマナーです。毛筆や筆ペンがないからといって、ボールペンは使わないようにしましょう。
お布施の包み方
お布施の包み方にはいくつかの種類があるので、詳しく見ていきます。入手できるものに応じて、適切な包み方をしましょう。
最も丁寧な包み方といわれているのが「奉書紙」を利用する方法です。奉書紙を使う場合は、紙幣を白い中袋に入れます。白い中袋の代わりに半紙を用いてもよいでしょう。中袋を奉書紙で包み、表書きを書けば完成です。
奉書紙が入手できない場合、白い封筒を利用します。封筒は無地のものを選び、その中に紙幣を入れます。紙幣を入れたら表書きを書いて完成です。安っぽく見える薄い封筒や郵便番号を書く欄が印刷されている封筒は避けましょう。
お布施の渡し方
お布施は葬儀が始まる前か終わった後に渡します。一般的には葬儀が終わった後に渡すことが多いようです。お布施を直接手渡すのはマナー違反なので、「切手盆」と呼ばれるお盆に乗せて渡します。切手盆は葬儀社で用意していることもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
切手盆がないときは「ふくさ」と呼ばれる布を使います。この場合、ふくさにお布施を入れた封筒を包んで持参します。渡す前に封筒を取り出し、ふくさの上に乗せて僧侶に渡しましょう。いずれの方法でも、僧侶から見て正面になる向きで渡すのがマナーです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
今回は真言宗で葬儀を執り行う場合のお布施について詳しく見てきました。僧侶にお布施のことを尋ねても「お布施は気持ちです」といわれることが多く、いくら包めばいいのか迷う方も多いでしょう。お布施の相場は地域や寺院によって異なるので、記事で紹介した金額を参考にしてみてください。
小さなお葬式では寺院手配サービスも提供しており、お布施を節約したい方にも安心です。お布施や葬儀のことでわからないことがある方や専門家に質問したい方は、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



四十九日法要は、故人が亡くなってから48日目に執り行います。ホゥ。