自分のお葬式にさまざまな希望をもっている方も多いのではないでしょうか。「誰を呼ぶのか」「どのような葬儀にするのか」「墓はどこにするのか」など、望むことは尽きないでしょう。しかし、亡くなった後では細かく指示をすることはできません。
ご自身の希望を叶えるためにも、また、残されたご遺族の負担を軽減するためにも、生前に準備できることはしておくのがおすすめです。今回は、生前準備のメリットや、やるべきことを解説します。ここで確認をすれば、自分の望む葬儀を実施してもらえる可能性が高まるだけでなく、残していく家族もスムーズに葬儀の準備ができるようになるでしょう。
<この記事の要点>
・生前に葬儀準備をしたい方は、葬儀の形式や宗派、内容、希望を具体的に決めておく
・遺影写真の撮影や納骨先を事前に決めておくと遺族の負担を軽減できる
・預金を増やしたり、生前契約や葬儀保険に加入して葬儀費用を準備しておく
こんな人におすすめ
葬儀準備で生前にやるべきことを知りたい方
葬儀費用の準備を知りたい方
メリットが多い生前の葬儀準備について知りたい方
葬儀準備で生前にやるべきこと
葬儀準備において、生前にどこまで決めておけるのでしょうか。葬儀の形式ひとつとっても、数多くの選択肢があります。また自分の要望などを反映させていくためには、葬儀に関するさまざまな事柄を把握したうえで選択していく必要があるでしょう。生前に葬儀を準備するうえで、まずは決めておくべきことから考えていきましょう。
葬儀の形式を決める
まず、ポイントとなるのが葬儀の形式です。「僧侶を呼び、自宅やセレモニーホールなどができ、きちんと式を挙げる一般葬にするのか」「親族だけを集める家族葬にするのか」「儀式は一切行わず、病院や自宅から火葬場に直行する直葬にするのか」など、選択肢は数多くあります。
葬儀の形式によって予算が大きく変わるだけでなく準備するものも変わるため、まずはベースとなる形式を決めることから始めましょう。
葬儀の宗教をどうするか決める
葬儀は、その家が信仰している宗教・宗派の形式で行うことが一般的です。多いのは仏教葬ですが、葬儀には神式(神道)やキリスト教式(キリスト教)などもあります。
どの宗教で葬式を行うかは、送られる人の信じている宗教で送ります。たとえ家が仏教徒でも、本人がキリスト教を信じているのであれば、キリスト教式で葬儀を行うべきです。
無宗教者の家庭の場合、葬儀の宗教を決めておくのは特に重要です。宗教を決めていないときは残された遺族が迷うポイントとなる可能性が高いといえるでしょう。
生前のうちにどの宗教で葬儀を行うかは決めておくと、残された親族も、迷うことなく葬儀を行えます。
葬儀の内容・してほしいことを決める
葬儀の内容といっても、事細かな演出について指定する必要はありません。「どのくらいの規模にするのか」「どこで行うのか」「喪主は誰にするのか」を決める程度でもよいでしょう。
それ以外にも、特に好きな音楽や映像などがあり、葬儀のときにどうしても流してほしいなどの希望があれば、こういった内容も親族の方に伝えておきます。また、葬儀を行う場所についても希望があれば、この時点で決めておいて親族に伝えておくのが無難です。
誰を呼ぶか決める
葬儀の規模を決定づけるのは「誰を呼ぶのか」という部分です。自分が亡くなった場合、誰に連絡をするのかを決めておきましょう。
どの程度まで連絡をするかで、おおよその参列者数も想定でき、葬儀の大きさに合った葬儀会場を設定することも可能になります。希望の人数と予算の兼ね合いについて、残されることになる親族の要望も踏まえて決めておくことで、全員が納得する葬儀を行うことができるでしょう。
遺影の写真を撮っておく
近年終活の一環として取り組みの増加傾向にあるのが、遺影の撮影です。まだ元気なうちに、きれいな状態の遺影を残しておくのは、遺族にとってもありがたいことといえるでしょう。遺影の準備がないと、故人が亡くなって間もないタイミングでアルバムやパソコンのデータをひっくり返し、写真を探さなければいけません。
故人が亡くなって、悲しみの中の葬儀の準備は多忙を極めます。遺族の負担を少しでも減らすために、遺影のように事前に準備できるものは準備しておきましょう。また、遺影に関しては遺影撮影サービスを利用することもおすすめです。
納骨の方法を決める
日本国内でもっとも多いといわれる仏教葬の場合、故人は亡くなってから四十九日間かけて冥界に辿り着き、そこで初めて仏となるとされています。いわゆる「成仏をする」ということです。
お墓に納骨されるのは、成仏してからです。つまり、四十九日法要に合わせて納骨を行うのが一般的とされています。
ほかにもキリスト教式の場合、亡くなってから1か月後に行われるミサに合わせて、神式の場合五十日祭に合わせて納骨が行われます。こうした宗教家の立会いがある納骨の場合は、生前に細かいことを決めておく必要はありません。
問題は無宗教での納骨です。納骨堂や樹木葬、または特定の場所への散骨を希望する場合などは、事前に親族に伝えておくとよいでしょう。
葬儀費用の準備
生前に決めておいたほうがよいことは多岐にわたり、選択肢も数多くあります。そのための費用の準備に関しても、生前に抜かりなく行っておきたいものです。
生前にできる葬儀の準備でもっとも重要なのは、費用の確保・準備かもしれません。葬儀費用はどこにどのように保管すべきかを知っておかないと、大変な事態になりかねませんので注意が必要です。ここでは葬儀費用の準備方法としてどのようなものがあるか確認しましょう。
預金しておく
一番シンプルなのは、銀行や信用金庫に預金として保管する方法です。しかし、ここで注意すべきポイントがあります。預金口座の名義人が亡くなると、銀行や信用金庫の口座は一時的に凍結されます。この口座凍結を解凍するには、遺産相続権をもつすべての遺族の賛同が必要です。
この賛同は、口頭やサインだけではなく、印鑑証明の登録証なども必要ですので、解凍までにある程度の時間が必要で、肝心の葬儀のときに口座内の預金を使用できないというケースも考えられます。
しかし2019年7月の法改正で、遺産相続権をもつすべての人の同意がなくとも、1人の相続人の判断で、故人の口座から現金を引き出せるようになりました。この場合、引き出せる上限金額は、「ひとつの金融機関から150万円以内かつ法定相続金額の1/3以内」です。
預金に関しては家族に伝わるように、エンディングノートなどにしっかりと記載しておくようにしましょう。
生前契約する
葬儀費用として分かりやすく残す方法として、生前に葬儀社と生前契約を結ぶという方法もあります。すべての葬儀社が対応しているわけではありませんが、近年では生前契約に対応している葬儀社も増えています。
まだ生きているうちに葬儀の予約をするのは不謹慎と考える方もいるかもしれませんが、生前契約を行うことで、棺や装飾の花、会場なども本人の希望に近い形で事前に契約できるメリットがあります。
ご自宅の近所に信頼できる葬儀社がある場合、生前契約について相談してみるのも検討してみましょう。
小さなお葬式の生前契約
小さなお葬式では「生前契約」サービスを承っております。残された家族に負担を掛けないように生前に葬儀のお支払いができます。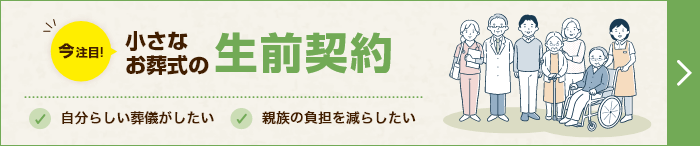
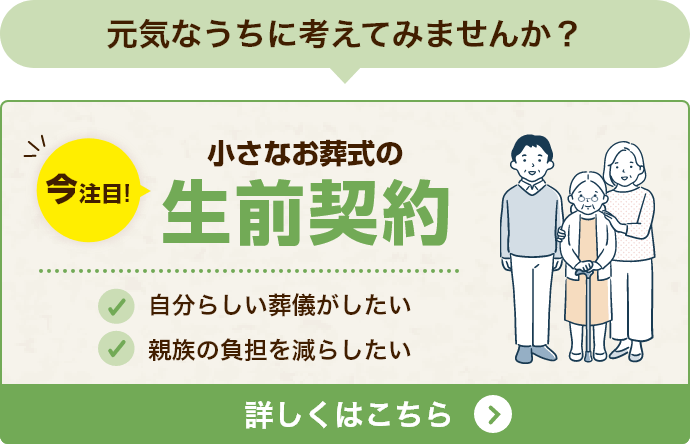
葬儀保険に入る
近年、「葬儀保険」と呼ばれる少額保険の商品も注目を集めています。葬儀保険のメリットは、医師の審査がないため、高齢者や持病のある方でも加入が可能なことです。さらに契約者が亡くなった場合、亡くなったことを署名する書類を提出すれば、早くて翌営業日には保険金が支払われます。
葬儀費用にあてるには最適な保険ですが、このような少額保険には「保険の責任開始期」が存在するので注意が必要です。保険会社と契約者の間で、保険契約が成立したとしても、1か月ほどは保険の支払い対象外となります。
不幸にも契約から1か月以内に亡くなられた場合、保険の支払いを受けられないことがありますので、契約するのであれば、早めに契約することを考えておくとよいでしょう。
互助会に入会する
「互助会」とは、正式名称を「冠婚葬祭互助会」といい、結婚式やお葬式のための積み立てを行うサービスです。互助会に加入すると、指定された葬儀会場を割引料金で利用できるなどのメリットがあります。
ただしデメリットもあり、葬儀のプランは事前に決められているケースがほとんどで、既存のタイプから選ぶ形になります。また、互助会の積立金だけでは葬儀費用のすべてを支払うことは難しく、ある程度追加で費用が必要です。
互助会の用意している葬儀プランの中に、希望にそったプランがある場合はおすすめですが、自分なりの葬儀を思い描いている方には、やや使いづらいサービスかもしれません。
メリットが多い生前の葬儀準備
葬儀の準備を生前に行っておくことには、さまざまなメリットが挙げられます。「生前から自分の死後のことについて考えるのはなんだか気分が乗らない」という方もいるでしょう。しかし、生前から自分の人生のラストについて考えておくことは、その後の人生を充実させるためにも有益な取り組みです。ここからは、生前の準備に関するメリットについて見ていきましょう。
自分の希望にそった葬儀ができる
ひとつめにあげられるメリットは故人の希望にそった葬儀を行えるということです。葬儀の規模や納骨の方法、細かいことをいってしまえば祭壇に飾り付ける花の種類まで自身の意向のままに選べます。
生前にしっかりと自分の葬儀について考えることで、葬儀でやりたいこと、やりたくないことが明確になります。自分の人生の最後を希望にそった形で幕引きできるということは、人生をよりよいものにするためにもとても重要なことだといえるでしょう。
遺族の負担を減らせる
生前の葬儀準備は、残された遺族にとっても大きなメリットがあります。故人が亡くなったとき、遺族は大きな悲しみの中にいます。
その悲しい気持ちの中で、遺体の引き取り、葬儀社探し、火葬場の日程調整、宗教者の手配、親族知人への連絡、墓所の確認、費用の準備など、多くのことをわずか数日の間に決めなければいけません。
遺族の中でも残された喪主にかかる負担は非常に大きくなってしまいますが、生前準備をしておけば、この負担を軽減することが可能です。葬儀のために決めなければならないことは、生前にできる限り決めておくとよいでしょう。
費用を抑えられる
生前に自身の葬儀について、細かい部分まで決めておくと、必然的に葬儀費用を抑えることが可能です。
遺族は葬儀に向けて限られた時間の中でいろいろなことを決めることが求められますので、複数の葬儀社から見積もりを取って比較したり、細かい部分の費用を抑えたりする交渉をしている時間はありません。
つまり、葬儀社の言い値での葬儀になってしまうケースもあり、どうしても割高感のある葬儀となってしまいがちです。費用を抑えるためにも、生前に準備することがおすすめです。
葬儀についての希望は、エンディングノートに書こう
葬儀に関しては、生前に決められるところは決めておきましょう。もちろん残される遺族の方と相談しながら決めていくのがベストですが、いざ葬儀となったときに、故人の希望をすべて遺族が思い出すというのは難しいものです。
そこで、自身の希望は、エンディングノートにまとめておくことをおすすめします。ここではエンディングノートとはどのようなものかについて詳しく解説します。
エンディングノートとは
日本国内にエンディングノートが登場したのは1990年代とされていますが、一般的に広まったのは、2010年ごろといわれています。エンディングノートは、自身の葬儀だけでなく、その後についての希望や、家系図、貴重品に関する情報、死後に連絡を入れてほしい友人の連絡先がわかるものなどを書き記しておくノートです。
葬儀社やお墓などの希望はもちろん、これまでの人生の振り返りや自身の預金、自分の大切にしているものの処分方法など、記載すべきことは多岐にわたります。
これらの事柄をエンディングノートとして1冊にまとめておくことで、自分に関するさまざまなことを整理することが可能です。親族がのちに見ても、把握しておきたい情報がわかりやすくなるという大きなメリットがあります。
遺言書との違い
エンディングノートには、故人が希望することや重要な情報を記すこともありますが、根本的に遺言書とは違い、法的拘束力はもちません。そのため、エンディングノートに遺産の分配などの重要な事柄について記入するのは、あまり意味のない行為ということになります。
きちんと法的拘束力をもつ遺言をしたい場合は、弁護士や司法書士といった法の専門家に相談し、法に則った書式で、エンディングノートとは別に残すことが必要です。
エンディングノートは無料でも手に入れられる
エンディングノートには、さまざまなタイプがあります。書店や文具店で購入することも可能ですが、無料で手に入れることもできます。
お住まいの自治体やNPO法人の中には、エンディングノートを無料で配布し、記入方法を教える教室を開いているところも少なくありません。こうした教室に参加すると、無料でエンディングノートをもらえることが多いようです。
また、葬儀社が配布したり、インターネットサイトからダウンロードできたりするものもあります。まずは無料で入手できるもので試してみるのもよいでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
生前に葬儀の準備をすることは本人のとっても、残していく家族にとっても大きなメリットをもたらします。費用の削減といった金銭面だけでなく、いざ葬儀のときに本人の希望通りにスムーズに行えるなど、遺族の心の負担軽減にも大いに役立つでしょう。
本人と家族が前向きに生前準備について話し合うことで、ひとりでは気づかなかったようなことに気づくこともあります。生前の準備では家族と足並みをそろえて取り組むとより実現可能な内容を決めることができるでしょう。
「小さなお葬式」では、生前の葬儀の準備に関するご相談も承っております。準備を進める上でわからない事柄も、まずはお気軽にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


葬儀の挨拶では、不幸を連想させてしまう忌み言葉と重ね言葉には気をつけましょう。ホゥ。






























