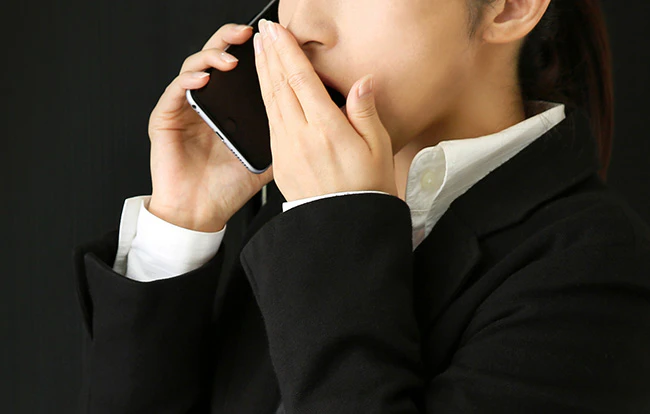人はいつか誰もが死という運命を迎えることになりますが、身寄りのない人が亡くなった場合、その後はどうなるのでしょうか。高齢化社会真っただ中の日本においては、多くの高齢者がひとり暮らしという現実もあり、先行きに不安を感じる方もいるかもしれません。
この記事では、身寄りのない方が亡くなった場合にどのような流れで埋葬まで進むのかを紹介します。
<この記事の要点>
・ 身寄りのない方が病院で亡くなると、自治体に連絡がいき、火葬や埋葬が行われる
・自宅で亡くなっても、自治体が火葬や埋葬を行う
・身寄りのない方は、任意後見契約や見守り契約などの終活を始めておく
こんな人におすすめ
もしもの時にどうすべきか気になっている方
身寄りがなく、将来に不安を感じている方
自分でできる葬儀の準備について知りたい方
おひとりさまの高齢者はどれくらいいるの?
超高齢化社会に向かっている日本には、おひとりさまの高齢者がどれくらいいるのでしょうか。孤独死は自分だけの問題でなく、今や日本社会そのものの課題でもあります。
お金があればさまざまな対策ができることは確かですが、金銭的な余裕をもてないケースも少なくありません。まずは日本全国の現状について正しく知っておきましょう。
65歳以上の約600万人がひとり暮らし
内閣府が発表した平成27年(2015年)の統計によると、男性の約192万人、女性の約400万人がひとり暮らしとなっており、多くの人が孤独死と向き合う必要があるのが現実です。これは65歳以上の人口のうち21.1%を占める割合なので、全国の高齢者のうち5人に1人はひとり暮らしをしている計算になります。
この割合は、内閣府が統計を取りはじめて以降着々と上がり続けており、昭和55年(1980)年に11.2%だった事実を踏まえれば、わずか40年に満たない期間で高齢者のひとり暮らし世帯は約2倍にまで膨れ上がってしまっているのです。2040年には24.5%にまでさらに上昇すると試算されています。
(参考:内閣府『平成30年版高齢社会白書(全体版)』)
窮乏している人も多い
続いて高齢者の経済状況を見てみますと、将来に関するアンケート調査を受けた60歳以上の方の26.8%が「家計にゆとりがなく、多少心配である」、8%が「家計が苦しく、非常に心配である」と回答しており、全体の三分の一以上の方が金銭的に窮乏していることがわかりました。
65歳以上の生活保護受給者数も、2004年には2.11%だったものが、2015年の調査では2.86%にまで上昇し、右肩上がりの増加傾向が見られます。老後2,000万円問題が話題になったのはつい最近のことですが、現実として高齢者が年金だけで食いつないでいくのは難しく、なんらかの対策が必要であることは明らかです。
(参考: 内閣府『平成29年版高齢社会白書(全体版)』)
身寄りのない人が病院で亡くなったあとの流れ
身寄りのない方が入院、あるいは事故などで病院へ運ばれたあとに亡くなった際には、埋葬までどのような流れで進むことになるのでしょうか。
病院が自治体に連絡する
身寄りのない方が病院で亡くなると、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律により、病院から各地方自治体に向けて連絡が行われます。これは、もしも行旅人が病気をしたり、死亡したりした場合には、その所在地を管轄する市町村が救護を行うよう求めた法律です。
身寄りがある方の場合は、まずは家族に連絡がいき、自宅で遺体を引き取ってもらうことが一般的ですが、それができない方の場合には、原則として亡くなった地域に遺体が安置されることになり、病院としては遺体の扱いを自治体に任せることになります。
自治体が火葬・埋葬を行う
病院から連絡を受けた自治体は、身寄りがない人であることを確認した上で、そのまま火葬や埋葬の手続きに進みます。これも法律にもとづいて行われるものであり、誰かの私情が絡んだり、特例が認められたりすることはありません。
火葬や埋葬は、いずれも死亡した市町村内で行われることになります。たとえ身分証などで本籍地や所在地がわかったとしても、結局は受け取り手が見つからないため、亡くなった地域に埋葬されることになるのです。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
身寄りのない人が自宅で突然亡くなったら
病院に運ばれた場合は速やかに病院と自治体が対応してくれますが、もし身寄りのない人が自宅で突然亡くなった場合には、その後どうなるのでしょうか。
いわゆる「孤独死」の問題ですが、今や決して珍しい話ではありません。孤独死を遂げた場合のその後について、発見から埋葬までを具体的に紹介していきます。
発見が遅れると遺体が腐敗することも
身寄りなしのまま自宅で亡くなった場合、どのタイミングで誰が発見するかは極めて不確定です。友人や知り合いが多い場合は、連絡が取れなくなったことを不審に思い気付いてくれるかもしれませんし、賃貸物件に暮らしているなら、家賃の支払いが滞ったことを不審に思われて調査が入り、そこで遺体が発見されるかもしれません。
しかし、人付き合いをほとんどしていないという方の場合や、管理費など比較的少ない費用だけが銀行口座から引き落とされる分譲マンション、あるいは戸建てに住んでいる方の場合、発見が遅れて長期間放置されてしまうこともあります。恐ろしいようにも感じますが、結果として遺体が強く腐敗するリスクも抱えることになりますし、実際にそのような事案はあとを絶ちません。
自治体が火葬・埋葬する
自宅で亡くなった場合も、基本的には病院で亡くなった場合と同じように、最終的には自治体が火葬を行い、埋葬まで済ませます。つまり、日本人は国内のどこで亡くなったとしても、同じように火葬・埋葬してもらえるということです。
ただし、自宅で亡くなり、とくに腐敗が進んだ場合には物件の特殊清掃が必要になり、状態によっては事故物件として扱われることにもなりますので、誰かに迷惑をかけることになりかねません。
身寄りのない人が終活でやるべきこと
自分自身の身を守ることは当然として、周囲の人やものに迷惑をかけずに人生を終えるために、身寄りのない方が今から進めるべき終活の具体例には何があるのでしょうか。ここでは4つのポイントで解説します。
任意後見契約の締結
任意後見契約を結べば、肉親以外の誰かを後見人として指定し、自分自身の財産を管理するように指名したり、身上監護を任せる人を指名したりできます。家庭裁判所から選任を受けた任意後見監督人の元で、指名した人物の支援を行うのが任意後見人です。
任意後見人は、認知症などの症状が進み、判断能力が衰えないうちに決定することが重要となります。将来の遺産に関する話題だけではなく、生前に決めるべき介護施設への入居の有無や、どんな介護サービスを利用するのかという点を決定するのも後見人の役割ですので、信頼できる人物に任せましょう。
見守り契約の締結
家族や親族が近くにいない場合、健康状態などになんらかの問題が生じたときに察知してくれる人はいないものの、見守り契約を締結することによってこの問題を解消できます。これは、身近な友人などをパートナーに据えて、定期的に電話で連絡を取ったり、自宅に訪問してもらって元気かどうか見てもらったりするための契約です。
法的な力は弱いため、メインとして考えるべきなのは任意後見人契約であることには変わりありません。しかし、見守り契約を交わすことにより、任意後見人契約を行うべきタイミングも掴みやすくなり、安心して老後を迎えやすくなります。
身元保証サービスの利用
老人ホームに入居する際はもちろん、病院への入院手続きを行う際にも、身元保証人をつけるように迫られることは多くなっています。しかし身寄りのない方にとっては、身元保証人を見つけることなど不可能に近い要求となるので、希望している施設や病院に入れないという問題が起こりがちです。
そんな場合に利用価値をもつのが身元保証サービスになります。これは民間業者と結ぶ有料の契約になりますが、定められた料金を支払うことによって、特定の会社が身元保証人、あるいは連帯保証人になってくれるので、ひとり暮らしで住む家が見つからないという場合にも便利です。
遺言書を書く
身寄りのない方にすれば、遺言書など書いたところで何の役にも立たないのではないかと感じるかもしれませんが、そうとも限りません。財産が残る場合、思わぬ人物が法定相続人として認められる可能性があり、意図しない人物に財産が渡るという残念な結果を招くリスクがあります。
これを避けるためには、しっかりと遺言書を残して、それを見た人があなたの意思を引き継げるように準備することが大切です。遺産を渡したい人物が思い浮かばないという場合には、特定の団体に寄付をするという意思を遺言書に記すこともできるので、必ず遺言書を作成しましょう。
<関連記事>
遺言書についてイマイチ分かっていない方へ!書き方と無効になるケースについて
小さなお葬式で葬儀場をさがす
自分でやっておける葬儀の準備
葬儀は基本的に遺族が内容を決めて執り行うものですが、誰かに任せられない状況に置かれているならば、自分で自分の葬儀の準備を進めておくことも可能です。将来の葬儀に備えて自分でできることは今のうちから準備をはじめましょう。
葬儀プランを決める
葬儀は死後に決めなくても、生前の段階からプランを決定して契約を結んでおける場合があることをご存知でしょうか。葬儀に誰を呼ぶのか、どの程度の予算で実施したいのかという点を、担当者と相談した上で決めることも可能なので、まずはお近くの業者に連絡を取ってみてはいかがでしょうか。
<関連記事>
生前契約で希望の葬儀を。安心して任せられる生前契約とは
エンディングノートの作成
遺言書には書ききれないさまざまな希望を残せるのがエンディングノートです。日記の延長線上のような形で利用する方も多く、これまでの半生を振り返ったり、今どんな心境で生きているのかを書き記したりできるものなので、死後に手に取った方は貴重な資料として読んでくれるかもしれません。
エンディングノートには、希望する葬儀の方法や、埋葬の仕方などを書いて伝えることもできます。なるべくお金のかからない方法で弔ってほしいと希望することも、反対にこれだけはやってほしいと伝えることもできますし、お墓参りにはこれくらいのペースで来てほしいといった希望を残すことも可能です。
死後事務委任契約の締結
亡くなったあとはさまざまな手続きが必要です。たとえば火葬をするためにも、市町村の役場に誰かが出掛けて書類を提出する必要がありますし、保険金を受け取るためにも、不審死ではないことを証明するための死亡診断書などの書類提出が義務付けられています。
「死後事務委任契約」を締結することで、これらの作業を誰かに依頼できるようになります。この契約は友人や知人だけでなく、弁護士や行政書士、司法書士に依頼することも認められており、死去後には必ず遂行されるので、希望どおりの火葬・埋葬が行われるか心配な場合は、契約を結んでおきましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
身寄りのない方が亡くなった場合、原則として火葬と埋葬は亡くなった市区町村の中で行われることになります。しかし友人や知人と協力すれば、遺体の発見も速やかに進めやすく、希望どおりの葬儀や埋葬を行える可能性も高くなるでしょう。
亡くなった後に友人や知人に金銭面の負担をかけないためにも、生前にある程度のことを準備しておくことは大切です。葬儀の事前相談はぜひ「小さなお葬式」にお電話ください。専門知識のあるスタッフが24時間体制でご対応いたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



故人が年金受給者の場合は、すぐに年金受給停止の手続きが必要になります。ホゥ。