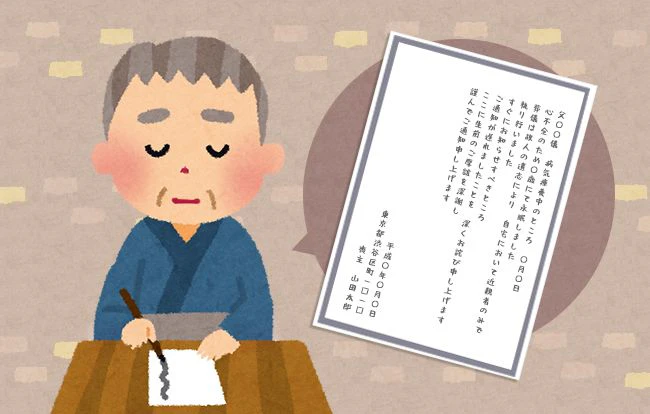身内が亡くなったとき、遺族にはやらなければならないことがたくさんあります。葬儀などのご供養に加え、役所への手続き、保険の請求、銀行とのやりとり……そして、忙しい中でも忘れてはいけないのが、運転免許証の返納です。
死亡した方が運転免許を保有していた場合は返納の手続きが必要になりますが、あまり頻繁に行う手続きではないので、わからないという方も多いのではないでしょうか。この記事では死亡した方の運転免許証を返納する手続きや方法について、詳しくご紹介します。
<この記事の要点>
・故人の運転免許証を返納する義務はないが、悪用のリスク回避のために返納するのがおすすめ
・返納手続きは、運転免許センターで行う
・返納には、死亡診断書・運転免許証・印鑑証明書・返納届(運転免許証返納申請書)が必要
こんな人におすすめ
死亡した場合に運転免許証を返納する方法を知りたい方
持ち主が死亡した車の手続きを知りたい方
免許証を返納する際の必要書類を知りたい方
死亡した方の免許証を返納する方法とは?
運転免許証は法的な身分証明書としても利用できます。また交通機関の発達していない地域にお住いの方の場合は、生活必需品として車を保有し、運転される方も少なくありません。死亡した方が免許証を持っていたのであれば、遺族の方が返納の手続きを行わなくてはいけません。
では実際に運転免許証の返納とはどのような手続きを行えば良いのか、詳しくご紹介します。
免許証は返納しなければならない?
死亡した方が運転免許証を保有していた場合は、遺族の方が代理で返納の手続きを行う必要があります。
運転免許証には期間が定められているため、更新をしなければそのまま失効とみなされます。しかし運転免許証は公的な身分証明書として使用できる効力がありますので、悪用されないよう注意しなければいけません。
顔写真が付いている・住所や生年月日の個人情報が記載されているという特徴があるため、間違ってもそのまま捨ててしまうことは避けましょう。代理の方がきちんと返納の手続きを行うことが大切です。
<関連記事>
死亡後の免許証は返納しなければならない?手続き方法は?
免許証を返納する方法
免許証を返納する方法は、最寄りの警察署もしくは運転免許センターへ出向いて行います。原則として手続きは遺族の方が行うこととされています。万が一遺族の方以外の代理人が手続きを行う場合は、必要書類などが変わることがあるので、事前に確認をしておきましょう。
警察署の運転免許窓口や運転免許センターには『運転免許証返納届』という書類があります。この書類に必要事項を記載し、所定の必要書類と併せて提出を行います。
死亡した人の手続きとして、役所に死亡届を提出し、除籍などを行ってもらいます。しかしこの手続きは運転免許証を管轄する国家公安委員会や警察とは情報を共有していません。そのため、運転免許証の返納手続きは、別途行わなくてはいけないのです。
免許証を返納する時期
死亡した方の運転免許証を返納する時期は、明確に定められていません。時期的にいつまでと決められていないので、万が一返納をしなかったとしても、罰則はありません。
葬儀から納骨までの手続き、死亡届の提出、口座や契約の解約手続きなど、身内が死亡した場合は非常に多くの手続きがあります。しかし悪用されるリスクを回避するためにも、役所の手続きが終わった時点で、早めに返納の手続きを行うことをおすすめします。
免許証の返納に必要な書類
運転免許証の返納に必要な書類は、以下の4点です。
1. 死亡した人の運転免許証
2. 死亡診断書もしくは戸籍謄本(除籍後)の写し
3. 届け出をする人(代理人)の身分を証明するもの
4. 運転免許証返納届
5. 届出人の印鑑(認印でOK)
4の運転免許証返納届は、受付の窓口にあります。事前に用意しておかなくてはいけないのは、2の死亡診断書もしくは戸籍謄本の写しです。死亡診断書は運転免許証の返納手続き以外にも使用することが多いので、予め何枚かコピーを取っておくと良いでしょう。
戸籍謄本の写しについては、死亡届を提出し、手続きが終了した時点のものが必要になります。死亡届を出したとき、一緒に戸籍謄本が必要になることを役所の窓口で伝えると手続きがスムーズです。
持ち主が死亡した車はどうする?
運転免許証を保有している人は、多くの人が車を保有しています。車は相続財産と見なされるため、売却・譲渡・廃車どの場合でも手続きが必要です。死亡した人が車を保有していた場合、遺族はどのような手続きを行わなければいけないのか、その詳細を解説します。
まずは名義変更を行う
死亡した人が車を所有していた場合はまず名義変更を行うことが必要です。売却・譲渡・廃車、どの手続きを行うケースでも、所有者もしくは使用者が故人のままでは手続きが行えないからです。
名義変更の手続きは、軽自動車の場合は軽自動車検査協会、普通車の場合は運輸支局で行います。名義変更を行わないと、時期によっては故人に納税の納付書が届いてしまうことになります。相続の協議を行う際に、所有していた車を加えることを忘れないようにしましょう。
軽自動車の名義変更に必要な書類
故人が所有していた車が軽自動車の場合に必要な書類は、次の7種類の書類になります。
| 必要な書類 | 備考 |
| 自動車検査証 | 車検証といわれるもの |
| 新使用者の印鑑 | 認印または署名 |
| 新所有者の印鑑 | 認印 |
| 新使用者の住所を証明できる書面(住民票・印鑑証明書) | 発行されてから3ヶ月以内のもの コピーでもOK |
| 故人の戸籍謄本 | 死亡の事実が記載されているもの |
| 自動車検査証記入申請書 | 軽自動車検査協会の窓口で入手可 |
| 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書 | 軽自動車検査協会の窓口で入手可 |
注意したいのは故人が車の使用者で、所有者がディーラーやローン会社になっている場合です。その場合は手続きに必要な書類が異なるので、所有者に連絡し、必要な手続きを行いましょう。
普通車の名義変更に必要な書類
故人が所有していた車が普通車の場合に必要な書類は、手続きを行う人が誰かによって書類の種類が異なります。
【新所有者となる相続人が手続きを行う場合】
| 必要な書類 | 備考 |
| 自動車検査証 | 車検証といわれるもの |
| 戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書 | 死亡の事実が確認できるもの 相続人全員が確認できるもの |
| 車庫証明書 | 発行から40日以内のもの |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の実印押印 |
| 代表相続人の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 代表相続人の実印 | 代理人の手続きの場合は代表相続人の実印が押印された委任状 |
【相続人全員が手続きを行う場合】
| 必要な書類 | 備考 |
| 自動車検査証 | 車検証といわれるもの |
| 戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書 | 死亡の事実が確認できるもの 相続人全員が確認できるもの |
| 車庫証明書 | 発行から40日以内のもの |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書 | 実印が押印されているもの |
| 相続人全員の実印 | 代理人の手続きの場合は相続人全員の実印が押印された委任状 |
自動車保険の名義変更は必要?
車の名義変更を行う際には、自動車保険(任意保険)の名義変更も必要になります。名義変更を行えば自賠責保険の名義は変更ができますが、任意保険の場合は手続きが必要です。
故人の加入していた保険会社へ連絡し、契約者を変更する手続きを依頼しましょう。多くの保険会社の場合、郵送されてくる書類に記入し、必要書類を添付すれば手続きが可能です。
第三者に譲渡する場合
相続人ではない第三者に譲渡する場合は、相続とは別の手続きになります。その際に注意したいのは、車の所有者が誰かということです。
所有者も使用者も故人であれば問題ありません。しかし故人がローンを組んで車を購入している場合、車の所有者はディーラーやローン会社になっています。所有者が異なる場合は、譲渡の前に所有者に連絡し、必要書類を運輸支局に提出することが必要です。
第三者に譲渡する場合の必要書類
第三者に車を譲渡することが決まった場合、相続人と新しい所有者は、それぞれ下記の書類を準備しなくてはいけません。
【相続人が準備する書類】
| 必要な書類 | 備考 |
| 自動車検査証 | 車検証といわれるもの |
| 戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書 | 死亡の事実が確認できるもの |
| 譲渡証明書 | 相続人全員分 |
| 印鑑証明書 | 相続人全員分 |
| 相続人全員の実印 | 代理人の手続きの場合は相続人全員の実印が押印された委任状 |
【新所有者が準備する書類】
| 必要な書類 | 備考 |
| 印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 所有者の実印 | 代理人の手続きの場合は所有者の実印が押印された委任状 |
| 車庫証明書 | 所有者と使用者が異なる場合 発行から40日以内のもの |
| ※使用者の住民票 | 所有者と使用者が異なる場合 |
| ※委任状 | 所有者と使用者が異なる場合 |
名義変更にはどのくらいの費用が必要?
名義変更の手続きには下記の費用が必要になります。
| 項目 | 費用 |
| 移転登録手数料 | 500円(運輸支局で印紙を購入) |
| 自動車保管場所証明書 | 2,000円~3,000円(自治体により異なる) |
| ナンバープレート | 1,500円程(自治体により異なる) ※希望ナンバーの場合は別途費用が必要 |
| 自動車取得税 | 車種・経過年数により異なる |
名義変更の場合、移転登録手数料以外は新所有者が負担することになります。譲渡が決まったら、車庫証明を準備しておくと手続きがスムーズです。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
家族が亡くなった場合は、悲しみに暮れる暇もなく煩雑な手続きに追われることになります。特に相続が発生した場合は、手続きや書類の作成に時間を割かれてしまうので、非常に大変です。車の相続も簡単ではありません。
小さなお葬式では、葬儀の前からその後の手続きまでを徹底的にサポートします。葬儀や手続きに関しては、わからないことが多い場合は、ぜひ小さなお葬式のサービスをご検討ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。