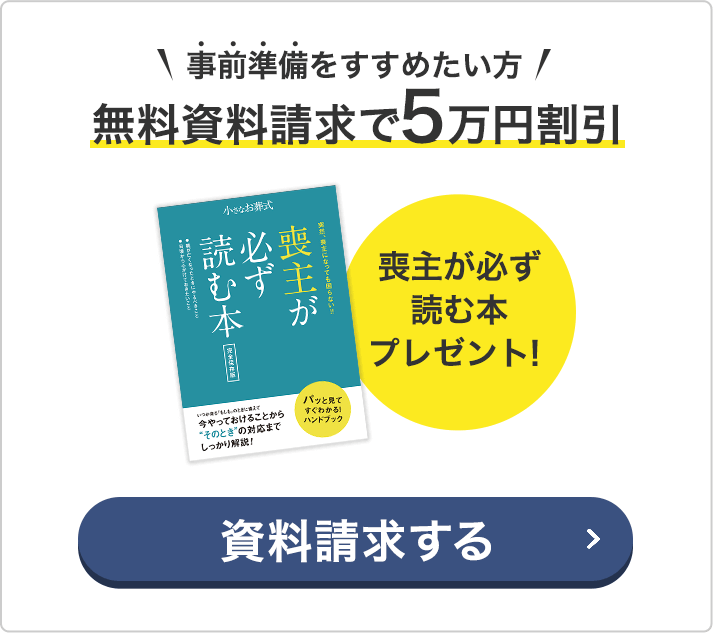近しい人を亡くしたら、遺族は「喪中」として故人を偲ぶ期間を過ごします。この間は、慶事のお祝いごとからは距離を置き、慎んだ生活を送るべきとされていることをご存知の方も多いことでしょう。
では、喪中に知人の訃報に接したとき、葬式に参列することは問題ないでしょうか。葬式以外の行事への参加とあわせてご紹介していきます。
<この記事の要点>
・喪中に他の葬式に参列することは基本的には問題ない
・葬式の参列を断る場合は、喪中のため出席できないことを伝える
・喪中期間には四十九日法要を執り行う
こんな人におすすめ
喪中の間に知人の訃報を受けた方
喪中にほかの葬儀や慶事に参列してよいかお悩みの方
喪中に控えるべきことを知りたい方
喪中とは?
もともと神道信仰に由来し、わが国独自の文化とも言われる喪中は、長きにわたって続けられることで習慣化されてきました。身内に死者が出た翌年の年賀を欠礼する旨の挨拶である「喪中はがき」などはその具体例の一つであり、受け取ったことがある方も少なくないことでしょう。
ここでは、私たちの生活に深く根付いている喪中について、改めておさらいしてみましょう。
喪中とは喪に服す期間のこと
喪中とは、近しい人を亡くしたときに故人を偲ぶとともに、死別の悲しみから立ち直るための期間を言います。
期間の目安は1年間とされるのが一般的です。この期間は慶事との関わりを避け、慎んだ生活を送るべきとされており、このようなふるまいを「喪に服す」といいます。
これは死を「穢れ(けがれ)」とみなし忌み嫌う神道からくる考え方であり、かつては喪中には家内でも喪服を着て、社会とは距離を置き、穢れが外に出ていかないよう閉じこもって過ごすのが一般的でした。しかし、現在は後述するように、価値観・ライフスタイルの変容とともに、喪中の生活にかけられる制限も緩やかなものに変わってきています。
忌中との違い
喪中と近しい言葉に「忌中」があります。どちらも神道からくる考えですが、忌中は四十九日法要の忌明けまでとされ、穢れを避けるために社会との関わりを厳しく慎むべきであるという意味合いがより強い期間といえます。
ただ、実際は喪中も忌中も「身を慎む期間」であることに変わりはなく、心構えや過ごし方に違いはありません。両者を区別する実益は、その期間にあります。
忌明けとなる四十九日法要の機会にあわせて埋葬や納骨が行われることが多いので、遺族や親族にとっては気持ちに一区切りつけるという意味合いにおいて、忌中の意味は小さくないといえるでしょう。
喪に服すべき人と期間について
喪中の期間については、一周忌、すなわち1年間が目安になります。ただ、より細かい定義としては、喪に服すべき人と期間は、故人との血縁関係によって変わってくると一般には認識されています。
地域や家族形態によっても変わってきますが、一般的には、故人から2親等以内の親族が喪に服すべき続柄にあるとされています。以下、主な続柄とその喪中期間についてご紹介します。なお、配偶者には親等がありませんので、0親等として扱います。
0親等・1親等
配偶者・父母・義父母 : 12ヶ月~13ヶ月
子ども : 3ヶ月~12ヶ月
2親等
祖父母・兄弟姉妹:3ヶ月~6ヶ月
以上はあくまで目安です。親等の近い・遠いに関わらず、生前の故人と深いつき合いがあったり、同居期間が長かったりしたというような事情がある場合に、自ら進んで喪に服することを妨げるものではもちろんありません。
逆に、2親等である祖父母の死に際して、「同居していないので喪中にはしない」といった例が増えてきていることもまた事実です。
喪中に他の葬式に参列してもよいか?
自分が喪中にあるときに、知人の訃報に接することも当然あるでしょう。そのようなとき、葬式に参列してもよいでしょうか。
基本的には問題ない
ご紹介してきた通り、「穢れを避けるために、社会との関わりを慎んだ生活を送る」というのが喪中のそもそもの趣旨でした。したがって、身内の死に遭って間もない人間が、厳粛なセレモニーである葬式に参列してはいけないことのように感じられる方もいるでしょう。
しかし、喪中に他の葬儀へ参列することは、慶事に出席するのとは意味合いが異なりますので基本的に何ら問題はないとされています。とくに、身内の葬式に参列して下さった方が関係する葬儀の場合、むしろ参列するのが正しいマナーとも言えます。
また、式典後の会食についても、故人を偲ぶための集いですから、節度を持って出席する限り問題ないでしょう。ただし、地域によっては難色を示されることもあります。迷った際は事前に確認しておくとよいでしょう。
出席の際に喪中であることを伝えるべきか?
葬式に出席した際に、喪中であることを自ら進んで申し出る必要はないとされています。事情を知る先方から出席へのお礼やねぎらいの言葉をいただいたときには、きちんと挨拶を返しておくとよいでしょう。
忌中期間ではどうか?
忌中期間についても、弔事である葬式への参列は問題視されないのが一般的です。
ただし、先述した通り、地域の慣習により参列がタブー視されることもあり得ます。したがって、同じ喪中とはいえ、故人の死後まだそれ程時間が経っていないという忌中の時期的な特徴に考慮すれば、参列するかしないかの判断はより慎重になった方がよいでしょう。
一般的に49日間とされる忌中ですが、その一般的な期間は、宗教や故人との関係性により異なるものとされています。たとえば、日本でも多くの信者がいるキリスト教では、没後およそ1ヶ月後を故人への区切りのタイミングと捉えています。
したがって、まず忌中の期間を確認し、そのうえで参列が問題ないかを先方、あるいは年長者など事情を心得ていそうな周囲の方に尋ねるのが確実です。
喪中に他の葬式に参列したくない場合の対応方法
基本的に問題ないとされる喪中の他葬式への参列ですが、故人の死による精神的ダメージが癒えていなかったり、喪中期間は故人の死を悼む態度を貫きたかったりする理由で、そもそも参列する気になれないという方もいらっしゃるでしょう。ここでは、そのような場合の対応方法をご紹介します。
喪中のため出席できないことを先方に伝える
葬式を執り行う旨の知らせを受けたにもかかわらず参列を控えるのであれば、喪中のため出席できないことを、前もって先方に伝えておきましょう。
その際、欠席の理由を婉曲的に伝えたりはせずに、自らの心中を率直に表すことが大切です。先方も自身と同様に身内の不幸に向きあっている立場なので、きちんと伝えれば理解してもらえるでしょう。
供花や香典とともにお悔やみの手紙を出そう
訃報に接したわけですから、参列が叶わないとしてもお悔やみの気持ちを伝えることを疎かにしてはいけません。
葬式当日には、供花やお供え物、そして香典を送ります。香典を包む額については、故人との関係性やこちらの葬儀のときに先方からいただいた金額などを踏まえて決めるとよいでしょう。
そして、故人を悼む心情と、参列を控えるお詫びの気持ちを言葉にして先方に伝えることも大切です。葬式当日に弔電を打つだけでなく、お悔やみの手紙をしたため、忌明け、もしくは喪が明けた頃に改めて弔問する意思がある旨を伝えるとよいでしょう。
代理の参列者をたてる
喪中で自分が参列する気になれないときであっても、代理の参列者をたててお悔やみの気持ちを伝えることはできます。自分と故人との関係性をよく知る人であれば、自らが参列する場合と遜色ない役割を果たしてくれることが期待できるでしょう。
また、その際に供花を頼んだり、お香典を預けたりもできます。そのうえで、代理の人に喪中により参列を見合わせた旨を伝えてもらえれば安心です。
喪中にやるべきこと
慎んだ生活を送るべきとされる喪中期間ですが、一方ではやるべきことが思いのほか多く、時間が過ぎる速さを実感させられることが少なくありません。ただ、そのような慌ただしい中にあってもきちんと行っていくべきことがいくつかあるため、ここでしっかり押さえておきましょう。
四十九日法要を執り行う
四十九日法要は、故人の死に関わる一連の行事の中でも葬儀と並び、特に重要度が高いものです。仏教ではこの日をもって亡くなった方の次の生まれ変わり先が決まるとされます。したがって、昔から、故人ができるだけよい世界に辿り着けるようにと、盛大に法要が執り行われてきたのです。
四十九日法要により遺族は忌明けを迎え、埋葬や納骨を済ませることで気持ち的にも1つの区切りをつけることができるでしょう。故人を亡くしてからこの日まではなすべきことが多いため、できれば葬儀の段取りを組む際に日程を押さえるなど、早めの対応が肝要です。
香典返しをする
四十九日法要を終えたら、「香典返し」をします。香典は葬儀のときにいただいたものなので、いただいた金額の半額~3分の1とされる香典返しを、なるべく早く済ませたいと思われる方も多いでしょう。実際に、昨今は葬儀当日の「即返し」も増えてきています。
ただ、昔から伝わる死と穢れの捉えられ方により、忌中の香典返しは適当ではないとされる価値観はいまだ根強いものがあります。
また、遺族にとっても、忌明けになる四十九日法要後は、諸手続きがある程度片付き、気持ちの面でも一息つける時期でもあるため、このタイミングで香典返しをすることが習慣として定着しているのです。
喪中はがきを出す
親戚や故人が懇意にしていた友人などで、毎年年賀状のやりとりがあった方に対しては、喪中はがきを出すことも忘れないようにしましょう。
どこまでの間柄で出す対象を線引きすべきかですが、喪中は私事に関わることですから、取引先など仕事上のみのつき合いであれば、通常は出す必要はないでしょう。
なお、出すタイミングの目安としては、11月中旬から遅くても12月初旬までがマナーです。これは、相手方が年賀状の準備に取り掛かる前に届けられる必要があるためです。
結婚式など慶事の予定があるときは?
では、もともと結婚式など慶事の予定があるときに喪中が重なってしまったらどうすべきでしょうか。詳しく見ていきましょう。
出席は控えるのがマナー
お葬式とは異なり、結婚式やお祝いパーティーといった慶事への出席は控えるのがマナーです。
ただし、最近では、事情を知っていても招待する側が出席を強く望んだり、故人とそれ程近しい関係になかったりなどの事情があれば、出席しても問題ないという考え方も有力になりつつあります。
一概に言えませんが、周囲の人間を含め、先方の了解が確実に得られるなどの場合であれば、出席しても問題ないケースもあります。
執り行いは故人との関係性から判断
慶事の執り行いについても、出席と同様に控えた方がよいでしょう。通常はキャンセルするか、喪中明けに延期するかの選択を検討しましょう。
出席の場合は、招待を断っても先方の理解と、別の機会に改めてお祝いを行えば問題はありません。しかし、執り行いの日程を変更すれば、キャンセル料や式場との日程調整といった問題が生じますし、応じてくれた方々のスケジュールにも影響を与えます。
このため、故人との関係性や年齢などの諸事情に応じて判断し、予定どおりの日取りで執り行い、場合によっては規模を縮小したり、派手さを抑えたりといった形で喪中の気持ちを表そういう例も見られるようになってきています。
「忌明け」が区切りになりつつある
慶事への向き合い方としては、「忌明け」である四十九日以降であれば、出席したり、執り行ったりしても問題ないという考え方も近年広がってきています。
これまで見てきた通り、忌明けを境に対応の仕方を変えていってもよいのではないかという考え方は、喪中における葬式への参列の可否においても浸透してきています。
喪中に控えるべきこと・許されること
葬式や慶事の他にも、喪中に控えるべきこと・許されることの判断が難しい事柄は少なくありません。ここでは、それらを具体的にご紹介します。
神社・寺院への参拝
神道では死を穢れ忌み嫌うので、喪に服している人間の神社への立ち入り・参拝は許されていません。ただ、忌明けすれば可能です。神道における忌中は50日とされていますが、詳細は参拝したい神社に確認してみることをおすすめします。
一方、穢れの観念を持たない寺院への参拝は忌中であっても問題ありません。
お中元・お歳暮・時候の挨拶
お中元・お歳暮・時候の挨拶などは、いずれもお祝いの気持ちを込めてやりとりするものではありません。したがって、喪中にこれらを行っても問題ありませんし、先方が喪中であっても同様です。
ただし、お中元・お歳暮の品につける熨斗(のし)には注意が必要です。通常の紅白の水引ではなく、白地または無地の包装にして贈りましょう。
ホームパーティー・旅行・飲み会
社会生活を送っていれば、ホームパーティー・旅行・飲み会など、友人や取引先との関係上参加したいイベントも多々あることでしょう。たしかに一見すると、参加するのは喪中にふさわしくない行動のように思われるかもしれません。
ただ、近しい人を亡くしたばかりのときには、癒しや息抜きも大切です。たしかに、結婚披露宴の二次会として催される飲み会のような、祝いごとでの賑やかな場への参加などは避けるべきでしょう。
しかし、現代は喪中であるという事情を知らせたうえで、知人同士で気軽に食べたり飲んだり、旅行に出かける程度の遊びであれば、許容範囲内の活動になりつつあります。
喪中についてもっと詳しく知りたい方はこちら
この記事を読んで「もっと喪中について詳しく知りたい」「◯◯の部分がよくわからなかった」という方へ向けて、喪中に関連する内容を網羅的にまとめた記事をご用意しました。ぜひこちらもあわせてご確認ください。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
この記事では、喪中に他の葬式に参列することの可否を中心として、喪中や忌中の意味やその期間の過ごし方についてご紹介してきました。
時代の流れとともに喪に服すべき時期の過ごし方が変わってきていることは事実です。ただし、肝心なことは、喪中には慎ましい生活を送りつつ、故人を偲ぶ気持ちを失わずにいることです。
この点を踏まえている限り、たとえ見た目の過ごし方が時代とともに変化していくとしても、喪中における新しいスタンダードが形づくられていくことになるでしょう。
「小さなお葬式」では、お葬式にまつわる皆さまからのあらゆるご相談に応じられるサービスを整えています。まずはお気軽にお問い合わせください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



初七日とは故人の命日から7日目に行われる法要のことです。ホゥ。