故人を供養する方法はさまざまありますが、永代供養もその1つです。永代供養のなかにも種類が複数あるので、メリット・デメリットを理解したうえで自身にあった種類の永代供養を選ぶことが大切です。
今回は、永代供養の選び方や選ぶ際のポイントを紹介します。改葬の手順や宗派ごとの永代供養についても解説しているので、永代供養を検討している方はぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・「永代供養」とは、遺族に代わりお寺や霊園が遺骨の管理や供養を行うことです
・永代供養のメリットは、遺族が遺骨を供養する必要なく費用が安価である点です
・永代供養のデメリットは、個別の墓石がないことや、契約内容や費用が寺院や霊園によって異なるです
こんな人におすすめ
永代供養をお考えの方
永代供養の種類や違いを知りたい方
墓じまい・改葬の手順について知りたい方
永代供養とは?
永代供養自体は古くからある供養方法なので、耳にしたことがある方も多いでしょう。しかし、一般的なお墓との違いや供養の方法については詳しく知らない、よく理解していないという方も少なくありません。ここからは、永代供養の基本的な情報について紹介します。
永代供養の意味
先祖代々のお墓があっても、お墓が遠かったり管理者が高齢になってしまったりしてお墓参りに行けない家庭もあるでしょう。そんな遺族に代わり、お寺や霊園が遺骨の管理や供養を行うのが「永代供養」です。
遺族や親族がお墓の管理を継承する必要がないので、お墓の後継者がいない方や身寄りのない方でも永代供養を選択できます。
永代供養墓と一般のお墓の違いは?
一般的なお墓は、お墓の後継者がいなくなってしまったタイミングで墓じまいを行う必要があります。一方で、永代供養墓はお寺や霊園が代わりに管理・供養をしてくれるため、お墓の管理者がいなくても墓じまいを行う必要はありません。
永代供養墓と一般的なお墓の違いは、以下のようになります。
| 内容 | 永代供養墓 | 一般的なお墓 |
| 管理 | お寺や霊園がしてくれる | 管理者がいなくなると合祀墓に埋葬される |
| 費用 | 初期費用を支払えば管理費などは不要 | 定期的な管理費やお布施の支払いが必要 |
| 檀家 | ならなくてよい | ならなくてはいけない |
永代供養の供養方法は?
永代供養における供養方法は大きく2種類に分けられます。1つ目は骨壺に入れた遺骨をひとつひとつ納骨する方法です。お寺や霊園が決めた期間は個別の納骨スペースに遺骨を保管して、その後合祀されることが一般的です。
2つ目は、はじめから1つの場所に合祀する方法です。骨壺から遺骨を取り出して1ヶ所にまとめて供養します。多くの方の遺骨を1ヶ所に納められる反面、遺骨が他の方のものと混ざってしまうので、供養後に取り出すことができないというデメリットも存在します。
永代供養のメリット
永代供養をするメリットとして挙げられるのは、次の4点です。
・寺院や霊園に供養・管理を任せられる
・新しく墓を建てるより費用を抑えられる
・宗派・宗旨を問われない
・利便性が高い
寺院や霊園に供養・管理を任せられる
供養と管理は基本的に寺や霊園が行ってくれるので、ご自身で管理をする必要がありません。ただし、管理先によっては供養の回数や頻度が決まっているので、故人の命日など、希望する供養の時期がある場合は事前に確認しておきましょう。
新しく墓を建てるより費用を抑えられる
合同墓の場合は墓石代がかかりませんし、墓地の使用料なども安くなります。そのため、一般的な個人墓よりも安く利用することができます。
宗派・宗旨を問われない
永代供養墓の場合、宗派や宗旨を問われず、誰でも利用することができます。ただし、寺によっては檀家になることを条件としている場合もあるので確認が必要です。
利便性が高い
交通の便が良いところに立てられていることが多いです。多少駅から遠くても、駐車場が完備されていることが多く、お参りに通いやすい点もメリットとしてあげられます。
永代供養のデメリット
ご遺族が管理を続けることが難しい場合には永代供養を選びたいと思われる方も多いでしょうが、以下のようなデメリットが存在することも、忘れてはいけません。
・合同墓では遺骨を取り出すことができない
・弔い上げまでの供養となることが多い
・親族の説得に時間がかかる場合がある
合同墓では遺骨を取り出すことができない
永代供養で預かったご遺骨は、多くの場合「合同墓」や「合祀墓(ごうしぼ)」と呼ばれる、共同で使う墓で管理されます。この場合は他の人と一緒に骨を埋めることになるので、再び遺骨を取り出すことができません。親族に相談せずに決めると後々トラブルになる可能性があるため、合同墓を検討するのであれば親族と相談した上で決めるようにしましょう。
弔い上げまでの供養となることが多い
将来的に合祀になることを理解しておきましょう。多くの場合、33回忌などのタイミングで合祀されることを知った上で依頼することをおすすめします。
「小さなお葬式」では、宗派不問・全国対応のOHAKO-おはこ-の永代供養サービスをご用意しております。個別合祀などの安置方法や個別安置期間など、ご希望に沿った永代供養サービスをご利用いただけます。
親族の説得に時間がかかる場合がある
永代供養墓は古くからあるものなので、親族のなかには「身寄りのない方、寂しい方が入るためのお墓」という先入観を抱いている方もいるかもしれません。自分の親族のなかに永代供養墓に入ることに抵抗を持つ方がいると、説得に時間がかかったり理解してもらえなかったりすることもあるので注意が必要です。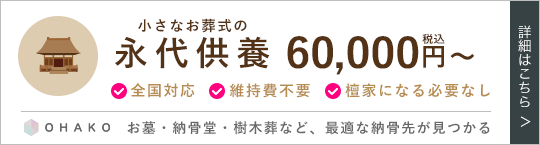
永代供養墓の種類
一口に永代供養墓といっても、複数の種類が存在します。ここでは、どのような種類があるのか確認しましょう。
永代供養墓には屋内型・屋外型がある
永代供養墓は屋内型と屋外型の2タイプがあります。屋内型・屋外型の2つの特徴・違いは以下の通りです。
屋内型
・霊廟(れいびょう)型:上段に仏壇があり、下部に骨壺を納骨する
・納骨塔型:石でできた塔のモニュメントの地下部分に納骨をする
・室内ロッカー型:ロッカーや棚のような場所のなかに1つずつ骨壺を納める
屋外型
・納骨壇型:総石造りの建物が設置されており、そのなかに納骨する
・納骨塔型:納骨壇型とほぼ同じで、塔型のモニュメントの下に納骨する
・墳陵(ふんりょう)型:前方後円型の古墳のような形の合同墓に納骨する
安置方法によって3種類に分けられる
「永代供養=合祀墓」というイメージを持つ方も多いかもしれませが、永代供養の安置方法は個別・集合・合祀の3種類に分けられます。それぞれの特徴は以下の通りです。
・個別タイプ:納骨堂やロッカー式の永代供養墓で、遺骨を個別に納骨できる
・集合タイプ:樹木葬と同じように、一ヶ所に複数の遺骨を納骨する。骨壺のまま埋葬するのが特徴
・合祀タイプ:遺骨を骨壺から出して、他者の遺骨とともに納骨する。一度納骨した遺骨は取り出せない
永代供養にかかる費用
永代供養を検討する方は費用についても気になるでしょう。永代供養の費用は、納骨タイプによって異なります。
単独墓の費用の目安
遺骨を個別で納める「単独墓」の費用の目安は、50万円~150万円ほどです。シンボルとなる墓石などにお金がかかるため、ほかの2種類よりも費用が高いケースが多いでしょう。
集合墓の費用目安
樹木や石塔などのシンボルを共有して納骨は個別に行う「集合墓」の費用の目安は、20万円~60万円ほどです。ひとつひとつの遺骨を納めるための場所が必要な分、費用はかかりますが、単独墓よりも大きく費用を抑えることができます。
合祀墓の費用の目安
骨壺から遺骨を取り出して1ヶ所に納骨する「合祀墓」の費用の目安は、5万円~30万円です。個別の納骨スペースが必要なく管理の手間もかかりません。永代供養料のみを支払えばよいことが多く、永代供養墓のなかでもっとも安価に供養できます。
永代供養墓の選び方のポイント
永代供養の「永代」というのは未来永劫という意味ではありません。お寺や霊園ごとに供養の期間が決められており、33年程度が一般的と言われていますが、依頼先に相談することで希望の年数で供養してもらえることもあります。管理方法が寺院や霊園によって異なるため、検討する際に確認するポイントをご紹介します。
1. 供養方法
永代供養墓には、大きく2つに分けて、お骨を個別に供養する「分骨型」のものと、お骨を他の方と一緒に供養する「合祀(ごうし)」の2種類があります。合祀の場合は費用負担が小さいというメリットがありますが、一度、お骨を納めてしまうと取り出すことができないことが注意点になりますので、親族の考えに合うかどうかを検討しましょう。
2. 合祀するまでの期間
永代供養墓の多くが、分骨型での供養は33年や50年などの一定期間を区切りとして、その後は合祀(他の方のお骨と一緒になって)で供養する形式を取っています。その期間は様々ですので、確認したうえで選ぶようにしましょう。
3. お寺や運営者の供養に対する考え方
永代供養は、将来に渡って末永く供養をしてもらうことになります。そのため供養を任せるお寺や運営者が、どのような考え方を持って供養に取り組まれているかを確認することも大切です。
4. 場所や利便性
管理を第三者に任せられるとはいえ、遠い場所の永代供養墓を選ぶとお墓参りの際に不便です。自宅の近くで交通アクセスがよい、バリアフリーに対応している、景色がよいなど、永代供養墓の立地や利便性にも注目しましょう。
5. 費用や維持費
永代供養墓は初期費用を支払えば、管理費やお布施などは不要なケースが多いです。しかし、なかには定期的な維持費やお布施が必要な寺院、霊園も存在します。「遺族が把握していなかった」「天涯孤独で支払える方がいなくなってしまった」ということにならないように、費用内訳や追加費用などについては事前に細かく確認しましょう。
永代供養墓に変更するための墓じまい・改葬の手順
現在一般の個人墓を使っている方で、永代供養墓に変更したいという場合の手続きを、簡単にまとめました。
1. 役場で「改葬許可申請書」をもらい、各項目に記入する
2. 使用する永代供養墓のある寺から「使用許可証」をもらう
3. これらを持って役場へ行き、「改葬許可証」を発行してもらう
4. 今までの寺で「※魂抜き」をしてもらい、墓地を整理する
5. 「改葬許可証」を寺に提出し、永代供養墓へ遺骨を移す
※「魂抜き」は墓から霊魂を抜き取るための儀式です。墓石は石材店などに取り払ってもらいます。
【浄土真宗・曹洞宗】宗派ごとの永代供養
どの宗教・宗派でも永代供養を選択できるのか気になる方もいるかもしれませんが、基本的に宗派による制限はありません。
曹洞宗では「葬儀後に故人が仏の弟子になる」という、一般的な仏教の宗派とはやや異なる思想がありますが、希望すれば特に問題なく永代供養墓に入ることができます。
しかし、そもそも浄土真宗には「永代供養」という考えがありません。浄土真宗の思想では、亡くなった方は浄土へすぐにたどり着いて成仏できるので、供養そのものをしないからです。とはいえ、浄土真宗の方もお墓を所有するので、永代供養をしたいと思えば曹洞宗の方と同様に永代供養墓に入ることができるでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
永代供養には後継者がいなくても供養できるメリットがありますが、遺骨を取り出すことができなかったり親族の説得に時間がかかったりしてしまうデメリットもあります。自身の永代供養を希望する場合は、家族や親族の方とよく相談してからお墓のタイプなどを選択しましょう。
「小さなお葬式」でも永代供養墓に関するご相談を承っております。葬儀はもちろん、お墓に関する疑問にも24時間365日対応のお客様サポートダイヤルにて、知識豊富なスタッフがお答えいたします。お気軽にご相談ください。


訃報は、死亡確定後、なるべく早く届けることが大切です。ホゥ。



































