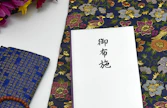33回忌とは、亡くなった年から32年後に行う年忌法要のことです。長い時間が経過してから営む法要であるため、どのように執り行われるのかわからないという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、33回忌法要の基礎知識を紹介します。お布施の金額の目安や袋の選び方、渡す際のマナーなども解説するので、ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・33回忌のお布施は、自宅やお寺で行う場合1万円~5万円程度が目安
・お布施は奉書紙を使用した包み方が正式であるが、白い無地の封筒や不祝儀袋で代用できる
・33回忌を弔い上げとするケースが多く、33回忌は重要視される法要のひとつ
こんな人におすすめ
三十三回忌のお布施の目安について知りたい方
香典袋の選び方について知りたい方
お布施を渡すときのマナーについて知りたい方
33回忌とは?
33回忌は、故人が亡くなってから32年目に行われる法要です。法要の回数は、亡くなった年を1年目と数えるため、32年目に33回忌を執り行います。年数の数え方に悩んだ際には、「亡くなってからの経過年数から1を引く」と覚えておくと便利です。
33回忌は遺族のみで執り行う場合もありますが、故人と関係が深かった友人を招くこともあります。また、最後の年忌法要として盛大に執り行うケースもあるでしょう。
33回忌のお布施の目安
33回忌のお布施の目安がわからず悩んでいる方もいるかもしれません。お布施の金額の目安は、執り行う場所や宗派によって異なります。また、地域や故人との関係性、親族の考え方でも金額は異なりますが、ここではおおよその目安をケース別に紹介します。
自宅で行う場合
自宅で33回忌を執り行う場合のお布施の目安は1万円~5万円程度といわれています。この金額はほかの年忌法要のお布施の目安とほぼ変わりません。
お布施とは別に、僧侶に自宅まで来てもらうための交通費として「お車代」が必要です。法要後の会食に僧侶が参加しないときは、「御膳料」も用意しましょう。僧侶が会食に参加する場合、御膳料は不要です。
お寺で行う場合
菩提寺で33回忌を行う場合も、お布施の目安は1万円~5万円ほどです。
自宅と違って僧侶に来てもらう必要がないため、お車代は不要です。会食を別の会場で行う場合は僧侶は同席しないことが多いので、その際は御膳料を渡す必要があります。
浄土宗や浄土真宗の場合
浄土宗や浄土真宗の場合は、お布施に対する考え方が他の宗派と異なるため、注意が必要です。お布施は僧侶への謝礼という考え方が一般的ですが、浄土宗や浄土真宗では仏様への感謝の気持ちを表すものと考えられています。
したがって、金額はきまっておらず、感謝の気持ち包めばよいとされています。目安は3万円前後といわれていますが、地域やお寺によっては金額がきまっている場合もあります。可能であれば、事前に確認するとよいでしょう。
曹洞宗の場合
臨済宗とともに、禅宗の2大宗派とされる曹洞宗のお布施の目安は3万円~5万円で、他の宗派とほとんど変わりません。日本で信仰している方が多い真言宗・日蓮宗・天台宗のお布施の目安も3万円~5万円程度です。
ただし、お布施には地域差があるので、前もって確認しておくと安心です。
お布施以外に渡す金銭
お布施以外に渡す金銭には、「お車代」と「御膳料」があります。お車代は僧侶に自宅に来てもらう際の交通費で、5,000円~1万円程度が目安です。ただし、遠方の場合は距離に比例して上乗せします。お寺で法要を行う場合には必要ありません。
御膳料は僧侶が法要後の会食に参加しないときに渡すお金です。目安は5,000円~1万円ですが、僧侶が会食に参加する場合は不要です。
33回忌におけるお布施のマナー
33回忌のお布施を渡す際にはさまざまなマナーがあります。お布施を包む袋の選び方や書き方を知って、正しい作法で渡しましょう。ここからは、袋の選び方や表書きの書き方など、基本的なお布施のマナーについて解説します。
袋の選び方
お布施の包み方として正式なのは、奉書紙を使用した包み方です。奉書紙とは、和紙の種類のひとつで、昔から大切なことを伝えるときや進物を贈るときに用いられてきました。弔事でも、弔辞を書いたり香典やお布施を包んだりする場面で使われます。
お世話になるお寺にきちんと誠意を伝えたいのであれば、奉書紙を使用するとよいでしょう。奉書紙を用意するのが難しい場合は、簡易的な方法として白い無地の封筒や不祝儀袋で代用できます。
表書きの書き方
お布施を入れる袋の表書きは「お布施」「御布施」が一般的です。他にも、神道の式年祭では「御玉串料」「御祭祀料」と書く場合があります。何も書かずにお渡ししても問題ありません。
ただし、浄土宗や浄土真宗はお布施の考え方が異なるため注意が必要です。浄土宗や浄土真宗におけるお布施は仏様への感謝の気持ちと考えられています。そのため、「志」や「寸志」など僧侶やお寺に対して感謝を表す書き方はしません。
葬儀に持参する香典袋の表書きは、薄墨で書くのが一般的ですが、お布施の表書きには濃墨の筆や筆ペンを使用します。
名前の書き方
表書きを書いた下の段には、お布施を包んだ方の名前を書きましょう。法要を執り行う施主の氏名、もしくは家の名前を「○○家」と書くのが一般的です。
また、奉書紙や不祝儀袋のように中に入れる袋がある場合は、中袋にも名前を書きます。名前を記入する場所は、裏面の左側です。名前と一緒に、郵便番号や住所も記載します。電話番号の記入欄があれば漏れなく記入しましょう。
お金の入れ方
お布施は慶事と同様、袋のおもて側に紙幣のおもて面が来るように入れます。向きをそろえて、肖像画が上になるように入れましょう。
また、使用感のあるお紙幣を包む香典とは異なり、お布施には新札や使用感の少ない紙幣を使用します。ただし、地域によって作法が異なるので、心配な方は周りに相談するとよいでしょう。
包み方
奉書紙を使用するときは、半紙で作った中包みに紙幣を包みます。紙幣は肖像画が上になるように半紙に置きましょう。続いて、中包みを奉書紙で包みます。奉書紙はつるつるした面が表でざらざらした面が裏です。ざらざらした面に中包みを置き、左、右、下、上の順番に折りましょう。
白い無地の封筒を使用する場合は、郵便番号の欄がないものを用意します。不幸が重なることを連想させる二重の封筒は避けましょう。また、お布施に水引は不要ですが、不祝儀袋を使う際には水引を付けるのがマナーです。
渡すタイミングと注意点
33回忌のお布施は、僧侶が帰るときに渡すのが一般的です。法要を滞りなく終えたことや読経へのお礼を述べながら渡すとよいでしょう。ただし、時間がある場合には法要が始まる前でも構いません。
お布施は「袱紗(ふくさ)」に包んで持参します。渡す際は、お布施を小さなお盆(切手盆)に載せて「本日はよろしくお願いいたします」と一言添えて渡します。自宅以外の法要では、袱紗に包んで持参したお布施を袱紗の上に重ねて渡しても問題ありません。
33回忌で多い弔い上げとは?
亡くなった直後に執り行う葬儀の後は、1周忌や3回忌など節目ごとに年忌法要を行います。弔い上げとは、故人に対して行う最後の年忌法要のことです。弔い上げをもって年忌法要は終了し、以降は先祖代々の霊と一緒に弔います。
一般的に、33回忌もしくは50回忌を弔い上げとするケースが多いため、33回忌は重要視される法要のひとつです。他の法要に比べて、盛大に執り行う場合もあります。
33回忌の準備
33回忌を施主として執り行う場合は、事前にさまざまな準備をする必要があります。直前になって慌てないように、余裕を持って進めましょう。
日程と場所をきめて住職に相談
まずは日程と場所をきめましょう。一般的には故人の命日に執り行いますが、難しい場合は、直前の週末などでも問題ありません。仏教では、法事を後回しにすることはよくないと考えられているため、命日よりも後にならないように注意が必要です。
日程と場所がきまったら、住職に相談します。繁忙期だと希望がかなわないこともあるので、早めの連絡を心がけましょう。
会食を行う場合は会場の手配
法要後に会食を行う場合は、料理店の予約も早めに済ませておくと安心です。予約の際に人数を伝える必要があるため、ある程度の人数が確定してから連絡するとよいでしょう。
香典返しとお布施の準備
香典をいただいた方へのお返しや、僧侶に渡すお布施の準備も忘れないようにしましょう。香典返しは、お菓子やお茶などの「消えもの」がよく選ばれます。常温保存が可能な持ち運びやすい品を選ぶとよいでしょう。
「四つ足生臭もの」といわれる肉や魚、おめでたいイメージのある品など、タブーとされている品もあるため選ぶ際には注意が必要です。
33回忌当日の流れ
33回忌の当日の流れは、ほかの年忌法要と同様と考えてよいでしょう。一般的な流れは以下のとおりです。
1. 僧侶の入場
2. 施主の挨拶
3. 読経と焼香
4. 僧侶の法話
5. 施主の挨拶
6. 会食
33回忌に参列する際のマナー
ここからは、33回忌法要に参列する際の服装や香典のマナーを紹介します。
服装
家族や近しい親族だけで執り行う場合は、基本的に平服(略喪服)で問題ありません。しかし、33回忌法要を弔い上げとし、盛大に執り行う場合は喪服の着用がおすすめです。
案内状に服装について書かれている場合もありますが、記載がなく不安な場合は、事前に施主に確認してみるとよいでしょう。
香典
香典の金額は1万円~5万円程度が目安ですが、故人との関係性や年齢によって異なります。また、会食の有無や、地域や親族の考えによっても金額の目安は変わるでしょう。
ほかにも、包む金額や宗派によって香典袋のデザインにルールがあり、表書きの書き方にもマナーがあります。失礼のないように、家族や詳しい知人などに相談してから用意すると安心です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
33回忌は亡くなってから32年後の命日に執り行う年忌法要です。33回忌法要をもって「弔い上げ」とする場合も多く、重要な節目ともいえるでしょう。お布施の目安は3万円~5万円程度で、包む際は袋のおもて側に紙幣のおもて面が来るように入れましょう。向きは、肖像画が上になるように入れます。
小さなお葬式では、三十三回忌をはじめとした法要のご相談も承っています。法要に関する悩みを抱えている方は、小さなお葬式にお問い合わせください。
また法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば、ぜひ「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


葬儀費用は「葬儀一式費用・飲食接待費用・宗教者手配費用」で構成されます。ホゥ。