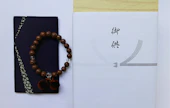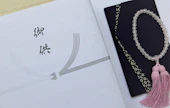葬儀や一周忌を終えると、肩の荷が降りて一息つく方も多いでしょう。しかし、続いて訪れる三回忌も大きな法要のひとつであり、滞りなく行う必要があります。
三回忌の持ち物は、立場によって違いがあるものもあり、細々と準備しなくてはならず、何が要るのか分からなくなる方もいるかもしれません。
こちらの記事では、三回忌における持ち物についてご紹介します。施主だけでなく、参列者の方も持ち物チェックは必要です。
<この記事の要点>
・施主は参列者への謝意として3,000円~5,000円程度の返礼品を用意しておく
・三回忌法要に参列する際には香典、ふくさ、数珠などが必要
・三回忌法要に香典を持参するときは袱紗に包むのがマナー
こんな人におすすめ
三回忌法要に必要な持ち物を知りたい方
自宅で葬儀を行う際の持ち物を知りたい方
法要に持参する小物のマナーを知りたい方
【施主】三回忌の持ち物
三回忌の施主になると、会場の手配や参列者への案内など、さまざまな準備が必要となります。当日の持ち物は全て重要な物で、忘れてしまうわけにはいきません。
当日になってから慌てないためにも、事前に必要なものをまとめておくことが大切です。忘れ物をしないように、持ち物のチェックリストを作っておきましょう。
一般的な持ち物リスト
宗派や地域性によっても異なる面がありますが、三回忌の持ち物として一般的なアイテムは下記の通りです。
・お布施
・位牌
・遺影
・お供え物(果物・仏花・線香・ろうそくなど)
・白いハンカチ
・黒バッグ
・返礼品
・数珠
・袱紗(ふくさ)
このように、意外とたくさんの持ち物が必要となるため、ひとつずつ確認した上でまとめておいておくと安心です。
また、服装に関しても注意しなければなりません。三回忌のおける施主側の服装は、喪服が通例となっています。ハンガーに吊るしておくなどして準備しておくようにしましょう。
持参するお布施はいくらくらいで用意する?
三回忌の持ち物の中でも、特に忘れてはならないのがお布施です。お布施は「お気持ちで包むもの」と言われており、具体的な金額が定められていません。お寺との関係や地域性によっても金額は異なります。
一般的には1万円~5万円程度と言われていますが、金額に幅があるため適当に包んでしまうと、トラブルにつながる可能性も否めません。どれくらい包めばよいか分からないときは、前もってお寺や周囲の人に相談してみましょう。
また、自宅や斎場に住職をお呼びするときは、お布施とは別にお車代が必要となります。お車代は5,000円~1万円程度を考えておきましょう。会食の場を設けない場合や、住職が会食に参加しないときには御膳料も必要となるので注意が必要です。
返礼品の用意はどうする?
三回忌では、施主は参列への謝意を示すために返礼品を用意するのが一般的です。返礼品は香典返しとも言い、参列者からいただく香典に対する謝意も含まれています。
金額はいただいた香典の3分の1~半額程度で用意しましょう。三回忌の場合、3,000円~5,000円程度のものを用意しておくと無難です。
気をつけたいのは、返礼品にかける掛け紙(のし紙)です。葬儀や一周忌のときは黒白か双銀の水引が施された掛け紙をかけますが、三回忌になると青白か黄白に変わるとする地域もあります。業者に頼まず自分で用意する場合には特に注意しましょう。
三回忌を斎場で行う場合、返礼品は斎場で一気に手配できます。しかし、お寺や自宅で行う場合には事前に自分で手配する必要があるため、持ち物リストの中にきちんと追加しておかなければなりません。
【参列者】三回忌の持ち物
三回忌では、参列者も施主と同じく多くの持ち物が必要となります。三回忌は事前に案内が届くので、持ち物についても前もって用意できるので安心でしょう。
とはいえ、うっかりしていると三回忌当日はすぐに訪れます。慌てて忘れ物をしないように、三回忌に必要な持ち物をしっかり確認しておきましょう。
参列者の持ち物リスト
三回忌に参列する場合、次のアイテムを持っていくのが一般的となっています。早めに準備しておけば問題ないものばかりなので、前日までに確認するようにしましょう。
・香典
・袱紗
・数珠
・バッグ
・ハンカチ
三回忌の場合、「平服で」と案内状にある場合があります。そのような場合は、黒や紺色などのダークカラーのスーツやワンピースでも構いません。
装いについての記載が無い場合には準喪服を着用するのが無難です。アクセサリーに関しては、結婚指輪以外はマナー違反と言われています。マニキュアも控えましょう。
香典はどのくらい包む?
三回忌に持参する香典は不祝儀袋に入れるようにしましょう。包む金額は、故人との生前の関係性によって異なります。また、宗派や地域性などによって一概には言えませんが、親族では1万円~3万円が一般的です。
仏事においてのタブーとして、「死」や「苦」をイメージさせるため「4」や「9」を含む数字は控える必要があります。
また、香典袋を持参するときは袱紗(ふくさ)に包むのがマナーです。袱紗の色は、紫や紺など落ち着いた色のものを使用します。
お供え物には何を選ぶ?
三回忌に参列する際に、香典と合わせてお供え物を渡すケースもあります。香典と同時に渡すため、高価なものを用意する必要はありません。
三回忌のお供え物として適切なのは、生花や果物、日持ちのするお菓子などです。故人が好きだったものをお供えするのもよいでしょう。ただし、魚や肉などの生ものは殺生をイメージさせるためタブーとなっています。
また、お供え物にも掛け紙をかけるのが一般的となっており、表書きは「御供」もしくは「御供物」と書くのが通例です。
身内だけで法要を行う場合の持ち物
最近はできるだけ法要をシンプルにしたいという考えもあり、遺族や親戚など身内だけで行うケースも少なくはありません。とはいえ、三回忌法要に必要な持ち物は一般的な法要とほとんど同じです。
例えば、身内だけの法要であっても、参列者は香典を持参するのが一般的でしょう。一方、施主はそれに対する返礼品(香典返し)を準備する必要があります。
また、三回忌の服装は喪服を着用するのがマナーです。しかし、身内だけの法要の場合はそこまで気を張らず、平服でもかまわないというケースも多いでしょう。平服を着て参列する際は、できるだけ暗めのトーンの服を選ぶことをおすすめします。
自宅で法要を行う場合の持ち物
身内だけや参列者を多く呼ばない場合は、ささやかな法要として自宅で行うこともあるでしょう。お寺や斎場で三回忌を行うときは、持ち物を忘れないように気を配る必要がありますが、自宅で行う場合はその心配がありません。
とはいえ、お供え物や返礼品など前もって準備しておくべきものはたくさんあります。当日になって思い出しても、施主側はなかなか買いに出かけるような時間が取れません。遅くとも前日までに必要なものは全て整えておくように心がけましょう。
また、自宅で法要をする場合は、住職に出向いてもらわなければなりません。そのため、お車代を包む必要があります。お布施とは別に用意するのが通例のため忘れないように準備しておくことが大切です。
気をつけたい小物のマナー
三回忌の持ち物として、施主も参列者も共通してあげられるのが普段から持ち歩いている小物類です。服装や法事特有のアイテムについては意識していたとしても、小物のマナーまでは考えていなかったというケースも少なくありません。
何気なくバッグから取り出した小物がマナー違反にならないように、小物に対しても意識を払っておく必要があります。
財布
いつも持ち歩いている物の代表といえば、財布が挙げられます。黒やグレーなど落ち着いた色の財布なら問題ありませんが、黄色や派手な柄の財布は要注意です。
特に、ファーのついた財布は殺生をイメージさせることから、三回忌を含む仏事で身に着けるものとしてはタブーの素材となっています。
いつもの財布の場合でも、法要会場で出すことがなければ、そのままバッグに入れておいてもよいでしょう。不安に感じる場合は、マナーに適した財布に入れ替えて持っていくことをおすすめします。
スマートフォンケース
スマートフォンは、今や誰もが日常的に持ち歩いています。財布はいつもと違うものに変えても、スマホケースはそのままというのはよくあるパターンです。しかしながら、三回忌のためにスマホケースを変えるのは現実的ではありません。
法要中は、マナーモードにして通話を控える必要があるため、そこまでスマホケースのことを気にしなくてもよいでしょう。しかし、あまりにも派手な場合は、できれば法要が終わるまでスマートフォンをバッグから出さないほうが賢明です。
雨具
三回忌法要が必ずしも晴れになるとは限りません。出かける前は晴れていても、急な雨に見舞われることもあるでしょう。慌てて自宅にある傘やカッパなどの雨具を持参したところ、花柄やピンクなどカラフルな雨具だったということもあり得ます。また、アニマル柄なども殺生を連想させるため控えましょう。
普段から黒や紺など地味な色の雨具を用意しておくと、いざというときに助かります。法要用の折り畳み傘を持っておくと安心でしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
葬儀や一周忌に続き、三回忌は比較的大きい規模で執り行う大切な法要となります。三回忌にはさまざまなマナーがあり、持ち物も例外ではありません。施主側だけではなく参列者も失礼がないように意識することで、三回忌自体がスムーズで気持ちの良いものになるでしょう。
また、必要な持ち物は前もって準備しておくことで、当日慌てることなく落ち着いて三回忌に臨めます。三回忌を控えている方は、しっかりとチェックしておきましょう。
「小さなお葬式」では、三回忌法要に関するサポートも行っております。細かなことでも構いません。何か分からないことや不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。
法事・法要に関する疑問以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


人が亡くなった後に行う死後処置と、死化粧などをまとめて「エンゼルケア」と呼びます。ホゥ。