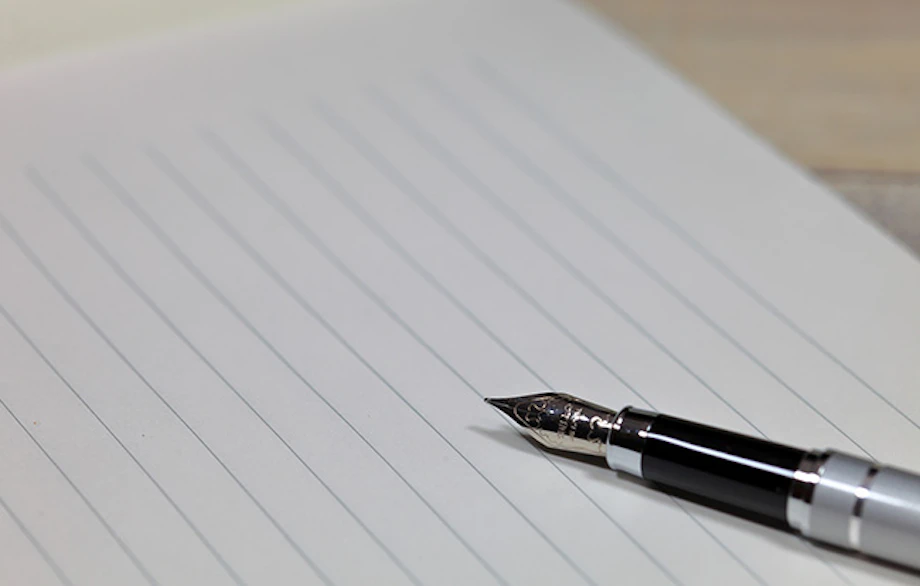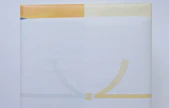一周忌に参列していただいた方や、参列しなかったものの、香典やお供え物料、お供え物などを送っていただいた方に対しては、お礼の品を送るのが一般的です。その際は、感謝の気持ちを表すためにも、お礼状を添えてお送りしましょう。
お礼状は相手に感謝の気持ちを伝えるためのものですが、いざ自分がお礼状を準備する立場になったときには、どのようなことを書けばよいのか悩んでしまう方もいるのではないでしょうか。
この記事では、一周忌の準備や当日の流れ、お礼状の書き方や返礼品などについて詳しくご紹介します。
<この記事の要点>
・一周忌を行う際には、事前に日時や場所・会食場所・返礼品などを準備する
・お礼状の文中に「句読点」や「繰り返し言葉」を使わない
・お礼状は手書きではなく、印刷したものを使用してもよい
こんな人におすすめ
一周忌の準備について知りたい方
お礼状の書き方を知りたい方
お礼状の例文を知りたい方
一周忌とは
「一周忌」は故人が亡くなってから1年後の命日に行う法要を指し、正式には一周忌法要と言います。よく「一周忌」と「一回忌」を混同してしまう方がいますが、一周忌と一回忌は全く違う意味を持ったものです。
「一周忌」は故人が亡くなってから1年後の命日に行う法要を指すのに対し、「一回忌」は故人が亡くなったその年の命日を指します。つまり、期間でいうと、一周忌と一回忌には1年の開きがあるということになります。
一周忌は故人の命日に行われる年忌法要の中でも、もっとも大切な法要とされています。遺族や親族だけでなく、故人と関係が深かった友人や知人も参列するのが一般的です。
一周忌の準備
年忌法要の中でも、大切な法要とされている一周忌を開催するにあたっては、準備することが多くあります。ここでは、一周忌を執り行う側が準備することについて解説します。
日にちを決める
祥月命日が平日の場合、仕事や学校があるため、多くの方が参加するのは難しいでしょう。
その際には、直前の土曜日や日曜日に一周忌を行うことが一般的です。日程を決める際には、なるべく多くの関係者が参列できるよう、親族の予定を確認しながら決めるとよいでしょう。
場所を決める
一周忌を行う場所は、行う場所に決まりなどはありません。自宅や寺院、ホテルなどが一般的ですが、どこにすればよいのか迷う場合は、法要後のお墓参りのことも勘案し、故人のお墓から近い場所を選ぶのがおすすめです。
会食について決める
会食をする場所については、法要を行う場所から近い距離にあるレストランや料亭などを選ぶのが一般的です。
寺院で行う場合は、寺院に併設されている会館などを利用することもできます。会場選びの際は、参列者が参加しやすいように、法要を行う場所からなるべく近い場所を選ぶとよいでしょう。
法要後の会食は、必ず行わなければならないというものではありません。会食なしでも問題はありませんが、その場合は参列者へのお弁当と日本酒(小瓶)を用意しておくのが一般的です。
返礼品を決める
法要に参列していただいたり、香典をいただいたりした方々へのお礼の品は、「返礼品」と呼びます。「引き出物」は慶事を連想させる表現なので、使い方の間違いに注意しましょう。
法要の場所や会食などを決めたら、返礼品選びをしましょう。返礼品の相場としては、2,000円~5,000円程度とされています。
返礼品は「消えてなくなるもの(消えもの)」がよいとされており、お茶、洗剤、石鹸などを選ぶのが一般的です。形に残るものや、参列者が持ち帰る際に重すぎたり大きすぎたりするものは避けるのが無難でしょう。
お礼状を書く際のポイント
お礼状は、相手から贈り物をいただいた際に、感謝を伝えるために準備します。一周忌法要に参列していただいた方々や、参列できずともお供えものや香典を送っていただいた方々に対して失礼のないよう、感謝の気持ちがこもったお礼状を準備したいものです。
ここでは、お礼状を送る際の注意点についてご紹介します。
文中に句読点や繰り返し言葉を使わない
句読点には文章を「止める」役割があるため、お礼状においては、句読点を使用しません。「行事が止まることなくスムーズに進む」という意味を込めて句読点無しの文章にしましょう。
また「畳語(じょうご)」と呼ばれる繰り返し言葉も用いません。畳語は、「ものごとを折り重ねる」という由来があります。弔事における不幸を繰り返すことを避けるために、「たびたび」「重ね重ね」「くれぐれも」「益々」などといった表現は使わないように注意しましょう。
お礼状は印刷したものでも問題ない
「お礼状を手書きでしたためたい」という方ももちろんいますが、参列者やお供えものや香典をいただいた方々すべてに手書きでお礼状を書いていると、手間や時間がかかってしまうため、印刷したお礼状でも問題ありません。
お礼状を準備する際は、不測の事態に迅速に対応できるよう、予定されている参列者数よりも少し多めに作成しておくとよいでしょう。
お礼状の例文
お礼状で一番大切なのは、感謝の気持ちが伝わるような心をこもった文章です。とはいえ、さまざまな立場・年代の方々にお送りするものなので、マナーを欠くことのないようにしたいものです。
このようなかしこまったシーンにおける文章を書く機会は少ないため、書き出しや文章の締め方、書く内容などについて頭を悩ませてしまう方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、お礼状の文例をご紹介します。
拝啓
亡父 〇〇儀 一周忌法要に際しては 御多用中のところをお運びいただき 誠に有難く厚く御礼申し上げます
この1年 皆様には公私にわたり 温かい励ましの言葉をいただき 私たち家族もようやく前向きに生活を営んでいけるようになりました
心から感謝いたしております
早速拝趨親しく御礼申し上げるところではございますが 略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます。
敬具
お礼状はあくまでも略式なお礼となりますので、「本来、直接お伺いをしてお礼を申し上げるべきところ、書面でのお礼となり申し訳ございません」といった趣旨の文を記しておくのがポイントです。
参列者へのお礼の品について
一周忌に参列してくださった方への返礼品は、一般的に「消えてなくなるもの(消えもの)」がよいとされています。では、具体的にどのような品を選ぶとよいのか、詳しく見ていきましょう。
石鹸・洗剤
毎日の生活に欠かせないものであり、もらっても困る人も少ないということで、石鹸や洗剤は一周忌の返礼品として選ばれることが多い品です。香りのよいものや、おしゃれなデザインの品を選べば、もらった方も喜んでお使いいただけます。
また、石鹸や洗剤には「不幸を洗い流す」という意味合いもあるため、気の利いた返礼品という印象を持たれるでしょう。
お茶・海苔
お茶や海苔も弔事の返礼品としてよく選ばれます。食べたらなくなる食品も消えものにあたるため多く選ばれますが、お菓子やその他の食品ではどうしても好みがあるでしょう。その点、お茶や海苔は、好き嫌いが分かれることが少ないため、便利に使えます。
また、「朝茶は一日の難逃れ」という言葉もあるように、お茶には魔除けや災難除けの意味合いがあり、参列してくださった方々の厄除けにもつながるので、配慮のある返礼品となるでしょう。
一周忌の流れ
一周忌当日の流れについては、下記が一般的です。
・僧侶入場
・施主のあいさつ
・読経
・お焼香
・僧侶による法話
・僧侶退場
・施主のあいさつ
・お墓参り
ここでは、この中でも気をつけておくべき点について解説します。
席次やお焼香の順番は故人と血縁関係の深いほうから
一周忌の会場における席順は、故人との血縁関係が深い順で前列から座るのが一般的です。お焼香の順番についても、席順と同様に故人と関係が深い順に行います。
ただし、さまざまな家族事情があることも考えられますので、あらかじめ親族間で確認をしておくのがおすすめです。
お布施は一周忌法要の前後に渡す
会食の終盤でタイミングを見計らって、参列者に返礼品をお渡しします。その際には、参列者の1人1人にお礼の言葉などを添えることも忘れないようにしましょう。
ただし、会食に参加する人数が多い場合は、会食が終わる直前に配るのでは間に合わない可能性があります。このようなときは、会食が始まる前に各席に返礼品を置いておくのがおすすめです。そうすることで、返礼品の渡しそびれを防ぐことができます。
会食をレストランや料亭で行う場合は、お店のスタッフに返礼品の配布をお願いすることができるケースもあるようです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
一周忌を行うにあたっては、会場・会食の手配から、お礼状の準備や返礼品選びなど、多くのことを準備しなければいけません。
また、当日は僧侶や参列者への対応などでとても忙しくなります。慌てないためにも、この記事でご紹介したポイントについて事前に確認をしながら準備をしておきましょう。
「小さなお葬式」では法事・法要に関するご相談を承っております。専門のスタッフによるご相談のケースに合わせたアドバイスが可能です。何かお困りのことがあればまずはお気軽にご相談ください。
法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


包む香典の金額は、故人・遺族との関係の深さ、年齢や社会的な立場で異なります。ホゥ。