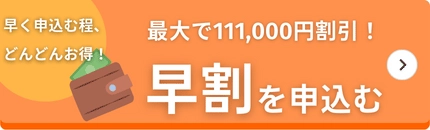遺留分制度についての理解は、相続のルールを理解する上で欠かせません。しかし、なんとなく「遺留分」という言葉は知っていても、その理解はあいまいだという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2018年に改正された点も含めて、遺留分制度をくわしく解説します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・遺留分とは、相続人に保証された最低限の取り分のことを指す
・遺留分の割合は、原則として相続財産の2分の1
・民法相続法改正により遺留分は原則として金銭請求となった
こんな人におすすめ
相続で注意すべき遺留分について知りたい方
具体的な遺留分計算例を知りたい方
2018年の相続法改正で遺留分はどう変わったのか知りたい方
相続で注意すべき遺留分とは?
遺留分についてひとことで言えば、一定の相続人に保証された相続での最低限の取り分のことです。
例えば、幼い子がいるにも関わらず友人に全財産を遺贈するなどという遺言書を作成して亡くなってしまえば、家族は路頭に迷ってしまうかもしれません。そのため、一定の相続人に遺留分の権利を与えることで、遺留分相当の財産だけは受け取れるルールとなっています。
まずは、遺留分の基本について知っておきましょう。
相続人のうち遺留分があるのは誰?
遺留分は、すべての相続人が持つ権利ではありません。相続人になる場合であっても、遺留分が発生しない人も存在します。
遺留分のない相続人とは、第三順位の相続人である次の人です。
・兄弟姉妹
・甥姪
裏を返せば、これら以外の人が相続人となる場合には、すべて遺留分があるということです。例えば、配偶者や子、孫、両親などには遺留分があります。
なお、遺留分は相続人である場合のみ発生する権利です。例えば亡くなった方の子が存命の場合、その存命の子の子である亡くなった方の孫は相続人ではありませんから、この場合の孫には遺留分はありません。
遺留分の割合はどれだけか
遺留分の割合は、原則として相続財産の2分の1です。ただし、両親や祖父母といった第二順位の相続人だけが相続人となる場合のみは、遺留分は3分の1とされています。
具体的な計算は、後ほど例を挙げてくわしく解説します。
遺留分を侵害した遺言書は有効か
遺留分についてのよくある誤解に、遺留分を侵害した遺言書は無効だというものがあります。しかし、実はそうではありません。
遺留分が一定の相続人に保証された権利であるとはいえ、遺留分を侵害した遺言書も有効に作成することができます。例えば、長男と長女がいるにも関わらず「長女に全財産を相続させる」という内容の遺言書や「他人に全財産を遺贈する」という内容の遺言書を作ることもできるということです。
ただし、遺留分を侵害した遺言書を作った場合には、相続が起きた後で遺留分を侵害された相続人から財産を多く受け取った人に対し遺留分侵害額請求がなされてトラブルになる可能性があります。遺留分侵害額請求とは、侵害した遺留分相当額を、金銭で支払うよう請求することです。
そのため、仮に受け取った財産の大半が不動産など換金の難しいものであった場合には、財産を受け取った人が遺留分の支払いに苦慮してしまう可能性があります。遺留分を侵害した遺言書を作成する場合には、この点まで理解をしたうえで作成するようにしましょう。
遺留分の対象となる行為とは
遺留分の対象となる行為は遺言だけかと思われがちですが、実はそうではありません。ほかにも、死因贈与や一定の生前贈与も遺留分の対象となります。では、それぞれ見ていきましょう。
遺言
遺言とは、被相続人が生前に作成した遺言書で財産の配分を決めておくことです。
遺言には自筆証書遺言や公正証書遺言などの方式があり、法律に定められたルールに則って作成する必要があります。遺言は遺言を作成する人が一方的に作成することができ、作成にあたって相手方の承諾などは必要ありません。
遺言は、遺留分の対象となる代表的なものです。
死因贈与
死因贈与とは、死亡を原因として効力が発生する贈与契約です。遺言と似ていますが、遺言とは異なり「あげます」「もらいます」といった双方の合意で成立します。
死因贈与は遺言と異なりその方式に厳密なルールはありませんが、実現性の観点から公正証書などの書面で行うことが一般的です。
この死因贈与も、遺留分の対象となります。
一定の生前贈与
生前贈与も、遺留分の対象となります。
ただし、すべての生前贈与が遺留分の対象となるわけではありません。遺留分の対象となる贈与は、原則として次のとおりです。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、これ以前のものであっても遺留分の対象になるとされています。
相続人に対する生前贈与:相続開始前の10年間にしたもの
相続人以外に対する生前贈与:相続開始前の1年間にしたもの
具体的な遺留分計算例
遺留分は、どのように計算するのでしょうか。遺留分の対象となる財産が8,000万円である前提で見ていきましょう。
ケース1相続人が配偶者と子である場合
相続人が配偶者と長男、長女である場合の遺留分は、2分の1です。
配偶者と子の遺留分は、それぞれ次のようになります。
配偶者:8,000万円×2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=2,000万円
長男:8,000万円×2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=1,000万円
長女:8,000万円×2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=1,000万円
ケース2相続人が子と孫である場合
相続人が子と孫である場合の遺留分も、2分の1です。
例えば、すでに死亡した次男の子である2名の孫と長男の計3名が相続人である場合の遺留分は、それぞれ次のようになります。
長男:8,000万円×2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=2,000万円
次男の子1(孫):8,000万円×2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=1,000万円
次男の子2(孫):8,000万円×2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=1,000万円
ケース3相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合
相続人が配偶者と兄弟姉妹である分の遺留分も、2分の1です。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
それぞれの遺留分は、次のようになります。
配偶者:8,000万円×2分の1(遺留分割合)=4,000万円
兄弟姉妹:なし
ケース4相続人が両親のみである場合
相続人が両親のみである場合の遺留分は、3分の1です。
それぞれの遺留分は、次のようになります。
父:8,000万円×3分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)≒1,333万円
母:8,000万円×3分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)≒1,333万円
相続人が親など第二順位の相続人である場合のみ、遺留分は3分の1となります。なお、配偶者と親が相続人である場合の遺留分は原則どおり2分の1ですので、間違えないようにしましょう。
遺留分の放棄はできる?
遺言を残す側からすれば、遺留分があることで遺言の内容に実質的に制限がかかってしまいます。
例えば、長男に財産の大半を渡したいと考えている方としては、次男には遺留分を放棄させたいと考えることでしょう。
では、遺留分の放棄をさせることはできるのでしょうか。
強制的に遺留分を放棄させることはできない
結論から言うと、遺言者本人であっても、強制的に遺留分を放棄させることはできません。強制的に放棄させることができてしまえば、遺留分制度の意味がなくなってしまうためです。
ただし、本人の意思で遺留分を放棄することは認められています。遺留分放棄の方法は、相続が起きる前と起きた後とで異なりますので、それぞれ見ていきましょう。
相続が起きる前の遺留分放棄
相続が起きる前に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所に申し立てをして許可を受けなければなりません。単に口頭で遺留分放棄をする旨の制約をさせたり書面に書いたりしただけでは遺留分放棄の効力は生じないので、注意しましょう。
また、家庭裁判所に申し立てたからといって、必ずしも許可がされるわけでもありません。
遺留分放棄についての家庭裁判所の許可基準は決して低くはなく、おおむね次のような事情が必要とされています。
1.遺留分放棄が放棄をしようとする人の自由意思に基づくものであること
2.遺留分放棄の理由に合理性や必要性が認められること
3.遺留分放棄の代償として相当の財産を渡していること
そのため、例えば次のような事情では許可がされない可能性が高いでしょう。
・遺留分放棄の見返りがない
・遺言者が無理に遺留分放棄をさせようとしている
・単に遺言者と遺留分権利者との仲が悪いという理由
生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可を受ければ可能であるとはいえ、許可のハードルは決して低くないことを知っておきましょう。
参考:『遺留分放棄の許可 裁判所』
相続が起きた後での遺留分放棄
相続が起きた後での遺留分放棄は、生前の遺留分放棄とは異なり特別な手続きは必要ありません。単に、遺留分を侵害された人から多く財産を受け取った人に対して、遺留分を侵害しない旨を通知するだけで放棄をすることが可能です。
また、後ほど説明する遺留分の請求期限内に遺留分の請求をしなければ、自動的に遺留分を放棄したこととなります。
遺留分侵害額請求をしたい場合のポイントとは
ここでは、遺留分を侵害され、遺留分請求をしようとしている場合のポイントを3つご紹介します。
遺留分侵害額請求には時効がある
遺留分を請求しようとする場合には、期限に注意しましょう。遺留分を請求する期限は、次のとおりです。
・相続が起きたことと遺留分侵害をされたことを知ってから1年間
・相続が起きてから10年間
内容証明郵便など記録の残る方法で請求する
遺留分の請求方法は、法律で特に定められているわけではありません。そのため、例えば口頭での請求や、普通郵便での請求であっても請求の効力は生じます。
しかし、口頭では「言った・言わない」の問題が生じてしまいますし、普通郵便であっても「受け取っていない」「郵便は受け取ったが遺留分とは関係のない内容だった」などと主張されてしまうかもしれません。
こうした問題を避けるため、遺留分の請求は請求をした日時と相手に送った内容が記録される内容証明郵便で行うと良いでしょう。
弁護士への相談がベター
遺留分の請求は、ご自身で行うこともできます。ただし、遺留分の請求をしたからといって、請求どおりに支払ってもらえるケースばかりではありません。現実的には、遺留分の対象となる財産や対象となる価額などについて主張が食い違う場合も少なくないでしょう。
そのため、遺留分請求をする際には弁護士へ相談することをおすすめします。
2018年の相続法改正で遺留分はどう変わった?
遺留分の制度は、2018年の民法相続法改正により見直されています。この改正でどの点が変更となったのか、改めて見ていきましょう。
なお、この改正は2019年7月1日から既に施行されており、ここまでの内容はすべて改正後の内容で記載しています。
遺留分の対象が明確となる贈与が明確になった
上で説明したとおり、一定の生前贈与も遺留分の対象です。この生前贈与のうち相続人に対する生前贈与が何年前の分まで対象となるのかについて、従来は法律に明記されていませんでした。
これについて、相続開始前10年間になされた生前贈与が遺留分の対象となることが、改正により明記されています。
遺留分が原則として金銭請求になった
従来、遺留分は現物での返還請求が原則で、その名称も「遺留分減殺(げんさい)請求」でした。これによる問題点は、遺留分の請求をした結果、遺留分を請求した人と請求をされた人とで土地や建物などの財産が共有となってしまう点です。
例えば相続人が前妻との間の子である長男と後妻の2名、相続財産が2,000万円相当の土地のみであった場合に、後妻が遺言でこの土地を取得した場合で考えてみましょう。
この場合、長男が後妻に対して遺留分減殺請求をすると、この土地が後妻4分の3、長男4分の1の共有となってしまいます。
遺留分減殺請求をする側とされる側とではあまり関係性がよくない場合も多いため、こうした間柄同士での共有となると、不都合も少なくありませんでした。
こうした不都合を解消するため、改正後は、遺留分は原則として金銭の請求となっています。その結果、長男は後妻に対して遺留分相当(2,000万円×2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=500万円)の金銭を請求できるのみとなり、土地が共有となることはなくなりました。
これにより、遺留分請求の名称も「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと変更されています。
なお、支払うべき遺留分を一括で支払うことができない場合には、支払い期限の猶予を裁判所へ申し立てることもできるようになりました。
家族信託という選択肢もある
遺留分制度について詳しく知りたい際に、認知症についても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。
ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組成できるサービスです。資産管理にお困りの方は、お気軽にお問合せください。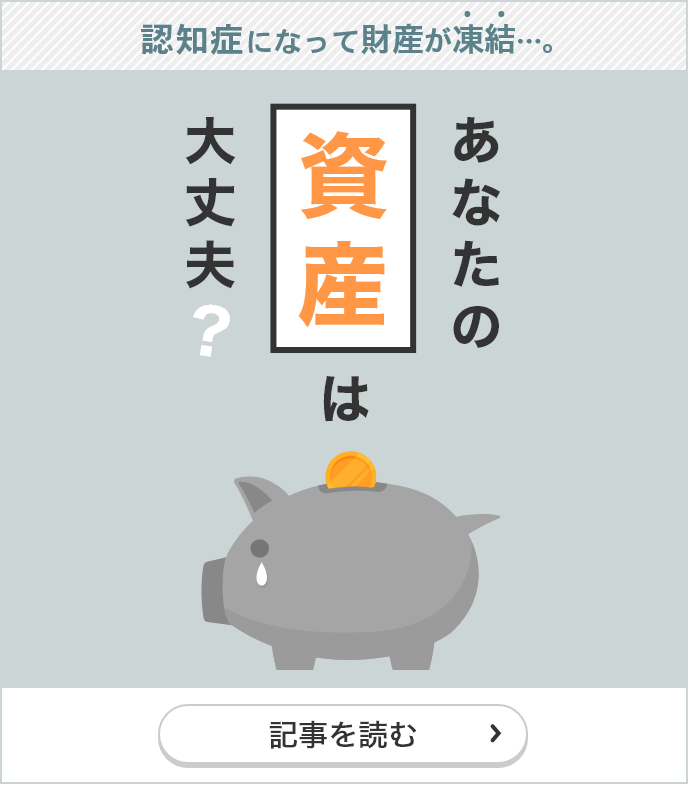
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
遺留分を侵害した遺言書も作成することはできますが、遺留分侵害はトラブルの元となる可能性があります。遺言書をつくる際には遺留分についても正しく理解をして、トラブルのない相続を目指しましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
遺留分とは?
相続人のうち遺留分がないのは誰?
遺留分の対象となる行為は?
遺留分の放棄はできる?
亡くなった方や仏に向けて、香を焚いて拝む行為を焼香(しょうこう)といいます。ホゥ。