生計を立てている人が死亡したときに、遺族がどうやって生計を立てればよいのかわからないといった方は多いのではないでしょうか。そのときに役立つ制度の1つに「遺族年金」と呼ばれるものがあります。遺族年金は残された遺族にとっては非常に助けになるでしょう。
とはいえ、このようなお金に関する制度は学校等で習う機会は皆無に等しく、知識が少ない方が一般的です。しかし、この制度を知っておくと暮らしの負担を減らせるのも事実です。
この記事では遺族年金の概要や受領する際の手続きの方法について解説します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類がある
・遺族基礎年金の額は、年間81万6,000円が基本である
・遺族厚生年金の額は、故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の割合である
こんな人におすすめ
遺族年金とは何かを知りたい方
遺族年金の受領のための手続きを知りたい方
遺族年金についての注意点を知りたい方
遺族年金とは
遺族年金とは、国民年金・厚生年金に加入していた方、もしくは現在も加入している方がなんらかの理由で亡くなった際、その方が扶育していた家族に対し、今後の生活を保障するために支払われるお金です。
遺族年金には受領に条件があったり、受領の仕方に複数の手続きを要したりします。さらに、家庭ごとに受領できる額が異なったり、手続きの内容が大きく変わったりするため、申請や受領の難度が高いとされています。
遺族年金は2種類ある
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。「サラリーマンや公務員」と「自営業」の方で受領の可能不可能が変わってきますが、それ以外にも大きな違いが存在するため、それぞれの条件と受領できる金額について確認しましょう。
【遺族年金1】遺族基礎年金
遺族基礎年金は、条件を満たせばだれでも受領できるのが原則です。例えば、自営業の方でも国民年金に加入しており条件に当てはまっていれば受領することができます。
しかし、全員が必ず受領できるわけではありません。条件は、亡くなった方の状況や受領される方の状態が重要になってくるので詳しく解説します。
亡くなった方の状態
亡くなった方が以下のいずれかに当てはまっていないと受領は不可能です。
・国民年金に加入している
・60歳以上~65歳未満で国民年金に加入していた、かつ日本に住所がある
・老齢基礎年金の受給権者である(ただし合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方)
・25年以上の老齢基礎年金の受給資格期間がある
「国民年金に加入している」「60歳以上~65歳未満で国民年金に加入していた、かつ日本に住所がある」の条件によって年金を受領する場合は、保険料納付要件に該当しなければなりません。
| 保険料納付要件 | ・保険料納付済期間が国民年金に加入している期間の3分の2以上である。 |
| ・亡くなった日が2026年の3月末日までで亡くなった方の年齢が65歳未満の場合、亡くなった月の前々月までの1年間で保険料の未納がない。 |
以上が亡くなった方についての条件です。続いて受領される方の条件について解説します。
受領される方の状態
受領される方の状態が以下のいずれかに当てはまっていないと受領は不可能になります。
・亡くなった方が自分を扶育していた配偶者で子供がいる方
・亡くなった方によって扶育されていた子供
「扶育」の定義は、同じ家に住んでいた、仕送りをもらっていた、扶養に入っていたことです。
受領される方の年収は年収が850万より少ない、年間の所得額が655万5,000円よりも少なくないといけません。
受領できる額
遺族基礎年金の額は、年間81万6,000円が基本です。これに子供の数を合わせて額が上乗せされます。上乗せされる額は2人目の子供までが23万4,800円、3人目以降が1人当たり7万8,300円です。配偶者と離別している場合は、1人目の子供を配偶者と仮定します。
※令和6年4月からの年金額。昭和31年4月2日以後生まれの方は上記の金額に、昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円 + 子の加算額となります。
参考:『厚生労働省 令和6年4月分からの年金額等について』
【遺族年金2】遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた公務員やサラリーマンなどの方々が死亡されたときに支払われる年金です。こちらについても、遺族基礎年金と同様に受領の際には条件があるので注意してください。
亡くなった方の状態
受領される方の状態が以下のいずれかに当てはまっていないと受領は不可能になります。
・亡くなった日が厚生年金の加入期間中
・初診を受けた怪我や病気が厚生年金の加入期間でその怪我や病気で初診から5年以内に亡くなった
・障害等級が1級もしくは2級で、障害厚生年金を受領している
・齢厚生年金の受給権者である(ただし合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方)
・25年以上の齢厚生年金の受給資格期間がある
「亡くなった期間が厚生年金に加入している期間中」「初診を受けた怪我や病気が厚生年金の加入期間でその怪我や病気が原因で初診から5年以内に亡くなった」の条件で年金を受領される場合は、保険料納付要件について満たしている必要があります。
受領される方の状態
遺族厚生年金は受領される方について、家族の中でも限定が加えられています。
| 夫(第1順位) | 遺族基礎年金を受領しているとともに、扶育してもらっていた方が亡くなったときに55歳以上である |
| 妻(第1順位) | 30歳未満で子供がいない場合のみ、5年間のみの受領になります |
| 子供(第1順位) | 18歳になった年度の3月31日まで。障害等級1級~2級に当てはまる場合は20歳まで |
| 両親(第2順位) | 扶育してもらっていた方が亡くなったときに55歳以上である |
| 孫(第3順位) | 18歳になった年度の3月31日まで。障害等級1級~2級に当てはまる場合は20歳まで |
| 祖父母(第4順位) | 扶育してもらっていた方が亡くなったときに55歳以上である |
順位が高い方が年金を受領された場合には、それ以降の順位の方は受領することが不可能となるので注意してください。なお、「扶育」の定義は遺族基礎年金と同じで、同居していた、仕送りを受けていた、扶養に入っていたことです。
受領できる額
受給額は、故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の割合になります。遺族厚生年金は基本的に、{平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月までの被保険者期間(月数)+平均標準報酬額×5.481/1,000×2003年5月以降の被保険者期間(月数)}×3/4で計算します。加入月の数が300に満たない場合は、300として計算します。
遺族年金の受領のための手続き
遺族年金の受領には複雑な手続きを複数回行わなければいけないため、決して簡単ではありません。
そこで、以下の一連の流れを確認してスムーズに手続きを進められるようにしましょう。
1.必要な書類を揃える
2.年金請求書を書く
3.書類と請求書を窓口に提出する
4.年金証書を受け取る
5.振り込みが開始される
それでは1つずつ解説します。
1.必要な書類を揃える
以下の書類が必要になるので、手続きを行う際は準備しておきましょう。
・年金手帳
・年金証書
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・死亡者の住民票の除票
・所得証明書などの請求者の収入が確認できるもの
・子供の収入を確認できるもの(義務教育の場合は不要)
・死亡診断書のコピー
・受領先金融機関の通帳もしくはキャッシュカード
・印鑑
これらに合わせて、死亡の原因が第三者によるものだった場合は以下の書類が必要になります。
・第三者行為事故状況届
・交通事故証明
・確認書
・被害者が被扶養者を扶育していたことを証明できる書類
・損害賠償金の算定書
また、申請を代行してもらう場合は「委任状」が必要になります。
2.年金請求書を書く
次に年金請求書を書きます。この書類は、遺族基礎年金のみを受領する場合は亡くなった方の所在地を所管する役場でもらいましょう。遺族厚生年金も受領する場合は年金相談センターか年金事務所でもらいましょう。
3.書類と請求書を窓口に提出する
書類と請求書を準備したら、それらを揃えて窓口へ提出しましょう。必然的に書類が多くなるので不備がないように注意しましょう。
4.年金証書を受領する
申請が通ると、年金証書が郵送されてきます。申請から年金証書が手元に届くまでの期間は約1ヶ月です。
5.振り込みが開始される
年金証書を受領してから1ヶ月~2ヶ月後に指定した口座に年金が振り込まれます。振り込まれる日は毎月ではなく、2ヶ月ごとです。
遺族年金についての注意点
遺族年金には、以下のような注意点があるため知っておきましょう。
・離別した配偶者が死亡した場合には、遺族年金を受領できない
・年金の他に収入があると確定申告が必要
これらの注意点を蔑ろにすると、遺族年金を受領できない可能性があるので注意しなければなりません。
離別した配偶者が死亡した場合遺族年金は受領できない
過去に扶育してくれていた、離別した配偶者が亡くなった場合には、遺族年金の受領は不可能です。しかし、子供は条件次第では受領できる可能性があります。
受領できる条件は以下の通りです。
・未婚である場合、18歳の誕生日を迎える月が含まれる年度末まで受領できる(遺族基礎年金)
・子供がいない(遺族厚生年金)
年金の他に収入があると確定申告が必要
基本的に遺族年金自体は非課税であるので、確定申告を行う必要はありません。しかし、年金の他に年間38万円を超える収入がある場合は確定申告が要ります。
また、同年内に退職し年末調整を行っていない場合は収入分のみの確定申告が必要です。
もらえる遺族年金のシミュレーション
ケースごとにもらえる金額をシミュレーションします。
サラリーマンの方が亡くなった場合
(例)サラリーマンの夫が47歳で死亡した。家族は40歳の妻と14歳の長女、10歳の長男。厚生年金は30年間加入、平均標準報酬月額は40万円、平均標準報酬額は50万円。
サラリーマンの場合、両方受領できます。ここで、遺族厚生年金を計算してみます。
(400,000円×7.125÷1,000×180月+500,000×5.481÷1,000×180月)×3/4=754,717円
よって、上記が年間にもらえる遺族厚生年金の金額です。これに子供の年齢に応じて変動する遺族基礎年金を足すと額が算出されます。
資産凍結の不安を解消する「家族信託」をかしこく活用しよう
遺族年金について詳しく知りたい際に、認知症による口座の凍結などについても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。
ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組成できるサービスです。資産管理にお困りの方は、お気軽にお問合せください。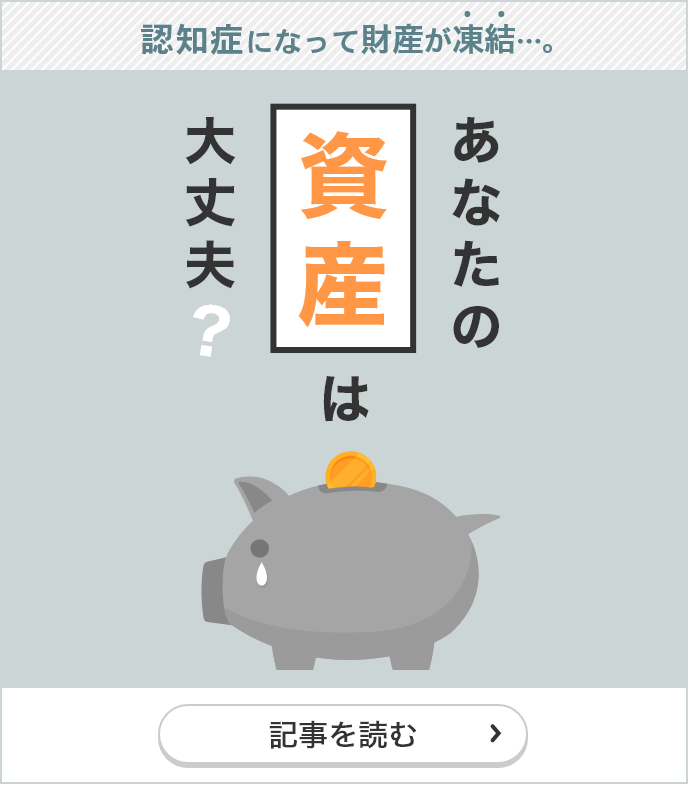
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
今まで家族を扶育くれていた方が亡くなった場合、家族のその後の生活を支えるために「遺族年金」という年金が振り込まれる場合があります。遺族年金は生活の負担を和らげてくれるため、非常にありがたい制度です。
しかし、申請手続きや受領できる方の条件が複雑なため、受領の方法がわからない方も多くいます。そこで、今回紹介した手続きの方法や条件を確かめて手続きを行いましょう。
それでも、遺族年金に関する不安が出てくるかもしれません。そんなときは、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。専門の知識が豊富なスタッフが24時間お客様に寄り添ってご対応いたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


「お悔やみ申し上げます」は通夜や葬儀の定型句なので、宗派を気にせず使えます。ホゥ。






























