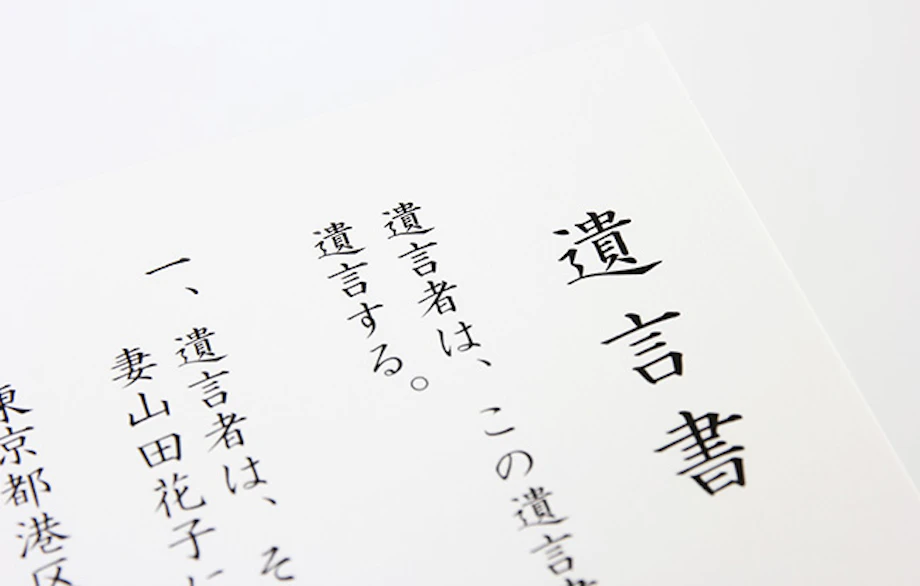遺言にはいくつかの種類があります。どの遺言書にも共通して、故人が遺族の方々や相続人へ対して法律的な効力を発生させる目的で生前に準備しておくものです。
遺言状には、遺産の分配を記した内容や、故人の葬儀の意向などが記載されていることが一般的です。とはいえ、必ず故人の遺言通りの内容で葬儀を執り行わなければならないのか、という点については気になるところでしょう。また、葬儀予定を決定した後に遺言状を発見してしまい悩んでいる、といった遺言に関する疑問や不安な点がある方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、遺言の効力や、遺言状に直葬の希望があった場合にはどのように対処するべきかについて詳しく解説します。遺言に関するお悩みの際に、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・葬儀に関する遺言は法律的な強制力がない
・故人が直葬を希望していても、菩提寺へ連絡せずに通夜や告別式を省くとトラブルに発展しかねない
・葬儀に関する内容は生前に話し合っておくのがおすすめ
こんな人におすすめ
遺言書に直葬の希望があった人
遺言書の効力が知りたい人
遺言の種類
「遺言」と一言にまとめられる場合が多いですが、遺言には大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」が存在します。その大枠の中でさらに細分化されていて、厳密に遺言の種類分けを行うと下記の7種類があります。
・自筆証書遺言(普通方式遺言)
・公正証書遺言(普通方式遺言)
・秘密証書遺言(普通方式遺言)
・一般臨終遺言(特別方式遺言の危急時遺言)
・難破臨終遺言(特別方式遺言の危急時遺言)
・一般隔絶地遺言(特別方式遺言の隔絶置遺言)
・船舶隔絶地遺言(特別方式遺言の隔絶置遺言)
一般的な遺言としては、普通方式遺言が採用され、緊急時などの状況に遺言を作成するときは特別方式遺言を採用します。
普通方式遺言
普通方式遺言の大きな特徴としては、有効期限が存在しないことです。したがって、作成するタイミングに関しては、早すぎるということはありません。しかし、異なる内容の記載を行った遺言を新たに作成した場合は、その時点で以前に作成した遺言は効力を持たなくなります。
特別方式遺言
特別方式遺言が使用されるときは、まったくもって想定外の事態、災害や事故などにより死の危険があるときです。こちらの遺言には有効期限があり、作成後から6カ月間生存している場合には効力を失ってしまうので注意しましょう。
<関連記事>
遺言書の種類は7つ|特徴やメリットに書き方の注意点も紹介
葬儀に関する遺言の効力
遺言は、生前に遺言を作成した方が亡くなられて初めてその効力を発揮します。しかし、その効力とは果たしてどこまでの強制力があるのか、どれほど守らないといけないのかなどはわからない方が多いでしょう。
結論からいえば、遺言の全ての事項に効力があるわけではありません。しかし、法律によって定められている「遺言事項(遺贈、遺産分割の禁止、遺言執行者の指名など)」には、法律的な効力が生じます。
しかし、遺族への個人的な感謝の言葉、財産分割に関する理由の説明といった「付言事項」には法律的な効力はありません。葬儀の内容や埋葬方法に関する希望なども、この付言事項の中に含まれています。
つまり、葬儀に関する遺言は法律的な強制力がありません。そのため、故人が遺言書に「直葬してほしい」といった葬儀に関して希望を記入していた場合、その全てを遺言通りに実行しなくても法律上の問題はありません。
<関連記事>
遺言書の法的効力は?条件や無効になるケース、作成の際の注意点も解説
小さなお葬式で葬儀場をさがす
もしも故人が直葬を希望していた場合
一般的にはお通夜や告別式を執り行いますが、もしも故人が「直葬」や火葬のみで弔う形式を望んでいた場合は、どうすればよいのか悩んでしまうこともあるでしょう。
弔いの際は、遺言の意向を汲みその意思を尊重したいと思う方や、やはり葬儀は行うべきだと思う方など、さまざまな考え方があるでしょう。もちろん、どの考え方が正しいとか間違っているというわけではありません。大事なのは故人を想う心に尽きます。
ここでは、もしも故人が直葬を希望していた場合の対応を解説していきます。一般的な葬儀とは違い、自分で対応しなければならないことが多い直葬において、特に気をつけるべき3つの点を確認しておきましょう。
埋葬方法
通常、葬儀を行わない場合でも故人は必ず埋葬する必要があります。埋葬方法には「火葬」と「土葬」がありますが、一般的には火葬を行います。火葬に関しては、必ず火葬場で行ってもらう必要があるので、個人で火葬することは絶対にしてはいけません。土葬に関してはごく一部の地域や霊園でのみ可能になっています。
散骨
故人が散骨を望んでいた場合、散骨も法律的には問題なく行えます。法律上では埋葬に関しては明確に定められていますが、散骨に関しては一切定められていません。しかし、墓地に埋葬せずに散骨を検討する場合は、遺族間で十分に話し合う必要があります。これは後々の遺族間のトラブル等につながることを避けるためです。
不明な点に関しては、お世話になっているお寺や葬儀社など、専門的な知識を備えた機関に相談してみるのも一つの手段でしょう。
宗教的な儀式
直葬を選択した場合、お通夜や告別式は行いません。しかし、長く交流してきたお寺などへ事前の連絡をせずに、お通夜や告別式のような宗教的儀式を省略してしまうとトラブルに発展するおそれがあります。故人の遺言通りに行っていたとしても、以前のような関係性を保つことが難しくなるかもしれません。
トラブルにならないように、事前に故人の遺言を遺族間できちんと確認し、情報を共有すべき人には必ず遺言の内容を伝えて相談しましょう。
生前から備えておきたいこと
遺言をした側もされた側も、お互いが死別した後のことを考えているからこそ、いろいろな悩みが生まれるでしょう。その際は、遺言をしたいがどうすればよいのか、遺言はしっかりしてほしいなど、お互いに話し合ってみるのもよいかもしれません。
ここでは、生前からしっかりと備えておきたいことについて、それぞれの立場から考えてみましょう。
遺言する側が生前から備えておきたいこと
これから遺言書を作成しようと考えている方は、まず、遺言書の種類や作成方法についてきちんと下調べを行いましょう。せっかく作成したのに不備があり、効力をもたない遺言書になってしまっては意味がありません。また、そのような遺言書は遺族の混乱を招いてしまうおそれもあるので注意が必要です。
遺言書をしっかりと作成した後は、家族や親族へ遺言の保管場所を伝える、専門の機関に預けるといった管理方法についても考えておく必要があります。葬儀がすべて終わってから遺言書が出てきた場合、故人が希望していた葬儀の意向と内容が違っていたなど、遺族が後悔するケースも少なくはないからです。
また、葬儀に関する遺言の内容はあまり強制的な文面は残さないほうがよいかもしれません。葬儀にはもちろん遺族側の意向もあるので、その点も十分留意した遺言書を作成するようにしましょう。
また、葬儀に関する内容は生前にあらかじめ話し合っておくのがおすすめです。すれ違いや食い違いが少なくなることに加え、自身が亡くなった際の段取りなどがスムーズに進むでしょう。
<関連記事>
【遺言書の作成方法を完全ガイド】種類ごとの書き方と注意点を徹底解説
遺言される側が生前から備えておきたいこと
近年では「終活」という言葉が、ごく一般的な言葉として定着してきています。そのため、自身の周りで終活を始めている方もいるのではないでしょうか。もしも終活を行っている家族や親族がいる場合は、残される側として、終活を行っている方をできる限りサポートするようにしましょう。
普段の会話のやり取りを大切にし、相談を受けた際には一緒に疑問点を調べる、話し合うといったことをして解決に導いてあげるとよいかもしれません。生前から積極的に関わっておくことで、自身にとって大切な方の意思を理解することに繋がります。
また、終活を行っているわけでなくとも、日常的に死別した後のことを話し合っておくことも重要です。家族が亡くなった際は、精神的に非常に辛くなり、さらには亡くなった後の手続きや対応などでも慌ただしくなります。
遺言の内容や死別した後の意向について、生前から家族間で共有しておくことで、亡くなった後の対応をスムーズに行うことが可能です。また、遺族の精神的な負担の軽減へと繋がるでしょう。
他にも、「遺言執行責任者に指名したために遺言書を預けたい」と頼まれる方もいます。依頼があったときはトラブルを避けるために、遺言書を書いた当人やその他に相続人がいる場合はその相続人なども交えて話し合いを重ね、お互いが納得できるようにしましょう。話し合いの際には、弁護士などの専門的知識のある人に同席してもらうと円滑に話がまとまることが多いでしょう。
遺言書の存在やその保管方法について生前から話し合う機会がなかった場合は、亡くなった後になるべく早く故人の身の回りを整理するなどして、遺言書や葬儀に関する希望が書かれたメモなどがないか確認をするとよいでしょう。そうすることで執り行った後に遺言を発見した、というパターンを防ぐことができます。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
この記事では、遺言の種類や遺言の効力、直葬を望んでいた場合はどうすべきかについて解説しました。近年では、自らの死後に関して生前から計画し、専門の業者へ相談する方も増えてきています。
終活を進めていく上で、どのような葬儀がよいのか、遺言の書き方はどうすればよいかなど、お悩みになる方も多いでしょう。そうしたお悩みを解消する方法として、専門知識のある業者への相談等は非常に有効な解決手段の一つです。
少しでも疑問点や不明点がある際には、ぜひ小さなお葬式までご相談ください。遺言については法律問題も絡んでくるので、自身で調べてもわかりづらい、解決しない場合が多いのも事実です。
また、小さなお葬式では一般的な葬儀はもちろん、直葬プランなど、故人のさまざまな希望に応じたサポートも可能です。終活中で葬儀についてプランを立てたいがどうしたらよいのかわからない、遺言に書かれていた希望に添って葬儀をしたいなどでお悩みの方も、経験豊富な我々スタッフ一同にお任せください。お客様一人一人の気持ちへ寄り添い、最も適切なプランをご提案いたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


東京や一部の地域では7月、ほかの地域では8月にお盆を迎えることが多いようです。ホゥ。