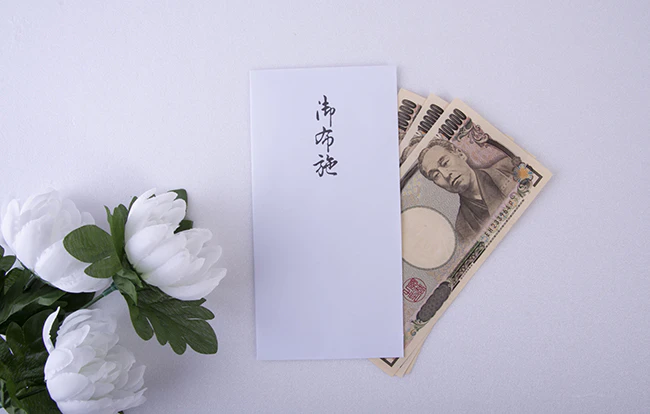お墓は自分の家族や近しい親族の遺骨を納め、永く供養するためのものです。しかし、お墓を維持していくためには、家族や親族がお墓を引き継いで管理する必要があります。特に、遺族や親族が遠方に在住している場合や、今後引き継いでいく人がいない場合は、お墓を誰も管理できなくなる可能性があります。
その場合は「墓じまい」や「永代供養」という方法を選ぶのも1つの方法です。この2つは混同しやすいので、それぞれの違いについて解説します。
<この記事の要点>
・墓じまいとは、墓から遺骨を取り出し墓石を撤去して土地を管理者へ返すこと
・永代供養とは、お寺や霊園の管理者が永代的に遺骨の管理や供養を行うこと
・墓じまいに必要な費用は50万円程度、永代供養の場合は3万円~200万円程度かかかる
こんな人におすすめ
墓じまいと永代供養の違いを知りたい方
墓じまいの流れと費用を知りたい方
永代供養の流れと費用を知りたい方
墓じまいと永代供養の違い
墓じまいと永代供養について、あまり違いがわからないという方もいるのではないでしょうか。どちらも「現在のお墓」を使わなくなる方法なので、混同しやすいのかもしれません。しかし、墓じまいと永代供養は目的が大きく異なります。
とはいえ、墓じまいと永代供養は大きく関連する部分もあります。そこでまずは、墓じまいと永代供養の基本を知っておきましょう。
墓じまいとは
墓じまいとは、「墓を仕舞う」こと、つまり今あるお墓を片付けることです。内容としては、墓に納められている遺骨を取り出し、墓石を撤去して更地に戻して、お墓を建てていた土地をお墓の管理者へ返します。
墓じまいを行う理由には、以下のようなものがあります。
・お墓を管理する人がいない
・管理の手間と金銭的負担が大きい
・家族や親族に管理の負担をかけさせたくない
墓そのものを片付けるので、家族や親族が遠方に在住しているケースや、子どもや孫など墓を引き継ぐ人がいないケースでも問題ありません。ただし、墓じまいには工事の費用がかかる点と、相談せずに実施するとほかの親族とトラブルになり得る点に注意が必要です。
永代供養とは
永代供養とは、家族や親族に代わってお寺や霊園の管理者が「永代的に」遺骨の管理や「供養」を行うことです。墓じまいの目的は「墓を片付ける」ことでしたが、永代供養の目的は「納骨」と「供養」といえます。
具体的には、お寺や霊園で単独の納骨区画を借り、一定年数はそこに遺骨を納めます。一定年数が経過したのちは「合祀」という共同納骨の形式となるのが一般的です。単独の納骨スペースに納められている間は、家族や親族が個別形式でお参りができます。
墓じまいから永代供養先へ移すこともできる
墓じまいを行う際は、納骨されている遺骨を別の場所へ移す必要があります。このとき永代供養先へ移す、つまり改葬することも可能です。墓じまいを検討しているならば、あわせて永代供養先についても同時に候補を探して比較しておくとよいでしょう。
家族や親族が遺骨の保管で悩む必要がないうえに、永代供養先で定期的な法要を行える場合もあります。
お墓を引き継ぐ人がいなくても永代供養は利用できます。また、お墓を建てるのに比べて初期費用を大きく軽減できるでしょう。ただし、個別に納骨できる期間が決まっている点と、家族や親族の理解を得るのが難しい場合もある点に注意が必要です。
墓じまいの流れと費用
墓じまい検討している場合は、遺骨をどうするかを考えなくてはなりません。現地での行政手続きが必要になるうえ、事前に親族へ相談して承諾を得ておく必要もあります。またどのくらいの費用が必要かという点に関しても気になることでしょう。
ここでは墓じまい後の供養方法と墓じまいの流れ、費用目安について解説します。
1.墓じまいの方法を選ぶ
お墓以外に供養する方法は以下の3つです。
| ・手元供養 |
| 手元供養は、遺骨のすべて、または一部を自宅や専用のケースに入れて身につけるなど、身近なところに保管して供養します。お墓や仏壇が置けない家庭でも供養でき、費用や場所をとりません。故人とできるだけ永く一緒にいたいという方が利用するケースも見られます。 |
| ・散骨 |
| 遺骨を粉末状にし、野山や海などにまく方法を散骨といいます。日本では火葬をするのが一般的ですが、散骨専門の業者もあります。家庭の事情や費用面において、散骨はコストのかからない方法として注目されています。 散骨は個人でも可能ですが、散骨を行う場所は法律に関わるため、沖合や私有地などの他人に迷惑がかからない場所を選ぶようにしましょう。 |
| ・永代供養 |
| お寺の納骨堂に納骨し、住職が供養します。「永代」とつくことから、親族がお参りに行けない場合でも、住職がお経やお供物を供えるなどの供養・管理も行うのが特徴です。お墓を新たに購入する必要がないため、お墓の管理が難しい方に適した方法といえます。 |
2.墓じまいの手続きを行う
お墓を撤去する場合には、届け出する書類や遺骨の移動など、さまざまな手続きが必要となります。墓じまいの一般的な流れは以下の通りです。
| (1) | 親族と相談する |
| (2) | 遺骨の受け入れ先を決める |
| (3) | お墓の管理者に墓じまいすることを申し出る |
| (4) | 改葬の諸手続きを行う |
| (5) | 開眼供養と抜魂法要を行う(仏教の場合) |
| (6) | お墓の撤去作業を依頼 |
| (7) | 新しいお墓やお寺へ納骨する |
遺骨をどこに移動するか、管理するのは誰かなどを、親族間で相談しておくとよいでしょう。
墓じまいの費用目安
墓じまいをする際には、新たに墓地を購入するか、散骨するか、あるいはお寺で永代供養をするかなど、遺骨の移動先によっても費用は異なります。一般的な費用目安は50万円ほどですが、あくまで目安なので、詳しくは各業者や葬儀社へ問い合わせましょう。
また、墓じまいする際には、お墓から魂を抜く儀式である閉眼供養や法要の際に志としてお布施などを用意しておくと安心です。
永代供養の流れと費用
昭和初期頃の納骨堂は、お墓に入る前の一時的な保管場所でした。しかし現在では、利便性の高い供養スタイルの1つとして利用する人が増えています。
それに伴い、現在の永代供養には、さまざまな遺骨の安置方法があります。どの場所へどのように納骨するかで費用目安は変動します。
ここからは、永代供養の流れと費用について解説します。
1.永代供養の種類を選ぶ
永代供養は、お寺の納骨堂、あるいはお寺が所有する土地に遺骨を納めますが、いずれもお寺や宗派などによって種類が異なります。納骨堂と呼ばれる仏壇のようなものに骨壺を収蔵する方法が一般的ですが、永代供養にはほかにも種類があります。
| ・合祀型 |
| 故人の遺骨をほかの方々の遺骨と一緒に埋葬する方法です。永代供養の中でも、もっとも費用を安く抑えられる傾向にあります。しかし、一度合祀してしまうとほかの遺骨と一緒になってしまうため、その後でお墓へ入れたい場合などに故人の遺骨だけを取り出すことはできません。 |
| ・集合型 |
| 故人の遺骨や骨壷を、お寺の室内にある共通区画内の個別スペースに納めるタイプです。納骨堂あるいは納骨壇などの形態が代表的です。お墓を建てるまでの一定期間など、ほかの遺骨と分けて安置できるのが特徴です。お寺の永代供養でよく見られるタイプですが、お寺や宗派によって異なるので、確認しておくと安心でしょう。 |
| ・個別型 |
| 従来のように個別にお墓を建てるタイプが個別型です。夫婦や家族が入れるものもあり、人数によって大きさなどが異なります。また、施設によっては、一定の期間が経過した後は合祀される場合もあるため、永代供養をする際に確認しておくとよいでしょう。 |
2.永代供養先を選ぶ
永代供養先を運営しているのは主に寺院や霊園ですが、それぞれにおいて特徴や利点が異なります。
| ・寺院 |
| 寺院は、供養のプロである僧侶(住職)に相談できるという点が大きいメリットといえます。そのため先祖代々がお寺とお付き合いがある、あるいは宗派が決まっている場合に、寺院で永代供養を依頼するケースが多く見られます。檀家として長く寺院とお付き合いすることになるので、依頼する方のみでなく周りの家族も安心できるでしょう。 |
| ・霊園 |
| 民間企業が管理する民間霊園や、地方自治体が管理する公営霊園などです。どちらの霊園でも、宗教や宗派が決まっていない場合や無宗教でもお墓に入ることができます。 民間霊園は公益法人や宗教法人が管理しており、サービスの充実度が高い傾向にあります。例えばトイレや休憩所、駐車場などを完備している施設や、送迎バスなどの手配があり通いやすいといった点が利点です。 |
3.永代供養の手続きを行う
永代供養を依頼する際には申し込み手続きが必要です。申し込みの流れを簡単に紹介します。
| (1) | 施設へ問合せ、見学 |
| (2) | 入金 |
| (3) | 納骨 |
| (4) | 永代供養 |
| (5) | お参り、法事 |
親族などもお参りすることを考えると、親族なども見学に同行してもらい、納骨方法や納骨場所、法要の様子などを一緒に確認しておく方がよいでしょう。
永代供養の費用目安
永代供養では、どのような納骨方法を選ぶかによっても異なります。合祀と集合墓、個別型の費用目安は以下の通りです。
| 合祀墓 | 3万円~30万円程度 |
| 集合墓 | 40万円~150万円程度 |
| 個別型 | 30万円~200万円程度 |
費用は3万円~200万円と幅が大きい傾向にあります。区画の大きさや立地、法要回数や個別保管年数などでも費用は変動します。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
今後お墓の維持と管理が難しくなる場合は墓じまいを行い、お墓を片付けるという選択もあるでしょう。しかし、墓じまいをすると決めたら、遺骨をどのように保管するかを考えなくてはなりません。そのとき、納骨先として候補に挙がるのが永代供養です。
「先祖の墓を管理しきれなくなった」場合や「自分の死後、管理の負担を減らすために自分の墓を持ちたくない」という方は永代供養を検討してみましょう。
小さなお葬式でも、墓じまいや永代供養の依頼も承っております。「OHAKO(おはこ)」というサイトにて、地域や納骨タイプなどから最適な納骨先を探すことができます。
墓じまいと永代供養、さらにご遺骨の郵送や改葬手続きなども含めてサポートいたしますので、ぜひ一度小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


不祝儀袋は、包む金額に合わせて選ぶと丁寧です。ホゥ。