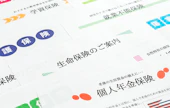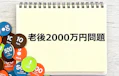ライフプランを考える際に、老後の生活まで思い描くのは重要です。現在の貯金額に関係なく、老後にいくらの貯金額が必要になるかが気になる方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、老後に備えるために必要な貯金額についてご紹介します。老後の平均支出額や平均貯金額をチェックしておけば、今からでも対策ができるでしょう。不足金をカバーする方法についてもご紹介します。
<この記事の要点>
・高齢夫婦の平均貯蓄額は2,400万円以上である
・老後に必要な資金は生活費や医療費、自宅修繕費などである
・老後資金の不足をカバーする方法として、できるだけ長く働くことやiDeCoの活用などが挙げられる
こんな人におすすめ
老後の貯金を心配している人
平均的な貯金額を知りたい人
計画的な貯金や資産運用の必要性を知りたい人
老後に必要な貯金額はいくらなのか
老後に必要な貯金額を調べようとすると、さまざまな情報が見つかるでしょう。より正確な数値を知りたい場合、総務省が行なった調査の結果を参考にできます。今回ご紹介するのは、2023年の調査で分かった高齢世帯の平均支出額と平均貯蓄額です。あくまでも平均値なので、地域やライフスタイルによって金額は変わります。
高齢夫婦の平均支出額
総務省が発表した「2023年(令和5年)家計の概要」によると、世帯主が60歳~69歳の世帯の消費支出は月額平均306,476円、70歳以上の世帯の月額平均は249,177円です。また65歳以上の夫婦のみの無職世帯の実収入は月額平均244,580円、消費支出の月額平均は250,959円となっています。
高齢夫婦の平均貯金額
総務省が2023年に行なった家計調査報告を見ると、2人以上の世帯の貯蓄状況も分かります。世帯主が60歳~69歳の場合、平均貯蓄額は2,432万円です。ただし、平均201万円の負債もあります。70歳以上の場合、平均貯蓄額は2,503万円で、負債の額は平均78万円です。
どの年齢であっても、負債の中で大きな割合を占めているのが住宅や土地のための費用です。
(参考:『家 計 調 査 報 告 貯蓄・負債編』2023年)※2024年11月時点
老後に備えて貯金をする必要性
老後のためにできるだけ早く貯金を始めるのは重要です。リタイア後は一般的に収入を増やすのが難しくなります。年金で十分に暮らしていけると思っていた方が、実際の年金額を知ってがっかりすることもあるでしょう。
健康であれば仕事を続ける選択肢もありますが、健康上の問題を抱えて働けないこともあります。治療のために出費が増えることもあり、事前の対策が必要です。収入が減るとライフスタイルを大幅に見直す必要が生じることもあるので、期待していた老後ライフを満喫できない恐れもあります。
老後に必要となる主な資金
子どもがいる家庭の場合、子どもが自活すれば養育費が減ります。しかし、老後にはさまざまな費用が発生するので事前の計画が大切です。
年齢に関係なく負担する必要がある生活費に加え、介護費や医療費の問題は軽視できません。長く住んでいる一軒家やマンションの修繕費がかかることもあります。老後に必要となる主な資金の特徴をチェックしましょう。
生活費
食費や服飾費・光熱費など毎月さまざまな費用が発生します。健康的な生活を送るためにはある程度の費用を負担する必要があるので、収入と支出のバランスを事前に計算するとよいでしょう。
例えば、夫婦共に働いていた場合ライフスタイルによっては年金だけで足りるケースもあります。問題となるのは、夫婦の片方が働いていない場合に国民年金しか得られないケースです。毎月の生活費が支払えなくなるケースもあり、貯金をしておく必要があります。
介護費・医療費
若いころは健康だったとしても、高齢になるにつれて病気と向き合うことが多くなるでしょう。十分な介護や医療を受けるためにも貯金は大切です。
ただし、介護費や医療費は国の制度が利用できます。介護費用の負担額が減る介護保険制度や、一定額以上の医療費を負担しなくて済む高額療養制度です。状況に合わせて国の制度を活用すると、支払いの負担が軽減するでしょう。
自宅の修繕費
一軒家やマンションを所有している場合、毎月の家賃は発生しません。しかし、建ててから時間が経っていると経年劣化で修繕が必要になってきます。簡単に直せるケースであれば費用はあまりかかりませんが、外壁や屋根などの修繕は比較的高額です。地域や修繕の規模にもよりますが、大規模修繕だと100万円以上になる場合もあるでしょう。
経年劣化以外に自然災害などによる被害もあります。マンションの修繕積立金のように、個人としても修繕費用を備えておくと安心です。
老後貯金の不足をカバーする方法
老後の支出と収入・貯金を比較すると、支出のほうが大きくなると気づくことがあります。事前に対処をしないと貯金が減り続け、最終的には生活するのが難しくなるでしょう。収入や貯金の不足をカバーするためにおすすめの方法を紹介します。できる限り長く働くことや支出の見直しをすることに加えて、計画的に資産運用をすることもおすすめです。
できる限り長く働く
定年後は趣味や家族との時間を大事にすると計画していた場合でも、収入が足りないと分かったらできる限り長く働くのがおすすめです。長年勤めた職場を離れて新たな職場を探したり、定年後も違う雇用形態で働き続けたり選択肢はあります。
定年前と同じ額の給料をもらえないとしても、年金の無給期間を増やせるのもメリットでしょう。定年後も働き続ければ、収入があるので年金を受け取らなくても生計は立てられます。年金を受け取る時期を先延ばしにすれば、本当に働けなくなったころでも生活水準を落とさずに生活ができるでしょう。
支出の見直しをする
年金だけでは生活が苦しいと分かった場合、支出の見直しが必要です。趣味や旅行などに費やしている費用を減らせないかを考えましょう。老後を見据えて、若いうちからあまり費用がかからない趣味を見つけて楽しむのもひとつです。
他にも携帯電話やインターネットなどの通信費、自動車のローンや維持費など固定費を見直すのも効果的です。子どもが結婚したり孫ができたりライフイベントによって必要な支出が変わることもあるので、定期的に必要な支出かどうかを見極めましょう。
保有資産を有効的に使う
一軒家やマンションを所有している場合、資産を有効活用しない手はありません。例えば、都市部から郊外に引っ越して、一軒家やマンションを賃貸にできます。賃貸にする場合の収入と引っ越し後に払う家賃を比較して検討しましょう。以前は通勤に便利な場所に住んでいた場合でも、定年後は郊外のほうが好ましい場合もあります。
子どもが家を離れた後に、夫婦2人で十分な広さの住居に引っ越すのもよいでしょう。家賃収入を得ながら生活費の不足分を補えます。賃貸にするのが難しい場合、自宅を売却して老後資金に充てるのもひとつの方法です。ただし、売却にともなって手数料や税金がかかるので、資金をより多く残せる方法を選びましょう。
iDeCoを利用する
個人型確定拠出年金ともいうiDeCoは、加入が任意の私的年金制度です。自分で掛金を払いながら、老後のために資産を運用します。
運用した資産を受け取れるのは60歳以降で、受取方法は年金形式や一時金形式です。資産を一括で受け取ったり、最長20年の年金として定期的に受け取ったりできます。資産の一部を受け取りつつ、残りを年金形式で受け取る方法も選択可能です。
iDeCoのメリットとして、税制上の優遇措置を受けられます。一般的に資産運用による収益には税金がかかりますが、iDeCoなら運用益は非課税です。iDeCoのために払った掛金は所得控除の対象になるので、所得税や住民税を抑えられます。ただし、iDeCoは貯金ではないので元本割れのリスクがあり、基本的に60歳までは途中解約できません。
つみたてNISAを利用する
つみたてNISAも税制上の優遇措置を受けられる資産運用法です。特定の投資信託を定期的に購入すると、投資信託の分配金や譲渡益が非課税になります。
非課税となる新規投資額は1年あたり40万円までなので、1か月あたり約3万3,000円をつみたてNISAに設定可能です。数千円や1万円でもつみたてNISAを利用できるので、資産運用の経験があまりない方にもおすすめです。
つみたてNISAを利用する場合、2018年~2037年までに購入した投資信託が対象になります。非課税期間は20年間です。2037年に購入した投資信託も、購入後20年目まで非課税になります。
つみたてNISAに対して一般NISAもありますが、両方の制度は同時に利用できません。資産運用を行うにあたってメリットが大きいほうを選ぶ必要があります。
参考:『金融庁|つみたてNISA』
個人年金保険に加入する
国民年金や厚生年金とは違って、保険会社などで加入する私的年金が個人年金保険です。国民年金や厚生年金に追加して老後の収入を得たい場合に加入を検討できます。
保険金は、一時金形式や年金形式で受取可能です。被保険者が亡くなったときのために個人年金保険に加入するのも良いでしょう。加入するサービスによって異なりますが、遺族が一時金や年金を受け取るよう設定できます。
個人年金保険のメリットは、税金の申告の際に生命保険料控除を受けられることです。ただし、生命保険料控除にはいくつか条件があるので、加入前に確認しておきましょう。個人年金保険に加入すると保険金が事前に分かるので、老後の計画を立てやすいのもメリットです。しかし、途中解約などによって元本割れするリスクもあります。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
地域やライフスタイルによって変わりますが、老後必要になる費用は総務省が行った調査結果が参考になります。生活費や介護費・医療費・自宅の修繕費など、さまざまな費用がかかるので老後に備えて計画的に貯金をしておきましょう。
老後の収入・貯金不足を回避するために、定年後も働いたり支出を減らしたりするのも有効です。自宅などの保有資産で老後費用を捻出するのも良いでしょう。iDeCoやつみたてNISAなどの資産運用もおすすめです。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


年金制度には大きく分けて公的年金制度と私的年金制度の2種類があります。ホゥ。