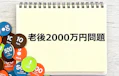老後の資金がどれくらい必要かご存じでしょうか。「老後資金2000万円」という言葉が一時期有名となったこともありました。人生100年時代といわれるようになり、昔と現在では、老後の在り方が一変しています。
今回は、「老後の資金はいくら必要であるのか」「老後資金を貯める方法」について解説していきます。ぜひ参考にして貯蓄や資金の増やし方や老後に向けた準備に活かしていってください。
<この記事の要点>
・夫婦の場合、老後資金は25万円以上が必要
・老後資金は「支出を減らす」「収入を増やす」「資産運用をする」の方法で貯めるのが一般的
・老後資金を準備する際、ファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめ
こんな人におすすめ
老後資金が気になっている人
老後資金の貯め方を考えている人
老後資金として年金がいくらもらえるのか気になっている人
老後資金とは
一般的に老後資金とは、老後に生活するために必要となる資金のことを指します。総務省の調査によれば世帯主が60歳~69歳の世帯の消費支出は月額平均306,476円、70歳以上の世帯の月額平均は249,177円です。また65歳以上の夫婦のみの無職世帯の実収入は月額平均244,580円、消費支出の月額平均は250,959円となっています。
また、公的年金のほとんどが生活費の捻出でギリギリになる場合もあります。例えば65歳から25年間生きると仮定した場合、公的年金の受給と生活費の支出との月々の差が7万円以上になってしまうとトータルで約2100万円の差に発展します。老後を楽しむためには、ある程度の資金が必要といえるでしょう。
(参考:『2023年(令和5年) 家計の概要』総務省統計局)※2024年11月時点
老後とは
老後とは、一般的にどこを起点として始まるのかは疑問に思うことだと思います。
実際にはいつからと明確な起点があるわけではなく、捉え方についても人それぞれです。個人によって相違があり、仕事を定年退職した直後からと認識している人もいれば、年金や退職金など自身が老後のために準備した資金を使い始めるタイミングで老後と捉える人もいるようです。
65歳を老後のスタートとした場合、平均で20〜25年ということがいえそうです。従って、資金準備する考えに至った際は、約20年~25年の間は生活できるほどの貯えが必要になってくると予想が立てられます。
老後の生活を考える
老後資金を考慮した際に、どの程度の金額を貯えておく必要があるのか予測を立てる場合は、どのような老後生活を送っているのか具体的な生活状況を想像する必要があります。
手始めに、老後の生活について具体的に想像し設計してみてください。
老後の生活費を見積もる
現役で働いている状況で老後の生活をイメージすることは難しいです。しかし、将来的にどのような生活をするかが分からないのは、誰もが同じことです。ですが、ぼんやりとどうしたいのか決めておかなければ、今後のための準備を明確なものにしづらくなります。
将来を見越して必要な費用を大きく見積もって計算することが大切です。大きく見積もることで、余分な部分に自分の趣味ややりたいことをする費用となり、実際に用意しなくてはならない資金となってくるでしょう。
年金と退職金の見込みを把握する
さらに退職後に受け取れる金額を把握しましょう。まず代表的な収入として公的年金が挙げられます。40代で送られてくる「ねんきん定期便」には、まだ支給開始日や支給見込み額は記載されていません。ここに記載されている参考金額は比較的少なく見積もって記載してあります。よって老後の生活を考える際の判断材料としてはあまり参考にならないかもしれません。
年金支給額を確認したい際は「ねんきんネット」に登録すると簡単に確認できます。ねんきんネットには自分の支給見込み額を試算できる仕組みになっているので、それを用いて支給額を確認して資産の計算に利用していくことを推奨します。
また、退職金についてはほとんどの場合、会社の就業規則に支給の基準といった記載があるので、制度の内容と退職金を大まかに把握することが可能です。
最終的に必要な老後資金を定める
公的年金、退職金そして老後の生活費がある程度把握できたら老後の生活設計をしましょう。この時は、あくまで現時点での生活設計で構いませんので、高望みしすぎないように設計することが大事です。
このようにして実際に計算してみると「老後資金2000万円」というのは的外れな数値ではないことが分かってくると思います。また、目標設定をすることで今後やらなければならないことが明確になってきます。
公的年金の受け取れる金額は?
公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。厚生年金はよく2階建ての建物に例えられることが多く、1階部分は国民年金で日本に住んでいる20歳以上から60歳未満の人は全て加入しています。そこからさらに2階建ての厚生年金で会社員や公務員が加入しており、国民年金に上乗せする形になるため2階建てに例えられています。
いつから受け取れるのか?
年金は65歳から受け取ることが可能です。また、年金制度には繰り上げたり繰り下げたりして受け取る期間の調整を行えます。これを利用すれば自分の希望したタイミングで公的年金を受け取れるようになります。
但し、受け取り期間を調整できるのは前後年までとなります。また受け取り時期を調整することで受け取れる金額も変わりますので、あらかじめ金額等を確認してから検討するようにしましょう。
公的年金の平均受給額
厚生労働省が発表した日本年金機構の令和6年4月分からの年金額によると、国民年金と厚生年金を受け取る場合、合計金額が298,483円(老齢基礎年金68,000円、老齢厚生年金230,483円)です。
あくまで上記の厚生年金の298,483円は、40年間就業した場合に受け取れる年金の給付水準となるので、この限りではありません。しかし、妻が働くことで老後の受給額にも大きな差が出ることは確かです。
(参考:『令和6年4月分からの年金額等について』日本年金機構)※2024年11月時点
老後資金の貯め方
公的年金は、老後の資金の一部に過ぎないことが分かりました。よって、今の生活を守りながら将来の生活を成り立たせることは容易ではありません。ではどんな方法で老後資金を準備すればよいのでしょうか。
資金の貯め方は「支出を減らす」「収入を増やす」「資産運用をする」の3種類の方法が一般的です。この3種類の方法に則った資金の貯め方について紹介していきます。
支出を抑える
比較的手軽に取り組めるのが支出を抑えることです。支出を抑えるのは、簡単にいうと節約をすることですので、老後の資金を貯めるためと難しく考えず気軽に取り組んでみてください。
まずは保険を見直してみてください。保険はライフスタイルによって適しているプランが変わってきます。特に家族構成が変わることや生活環境が変わればさらに状況も変わりますので、環境の変化ごとに見直しをしてみるとよいでしょう。
次に挙げられるのが通信費です。特に大手キャリアと契約している場合であれば、格安スマホに乗り換えるだけで結構な額の節約をすることが可能です。これは手軽にすぐできることですので、老後の資産を貯めるという目的でなくても一度見直してみることおすすめします。
続いて住宅ローンの見直しもおすすめです。老後にローンが残ってしまう場合や繰り上げ返済が難しい場合は、住宅ローンの銀行を見直すことも有効です。住み替えも含めて検討してみるのもすることをおすすめします。
長く働いて収入を増やす
体に問題がないのであれば、長く働き続けるのもよいでしょう。働くことで単純に収入が増えるというメリットがあります。現役時代と同程度働く必要はなく、自身の健康面や精神面にプラスになる程度にのんびりと働いてみるのもよいでしょう。
年金の繰り下げ受給
通常65歳から年金を受け取りますが、年金は繰り下げ受給をすることが可能です。このメリットは、年金を繰り下げ受給することで1カ月遅らせるたびに0.7%増額することが可能になります。
繰り下げができるのは、最大で5年間です。5年間遅らせることが叶った場合最大42%増えることになり、その分の年金を増やすことが可能になります。70歳まで年金受給を遅らせられるかは、その時の状況によって変わってくるので今からどうするかを決めることは難しいです。
しかし、最近では70過ぎても元気な人も増えてきていますので、今から健康に気を使って生活してみるのもよいかもしれません。また、先ほど紹介した長く働くことと組み合わせることで、収入も増えて年金も増え一気に老後資金問題が解消に繋がるかもしれませんので、有効な手段といえます。
資産運用を行う
老後に向けて資産運用をする場合、手堅く運用することをおすすめします。投資は「長期」「積み立て」「分散」が基本となってきます。資産運用は、長い時間をかけて運用することでリスクを減らしてコツコツ資産を増やしていけます。
老後の資産がないと分かってからでは、少し遅い場合もあります。基本的に若いうちから老後に向けて資産運用を考える場合なら、資産運用に時間をかけることが可能になりますので、資産を増やす方法としてはおすすめです。
貯金ではなく投資をして老後資金を準備しようと考えているのであれば「個人向け国債」か「つみたてNISA」を利用して手堅く投資していくことをおすすめします。これらは大きな金額を稼ぎにくいですが、リスクも少ないので、老後の資金形成には向いている方法といえます。
老後の資金についてプロに相談する
老後の資金やその貯め方について紹介してきましたが、人生何があるか分かりません。時には不測の事態にも陥ることがあります。そんな時こそ専門家に相談することが、1番間違いがなく早い方法といえます。
こういう場合にはファイナンシャルプランナーに相談することをおすすめします。相続や法律のことであれば弁護士が適任かと思いますが、お金のプロといえばファイナンシャルプランナーです。老後の資金について不安を感じた時には、早めにプロに相談をしたほうがよいでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
今回は老後の資金やその貯め方について紹介してきました。老後の資金を考える際にはまず、自分の老後の生活設計について考えることをおすすめします。そうすることによって自身が老後でいくら必要になるかが分かってきます。
そして貯めなければならない金額をある程度把握したら「支出を抑える」「収入を増やす」「資産運用をする」この3つの方法を基本に、自身にあった貯め方で資産形成をしていくことをおすすめします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


遺産相続が発生した場合、いかなる場合でも配偶者は相続人になります。ホゥ。