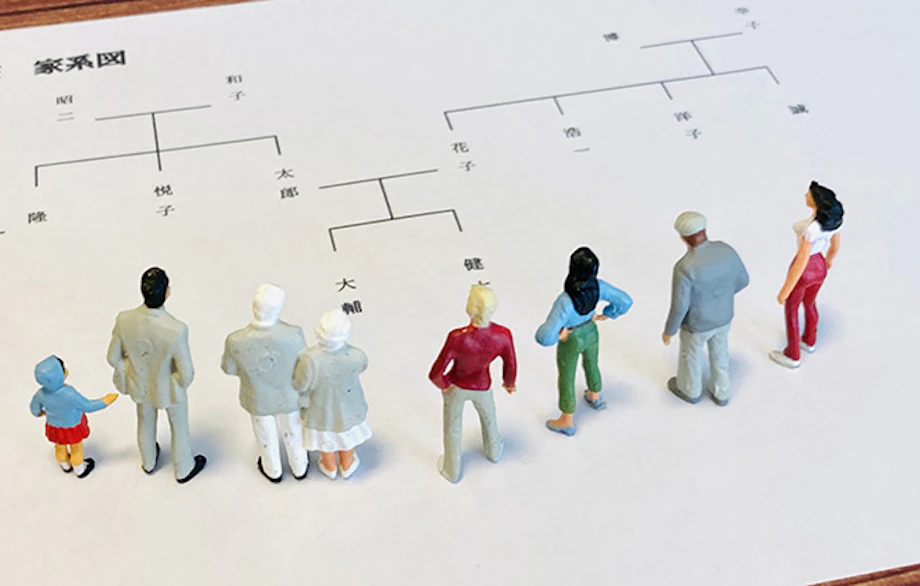「身近な方の死が近い」「最近さよならをした」という方は、葬儀や年金、相続の手続きが必要になります。相続を分配するうえで、遺留分について知っておくことが重要です。
しかし遺留分とは何か、具体的に知らない方もいるでしょう。ここでは遺留分の意味や、計算方法について解説します。遺産トラブルを防ぐためにも、遺留分の知識を深めましょう。
<この記事の要点>
・遺留分とは相続人に対して保証されている、最低限の財産を相続する権利を指す
・遺留分の対象財産は相続開始時の財産、生前贈与財産の一部、債務、不相当な有償行為である
・遺留分の合計額は相続財産の2分の1(親または祖父母のみが相続人である場合は3分の1)である
こんな人におすすめ
相続を控えている人
遺留分の試算をしたい人
遺留分とは|意味と対象者
遺留分とは、相続に関する権利のひとつです。その意味や対象者を知り、相続トラブル防止に役立てましょう。ここではトラブルの一例や、推定相続人についても解説しています。
遺留分とは?トラブルに注意
遺留分とは一定の相続人に対して保証されている、最低限の財産を相続する権利です。もし遺言書の内容に不公平だと感じている身内がいた場合、遺留分を主張することにより、一定の財産が受け取れます。
【遺留分トラブルを招く一例】
・遺言書に「1人の子に財産のほとんどを相続させる」と書いた
・遺言書に相続の分配方法について理由を書かなかった
・兄弟間もしくは親子間で仲がよくなかった
遺留分は誰と分ける?(推定相続人)
推定相続人との関係や状況にもよりますが、誰にどのくらい財産を相続するか慎重に決めなければなりません。遺留分をめぐるトラブルを防止するために、遺留分が認められる者を確認しましょう。
下記は、遺留分の認められる者です。
・配偶者
・直系卑属(子ども、孫)
・直系尊属(親、祖父母)
なお兄弟姉妹や甥姪には、遺留分が認められません。
遺留分の割合と計算方法について
相続を分配するうえで、誰にどのくらいの遺留分があるのか気になるかもしれません。ここでは基礎となる財産と、一人あたりの割合、計算方法について紹介します。被相続人との関係によって割合は異なるため、照らし合わせて見てみましょう。
基礎となる財産から確認
遺留分の対象となる財産は主に4種類あり、そこから債務を引いた額になります。
【基礎となる財産】=(1+2+3+4)- 債務
1.相続する前に所有していたすべての財産
2.生前贈与した財産
・相続の1年前に生前贈与した財産
・ただし遺留分侵害を目論んでいた場合は、期間に関わらず対象となる
3.特別受益で受けた贈与
・相続開始の10年以内にされた贈与
・一部の相続人のみに生前贈与された財産
4.不相当な対価をもってした有償行為
・遺留分の権利侵害を目論んでおこなわれた有償行為
補足ですが、民法では以下のように定められています。
【遺留分を算定するための財産の価額】
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
引用:民法第1043条
遺留分の割合は2段階で決まる
遺留分の割合は、「総体的遺留分」と「個別的遺留分」の2段階で計算します。
【総体的遺留分】
・親や祖父母といった直系尊属で財産を分ける場合、割合は3分の1
・上記以外の場合、割合は2分の1
【個別的遺留分】
個別的遺留分は、総体的遺留分にそれぞれ「法定相続分」の割合を乗じて計算します。
「法定相続分」は以下のとおりです。
・親や祖父母といった直系尊属で財産を分ける場合、割合は3分の1
・上記以外の場合、割合は2分の1
遺留分の割合を下記の表にまとめました。
| 相続人 | 総体的遺留分 | 個別的遺留分 | ||
| 配偶者 | 子 | 父母 | ||
| 配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | - | - |
| 配偶者と子 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 | - |
| 配偶者と父母 | 2分の1 | 6分の2 | - | 6分の1 |
| 子のみ | 2分の1 | - | 2分の1 | - |
| 父母のみ | 3分の1 | - | - | 3分の1 |
※兄弟は遺留分がありません
(参考:『民法1042条』https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_1042)
遺留分の計算方法とシミュレーション
具体的にどのように遺留分を計算するのか見ていきましょう。仮の財産と相続人を設定し、計算のシミュレーションをしてみました。
【遺留分の計算シミュレーション】
・基礎となる財産の総額:4,000万円
・遺留分の割合:妻(割合は4分の1)、2人の子ども(割合はそれぞれ8分の1)
・配偶者の計算例:4,000万円×4分の1=1,000万円
・子どもの計算例(1人分):それぞれ:4,000万円×8分の1=500万円
もし上記の割合で財産を分配していない場合、配偶者は1,000万円、子どもはそれぞれ500万円の遺留分を請求できます。
遺留分の侵害には「遺留分侵害額請求」で対応
「公平に財産が相続されていない」「遺留分を侵害された」という方は、遺留分侵害額請求をします。遺留分侵害額請求は、侵害した人に対して精算金を要求する行為です。ここでは請求の方法や、時効について確認しましょう。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求の方法は、以下を参考にしましょう。
1.対象となる財産と推定相続人を調べる
2.遺留分侵害額請求の文書を作成
3.内容証明郵便(配達証明郵便付)で送る
(郵便局により誰がいつ何を送ったのか証明する郵便)
4.相手から返答がないとき、直接会って話し合う
【話し合いで解決しない場合】
5.家庭裁判所にて遺留分侵害額の請求調停をする
(調停員が双方から話を聴き、解決を図る)
6.調停不成立の場合は、裁判で解決する
(遺留分侵害額請求訴訟を提起すると、地方裁判所で認否と反論を述べ合い、審判が下りる。ただし裁判官より話し合いによる和解を勧められるケースも少なくない。)
請求前に時効をチェック
遺留分侵害額請求には、時効があります。相続開始となり遺留分を侵害する「贈与」や「遺贈」があったと知ってから1年以内に時効を迎えます。もし侵害された事実に気付いていない場合は、10年以内だと請求する権利があると覚えておきましょう。
民法改正による変更点
民法改正により、遺留分の取り扱いについて変更点があります。
・改正前:遺留分減殺請求
・改正後:遺留分侵害額請求
以前まで株式や不動産といった財産も、相続人の共有財産になっていました。しかし「4分の1もしくは6分の1の土地や株式を遺留分として請求する」のが難しいケースもあるでしょう。そこで遺留分減殺請求は、財産に相当する金銭の請求である「遺留分侵害額請求」に変更となりました。
遺留分に関するQ&A
下記は、遺留分に関するよくある質問をまとめました。
| 【質問】 | 【回答】 |
| Q.遺留分の権利を持つ親族から「内容証明通知」が届きました。どうすればいいですか。 | A.感情的な話し合いを避けるために、代理人を立てるのが望ましいでしょう。無視をすると「請求調停」される恐れがあるため、早めに連絡します。 |
| Q.不動産の遺留分は、どのように計算しますか。 | A.土地や建物の財産は、地価公示、相続税路線価、不動産鑑定評価額を用いて計算します。また相続を開始するタイミングが算定基準です。 |
| Q.多めに財産を相続したい相続人がいます。 | A.遺留分損害額請求をされないように、生命保険に加入する方法があります。原則として、生命保険の死亡保険金は相続財産の協議対象になりません。 |
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
遺留分とは、最低限保障されている相続人の相続分です。最低限の権利が侵害されている方は、「相続の分配が不公平である」として精算金を請求できるのが特徴です。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。
身近な方の死が迫っている、もしくはお亡くなりになった場合、遺留分を含む相続や葬儀について検討することでしょう。「小さなお葬式」では、お葬式・法要・遺留品の整理をサポートしています。小さな疑問にもお答えする無料の「お客さまサポート」ダイヤルを用意しておりますので、気軽にお問い合わせください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


葬儀費用は「葬儀一式費用・飲食接待費用・宗教者手配費用」で構成されます。ホゥ。