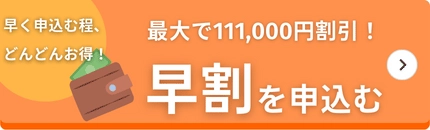これから喪主を務める方やまだ葬儀に行った経験がない方にとっては、告別式がどのような流れで執り行われるのかをイメージすることは難しいかもしれません。
この記事では、初めて告別式に参列する方にもわかりやすく告別式の流れを中心に解説します。
<この記事の要点>
・告別式は午前中に受付を開始し、お昼頃から行われるのが一般的
・喪主は式全体の流れやスケジュールを把握しておく必要がある
・参列者は黒を基調とした服装で、合唱時は数珠を身につけておくのがマナー
こんな人におすすめ
葬儀・告別式の経験がない人
葬儀・告別式の流れをイメージしたい人
葬儀・告別式とは?
葬儀とは、遺族が故人の冥福を祈り、無事に浄土へ辿り着くように見送る重要な儀式です。対して告別式は、故人とのお別れを意味します。ただし、現在では葬儀と告別式について明確な区分はありません。一連の流れとして執り行われるのが通例です。
一般的な葬儀・告別式のタイムスケジュール
葬儀・告別式当日は、タイムスケジュールに沿って行われます。大まかには、次の表のような流れで進行するのが一般的です。
| 集合・受付 | 10:00~ |
| 葬儀 | 10:30~ |
| 告別式 | 11:30~ |
| 火葬 | 12:00~ |
| 解散 | 14:00~ |
現在では、初七日法要を告別式当日に行う場合が多いでしょう。半日ほどかけて一連のスケジュールが進行します。
葬儀・告別式の事前準備
葬儀・告別式では、式の前に準備すべきことがあります。具体的には次の通りです。
・受付担当の取り決め
・座席の場所・焼香順の確認
・弔辞・弔電を読む方、順番の確認
・喪主挨拶の確認
・火葬場への同行者と移動手段の確認
・僧侶に渡すお布施の準備
葬儀・告別式の流れ①【集合~受付】
葬儀・告別式は、集合と受付から始まります。ここでは、葬儀・告別式における集合から受付までの流れを解説します。
喪主・遺族集合
式が11時に始まる場合では、集合時間は余裕を持って10時に設定されることが多く、喪主や遺族はさらに30分早い9時半に集合する場合もあります。一般参列者よりも早く到着して、当日のスケジュールを確認するためです。
受付開始
式が11時から始まる場合では、受付開始時刻は30分前の10時半からとなるのが通例です。特に会計を担当する方は、香典や記帳内容に間違いがないかを確認する作業もあるため、受付時刻よりも早い時間に到着しておくと安心です。
葬儀・告別式の流れ②【着席~焼香】
葬儀・告別式は、斎場へ着席してから始まります。式は下記の流れで進行します。
1.着席・僧侶入場・開式
2.読経・引導
3.弔辞・弔電
4.焼香
ここでは葬儀・告別式における、着席から焼香までの内容を解説します。
1.着席・僧侶入場・開式
葬儀・告別式の開式15分前には、参列者全員の着席が求められます。僧侶が入場してくるまで待機している状態です。そして、僧侶が入場すると同時に開式します。参列者は黙礼と合掌で僧侶を迎え入れるのが通例です。
2.読経・引導
葬儀・告別式の開式後は、僧侶の読経が始まります。目安として40分~60分程度の読経が続くため、参列者全員で故人への祈りを捧げましょう。そして読経の中では、故人に戒名が与えられます。「引導」とも呼ばれ、浄土への道を渡っていくうえで重要な名前だと考えられているのが特徴です。
3.弔辞・弔電
弔辞とは、指定の場所にて故人に対する想いや悼む気持ちを表し贈る、別れの言葉です。読み終えた弔辞は祭壇にお供えします。弔電は、式に参加できなかった方から故人に向けた電報のことです。葬儀担当者から名前を読み上げられます。
4.焼香
焼香とは、葬儀・告別式などの儀式において、香を焚いて故人に拝む一連の行為を指します。焼香は、喪主、遺族、親族、参列者の順番で行うのが一般的です。また、一般参列者の焼香開始から告別式へと移行します。
<関連記事>
【動画で解説】もう迷わない焼香のやり方・マナー
葬儀・告別式の流れ③【僧侶退場~出棺】
式の終盤では、閉式や出棺までを予定しているのが特徴です。具体的には次のような流れで式が進行します。
1.僧侶退場・閉式
2.お別れの儀(別れ花・釘打ち)
3.出棺
ここでは葬儀・告別式における、僧侶退場から出棺までの内容を解説します。
1.僧侶退場・閉式
読経をし終えた僧侶は、焼香が終わると退場します。遺族や親族、参列者全員で合掌して僧侶を見送りましょう。最後は葬儀場の担当者が挨拶を述べて、葬儀・告別式は閉式です。その後は、お別れの儀と出棺に向けた準備の時間となります。
2.お別れの儀(別れ花、釘打ち)
式が終わった後には、お別れの儀があります。故人と生前の姿で会える最後の瞬間です。別れ花にて棺に花を敷き詰め、思い出の品を詰め込みます。そして最後は遺体を安全に運べるように棺に釘を打つ「釘打ち」を行います。
3.出棺
出棺の際には、棺を霊柩車まで移動させる必要があります。遺族や斎場スタッフなどの男性たちで協力して、棺を火葬場まで運びます。またその際には、喪主から遺族代表の挨拶があります。参列者へのお礼や遺族へのサポートをお願いする旨など、伝えておくべき内容を述べる場です。
火葬の流れ
火葬場に到着したら、納めの儀として最後の焼香をあげます。故人との別れを告げ、1時間~2時間の火葬を経て、お骨上げへと移るのが通例です。お骨上げは、遺骨を専用の竹箸でつかみ、納骨していく儀式を指します。始めに歯を入れ、その後、足から順に頭部へ向かって骨を納めていくのが一般的です。
家族葬の流れは?
家族葬の流れは、一般葬と同様です。故人が亡くなってからは、お通夜・告別式などを経て自宅での法要に移ります。
【遺族】葬儀・告別式のマナー・注意点
遺族として葬儀・告別式に参列する際は、マナーや注意点にも気を配りましょう。ここでは、遺族側の葬儀・告別式におけるマナーや注意点を解説します。
喪主としての振る舞い
喪主は葬儀・告別式において、故人や参列者に挨拶を述べる立場です。特に参列者には、故人がお世話になったことや参列への感謝を伝えます。
全体の流れの把握・家族内での打ち合わせ
喪主は、式全体の流れやスケジュールを把握しておく必要があります。また、式をスムーズに進めるためには、家族内で打ち合わせをしておくことも欠かせません。
【参列者】葬儀・告別式のマナー・注意点
参列者として葬儀・告別式に参列する場合にも、守るべきマナーや注意点があります。ここでは、参列者側の葬儀・告別式におけるマナーや注意点を解説します。
服装・数珠のマナー
服装は、男女ともに黒を基調としたものを選ぶのがマナーです。また、式に参列する際には、数珠も持参しておきましょう。多くの宗派において、合掌時に数珠を身につけておくのが一般的です。
香典のマナー
香典には、金額に応じた水引が付いた香典袋の用意が必要です。ただし、5,000円以下の金額であれば、水引が印刷された香典袋を使用しても問題ありません。
式に出席できない時のマナー
式に出席できない場合は、弔電や手紙を送付します。最も重要なのは、迅速な連絡と参列が難しい理由を伝えることです。
<関連記事>
葬式に参列する際の服装の選び方は?喪服の格式についても紹介
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
告別式の流れは受付から始まり、読経や焼香、出棺を経て火葬へと移ります。喪主を務める場合は、1日のスケジュールを把握しておく必要があります。また、事前に打ち合わせをするなどして家族とも連携をとっておく必要があります。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話無料でご連絡をお待ちしております。告別式の流れをより詳しく知りたい方や葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



初七日とは故人の命日から7日目に行われる法要のことです。ホゥ。