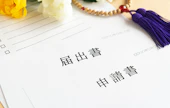告別式と葬式の違いについて、具体的に理解している方は少ないかもしれません。また、「告別式・葬式(葬儀)・通夜」は異なる意味を持つため、弔問に駆けつける際はそれぞれの違いを正しく理解しておく必要があります。
この記事では、告別式と葬式の違いや服装のマナー、香典の渡し方などを解説します。
こんな人におすすめ
葬儀・告別式のマナーについて知りたい方
葬儀の費用について調べている方
葬儀の流れについて知りたい方
告別式・葬式(葬儀)・通夜の違いとは?
告別式・葬式(葬儀)・通夜には、それぞれ違う意味があります。ここからは、それぞれの儀式の概要と違いについて詳しく解説します。
告別式
告別式とは、友人や近所の方、会社の同僚など、生前に交流の深かった方が故人とお別れする儀式です。
宗教的な要素は含んでいないため、故人と生前に関わりのあった方なら誰でも参加できます。葬式を執り行わず告別式のみを執り行う場合は、参列者が故人に別れを告げる場となります。
葬式(葬儀)
葬儀とは、告別式や火葬の前に執り行われるお別れの儀式のことです。告別式とは異なり宗教的な儀式であるため、僧侶による読経や神主による祭祀などが行われます。
告別式と葬儀という2つの儀式をまとめた言葉が「葬式」です。最近では、臨終から骨上げまでの一連の儀式を「葬儀」や「葬式」と呼ぶこともあります。
通夜
通夜は故人が亡くなった翌日の夕方から朝方にかけて執り行う儀式です。線香を絶やさないように注意しつつ、家族や弔問客が故人との思い出話を話したり、亡くなったことを悼んだりします。日程は、葬式との兼ね合いで変わることもあるため注意が必要です。
かつて通夜は夜通し実施する行事でしたが、最近では参列者の負担などに配慮して、2時間~3時間ほどで終了することが多くなっています。また、通夜の前夜に「仮通夜」を行う地域もあります。宗派や地域によって慣習が異なるため、事前に確認しておきましょう。
告別式・葬式(葬儀)・通夜の流れ
告別式・葬式(葬儀)・通夜は、それぞれ流れが異なります。どの儀式に参列するか確認し、流れを把握しておくと焦らずに参列できるでしょう。ここからは、一般的な告別式・葬式(葬儀)・通夜の流れを解説します。
告別式の流れ
告別式では、まず参列者が受付を済ませて、定刻になった時点で開式します。僧侶を招く場合は読経をしてもらい、読経中に参列者は焼香を行います。焼香は故人の宗派の作法に沿って行いましょう。焼香が終わると、弔辞や弔電が紹介されます。
僧侶が退場した後は「お別れの儀」に進みます。式の終盤では、喪主が参列者に挨拶をします。その後、遺族や親族、友人が棺の中に生花や手紙、故人が愛用していた品を入れて、故人と最後のお別れをした後、出棺します。
葬式(葬儀)の流れ
葬式(葬儀)開始から火葬後の精進落としまでの一般的な流れは、以下のとおりです。
1.喪主・遺族集合、受付準備
2.受付開始
3.開式
4.読経、弔辞・弔電の奉読
5.焼香
6.閉式・出棺
7.火葬
8.骨上げ
9.還骨法要・初七日法要
10.精進落とし
葬式(葬儀)は宗教儀式であるため、宗旨・宗派・地域によって流れが異なります。参列する前に故人の宗派や地域のしきたりを確認して、葬式のマナーをあらかじめ把握しておくと安心です。
通夜の流れ
通夜は、故人との別れを偲ぶ最後の儀式です。一般的には18時前後から始まり、遺族や参列者が着席すると僧侶が入場し、読経・焼香が行われます。
地域によっては閉式後に、僧侶や参列者を料理やお酒でもてなす「通夜振る舞い」が行われることもあります。「通夜振る舞い」では、参列者同士で故人の思い出話をして過ごします。最後に喪主が挨拶をして、葬式・告別式の告知などをして終了となります。
告別式や葬式の日程はどう決める?
告別式や葬式の日程は、地域の習わしや言い伝え、葬儀場や火葬場の予約状況などを確認しながら決める必要があります。
亡くなって2~3日ですべてを決める必要があるので、スケジュール管理が非常に重要です。ここからは、告別式や葬式の日程の決め方を解説します。
1.「亡くなった翌日にお通夜、翌々日に葬儀」が一般的
基本的に、お通夜は亡くなった翌日に行い、その翌日に葬儀・告別式を執り行います。身内が亡くなり深い悲しみのさなか、葬式の内容を決めるのは精神的な負担が大きいでしょう。
葬式に期限はありませんが、遺体は時間が経てば腐敗してしまいます。きれいな姿で見送ってあげるためにも、亡くなってからすぐに葬儀を行うのが望ましいでしょう。
しかし、自宅で葬式を行うことが少なくなった昨今、基本どおりの日程を組むのは難しくなっているのが実状です。
2. まずは火葬場を予約する
葬儀の日程を決める際は、まず火葬場を予約しましょう。先に通夜や葬儀・告別式の日程を決めると、火葬場の予約が埋まっていたときに再度日程調整が必要になります。
最初に火葬場の空きを確認し、そこから逆算してお通夜、葬儀・告別式のスケジュールを組みましょう。
火葬場は選べますが、混雑していると数日~一週間ほど待つこともあります。遠方の火葬場を選んでもよいですが、遺体の搬送にかかる費用負担や遺族・親族の手間が増えるため、あまり選択されることのない方法です。
3. 宗教者の予定を確認
お通夜や葬儀・告別式を行う際は、宗教者と予定を合わせる必要があります。火葬場の予約とあわせて、宗教者にも連絡を取って葬式の日程を決めましょう。会場を借りる場合はその問い合わせも同時に行います。
菩提寺がない場合は、葬儀社などに依頼して宗教者を手配してもらうとよいでしょう。
4. 友引の日に注意
日本では、六曜の「友引」の日の告別式や葬式を避ける風習があります。これは、「友を引き連れて行く」という字の印象が由来とされています。ただし、お通夜は友引でも行うことが多い傾向にあります。地域によって考え方が異なるので、事前に確認しておきましょう。
本来六曜は仏教とはまったく関係のない概念ですが、友引の日は休業している火葬場もあるので注意しましょう。
告別式・葬式の服装マナー
告別式・葬式に参列する際は、服装のマナーも確認しておきましょう。ここからは、告別式・葬式に参列する際の服装マナーを紹介します。
男性の服装マナー
男性は、告別式や葬式では準喪服を着用します。靴は黒のストレートチップかプレーントゥのものを着用し、靴下も黒無地を選ぶようにしましょう。
ネクタイピンやカフスボタンを使うことも多いため、準備しておくと安心です。アクセサリー類は結婚指輪以外はすべて外しておきましょう。
女性の服装マナー
女性の告別式や葬式における服装は、黒のワンピースやアンサンブル、スーツが適しています。装飾はついていないものが望ましいです。スカートの長さは膝下丈を選びます。
靴はシンプルな黒色のパンプス、ストッキングも同様に黒色のものを選びます。バッグは、光沢や金具のないものを持ちましょう。アクセサリーは、結婚指輪や真珠のネックレス・ピアスであればマナー違反にはなりません。ただし、ネックレスを重ねづけするのは「不幸が重なる」ことを連想させるため、着用しないようにしましょう。
子どもの服装マナー
子どもの告別式や葬式における服装は、制服が礼装となります。通っている幼稚園や学校に指定の制服がある場合は、制服を着用しましょう。
制服がない場合は、黒や紺色など落ち着いた色味の洋服を選びます。目立つ色合いの服や、キャラクターがデザインされた服などは避けましょう。足元は白や紺などの無地のソックスに、ローファーやフォーマルシューズなどが適しています。
告別式・葬式における香典の渡し方
告別式・葬式では、香典を持参します。渡す際は、タイミングやマナーを守る必要があります。ここからは、告別式・葬式における香典の渡し方を解説します。
香典は受付後に渡す
香典は受付後に渡すのが一般的です。しかし、会場によっては受付が設けられていないこともあります。その際は、遺族に直接渡したり会場のスタッフや世話役に渡したりするとよいでしょう。
自宅葬の場合は、挨拶の際に遺族に渡すか、仏前にお供えします。状況に応じて対応を変えられるようにしましょう。
香典は文字が読める向きで渡す
香典を渡す際は、相手側に読めるように向きをそろえて両手で渡します。袱紗(ふくさ)から取り出し、受付の方に「お供えください」と言って渡すとよいでしょう。直接祭壇に供える場合は、自分が名前を読める向きにして供えます。
告別式・葬儀後に行うこと
告別式・葬儀が終わった後にも行うことがあります。
料金の支払いや香典返しの準備、相続手続きなどさまざまな手続きを進める必要があります。中には期限が決まっているものもあるので、スケジュールをしっかり立てて進めていきましょう。ここからは、葬儀後に行うことを紹介します。
1. 事務の引き継ぎ
葬儀が終わってすぐは、葬儀社に依頼していた葬儀事務の引き継ぎを行います。終了日の翌日か、精進落としの会食を終えた後すぐに済ませましょう。葬儀でいただいた以下のものを受け取ります。
・芳名帳
・香典帳
・供物帳
・弔電
・供物・供花の記録帳
・出納帳
香典は大金になるので、金銭的なトラブルが起こる可能性もあります。終了後すぐに香典帳を確認して金額が合っているか確認しましょう。
2. 各所への代金支払
葬儀が終わったら、関係各所に代金を支払います。入院先の病院で亡くなった場合は、治療費などを病院に支払います。後払いに対応している病院も増えてきているので確認しておきましょう。
葬儀終了後には葬儀社からの請求もあります。参列人数が増えたりすると事前の見積もりから増額することもあるので、金額を再度確認しましょう。支払いまで1週間ほど猶予がある葬儀社もあります。打ち合わせの際に支払期限も確認しておくと安心です。
葬儀当日にお布施を渡せなかった場合は、2日以内に寺院や教会にも挨拶をして渡しましょう。お布施の金額がわからない場合は僧侶に聞いても失礼にはあたりません。
3. 挨拶回り
葬式が終わった後は挨拶回りをします。挨拶回りをするのは以下の方々です。
・受付などの世話役
・弔辞をもらった方(参列者)
・寺院
・葬儀前後に手伝ってもらった方
・近所の方
・直前までお世話になった病院
・故人の仕事先
香典の贈り主には、香典返しとして贈るものを用意しておきましょう。保険関係の手続きも、葬式後の早いタイミングでできると安心です。
4. 香典返し
香典返しは喪が明けた後に行うのが一般的で、仏教の場合は四十九日法要後にお渡しすることが多いでしょう。ただし、状況によっては四十九日法要前に香典返しを行う場合もあります。葬式当日に香典返しをする場合もあるので、地域の慣習を確認しておきましょう。
5. 各種手続き
役所での手続きや相続を進めます。役所関係で必要な手続きは、以下のとおりです。
・世帯主変更届(故人が世帯主の場合)
・住民票抹消届(故人が世帯主でない場合)
・健康保険の資格喪失手続き
・年金受給停止申請
・国民年金の一時死亡金請求
・所得税の申告と納税
・雇用保険受給資格者証の返還
・免許証やパスポートの返却
住民票や年金など、急いで行わないと税金がかかってしまう手続きから優先的に進めましょう。
相続関係の手続きは以下の通りです。
・遺言書の検認
・相続しない場合は、相続放棄の手続き
・相続税の申告と納付(発生した場合)
・不動産の名義変更(故人が所有していた場合)
・預貯金口座の名義変更
・株式の名義変更
相続税は基礎控除が適用されるため、課税の対象外となるケースも多く見られます。ただし、申告が必要な場合の期限は被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。相続放棄にも手続きが必要なため、なるべく早い段階から準備を始めるのが賢明です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
病院から危篤の連絡がきたときの対応方法や、親族が亡くなったときにやるべきこと、葬儀でのあいさつ文例など 、喪主を務めるのが初めてという方にも役立つ 情報が満載です。
いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
告別式とは、友人や会社の同僚など、生前に交流の深かった方が故人とお別れする儀式です。宗教的な要素は含んでいないため、故人と生前に関わりのあった方なら誰でも参加できます。
一方で、葬儀とは、告別式や火葬の前に執り行われるお別れの儀式のことです。告別式とは異なり宗教的な儀式であるため、僧侶による読経や神主による祭祀などが行われます。告別式と葬儀という2つの儀式をまとめた言葉が「葬式」です。
告別式や葬式にはルールやマナーが多いので、参列前に儀式の意味や違いを理解しておく必要があります。
小さなお葬式では、24時間365日対応のコールセンターを設けており、専門知識を持つスタッフがお客様のお悩みに合わせて丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。