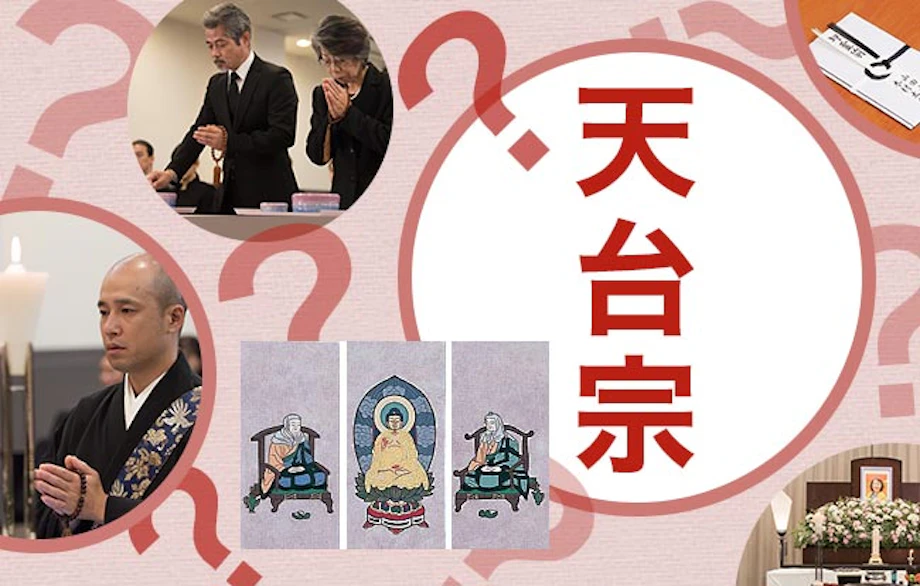日本の葬儀の多くは仏式で営まれています。ひとくちに仏教と言ってもさまざまな宗派があり、宗派によって葬儀の儀礼が異なることがあります。ご自分の家が天台宗だった場合、どのように葬儀を行えば良いか、どのようなお経が読まれるのか、ご存知でしょうか?
この記事では、長い歴史を持つ天台宗の葬儀の特徴、法要、マナーについてご紹介します。
<この記事の要点>
・天台宗の葬儀では「法華懺法」「例時作法」「光明供」の三つの儀礼が行われる
・納骨は四十九日の日に行うのが一般的
・天台宗では焼香の回数は特に回数は定められていない
こんな人におすすめ
天台宗の葬儀の流れが知りたい人
天台宗の法要について知りたい人
天台宗の法事のマナーを押さえたい人
天台宗の教えと歴史
天台宗の教え
天台宗の教えでは、人はみな仏性を持っているとされています。必ず仏になることができ、そのためには仏と縁を結ぶことが大切になります。葬儀ではまず、剃髪の儀や懺悔など心身ともに仏の弟子になる儀式を行います。その後、仏の教えである仏・法・僧の3つに帰依するという戒めを授かり、仏弟子としてこの世を離れ仏の国へと向かいます。
天台宗の歴史
天台宗の起源は、中国の僧侶智顗(ちぎ)が、「妙法蓮華経」という経典に述べられている教えに注目し、仏教全体の教義を体系付けた天台教学にあります。それを、最澄が日本に伝え、比叡山を開いて広めました。
開宗以来、天台宗は日本で国教に近い役割と威勢を誇ってきましたが、織田信長によって一時壊滅的な状況に追い込まれます。しかし、江戸時代に天海によって勢力の中心が関東に移されたことで盛り返し、日本全土にその影響力を及ぼすようになりました。現在、天台宗の宗派は9派に分かれています。
天台宗では、亡くなると仏弟子となり、必ず成仏すると言い渡されて、阿弥陀仏のお迎えによって仏の国へ向かうと考えられています。死後四十九日、この世と仏の世界との中間に居る期間を経て、浄土に生まれ直すのです。
<関連記事>
お葬式に適した髪型は?メイクや服装、身だしなみマナーを徹底解説
天台宗の葬儀の特徴
天台宗では、仏の教えを顕教(けんぎょう)と密教(みっきょう)に分けています。顕教とは、人々が理解しやすいように、言葉や文字を用いて説いた教え。一方で密教は、仏と自己が一体であることを念じ、仏の悟りそのものに到達しようというものです。
天台宗の葬儀は、顕教儀礼と密教儀礼あわせて3種類の儀礼によって営まれます。儀礼はいずれも、仏と同様の清浄心をめぐらすことに特色があります。供養する家族、縁のある人々、そして供養される故人が一体となり、ともに仏道をなしていくことが、天台宗の葬儀が持つ意義です。
葬儀で行われる3つの儀礼
天台宗の葬儀では、顕教儀礼である「法華懺法(ほっけせんぽう)」・「例時作法(れいじさほう)」と、密教である「光明供(こうみょうく)」、3種の儀礼が行われます。
顕教の儀礼
経典の読誦や懺悔によって、仏教徒としての正しい日常生活を送るために実践するもの。密教の儀礼は、加持祈祷(かじきとう)が中心です。いずれも崇拝の対象となる仏への供養と、仏になる可能性を持った自分自身の心の開発が重視されており、葬儀もその考えに則ったものとなっています。
法華懺法とは、法華経を読誦することによって、自らの犯した罪を懺悔する修法です。ここで言う「罪」とは、法律や道徳上のものではありません。「全ての存在は仏性を有した平等なものである」という真理に背いて妄念にとらわれた一切の言動を指します。
例時作法は、心に阿弥陀仏を念じ、南無阿弥陀仏を唱えることで、極楽浄土へ往生することを目的とする法要儀礼です。念仏によって自己の心の中に仏性を表す意味もあります。
密教儀礼
光明供は、大日如来または阿弥陀仏を本尊として光明真言を念じて経を唱える法要です。故人が極楽浄土へ導かれることを祈念する意味があります。
また、一般的な葬儀についてまとめた記事がありますので参考にしてください。
<関連記事>
葬儀は段取りが肝心。流れ・費用・マナーが「やさしくわかる!」
天台宗の法要
仏教では、命あるものは全て、生まれては死に、また生まれることを繰り返していると考えられています。これを輪廻転生(りんねてんせい)と言います。生を終えてから次の生を受けるまでの期間が49日とされており49日を7日ごとに区切って、それぞれの区切りの火に、次に生まれるところが決まるとされています。
しかし、49日までに決まらなかった場合、死者の霊は浄土へ行けず彷徨(さまよ)うとされています。そのため、臨終の日から四十九日まで7日ごとに追善法要を営み、故人の生前の罪を滅して、善処に生まれることができるように祈るのです。これが、7日ごとに区切られた中陰法要です。
四十九日の日に納骨をするのが一般的で、この日が忌明けとなります。その後は百カ日法要を経て、一周忌で喪明けとなります。年回忌は三回、七回、十三回、十七回、二十三回、二十七回で行い、三十三回で弔い上げの法要を営みます。以後は五十回忌、百回忌などを身内だけでしのびます。
<関連記事>
年回忌法要と法事の流れ|施主になる前に理解しておこう
焼香・数珠のマナー
天台宗の葬儀に参列するときは、基本的には一般的な葬儀と同じ心がまえで構いません。故人を偲ぶ気持ちを持ち、遺族に失礼のないよう心がけましょう。
焼香のマナー
参考動画:<天台宗>葬儀におけるお焼香の作法(やり方)【小さなお葬式 公式】 動画が見られない場合はこちら
焼香の回数は、宗派によってさまざまですが、天台宗では特に回数は定められていません。大切なのは、心をこめて故人の安らかな成仏を願うことなので、回数にこだわる必要はないのでしょう。ただ、最近では会葬者の数や時間的な問題で、1回で済ませることが多くなっているようです。
<関連記事>
【動画で解説】もう迷わない焼香のやり方・マナー
数珠のマナー
参考動画:<天台宗>葬儀の際の数珠の持ち方【小さなお葬式 公式】 動画が見られない場合はこちら
天台宗の正式数珠は、扁平な平玉になっているのが特徴です。親玉から連なる房には、20の平玉と10の丸玉が付けられています。数珠の玉は人間の煩悩を表していると言われ、その数は108あるのが正式です。天台宗では、正式念珠は得度を得た人のみ使うケースが多く、一般の人は略式念珠か、宗派共通の二連数珠で構いません。
持ち方は、左手首にかけます。合掌するときには両手の人差し指と中指の間にはさみ、ふさを下に垂らします。合掌は、両手のひらをぴったりとくっつけて、指が自然に合うようにしましょう。右手は悟りの世界である仏、左手は迷いの世界を表しており、合掌することで仏と一体になることを意味するようです。おつとめの最初と最後には、数珠をすりあわせます。
<関連記事>
納骨式で困らないために!納骨式の流れや準備を徹底解説!
葬儀は僧侶と相談しながら
葬儀の運営は葬儀社に任せることが多くなっていますが、天台宗にはお伝えしたように独特な儀礼もあります。細かい進行などは僧侶と相談しながら、適切にとり行えることが理想です。
「小さなお葬式」では天台宗のご葬儀を承っております。詳しくは下記をご覧ください。
参考:天台宗の葬儀に対応「小さなお葬式」
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
天台宗の教えとは?
天台宗の葬儀の特徴は?
天台宗の法要とは?
天台宗の焼香マナーは?
天台宗の数珠のマナーは?

故人が年金受給者の場合は、すぐに年金受給停止の手続きが必要になります。ホゥ。