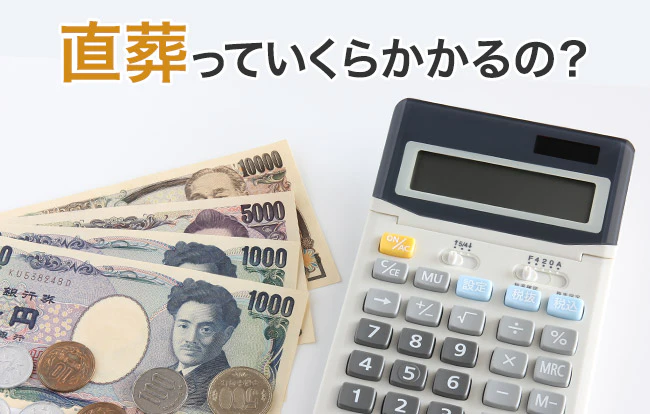供花(きょうか)は、親しい人や親族が亡くなったときに贈ります。供花には、贈る側と贈られる側、どちらにも注意すべき点があります。故人とお別れをする場で、お互いに嫌な思いをしないためにも、必要なマナーを理解しておくことが大切です。
ここでは、供花を贈るときに気をつけたいマナーと、供花をいただいたときのお返しに関するマナーについてご紹介いたします。いざというときに慌てないためにも、ここで確認しておきましょう。葬儀全体の流れについてあわせてご確認することもおすすめです。
<この記事の要点>
・供花にはスタンドタイプやアレンジメントタイプがあり、会場の大きさに応じて選ぶ
・宗派によってふさわしい供花の種類が異なる
・供花の相場は、フラワースタンド一基で15,000円~20,000円、アレンジメントは7,000円~20,000円
こんな人におすすめ
「供花(くげ・きょうか)」とは何か知りたい方
宗教別の供花を知りたい方
供花の相場を知りたい方
供花とはなにか
供花とは、故人へ贈る花のことをいいます。スタンドタイプやアレンジメントタイプなどがあり、価格もさまざまです。スタンドタイプであれば、会場の両サイドや入り口、アレンジメントタイプであれば祭壇に供えられることもあるでしょう。
供花には、死者の霊を慰めるとともに葬儀会場を飾る役割もあり、お悔やみの気持ちを表すために贈られます。個人で贈るほかに、友人関係や職場関係、親族関係など、数人が連名で贈るケースもあります。故人との関係性や遺族の意向によって、ふさわしい供花が変わりますので、この点にも配慮しましょう。
地域によって、供花のマナーが異なることもありますので、葬儀社に確認することをおすすめします。葬儀社や花屋であれば、ふさわしい供花を手配してくれるでしょう。遺族は葬儀の準備で忙しいため、できるだけ遺族への連絡は控えるようにします。
宗教別の供える花の種類
宗教によっても、供花の種類や贈るときのマナーが異なるため注意が必要です。さらに宗派や地域の風習によって異なることもありますので、マナー違反にならないようにしっかりと確認したうえで贈ることが大切です。
また、宗教によっても贈る花が異なりますので、わが国で多い仏教・キリスト教・神道の宗教別に見ていきましょう。
仏教の場合
仏教では、菊や百合、カーネーションや蘭などが供花として用いられ、予算によっては胡蝶蘭などの高級感のある花が用いられることもあります。もともとは、二基を一対として贈るものでした。最近では、葬儀会場の広さの関係などから、一基だけで贈ることも増えています。
供花のスタイルとしては、フラワースタンドやフラワーアレンジメントなどが一般的です。白を基調とした淡い色合いが多く、華やかになりすぎないように仕上げられた供花に、送り主の名前を札名に記して、供花とともに飾られます。
地域によっては、供花に黒や白黒の水引やリボンをかけたり、花輪を置いたりすることもあります。関西では、供花として樒(しきみ)という常葉樹を贈る習慣もあります。
キリスト教の場合
キリスト教の葬儀は教会でおこなわれますが、このときに贈る供花は、ユリやカーネーションなどの洋花が中心となります。フラワースタンドではなく、フラワーアレンジメントで贈ることが多くなってきました。
仏教の供花が故人の霊を慰める意味合いがあるのに対して、キリスト教の葬儀は神様に拝礼することを目的とするため、供花には札名をつけません。また、葬儀会場ではなく、故人の自宅に贈ります。
自宅から教会へ供花を運ぶ必要があるため、持ち運びのしやすいバスケットタイプのアレンジメントが好まれるでしょう。キリスト教の供花には、遺族や教会の関係者が贈るクロスアレンジメントと、親族や親しい友人などが贈るハートアレンジメントがあるのも特徴のひとつです。ただし、日本ではまだ浸透しておらず、クロスやハートに対応していない花屋もあるので注意しましょう。
神道の場合
神道の葬儀は神葬祭(しんそうさい)といいます。神葬祭に贈られる供花には、菊や百合などの生花が用いられます。神道と仏教では、葬儀に贈られる供花に、ほとんど違いはありませんが、神道では胡蝶蘭のような高価な花は使用しません。
花の色味は白を基調としますが、淡い黄色系やピンク系の花を使用する場合もあります。榊を贈る習慣もありましたが、近頃では、神道での喪主となる祭主が榊を用意して供えることが増えました。
このように神道の葬儀であっても、生花で作られた供花を贈りましょう。この場合、篭盛(かごもり)やフラワースタンドで贈ることが一般的です。
葬儀の花を手配する方法
供花を贈るのであれば、通夜がはじまる前には会場に届くように手配しましょう。手配するには、葬儀社に依頼する方法や、花屋に直接注文する方法などがあります。
葬儀社に依頼する場合は、会場の雰囲気に合わせた供花を手配してもらえます。比較的ギリギリの時間であっても注文を受けてくれることが多いため、通夜までの時間がない場合は葬儀社に依頼することをおすすめします。
自分で花の種類を選びたい人は、花屋で注文したほうが希望をとり入れてもらいやすいでしょう。ただし葬儀社によっては、契約している花屋以外の供花の搬入を認めていなかったり、搬入できたとしても持ち込み料がかかったりすることがあります。
まずは、葬儀社に確認してから供花を注文するとよいでしょう。また、親族や会社などで取りまとめて注文することもありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
供花の費用相場
続いて、供花の費用相場をご紹介します。フラワースタンドの場合、一基で15,000円~20,000円が相場価格です。フラワースタンドを二基で一対として贈る場合は、料金も2倍になりますので、30,000円~40,000円くらいを予算として考えておきましょう。
祭壇に飾るフラワーアレンジメントや篭盛の花は、フラワースタンドに比べると安く、7,000円~20,000円くらいが相場です。季節によっては花の価格が高い時期もあるため、花の種類を指定する場合は、さらに価格が高くなることもあります。
あまりにも高額な供花を贈ってしまうと、遺族側に気を遣わせることにもなりかねませんので、相場を参考に予算を組みましょう。支払いは、葬儀に参列したとき葬儀社に直接支払う方法のほか、後日振込で支払いできるケースもあります。
供花の札名の書き方やマナー
供花に添える札名の書き方にもマナーがありますので確認しておきましょう。キリスト教の葬儀では札名の必要はありませんが、仏教や神道の供花の場合は、贈り主の名前を札名に記します。供花を贈るときは、個人で贈るほかに連名で贈ったり、法人で贈ったりすることもありますので、それぞれの札名の書き方のマナーについてご説明します。
個人で供花を贈る場合のマナー
友人や親族が個人で供花を贈る場合は、自分の名前のみをフルネームで記載します。会社名や役職などは必要ありません。
苗字と名前は続けて記載されますが、氏名が3文字や5文字だったり、めずらしい名前や読み方で苗字と名前の境がわかりにくかったりする場合は、苗字と名前の間にスペースを入れるなど工夫しましょう。
個人で贈る場合はとくに難しいこともありませんので、名前の表記ミスに気をつけて札名を依頼します。札名は供花を手配する葬儀社や花屋で用意してくれますが、書き間違いの多い「崎」や「﨑」、「高」や「髙」などの漢字が名前に使われている場合は、注文時に間違いのないようにしっかり伝えましょう。
連名で供花を贈る場合のマナー
連名で贈る場合ですが、友人からの供花であれば、記載する順番を気にする必要はありません。いとこや兄弟姉妹で連名にする場合は、年長者が右側にくるように名前を記載します。とくに肩書を記す必要はありませんので、氏名だけを順番に記載しましょう。
札名に記載する人数が多くなると、その分文字が小さくなり見栄えも悪くなりますので、「友人一同」「いとこ一同」「孫一同」のように書くこともあります。連名として記載できる人数にきまりはありませんが、葬儀社によって「8人までOK」というところもあれば「連名は3人まで」と、独自にルールを設けている場合もあります。
確認のうえ、どのように記載するべきかを相談するとよいでしょう。
法人で供花を贈る場合のマナー
故人が働いていた会社や遺族が働いている会社から供花を贈る場合は、法人として札名に記載する必要があります。法人で供花を贈る場合は、札名に会社名を記載しましょう。
会社名が長くなってしまう場合は、株式会社や有限会社を(株)、(有)と短縮することもありますが、法事等のケースでは正式名称で記載するのが基本です。会社の代表として贈る場合は、役職に加えフルネームで名前を記載しましょう。役職は「代表取締役社長」を「代表取締役」と短縮するケースもあります。
部署として贈る場合には、正式な会社名に加えて部署名の記載が必要です。「株式会社○○商事 営業部 一同」のように記載しましょう。部署内で連名の供花を贈る場合は、肩書が上の人を右側にして名前を連ねます。
供花をいただいた場合のマナー
自分が喪主として葬儀を執りおこなう場合、今度は供花を贈っていただく側になります。そのときに悩むのが「お返しはどうするか」ということではないでしょうか。
供花をいただいた場合にもマナーがあります。せっかくの厚意に水を差すことにならないよう、供花をいただいた場合のマナーについても確認しておきましょう。
お礼状は早めに送る
供花をいただいた場合、まずはお礼状を送るようにしましょう。葬儀後は何かと慌ただしいものです。1週間くらいたって、落ち着いたころにお礼状を出すとよいでしょう。
あまり日にちがあきすぎないように、遅くても四十九日の法要前には送るようにします。ただし、故人の亡くなった時期が年末年始の場合は、まだ正月飾りを飾っている松の内を避けて送りましょう。相手方にとっては年明けのおめでたい時期でもあるため、この時期を避けるのがマナーです。
お礼の品は基本的に不要
祝いごとであれば、いただいたお祝いに対して品物でお返しするのがマナーですが、故人への贈り物である供花をいただいた場合は、基本的に返礼品は不要とされています。ただし、地域の風習や親族間での習わしによっては、返礼品が必要なケースもあるでしょう。
その場合は、供花の費用の1/2~1/3程度を目安に返礼品を用意します。供花とは別に香典もいただいている場合は、その費用も合わせたうえで、1/2~1/3ほどの返礼品を用意しましょう。供花と香典の返礼品を別々に用意する必要はありません。
返礼品を贈る場合の品物の選び方
供花をいただいた場合の返礼品には、使ってなくなる「消え物」が用いられます。洗剤や石鹸、タオルなどの日用品から、お茶や海苔、お菓子などの食べ物や飲み物も返礼品としてよく贈られる品物です。最近では、自分で好きな商品を選べるカタログギフトの需要も増えています。
返礼品を贈るときの熨斗紙には、黒白もしくは黄白の結びきりの水引を使用しましょう。表書きには「志」と記載しますが、地域によっては「粗供養」や「御礼」と記載することもあります。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
供花は、故人へのお悔やみの気持ちを示すものです。しかし、マナーを守らなければ、贈る側も贈られる側も、お互いに不快な思いをすることになりかねません。
葬儀は厳粛な儀式です。ここで紹介した供花に関するマナーを参考に、贈る側の人も贈られる側の人も、相手の気持ちを思いやって故人を偲びましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



遺産相続が発生した場合、いかなる場合でも配偶者は相続人になります。ホゥ。