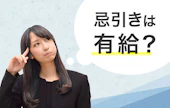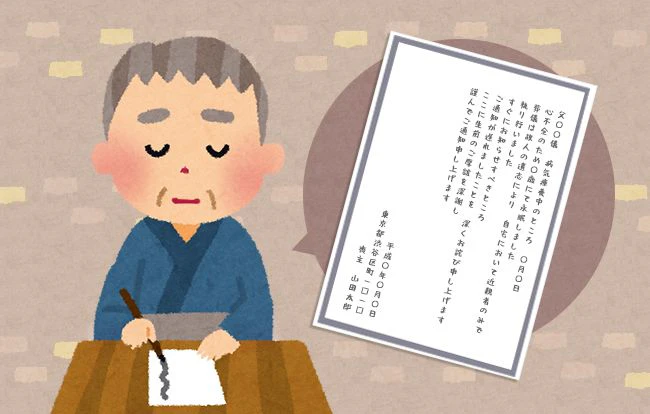親族が亡くなった際、喪主を務める方も参列者として葬儀に参列する方も、会社に勤めていれば会社を休み、葬儀に参列しなければなりません。その時、「忌引き」と「公休」のそれぞれの意味や違い、どれだけの期間の休暇がもらえるのかなど、いろいろと悩む方もいるのではないでしょうか。
今回は、「忌引き」と「公休」の違いについてご紹介します。忌引きを申請する際の注意点もあわせて確認しておきましょう。
<この記事の要点>
・「忌引き」は、親族が亡くなった際に通夜や葬儀に参列するための特別休暇で、会社の就業規則に基づく
・「公休」は、労働基準法や育児・介護休業法で定められた法定休暇のこと
・忌引き休暇の日数や、有給か無給かは会社の就業規則によって異なる
こんな人におすすめ
忌引きの意味を知りたい方
忌引きと公休の違いを知りたい方
忌引きを申請する際のポイントを知りたい方
忌引きの意味とは
一般的に「忌引き」とは、親族が亡くなった際に、通夜や葬儀などに参列するためや葬儀の前後に行わなければならない準備や手続き、喪に服すことなどを理由にやむを得ず休むことをいいます。
通夜や葬儀は通常突然訪れるものであり、暦上の六曜や火葬場の込み具合によるとはいえ、平日に行われる可能性が高く、都合よく休日の可能性は低いでしょう。多くの場合では会社勤めをされている方は会社に連絡をして休む必要が出てきます。このような場合で会社を休むことを「忌引き」といいます。
「忌引き」というのは会社を通夜や葬儀などを理由に休む場合だけでなく、学生であれば同様の理由で学校を休む場合にも同じ言葉を使います。
忌引きと公休の違いとは
「忌引き」と「公休」はどちらも休暇の事を示している言葉ですが、その大きな違いは「忌引き」が「会社休暇」なのに対して、「公休」は「法定休暇」であることです。つまり、法律上で制定されている休暇なのかどうかという点が「忌引き」と「公休」の大きな違いです。
ここからは、「忌引き」と「公休」について、それぞれ詳しく見てみましょう。
忌引きは「会社休暇」
「会社休暇」にあたる忌引きは労働基準法で制定されたものではないため、法律上で制定されていない休暇、つまり特別休暇です。従業員の満足度にもつながる制度やサービスである福利厚生の一環と覚えておくと良いでしょう。特別休暇と呼ばれる休暇には、夏季休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇などがあります。
内容は、就業規則によって会社独自で自由に決められるものです。就業規則の届出に関して労働基準法第89条で、常時10人以上の労働者を使用する使用者について、一定の事項を記載した就業規則を所轄の労働基準監督署長に届出ることが義務づけられています。
小規模の会社では、忌引き自体が設けられていない場合もあります。もちろん労働基準法の違反にはなりません。
公休は「法定休暇」
公休は労働基準法や育児・介護休業法で制定された「法定休暇」にあたります。法定休暇にあたる休暇は、労働基準法で制定されている年次有給休暇や産前産後の休暇、生理休暇と育児・介護休業法に基づく育児休暇と介護休暇、子の看護休暇があります。
年次有給休暇は、勤続年数によって毎年一定の休暇が与えられることが法律で制定されており、それ以外の休暇は会社ごとに条件が決められています。
土、日、祝日が休日と会社が決めているのならば、これらの休日も公休にあたります。24時間365日営業している会社であれば休日を一律に固定するのではなく、従業員ごとに休日決めているか、あるいは月ごとに休日を調整している場合もあります。
忌引きと公休に関する疑問
忌引きと公休に関してどのような規則で運用されているものかなどの疑問だけでなく、忌引きと公休が重なった場合や有休なのか無給なのかなど、いろいろな疑問を持つ方は多いでしょう。ここからはみなさまから良くいただく2つの質問にお答えします。
①忌引きと公休が重なる場合はどうなるのか?
忌引きと公休が重なる場合というのは、忌引きの希望日が会社の決める公休日と重なる場合です。この場合、どのように休暇の日数をカウントするのかと疑問に感じている方も多いでしょう。
休暇の日数のカウントの方法は、会社が独自で決めているためさまざまです。例えば、土、日や祝日を公休と決めている会社があるとして、その会社の従業員の親族が土曜に亡くなったとします。土曜、日曜で通夜と葬儀が行われるのであれば、忌引きと公休が重なります。
公休と重なって忌引きを取得する場合、「含めてカウント」と決めている会社もあれば全く逆の「除いてカウント」と決めている会社もあります。
②忌引き中は無給になるのか?
会社を休むことになるため、その間が無給になるのかどうかは、多くの人が疑問に感じるポイントではないでしょうか。生活に直結する問題であることから、疑問に感じる方が多いのかもしれません。
忌引きは年次有給休暇とは全くの別物のため、「忌引き=有給」と考えないようにしておきましょう。忌引きが有給になるのか無給になるのかは、勤め先の会社の就業規則で制定されている通りです。つまり会社にゆだねられているということになります。
就業規則によって無給と決められている場合でも、もし有給が良ければ、年次有給休暇を消化できないか直接掛け合ってみるのも良いでしょう。ただし、年次有給休暇がある場合に限られます。
忌引きの日数目安
休める日数が何日あるのかを知っておかなければ、予定を組むことが難しい場合もあるでしょう。例えば、遠方で行われる葬儀であれば往復に要する時間を考慮して予定を組む必要があり、喪主であれば葬儀前後の準備や手続きなどをスムーズに行うためにも予定を組むことは大切です。
日数は、忌引きを申請する方と亡くなった方との関係で変化します。会社ごとに決められているので、全ての会社において同じというわけではありません。
【一般的な忌引き日数】
| 申請者との関係 | 日数 |
| 配偶者 | 10日 |
| 父母 | 7日 |
| 祖父母 | 3日 |
| 兄弟姉妹 | 3日 |
| 叔父・伯父・叔母・伯母 | 1日 |
| 孫 | 1日 |
| 配偶者の父母 | 3日 |
| 配偶者の祖父母 | 1日 |
| 配偶者の兄弟姉妹 | 1日 |
忌引きを申請する際のポイント
何度も経験をすることではない忌引きの申請は、慣れなければ戸惑いを覚えることもあるでしょう。忌引きを申請する際は、申請を迅速に行うことがポイントです。
休む間の業務の引継ぎやフォローをしてもらうことを考えると、少しでも早く会社へ報告できるように、事前に忌引きを申請する際のポイントを確認しておきましょう。
就業規則を確認する
一番大切なことは、就業規則を確認することです。就業規則によって忌引きの有無、休暇日数、起算日、申請方法、有給なのか無給なのかと言った細かい内容が制定されています。
アルバイトやパート、正社員といった就業形態によっても忌引きの内容が異なる場合もあり、その場合はそれぞれの就業形態によって就業規則が決められています。アルバイトやパートには忌引きが認められていない場合が多いため、その点も含めて確認しましょう。
就業規則は、労働基準法にて使用者は周知する義務を負っています。そのため、保管場所が分からなければ上司や人事、総務に聞くと良いでしょう。就業規則を見ても分からない場合は自己判断せず、上司に相談したり人事や総務に確認を取ったりしましょう。
忌引きの申請は迅速に行う
忌引きの申請は迅速に行いましょう。会社に出向く、または電話をして口頭で伝えることが一番丁寧な方法ですが、メールで伝える方法もあります。まずは口頭で伝えた後に、メールで葬儀の日時や場所などの詳細を連絡する方法もおすすめです。
自身にとって迅速に申請を行うメリットは、少しでも早く申請を通史、通夜や葬儀へ参列する準備に取り掛かることです。会社側としては、休む従業員の分の仕事を他の従業員で分担し、業務に差支えが無いようにする必要があるため、少しでも早く状況を把握したいと思うものです。
就業中に訃報を受け忌引きを申請したい場合、まずは直属の上司に相談をしてから申請の準備を進めましょう。
休暇明けの挨拶をきちんと行う
忌引きが明けて通常通りに出勤をした際、きちんと挨拶を行いましょう。年次有給休暇などとは違い急な休暇なため、少なからず同じ会社で働く方々に仕事の調整で迷惑をかけたことが予想されます。今後の付き合いを考えても挨拶は大切です。
【忌引き明けの挨拶例】
通夜から葬儀まで無事に終了することができました。お忙しいところ休暇をいただきご迷惑をおかけしましたが、本日より復帰させていただきますのでよろしくお願いいたします。
香典や供花をいただいた場合は、「ご香典を賜りましてありがとうございました」や「ご丁寧にご供花をいただきましてありがとうございます」という言葉も添えます。
場合によっては、会社内の方々だけでなく、社外の関係者やお取引先などにも休暇を取ったことで迷惑をかけていることもあるため、必要に応じて挨拶をしましょう。
忌引き申請の例文
一般的には口頭で伝えた後、忌引きの申請を書面で提出する場合が多いでしょう。申請書には、休暇日数に関係する亡くなった方との関係はもちろんのこと、会社によっては弔電や香典の準備のために、葬儀の日時や会場といった内容を具体的に記入する必要があります。
申請書を提出する際に必要な口頭やメールでの申請の例文をご紹介します。
口頭・電話の場合
上司や人事、総務の方と直接、または電話で申請をする際は、明確かつ簡潔に伝える必要があります。メールと比べると口頭で伝えることは一番丁寧な方法ではありますが、相手に時間を取らせてしまうことにもなりかねないため、明確かつ簡潔に伝えることが大切です。
急なことですが、〇月〇日に(関係)の(名前)が永眠いたしました。通夜は〇月〇日、葬儀は〇月〇日に(場所)にて行われます。つきましては、忌引きを頂きたいのですが、お願いできますでしょうか。通夜や葬儀の時間や場所に関しては、後程メールにて詳細をご連絡させていただきます。
通夜や葬儀の時間、場所の詳細な住所などは、後程改めてメールで詳しく伝えることを申し出ることで、相手の業務を邪魔することなく口頭での明確かつ簡潔な連絡ができます。
メールの場合
口頭で伝えることが一番丁寧な方法ではありますが、メールが必ずしも失礼というわけではありません。時と場合によっては、メールが一番良い場合もあります。
例えば、亡くなられた時間が夜間であれば、伝えなければならない相手にとってはプライベートな時間にあたります。プライベートな時間だと分かっているのであれば、電話をかけるよりも先にメールで一報を入れましょう。
【メールでの例文】
件名:忌引き取得のお願い
お疲れ様です。
このたび、祖母〇〇の死去に伴い、忌引きの取得をお願いしたくご連絡させていただきました。
期間:〇月〇日から〇日
理由:祖母の葬儀のため
緊急連絡先:000-0000-0000
詳細が決まりましたら、早急にご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。
休日や夜間にメールをする場合は、「お休みのところ、大変失礼いたします」などのことわりの言葉も一言添えましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
「忌引き」と「公休」の違いについてご紹介しました。忌引きをする際には、勤め先の会社の就業規則にしっかりと目を通し、分からないことは会社に直接確認を取ることが大切です。忌引きを利用する場合は、会社の方々に対して感謝や配慮を忘れないようにしましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



遺言書には、誰の遺言かを明確にするために署名が必要です。ホゥ。