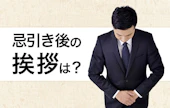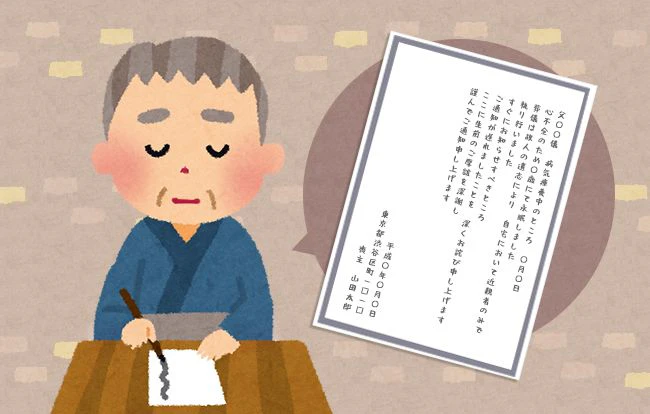家族や親族が亡くなるとお通夜や葬儀に参列しなければなりません。参列するだけではなく葬儀の準備や手続きをやらなければならない場合もあります。
十分な時間を確保するためには忌引き休暇を取るのが一般的です。会社員であれば就業規則に書いてあるはずですが、公務員の場合はどこに記載されているのか分からない場合もあるかもしれません。
地方公務員は自治体ごとに忌引き休暇が定められているため、条例などを確認してみましょう。公務員の忌引き日数や休暇の申請方法、忌引きに関する基礎知識をご紹介します。
<この記事の要点>
・公務員の忌引き休暇の日数は地方自治体ごとに異なり、親等によって決まる
・訃報を受けたらすぐに上司に連絡し、必要な情報を明確に伝えて忌引き休暇を取得する
・喪主を務めた場合は規定よりも長く忌引き休暇が付与されることがある
こんな人におすすめ
公務員の忌引き日数について知りたい方
公務員の忌引き休暇の申請方法を知りたい方
公務員の忌引き休暇申請の際に必要な書類を知りたい方
地方公務員の忌引き日数は各地方自治体によって異なる
地方公務員が忌引きで休める日数は、地方自治体によって規定が異なります。一般的には親等の近さによって休める日数が決まります。近ければ近いほど日数が長く、遠ければ短くなります。
東京都の場合
東京都の地方公務員の場合、身内が亡くなったことを証明できる書類を提出する必要があります。証明書類としてあげられるのは死亡診断書や会葬礼状などです。故人との関係性によって以下のように休暇を取れる日数が異なります。遠方での葬儀に参列する場合は、往復日数をプラスして休むことが可能です。
| 自分との関係性 | 休暇日数 |
| 配偶者 | 10日 |
| 父母 | 7日 |
| 義父母 | 3日(同居していた場合7日) |
| 祖父母 | 3日(相続・祭祀承継する場合は7日) |
| 義祖父母 | 1日(同居していた場合3日) |
| 兄弟姉妹 | 3日 |
| おじ・おば | 1日(相続・祭祀承継する場合は7日) |
大阪府の場合
大阪府の地方公務員の場合は、忌引きで休める日数に関して次のように決められています。東京都と同じく義父母などの姻族でも同居していた場合の休暇日数は血族に準じます。遠方での葬儀に参列する場合に移動にかかる日数を延長できるのも同様です。
| 自分との関係性 | 休暇日数 |
| 配偶者 | 7日 |
| 父母 | 7日 |
| 義父母 | 3日(同居していた場合7日) |
| 祖父母 | 3日 |
| 義祖父母 | 1日(同居していた場合3日) |
| 兄弟姉妹 | 3日 |
| おじ・おば | 1日 |
忌引き休暇の申請方法
近い親族が亡くなった場合、訃報を受けたらすぐに駆けつけたいものです。または危篤状態から看取って、そのまま葬儀の準備をしなければいけないこともあるかもしれません。しかしそのまま無断で仕事を休むわけにはいきません。忌引き休暇を取りたいときの申請方法をご紹介します。
忌引き規定で日数を確認する
地方公務員の場合は自治体によって規定が異なるため、休暇を取れる日数を確認しましょう。国家公務員の規定と同じかそれに準じていることが多いため、国家公務員が休める忌引きの日数をご紹介します。
| 自分との関係性 | 休暇日数 |
| 配偶者 | 7日 |
| 父母 | 7日 |
| 義父母 | 3日(同居していた場合7日) |
| 祖父母 | 3日(相続・祭祀承継する場合は7日) |
| 義祖父母 | 1日(同居していた場合3日) |
| 兄弟姉妹 | 3日 |
| おじ・おば | 1日(相続・祭祀承継する場合は7日) |
国家公務員の規定はあくまでも参考程度に、属している自治体の規定を見るようにしましょう。後々トラブルになってはいけないので、前もってしっかり確認しておくことをおすすめします。また正社員や契約社員、派遣社員、アルバイトなど、雇用形態によっても忌引き休暇を取れるかどうか変わる場合があるため注意が必要です。
上司に断りの連絡を入れる
亡くなったという知らせを受けたら、その旨を上司に伝える必要があります。基本的には直接伝えるのがマナーです。勤務中であればすぐに口頭で伝えることができますが、帰宅中や自宅で訃報を知った場合はどのように連絡したら良いのか迷うかもしれません。
直接伝えるのが難しい場合は電話での連絡がベターです。電話で連絡できる時間であれば一度電話で伝えた上で、細かい内容を後からメールで送ると良いでしょう。その際、誰がいつ亡くなったのか、関係性や親等を明確に伝え、お通夜や葬儀の日程、葬儀場の情報、連絡先なども併せて送るようにしましょう。
夜中や早朝など電話で連絡するには失礼になるような時間であればメールでの連絡でも問題ありません。その場合は、「夜分のためメールにて失礼します」といった旨を伝えるようにしましょう。
忌引き休暇時の引継ぎを行う
仕方のない理由であるとはいえ、休暇を取る前には仕事の引継ぎを行う必要があります。連絡があった時点ですぐに駆けつけたり、その日に出発しなければならなかったりするときは引継ぎを行う時間がない場合もあるかもしれません。葬儀が滞りなく終えられることが前提ですが、できる限り引継ぎを行っておくことをおすすめします。
忌引き休暇の申請書を作成・提出する
上司に連絡したあと、職場によっては休暇の申請書を作成して提出しなければなりません。誰が亡くなったのか、葬儀の日時や会場などを具体的に記入します。故人との親等によって休暇を取れる日数が違うため、忘れず記入するようにしましょう。
会社員の忌引き日数は就業規則に定められている
会社員の場合は忌引きの日数が労働基準法では定められておらず、会社ごとの就業規則によって定められています。会社員の忌引きに関する内容をご紹介します。
忌引き日数の目安
会社員が休暇を取れる日数は、公務員と同じように故人との親等の近さによって異なります。会社によって日数は異なりますが、一般的な目安をご紹介します。
| 自分との関係性 | 休暇日数 |
| 配偶者 | 10日 |
| 父母 | 7日 |
| 義父母 | 3日 |
| 祖父母 | 3日 |
| 義祖父母 | 1日 |
| 兄弟姉妹 | 3日 |
| おじ・おば | 1日 |
忌引き休暇は労働基準法で定められた休暇ではない
休暇に関することは労働基準法で定められていることが多いですが、忌引きに関しては定められていません。ほとんどの会社で家族や親族の葬儀に参列するための休暇制度を導入しており、会社や団体によって休める日数が異なります。
3親等より遠い親戚は休みを取ることができなかったり、忌引き休暇自体がない会社もあったりすることに注意が必要です。就業規則を確認した上で、上司に相談してみるとよいでしょう。
会社員の場合は直属の上司に「相談」しよう
一般的には親等の近い人が亡くなった場合に休める日数が長く、親等が遠ければ日数が短くなります。しかし親等が遠いからといって必ずしも親等が近い人よりも関係性が希薄だというわけではありません。
例えば義理の祖父母は1日しか休むことができませんが、「生前大変お世話になったため、どうしてもお通夜と葬儀のどちらも参列したい」「葬儀の準備をできる人が少ないため、早めに駆けつけたい」といった場合も考えられます。上司にその想いを伝えれば、規定よりも長い休暇を取ることができる可能性もあります。
公務員・会社員の場合は忌引きの証明が必要
公務員や会社員の家族や親族が亡くなった場合、それを証明する書類が必要な場合があります。死亡診断書や死亡届、火葬許可証、会葬礼状などが証明書類に当たります。就業規則で定められている場合は、必ず提出するようにしましょう。
一方で、亡くなったことを知ってからお通夜や葬儀に参列するまでに書類を用意することができないことも多いはずです。そういった場合は休暇中に書類を準備して、休暇明けすぐに提出するようにしましょう。
「忌引き日数=葬儀にかかった日数」ではない
忌引き休暇というぐらいなので、葬儀にかかった日数だけ休めるのではないかと思うかもしれません。しかし必ずしも葬儀にかかった日数だけ休めるというわけではありません。その理由や一般的な仕組みをご紹介します。
忌引き日数に移動日は含まれない
「忌引き日数=葬儀にかかった日数」ではない理由の一つとして、移動日が含まれていないことがあげられます。父母が亡くなった際の葬儀場は実家近くであることが多いでしょう。
実家から遠く離れたところで働いている場合は、遠方の葬儀場まで移動する必要があります。飛行機や新幹線を利用する場合は、移動に半日かかることも珍しくありません。
叔父や叔母が亡くなった場合は1日しか休むことができないため、移動日分の休暇がなければ参列できなくなってしまいます。そのため忌引きとしての休暇日は1日でも、往復の移動日としてプラス2日休める場合があります。会社によっては移動分の休暇を認めていないこともあるため、相談してみることをおすすめします。
休日が間に入っても忌引き日数には反映されない
移動日として休暇がプラスされることを紹介しましたが、逆に休日が間に入ったとしても日数に反映されないという場合もあります。例えば日曜日に祖父が亡くなって、月曜日にお通夜、火曜日に葬儀が行われると仮定します。3日間忌引き休暇があれば、月曜日、火曜日、水曜日が休暇となり、実質土曜日から水曜日まで休めることになります。
しかし例えば木曜日に祖父が亡くなって、金曜日にお通夜、土曜日に葬儀が行われると仮定すると、金曜日、土曜日、日曜日が休暇扱いとなります。「土日が間に入るから火曜日まで休み」というわけではありません。日数は同じですが、忌引きをとるのが平日と休日の場合とで少し状況が異なることに注意が必要です。
「喪主」を務める場合は規定よりも長く忌引き休暇が付与されることがある
配偶者や父母が亡くなった場合には、喪主を務めることもあります。喪主になれば、お通夜や葬儀の準備から、葬儀後の手続きまでやらなければならないことが多くあるでしょう。そのため規定よりも長い忌引き休暇が付与されることがあります。
会社によって規定が異なるので、故人との関係性や理由を整理した上で上司に相談してみてください。
忌引き後にはお礼を伝える
休暇を取った後、出勤した日には上司や同僚にしっかりお礼を伝えるようにしましょう。仕方のない理由であるとはいえ、1日から長ければ10日以上休むことになります。その間に誰かが仕事を引き継いでくれたり、取引先との予定を変更したりといった調整があったはずです。
小分けのお菓子を持参して、手渡しながら「休暇をいただきありがとうございました。お通夜と葬儀を滞りなく終えることができました。ご迷惑をおかけしてすみませんでした」といったお礼を伝えると良いでしょう。他の人が同じように忌引きで休暇を取る際には、快く仕事を引き受けるといった姿勢を見せるのも良いかもしれません。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
家族や親族が亡くなったら、お通夜や葬儀に参列することになります。近い関係性であれば喪主を務めることもあるかもしれません。会社員は就業規則に忌引き日数が定められていますが、公務員の場合はどこに記載されているのか分かりにくいこともあります。
自分と故人との関係性によって日数が決まっており、親等が近ければ近いほど休める日数が長くなります。3親等以上は休暇を取ることができない可能性もありますが、生前お世話になったからという理由でどうしても参列したい場合は上司に相談してみてください。
地方公務員であれば各自治体によって規定が異なるため、前もって確認するようにしましょう。休暇の申請をする際は、申請書や死亡診断書、会葬礼状といった証明書類を用意しなければなりません。休暇前に用意することができなければ、休暇後に提出しても問題ない場合もあります。
忌引きを取ることで葬儀関係のしきたりやルールに従うことになりますが、分からないことは自分だけで判断するのではなくプロに聞いてみましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



自身が亡くなったときのために、エンディングノートを書いておくのもおすすめです。ホゥ。