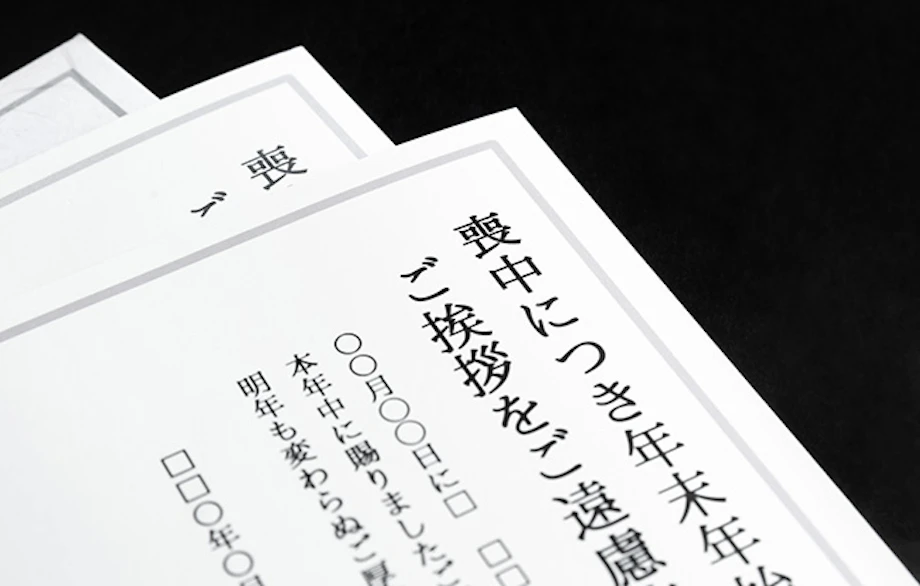身内が亡くなったら、年賀状の代わりに喪中はがきを出す必要があります。多くの関係者に届けなければならず、印刷方法に迷ってしまうという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、喪中はがき印刷におすすめのサービスについてご紹介します。これらを知っておくと、身内が亡くなったときに印刷先を探す手間が省けます。ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・セブンイレブンはカタログとネットの両方から注文可能で、24時間店舗が利用できる
・郵便局では多種多様なデザインやタイプ別のおすすめがあり、幅広いなかから選択できる
・おたより本舗は宛名印刷と送料が全国どこでも無料で、簡単にオンラインで注文できる
こんな人におすすめ
喪中はがきの印刷方法をお悩みの方
喪中はがきの投函時期を知りたい方
喪中はがきを印刷できるサービスを知りたい方
喪中はがきとは?いつ頃出すの?
親や親族など自身にとっての身内が逝去したら、その年は年賀状を自粛して、代わりに喪中はがきを送ることがマナーです。喪中はがきを出す際には失礼がないように、正確な意味や届けるタイミングを知りたい方もいるでしょう。
ここでは、喪中はがきの定義と送る際の適切な時期をご紹介します。身内が亡くなったときの年末年始の挨拶で失礼がないように、喪中はがきの意味を知りましょう。
喪中はがきとは?
喪中はがきは正式には「年賀欠礼状」と呼ばれます。年賀状は送らず、相手からの受け取りも断る意思表示とされます。親族に不幸があった場合は、祝いごとを行わず喪に服すことが日本文化のマナーであるためです。
家族の死は残された人たちに深い悲しみを与えるため、正月などの祝いごとは避け、気持ちの整理をつける期間を喪中といいます。
喪中と知らない相手がうっかり年賀状を送ってしまうと、失礼を犯したと余計な気を遣わせてしまいます。そのような事態を避けるためにも、こちら側から早めの欠礼挨拶を済ませましょう。
喪中はがきを出す時期
喪中はがきには、年賀状を断る目的があります。12月15日には郵便局が年賀状の受け入れサービスを開始するため、逆算して11月中旬から12月初旬までにすべての欠礼挨拶を済ませることが理想といえます。
年末年始、とくに年賀状を送った直後に身内が亡くなるケースも想定されます。届けたあとであれば、喪中はがきを出さずにお正月を祝う期間である松の内(1月7日まで)よりあとに、寒中見舞いとして身内の逝去を告げるとよいでしょう。
「セブンイレブン」の喪中はがき印刷サービス
コンビニ大手のセブンイレブンではさまざまなサービスがありますが、喪中はがき印刷も含まれます。カタログまたはネットから注文でき、店内に備えられたコピー機によるセルフサービスも使えます。
宛名や内容などの印刷も可能で、1枚ずつまっさらなはがきに書く手間も省けます。コンビニらしくきめ細やかなサービスが魅力です。
注文・印刷方法
注文は店舗カタログとネットの両方から可能です。毎年年賀状シーズンに並ぶカタログの後半部分に、喪中はがき印刷が載っています。ページ内のデザインから選択でき、カタログから決定したメニューを店頭で頼むことができます。
インターネットからもネットプリントとして喪中はがきを頼めます。郵便局のはがきデザインキットなどを使えば、自身の好みのデザインへカスタマイズすることもできます。とくに自宅にプリンターがない世帯にとって便利なサービスといえるでしょう。
宛名印刷の有無
セブンイレブンの喪中はがきサービスでは宛名印刷も可能です。差出人住所、挨拶文、故人の名前や逝去日などもあらかじめプリントできるため、それらと一緒に頼むとよいでしょう。
ただしデザインによっては宛名印刷不可能なものもあるため、カタログやネットメニューを確認しましょう。メニューにあるデザインは参考情報として宛名印刷の有無が示されています。印刷ありのデザインを優先して選ぶこともひとつの方法です。
料金
セブンイレブンに早割料金で印刷サービスを依頼した場合、10枚までで2,849円かかります。枚数は1枚から、1枚単位で注文可能ですが、印刷料金は10枚単位の計算となるため端数計算できないようになっています。また、申込日によって料金が変わるため注意が必要です。
セルフサービスと早割依頼ではコストが異なります。時間に余裕があったり節約を望んだりするなら、自力で店舗のコピー機を使用しましょう。ただしコピー機によるセルフサービスの開始は12月1日からのため、仕事や育児などで忙しく、1枚ずつの印刷に構っていられない方もいるでしょう。その場合は、予算の範囲内で早割依頼の印刷を検討しましょう。
「郵便局」の喪中はがき印刷サービス
喪中はがきの印刷は、郵便局で行うほうが安心できるという方もいるでしょう。こちらでも注文はカタログかネットで行い、プリント範囲を自分で決定できます。宛名印刷にも別途料金がかかるなどコンビニとは違った特徴が見られるため、事前の予算チェックは大切です。
郵便局ははがきの扱いを知り尽くした業種で信頼しやすい分、コストもそれなりにかかります。
注文・印刷方法
郵便局での喪中はがきの注文は、カタログやインターネットから行います。カタログは郵便局から無料で受け取ったり、インターネットの資料請求で取り寄せたりできます。自宅や勤務などで利用する駅の近くに郵便局がない場合は、インターネットから取り寄せるほうが賢明でしょう。
インターネットでも多種多様なデザインやタイプ別のおすすめが見られ、幅広いなかから選択できます。簡単に済ませたい方向けの挨拶文付きから、自力で気持ちを込めて作りたい方のために絵柄のみ印刷されているものまであるため、好みに応じて選ぶとよいでしょう。
宛名印刷の有無
郵便局で注文できる喪中はがきへ、宛名の印刷も追加で依頼することができます。しかし宛名だけで基本料金1,100円に加え、印刷1枚ごとに31円を要します。コスト計算は不可欠であり、節約を考えるなら宛名なしの安価なものを頼み、自力で仕上げるなどの工夫が必要です。
コンビニよりも宛名に対する価格設定がシビアな点が郵便局の特徴です。どうしても郵便局で喪中はがきを印刷してもらいたいが、なるべくコストを抑えたい場合は、宛名の印刷を頼まない選択肢も検討しましょう。
料金
喪中はがきを郵便局に印刷してもらうには価格が低いもので、1枚~10枚で2,940円かかります。ここに消費税や宛先への送料も含まれます。コンビニで自らコピー機で喪中はがきを印刷するよりは高価です。
ただし郵便局には早期の依頼やインターネット利用などによる割引が設けられています。このような割引があることから、郵便局に気兼ねなく頼めると思う方もいるようです。割引は、印刷料金から引かれる形で適用されます。
郵便局でははがきに対する扱いが丁寧である分、ほかのサービスより基本的なコストがかかりがちなので、予算との相談が大切です。
「おたより本舗」の喪中はがき印刷サービス
おたより本舗は、はがき専門の印刷サービスです。送料無料、宛名プリントでも料金はかからないなど、ほかの業種では見られないサービスが魅力です。
10枚単位での印刷依頼コストが安いなど、独自のサービスもポイントといえます。喪中はがき印刷の選択肢として押さえておきましょう。
注文・印刷方法
おたより本舗では紙媒体のカタログは扱っておらず、インターネットからのみ注文を受け付けています。公式サイトのメニューリストでは、スタンダードデザインから始まり、故人の写真付き、モノクロ、薄墨プリントなど、さまざまなニーズに応じた選択肢があります。
注文は、記入または選択式です。決定次第おたより本舗で印刷され、ネコポスで届きます。留守中でも自宅に投函してくれるため不在票が入ることもありません。仕事や家事などで忙しい方でも利用しやすいサービスでしょう。
宛名印刷の有無
おたより本舗では宛名印刷を無料で受け付けています。コンビニや郵便局では宛名印刷に追加料金を要するため、この違いに魅力を感じる方も多いようです。
はがきの注文には会員登録が必要ながら、宛名印刷サービスは会員でなくても利用可能です。ただし、注文数が多いと時間を要してしまいます。なお宛名印刷のみでは注文不可である点に注意しましょう。
料金
早期割引適用の場合、10枚1,895円で届けてもらえます。同時注文、会員特典など複数の割引パターンがあり、場合によっては併用もできます。ほかにも、全国場所を問わず送料無料などの特典が魅力です。
割引に関する積極的なキャンペーンを展開しているため、注文時はこちらもチェックしておきましょう。
喪中についてもっと詳しく知りたい方はこちら
この記事を読んで「もっと喪中について詳しく知りたい」「◯◯の部分がよくわからなかった」という方へ向けて、喪中に関連する内容を網羅的にまとめた記事をご用意しました。ぜひこちらもあわせてご確認ください。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
現在では郵便局だけでなく、コンビニやインターネットでも喪中はがきを頼めます。予算やサービス内容などを総合的に考えて、どこに頼めば得かの判断が大切です。デザインも多種多様なので自身や故人の思いをベースに理想のパターンを決めましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
誰が亡くなったら喪中になる?
故人が2人いる場合連名にしてもいい?
喪中はがきが間に合わない場合はどうする?
喪中はがきは早く出すとお得なの?
喪中はがきで使ってはいけない言葉はある?
喪中はがきのデザインの違いとは?

忌引き休暇は、実は労働基準法で定められた休暇ではありません。ホゥ。