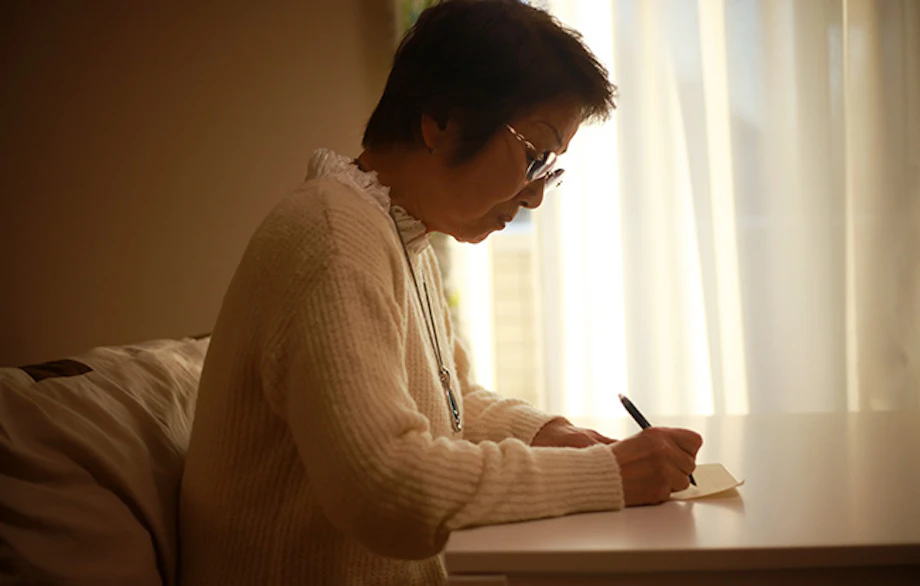四十九日法要の案内状が届いたら、できるだけ早急に返信することが大切です。とはいえ、日頃あまり触れる機会がないため、返信の仕方がわからないという方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、四十九日法要の案内状への返信の仕方をご紹介していきます。多くの方が悩む、返信ハガキの書き方からマナーまで詳しく解説していきますので、本記事を読んでいただければ今抱えている不明点はすっきり解消されることでしょう。
<この記事の要点>
・案内状が届いたら速やかに返信し、出席の場合は「御」の字を斜め二重線で消すのがマナー
・法要を欠席する場合は返信ハガキとともに詫び状を添えるのが理想
・返信ハガキには濃墨のペンを使用し、薄墨は避けるのがマナー
こんな人におすすめ
四十九日法要の案内状が届いた人
四十九日法要の案内状の返信に困っている人
マナーを守って返信を書きたい人
四十九日法要の案内状に対する返信ハガキの書き方
四十九日法要の案内状が手元に届いたら、できる限り早く返信する必要があります。案内状と一緒に法要への出席を確認する返信ハガキが同封されているため、そちらへ記入して送付しましょう。
ただし注意したいのが、返信ハガキへの記入はただ単に「出席」「欠席」に◯を付ければ良いというものではないという点です。ご遺族の心に寄り添う想いを丁寧に表現するために、返信ハガキの書き方のマナーを把握しておきましょう。
ここでは、四十九日法要の案内状に対する返信ハガキの書き方をご紹介します。
出席する場合
出席する場合の返信ハガキの書き方は、まず返信ハガキの表面に書かれた施主の宛名の下に記載された「行」や「宛」の謙譲表現を、右側を上、左側を下とした斜め二重線で消します。そしてその左横に敬語表現の「様」を書き添えましょう。
返信ハガキの裏側を見ると、「御出席」「御欠席」の2文字が大きく印字されています。「御出席」の文字の一番上「御」の文字のみを右側を上、左側を下とした斜め二重線で消し、「出席」の2文字を◯で囲みましょう。次に「御出席」の隣にある「御欠席」の3文字を縦二重線で消します。
返信ハガキの左側にある「御住所」の一番上「御」の文字のみを1同様に斜め二重線で消し、自分の住所を下に続けて記入しましょう。そして「御住所」の隣に記載された「御芳名」の「御芳」の2文字を縦二重線で消し、自分の名前をその下に続けて記入します。
記入している本人が自分に対して敬語表現を使うのは適切ではないため、返信ハガキではいずれの枠においても「御」の文字は二重線で消すのがマナーです。また「出席」に◯を付けるではなく、その下に「させていただきます」「いたします」などの文面を追記すると、より丁寧な印象を与えるでしょう。
欠席する場合
法要に欠席する際の返信ハガキの書き方は、前項「出席する場合」の1と同様に、返信ハガキ表面の施主の宛名に添えられた「行」「宛」の謙譲表現を消し、「様」を書き添えましょう。そして返信ハガキ裏側、「御出席」の文字をすべて右側から左側に引き下ろす形の縦二重線で消します。
次に「御欠席」の一番上「御」の文字を斜め二重線で消し、「欠席」の2文字を◯で囲みましょう。その下に、「させていただきます」「いたします」などの文面を追記します。
以降は、前項「出席する場合」の3、4と同様なので割愛します。
四十九日法要を主催する施主は、返信ハガキの出欠状況を見て料理や引き出物の手配をするため、欠席の場合においても返信は速やかに行ってください。また欠席を伝える場合には、詫び状を添えるのが理想的です。
欠席する際の例文
欠席する場合に添える、詫び状の例文をご紹介していきます。
謹啓
この度は亡○○◯◯様の◯◯忌の法要のご案内をいただき誠にありがとうございました。
長年お世話になりました◯◯さまのご法要にはぜひとも参列させていただく所存でおりましたが、現在出産を間近に控えた妊娠中の身であり、医師より自宅安静との指示を受けております。誠に申し訳ございませんが、今回は欠礼をさせていただきたくお詫び申し上げます。
心ばかりではございますが、亡○○様のお好きだったお花を別便にて送らせていただきましたので、御仏前にお供えいただければ存じます。出産後落ち着きましたらあらためてお伺いさせていただきたく、略儀ではございますが、まずは書面にて不参のお詫びを申し上げます。寒さ厳しき折にて、皆様どうかご自愛くださいませ。
返信ハガキにコメントを添えても良い?
四十九日法要の返信ハガキの場合、メッセージを書く欄は用意されていないことがほとんですが、余白の部分に書き添えても問題ありません。施主が遠方に住んでいて普段なかなか会う機会を持てない人物である場合には、一筆添える方が相手に丁寧な印象を与えます。
書き添えるメッセージの内容としては、「ご案内をいただきありがとうございます。ご法要当日は皆様とともに、亡○○様のご冥福をお祈りさせていただきたく存じます」などの文面を用いると良いでしょう。
返信ハガキを書くときに使うペンは?
四十九日法要の返信ハガキを書くペンは、ポールペンで問題ありません。筆や筆ペンを使う場合は、薄墨ではなく濃墨で書くようにしましょう。薄墨は「突然の訃報に悲しむ涙で墨がにじんでいる」という意味が込められていることから、葬式や通夜の際に用いるものです。
一方、四十九日法要は忌明けの日とされていることに加え、執り行われる日取りがわかっていることから、濃墨が好ましいとされています。ただし法要の返信ハガキで使うペンは、ボールペン、筆、筆ペンいずれの場合でも「黒」を使うようにしましょう。
案内状が届いたときの返信のタイミングは?
四十九日法要の案内状が届いたら、できる限り速やかに返信するよう心がけましょう。法要を取り仕切る施主は、返信ハガキに記入された各々の出欠状況を確認したうえで準備を行います。
返信が滞ると料理や引き出物といった法要準備の進捗に差し支えるため、施主が円滑に準備を進められるよう素早い返信を心がけてください。返信と同時に施主宛に挨拶の電話を入れておくとなお良いでしょう。
電話やメールで返信をしても良いのか
近年は法要の案内状を出さずに、電話やメールで案内を行うケースが増えています。この場合には、案内と同様に返事も電話やメールで行う形で構いません。ただしメールでの返信は、確実に確認してもらえるとは限らないため、メールを送ったと同時に施主に挨拶の電話を一本入れておいた方が良いでしょう。
また従来通り案内状をハガキでもらった場合でも、電話で返事をすることは何ら問題ありません。ただし案内状と一緒に返信ハガキが同封されているのであれば、ハガキも送るのが好ましいでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
四十九日法要の案内状をもらったら、出来る限り速やかに返信することが大切です。またただ返信をするのではなく、施主の心に寄り添った丁寧な書き方やマナーも必要です。この機会に、しっかりとした知識を身につけ、いざという時に困らないようにしましょう。
小さなお葬式では、セットプラン内で葬儀に必要な物品サービス※が含まれますので、安心して葬儀を行えます。全国4,000カ所以上の葬儀場と提携しており、どの宗教・宗派のお葬式にも対応しております。(※火葬料金別)
葬儀、納骨、法要に関するご相談は、ぜひ「小さなお葬式」をご利用ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。ホゥ。