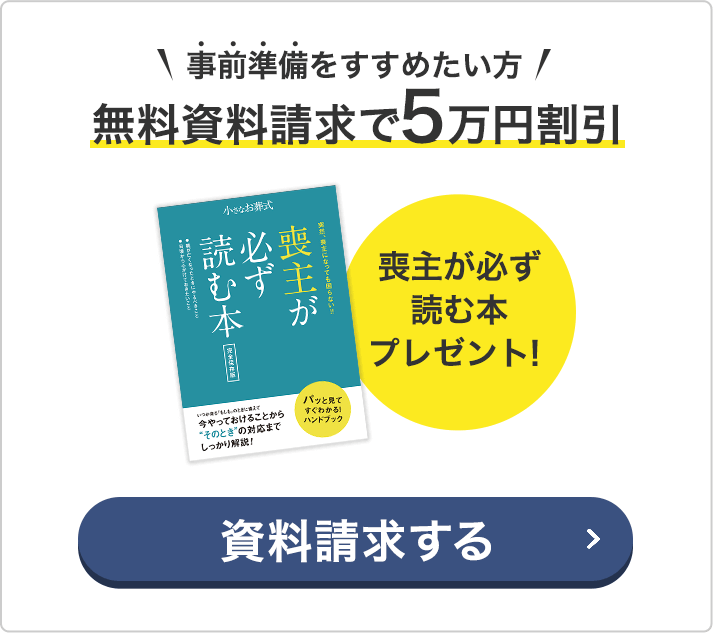「近しい人が亡くなり、喪中と厄年の期間が被ってしまった」場合はどうすればよいのでしょうか。厄払いをしたいけれど喪中の間に依頼をしてもいいのか否かという疑問についても解消するべきと言えます。
この記事では、厄払いの基本的な知識とあわせて、喪中期間に厄払いができるのかといった点を解説します。
<この記事の要点>
・喪中と厄年が重なった場合、忌明け後に厄払いを行うことが一般的
・厄払いの際は礼服・正装でなくてもよい
・お礼参りとは厄年を無難に過ごせた報告と感謝を伝えるための参拝のこと
こんな人におすすめ
喪中と厄年が重なってしまった方
厄年や厄払いの概要を知りたい方
厄払いを受ける際の注意点を知りたい方
そもそも厄年とは何か?
「今年は厄年だから気を付けなければ」などといった言葉を耳にしたことがある方は少なくないでしょう。日本では「前厄」「本厄」「後厄」の3年間は、注意が必要な年だとされているためです。ここでは、厄払いについて解説します。
厄払いを行う目的
仏教では男性は数え年で25・42・61歳、女性は19・33・37・61歳の1年間がそれぞれ「本厄」、前年が「前厄」、後年が「後厄」にあたるとして注意を促しています。中でも男性42歳、女性33歳は「大厄」と呼ばれ、特に注意が必要な年齢です。
厄年は一般的に人生の転機や変化が訪れることが多いタイミングと言われ、予期せぬ災難に見舞われたり、体調面や精神面で何かと落ち着かなかったりといったことが増える傾向にあります。
厄払いはこうした前厄・本厄・後厄の3年間を無難に過ごせるよう、祈祷・お祓いをして「大難を小難に、小難を無難に」するための儀式です。
厄払いに適した時期
現代では基本的に1年を通して厄払いを受け付けている神社が多く、例えば学校への入学前や就活準備期間、結婚式の前など、自分にとって節目となる時期に厄払いの祈祷を受けることができます。
元々厄払いは1月1日から2月3日の節分までの間に行われることが多く、これは2月4日ごろの「立春」が旧暦の新年にあたるため、それまでに済ませておこうという考えから古い時代に定着したものです。
神社の中にはこの時期に併せて厄払いを目的とした「厄除大祭」を開催するところもあるため、個別に依頼するのは気が引けるという方は、こうした機会に厄払いを済ませることも手段の一つでしょう。
厄除けと厄払いの違い
厄除けと厄払いを端的に言うと「厄除け」はお寺で、「厄払い」は神社で行われる「厄」への対処です。
仏教では仏の加護によって災いから身を守り、予防的に厄を除けるので「厄除け」、神道では降りかかった災いをお祓いによって追い払うため「厄払い」と呼ばれます。厄除け・厄払いの儀式はお寺では主に護摩祈願、神社ではお祓いによって行われる儀式です。
護摩祈願は僧侶が仏様をお招きし、燃え盛る炎の中に供物を捧げておもてなしをすることで願いを聞き入れてもらう儀式です。同時に、護摩で焚かれる清らかな炎で私たちの煩悩を焼き尽くすとも言われています。
お祓いは神職が「祓詞(はらえことば)」を奏上し、「大麻(おおぬさ)」で参列者を祓い清める儀式です。その後、参列者は「玉串」を神前に捧げます。神社によって異なりますが、儀式の間に巫女による「神楽」が入ることも場合もあります。
厄年になるべく避けるべきこと
運気が変化するとされる厄年の期間中は、「引越し・家の新築など、自分自身の大きな変化を重ね合わせるべきではない」というのが定説です。しかし、こうした定説をあまりに気にし過ぎてしまうと、気軽に旅行等も行けなくなってしまいます。
そこで「引越し・海外旅行など1年だけ我慢できるものを1つ決め、ほかは好きなことをした方が良い」という考え方もあるようです。
基本的には結婚のような特に大切な慶事をのぞき、厳密に厄年を意識した生活を送ろうと気を張る必要はありません。
喪中期間中に厄払いは可能か?
喪中の期間は、さまざまなことを禁じて身を慎むものだというイメージが現在でも定着しています。喪中と厄年が重なってしまった場合には厄払いも慎むべきなのだろうか、と迷われる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、喪中期間の厄払いについて解説します。
喪中とは?
「喪中」は家族・親族など、身近な人が亡くなった際に故人の死を悼んで冥福を祈り、その悲しみを乗り越えるまでの期間を指す言葉で、日本では古くからある風習の一つです。
一般的には故人が亡くなってからの1年間を喪中とし、1周忌の法要を完了することで「喪明け」、つまり通常の生活へ戻ることが多くなっています。
喪中の期間のはじめに「忌中」という期間もありますが、その意味合い・期間の長さは喪中とは大きく異なります。喪中は「哀悼の意を表す」が目的であるのに対して、忌中は「穢れを周囲に広めないこと」を目的とする期間です。
仏教では死者の魂が生前の行いに関して裁きを受け、それらが全て完了するまでに四十九日間がかかると言われており、これが忌中にあたります。そのため、四十九日法要の完了をもって「忌明け」とし、その後に故人の死を悼む喪中の期間へと移行するのが習わしとなっています。
神社とお寺で異なる
昔は喪中の期間には喪服を身に着け、お祝いの行事・お酒などを禁じて身を慎み、喪に服していた時代もありました。現代でも結婚式などの大切な慶事を避ける風習が残っています。しかし、神社とお寺では、喪中の扱いが異なることを知っておくことが大切です。
神社は日本古来の民族宗教である「神道」にまつわる神様を祀っている建物です。死に対しては「穢れ」、つまり「正常な状態ではなく、多くの人々に災いをもたらすもの」とみなして避ける立場がとられています。
一方、お寺は故人を弔う場でもあることから、死を遠ざける風習はありません。喪中・忌中であっても問題なく参拝や境内への立ち入りが可能です。
神社の穢れとは?
前述した通り、神道の考え方では死は「穢れ(けがれ)」にあたります。
元々神社は神様の住まいとも考えられており、「神様のおられる神社の中へ穢れを持ち込んではいけない」とする風習から、死を穢れとする風習は現在でも残っており、四十九日の忌明けまでは神社へ行くべきではないとされています。
また穢れは「気枯れ」とも書きます。この気枯れは簡単に言うと気力が非常に落ち込んでいる状態で、親しい人を亡くして悲しみに暮れている状態のことも指す言葉です。忌明けが済んだ方でも、気枯れしている状態の方は神社へ入るのを避けた方が良いでしょう。
神道での忌中期間は故人との関係性・地域の風習などにより変わりますが、一般的には50日程度とされています。
厄払いの祈祷を受ける際のマナー
神社で厄払いの祈祷を受ける際にも、場に適したマナーがあります。ここでは、当日の服装・初穂料の相場・のし袋の書き方・代理での厄払いについて解説します。
服装
厄払いの祈祷を受ける際、一般的に服装の決まりはありません。きちんとした礼服を用意すべきかと悩む人もいるかもしれませんが、厄払いといった祈祷の場合、基本的には礼服・正装でなくても構いません。
男性ならスーツやジャケットを、女性ならシックなワンピースなどを着るのが無難でしょう。
また、神社によっては靴を脱いで本殿や本堂へ上がる場合があります。神社は神様の住まいとされる場所です。サンダルなど脱ぐと素足になる靴は失礼にあたるため避けましょう。
厄払いの祈祷というと身構えてしまいがちですが、神様への敬意を持ちマナーを守れば、気軽に参加できる神社は多々あります。厄払いをご検討の方は、自分の地域の神社がどういった形で祈祷を行っているのかチェックしてみるのも良いでしょう。
初穂料の相場
「初穂(はつほ)」は、その年に初めて採れた農作物を神社へ捧げられるもののことです。日本では古くから収穫時期である秋に豊作の喜びと感謝の気持ちを込めて、神様へその年の初穂を奉納する習慣がありました。
神社への謝礼は時代を経て初穂から貨幣へと形を変え、現在では厄払いだけではなく七五三など、祈祷の際の神社への謝礼は「初穂料」としてお金を納めるようになっています。
厄払いの初穂料の目安は、全国的にみると5,000円から10,000円程度が相場です。ただし、縁起が悪いとされる「4」や「9」のつく金額は避け、切りの良い金額をお納めするようにしましょう。基本的には祈祷をお願いする際に神社へ確認しておき、それに従うのが無難でしょう。
「お気持ちで」と言われる場合もありますが、そうした場合には5,000円ほどを用意してお納めすると良いでしょう。
のし袋の書き方
厄払いの謝礼の表書きは「初穂料」「玉串料」「御礼」といった表書きが使用されることが多くなっていますが、初穂料という表書きは神社で行われる神事に対して幅広く使えます。どれを選べばいいのか分からないという方は、初穂料と記載しておくのが良いでしょう。
続いてのし袋への名前の書き方です。名前は祝儀袋と同じように、水引を境にして下段中央に奉納者の氏名を縦書きします。水引・のしがない場合には表書きに名前は書かず、裏面に住所・名前を並べて左下に書きましょう。
ただし、白封筒で謝礼を渡す場合では、封筒表面の上部中央に「御初穂料」と書き、その下に奉納者の氏名を記載します。
額面を記載するかどうかでも悩まれるかと思いますが、額面は裏面に記載するのが一般的です。
代理での厄払い
仕事や育児・介護・ご自身の病気などで直接神社へ厄払いに出向くことが難しいという場合には、配偶者や他の家族に代理で出向いてもらい、厄払いを受けることもできます。
その際、実際に出向くのは代理の方であることとあわせて、ご本人の名前・生年月日を神社へ伝えておけば問題ありません。
ただし、神社によっては代理での厄払いを受け付けていないところもあるため、厄払いをお願いする神社へ事前に問い合わせをしておくと良いでしょう。
いわゆる「リモート祈祷」を実施している神社もあります。神社へ直接出向くことが難しい場合には、これらの方法も手段の一つとして参考にされてみてはいかがでしょうか。
厄払いのお礼参りについて
厄払いのために神社へ行くことはあっても、「お礼参り」のことは忘れてしまいがちです。ここでは、お礼参りとは何か・適切な時期・服装・直接出向けない場合の対処法などをご紹介します。
お礼参りとは?
「お礼参り」は、厄年を無難に過ごせたことに対する報告と感謝を伝えるための参拝のことを言います。そもそも厄年は「人生の運気が下がり、良くないことが起きる可能性がある年」のことです。
体力面・精神面で変化が起きやすい年とされ、「前厄」「本厄」「後厄」と3年間にわたりこの「良くないことが起きる可能性がある年」が続きます。
この3年間の厄年を無難に過ごせるよう祈祷・お祓いをして「大難を小難に、小難を無難に」する行事が厄払いとなります。
例えば「厄年に大きな事故に遭うも、膝を擦りむいただけで済んだ」など、ふとした災難に遭っても小さな被害で済んだことはないでしょうか。こうした恩恵は厄払いのおかげかもしれません。
このように自身では気付かぬうちに災難を回避できていた可能性も考慮して、厄払いを行った翌年にはお礼参りで感謝の気持ちを伝え報告をしましょう。
時期
お礼参りは厄年終了の合図でもあるため、気持ちを切り替えるにも良いことだと言われています。このお礼参りに厳密な期日などはありませんが、目安としては厄払いの1年後が一般的です。
通常、厄払いは1月1日から2月3日の節分までの間に行う方が多くなっています。これは2月4日ごろの「立春」が旧暦の新年にあたるため、それまでに済ませておこうという考えから定着したものです。
厄年は3年間続くため、この3年間で厄払いとお礼参りを繰り返したり、本厄の年だけ厄払いをして翌年にお礼参りをしたりする方もいます。
服装
お礼参りは参拝で神様へその1年の出来事について感謝を伝え、報告をするものです。通常の参拝に関して服装に厳密な決まりはないため、私服でも問題はありません。
ただし、厄払いを受ける際と同様にカジュアルすぎる服装は避け、品の良いものやセミフォーマルのものを選ぶなど気を遣った服装を心掛けましょう。
お礼参りの際には、厄払いで授与されたお守り・お札を返納します。この際、神様へのお礼の品を渡したい時は「奉納品」をお贈りしましょう。
奉納品に決まりごとはありませんが、お米・お酒・季節の果物などの食べ物は「神撰(しんせん)」とされ、一般的に奉納されることが多い品となっています。
奉納では品物にのしを巻き、表書きに「奉納」や「奉献」と書いて氏名を記載します。お酒の奉納の際には「献酒」と表書きをしましょう。
お礼参りに行けない場合
「遠方へ旅行に行った際に祈祷をお願いしたのでお礼参りに行けない」という場合もあるでしょう。しかし、必ずしも直接厄払いの祈祷をお願いした神社へお礼参りをしなければならないという決まりはありません。
例えば、その神社の総本山や同じ系列の神社へ参拝するか、住んでいる場所に近い産土神様や氏神様へ参ることでもお礼参りができます。
これは伝言に近い考え方で、「あの方には大変お世話になりました。とても感謝していますとお伝えください。」と近くにおられる神様にお願いするのです。
ただし、こうしたお礼参りを近場で済ませるためにお願いするからには、きちんと日ごろからそちらの神社への参拝をするように心掛けましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
厄払いをはじめ、神社やお寺で行われる祈祷では普段耳にしない言葉が使われていたり、時代の変化に合わせながらも残ってきた特有の考え方やマナーが存在していたりします。そのうちの一つが喪中に対する扱いです。
喪中期間にどうしても厄払いをしたい場合にはお寺で「厄除け」を、時期を調整できるのであれば神社での「厄払い」を依頼すると良いでしょう。
「前厄」「本厄」「後厄」の3年間を憂いなく過ごせるよう、自身の状況やそのほかの細かな疑問は事前にしっかりと相談しておくことが大切です。
いざという時に困らないために、葬儀全般に関するご相談は「小さなお葬式」までお問い合わせください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


告別式とは、故人と最後のお別れをする社会的な式典のことです。ホゥ。