日本では喪中になると、喪中はがきを友人や知人に送って、翌年の年賀状のやりとりを行わない文化があります。ここで気になるのが、外国の文化であるクリスマスは、日本と同じように喪中は静かに過ごす必要があるのかという点です。
この記事では、喪中におけるクリスマスの過ごし方と喪中期間のイベントのマナーについて詳しくご紹介していきます。
<この記事の要点>
・喪中期間中でもクリスマスを楽しむことは問題ない
・クリスマスカードを送る相手が喪中の場合、送付するのは控えた方が良い
・喪中の年末年始は正月飾りやおせち料理を控えるのがマナー
こんな人におすすめ
喪中におけるクリスマスの過ごし方を知りたい方
喪中や忌中の際の年中行事の捉え方について知りたい方
喪中の際のクリスマスカードの扱いについて知りたい方
喪中のクリスマスはどうすれば良い?
喪中のクリスマスはどうすれば良いのでしょうか。ここでは、喪中や忌中に加えてクリスマスとは何かを解説したうえで、喪中におけるクリスマスの過ごし方をご紹介します。
喪中・忌中とは
喪中・忌中は何を意味するのでしょうか。両者について詳しく解説していきます。
まず、喪中・忌中ともに、亡くなった故人を偲び、喪に服す期間を指しますが、その期間の長さが異なります。
喪中は忌中を含む1年間で、忌中は仏式では四十九日の法要まで、神式では五十日祭までとされています。
喪中や忌中といった期間は、近しい人を失くした悲しみはすぐには癒えないため、この期間は遺族が悲しみと向き合ってその後の社会復帰のために必要な時間とし、気持ちの整理をつけるために設けられています。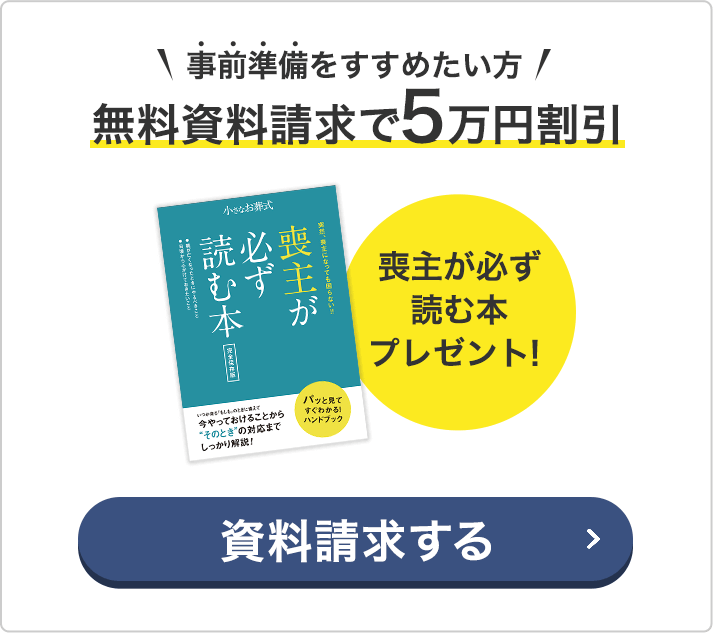
クリスマスとは
クリスマスとは、イエス・キリストの降誕を祝う祭です。
キリスト教の聖典である聖書では、キリストの誕生日を明確に規定していないので、正確に述べると、クリスマスはキリストの誕生日ではなく、キリストがこの世に生まれてきたことを祝う日とされています。現在では12月25日がクリスマスと決められています。
クリスマスになると、クリスマスツリーを飾ったり、子どもはサンタクロースからプレゼントを貰ったり、クリスマスカードを交換したりといった風習がありますが、これらは比較的新しい習慣です。
喪中のクリスマスの過ごし方
喪中のクリスマスはどのように過ごせば良いのでしょうか。実は、クリスマスは戦後日本に入ってきた新しい風習なので、特に取り決めも制約もありません。騒ぎすぎなければ家族や友人でパーティーを開いたり、イルミネーションを鑑賞したりといったことは、何ら問題ないでしょう。
また、キリスト教にはそもそも喪中がありません。キリスト教徒は死とともに神の元へ召されるので、親族が亡くなったとしてもクリスマスのミサを行います。
クリスマスツリーなどの飾り付けは控えるべき?
上述したように、キリスト教には喪中がないため、飾り付けを過度に控える必要はありません。しかし、日本においては、仏教や神道などで喪中の期間中はお祝いごとを控える傾向があります。
喪中に煌びやかなクリスマスツリーを飾って楽しむことは不謹慎と考える方もいるので、クリスマスツリーは家の外ではなく、家の中で飾って楽しむのが良いでしょう。
また、クリスマスケーキに関しても、喪中にクリスマスケーキを食べてクリスマスのお祝いをすることは、喪中に関するマナーに違反する行為ではありません。
しかし、喪中は宴会に参加する場合も慎み深い姿勢が求められることを考慮すると、クリスマスケーキを食べて派手に騒ぎすぎることは控えるようにしましょう。
喪中のクリスマスカードの扱い
キリスト教には喪中がないことがお分かりいただけたと思いますが、それでも喪中にクリスマスカードを送っても良いのか心配な方もいるでしょう。ここでは、そもそもクリスマスカードとは何かに加え、喪中はがきを送る目的や、喪中のクリスマスカードの扱いをご紹介します。
クリスマスカードとは
クリスマスカードとは、キリストの誕生を祝い、友人たちにその喜びを伝える手紙です。また、キリスト教圏の人々にとっては、日本における年賀状のような役割も果たしています。クリスマスカードには「メリークリスマス」の他に「ハッピーニューイヤー」といった文言も添えられるのが一般的です。
クリスマスカードを送る時期として、日本ではクリスマスの直前が望ましいのではと考えられがちですが、海外では11月の下旬から12月の上旬に届くように送ります。
欧米では、11月下旬の感謝祭後から一気に街の空気がクリスマスムードに変わるので、この時期に合わせてクリスマスカードを送るのが一般的です。
ただし、日本でキリスト教の文化に接していない人々からすれば、なぜ季節外れにクリスマスカードが届くのか不思議に思うケースもあるようなので、送るタイミングは相手に合わせて気を配るようにしましょう。
喪中はがき送る目的
喪中はがきは、1年以内に身内に不幸があったため、喪中なので年賀状を出さないことを事前に知らせる年賀欠礼の挨拶状です。一般的に喪中の期間はお祝いごとを避けて喪に服すので、年賀状は出しません。
また、喪中はがきは、10月から12月上旬の間に送ります。送付が早すぎたり、遅すぎたりすると相手が年賀状を書く頃に喪中のことを忘れてしまう、すでに年賀状を投函済みであるといったケースもあるため、適切な時期に送るようにしましょう。
さらに、喪中はがきを送る相手は、年賀状のやりとりをしている人々の全員が対象となります。ただし、仕事関係者には通常通り年賀状を出すこともあります。その他、会社名で出している年賀状は、社長が亡くなったとしても一般的には欠礼しません。
喪中にクリスマスカードを送るのは非常識?
自身が喪中である場合、クリスマスカードを送るのは非常識にあたるのでしょうか。結論から言えば、受け取る相手次第ということになります。
そもそも、キリスト教に喪中という慣習はないため、たとえ身近な人の不幸があったとしても、キリスト教圏ではクリスマスカードのやりとりは問題なく行われています。
しかし、日本では仏教や神道の慣習が根強いため、どうしても喪中の人からクリスマスカードが送られてくることに抵抗を感じる人もいます。そのため、クリスマスカードを送る人を選ぶようにし、不安な場合は直接本人に確認しておくと安心です。
喪中の方にクリスマスカードを送るのは失礼?
では、相手が喪中である場合、クリスマスカードを送るのは失礼にあたるのでしょうか。こちらも結論から言えば、受け取る相手次第で正解はありません。
しかし、日本においては喪中という慣習が強く根付いているので、キリスト教徒でない喪中の方にクリスマスカードを送ると、非常識だと思われる可能性があります。
また、何より重要なことは、喪中の相手の気持ちを思いやることです。相手が大切な人を亡くし、気持ちが沈んでいるようであればクリスマスカードを送付することは控えた方が良いでしょう。
喪中は寒中見舞いでの代用がおすすめ
喪中にクリスマスカードを交換するかどうかの判断で迷ったら、寒中見舞いで代用するという方法もあります。
寒中見舞いは、もともとは寒さの厳しい真冬に相手を気遣う挨拶状でしたが、最近では、「喪中の方への挨拶状」および「喪中の方からの挨拶状」として利用されるケースが増えています。
寒中見舞いを出す時期は、1月8日から2月3日前後までに投函して、立春である2月4日までには相手に届くようにするのが一般的です。ちなみに、喪中はがきは、年賀状の返信が遅れてしまった場合や、喪中と知らずに年賀状を出してしまった方へのお詫びとしても利用できます。
喪中・忌中期間の行事、習慣の捉え方
日本において喪中はさまざまな行事の主催や参加を自粛する傾向があります。ここでは、喪中・忌中期間の各行事や習慣の捉え方をご紹介します。
お中元・お歳暮
喪中期間中は、お祝いごとは避けるべきとされています。しかし、お中元やお歳暮は、感謝やお礼の気持ちを表明する贈り物なので、お祝いごとではありません。
したがって、お中元やお歳暮は喪中であっても贈っても問題ありません。さらに、先方が喪中である場合も同様で、お中元・お歳暮を贈っても大丈夫です。
ただし、忌中期間中はできる限り控えることが望ましいです。仏式の方は四十九日を、神式の方は五十日を過ぎてから贈るように心がけましょう。
なお、喪中にお中元やお歳暮をやりとりする場合は、熨斗や水引がついたのし紙は使用しません。白無地の奉書紙や白い短冊を用い、表書きに「御中元」などと記載して贈ります。
年末年始
喪中の年末年始はどのように過ごすべきでしょうか。年末年始はいくつか気をつけるべきことがあるので、それぞれ詳しくご紹介していきます。
まず、正月が喪中期間の場合は年賀状を出すのを控えなければなりません。もし喪中はがきを出さなかった人から年賀状が届いたら、寒中見舞いで喪中であることと年賀状を控えた旨を伝えましょう。
また、正月飾りは控えましょう。門松や鏡餅などは新年を祝うためのものなので、喪中の家で飾るには相応しくありません。
さらに、年越しそばやおせちですが、年越しそばは一年の厄を落としや長寿への願いを込めた食べ物なので、喪中の人が食べても全く問題ありません。
しかし、おせち料理は、縁起物を詰め込み、新年を祝す食べ物なので、避けた方が無難です。特に、「めでたい」とされる鯛や紅白のかまぼこなどは慎む必要があります。
その他にも、初詣も気をつけるべき点があります。初詣は神式と仏式で慣習が異なり、神式では喪中の期間中は神前に出ることを慎むべきという考えがあるので、神社への初詣は控えなければなりません。
一方で、仏式では喪中であっても寺院を訪れることは全く問題ないので、正月に初詣に行っても大丈夫です。
結婚式など祭典
結婚式は、四十九日よりも前に招待を受けた場合は、欠席することがマナーです。また、出席する旨を伝えたにも関わらず、その後喪中になってしまったら、心の整理がつかなければ欠席しましょう。喪中を理由に欠席することは決して無作法なことではありません。
四十九日後に結婚式に招待されたら、喪中であることを相手に伝えて、相手方の意向を確認して問題なければ出席できます。なお、喪中であっても、結婚式に祝電や花束を贈ることは問題ありません。
桃の節句や端午の節句などの年中行事
喪中に七夕などの節句が重なってしまった場合は、お祝いを避けるべきでしょうか。以下、詳しく見ていきましょう。
節句の「節」は、季節の節目を意味し、その季節の変わりに豊作・子孫繁栄・無病息災などを願う行事が節句です。
節句には1月7日の人日(じんじつ)、3月3日の上巳(じょうし)、5月5日の端午、7月7日の七夕、9月9日の重陽の5つがあり、これらを五節句と呼びます。なお、3月3日の上巳を、日本では桃の節句とも呼びます。
では、喪中期間中に桃の節句や端午の節句などで、何か気を付けるべきことはあるのでしょうか。
まず、桃の節句ですが、喪中であっても祝うことは問題ありません。喪中期間中は、確かにお祝いごとを避けるべきという慣習がありますが、子どものためという前向きな行事なのでお祝いをしてもマナー違反ではありません。
そのため、雛人形を飾ることやちらし寿司を食べることも問題ありません。しかし、喪中で桃の節句を祝うことに迷いがある方は、控えめに行うと良いでしょう。
また、端午の節句に関しても、基本的には桃の節句と同様で、子どもの成長を願うという前向きな気持ちによる行事なので、お祝いしても問題ありません。また、兜は飾っても大丈夫ですが、鯉のぼりに関しては注意が必要です。
鯉のぼりは室外に飾るため、近所の方や親類が、「喪中にも関わらず鯉のぼりを飾っている」と思われてしまうことも考えられます。喪中に鯉のぼりを飾るのは控えておくのが無難と言えます。
ただし、遺族の悲しみが深く、子どもの成長をとてもお祝いする気になれない場合は、延期して家族全員が心からお祝いする気持ちになれた頃に執り行うことをおすすめします。
節分
節分は仏教の教えとは無関係の、福を招き入れたいという願いを込めて行う行事ですので、節分の行事を行うことはもちろん、恵方巻きを食べることも問題ありません。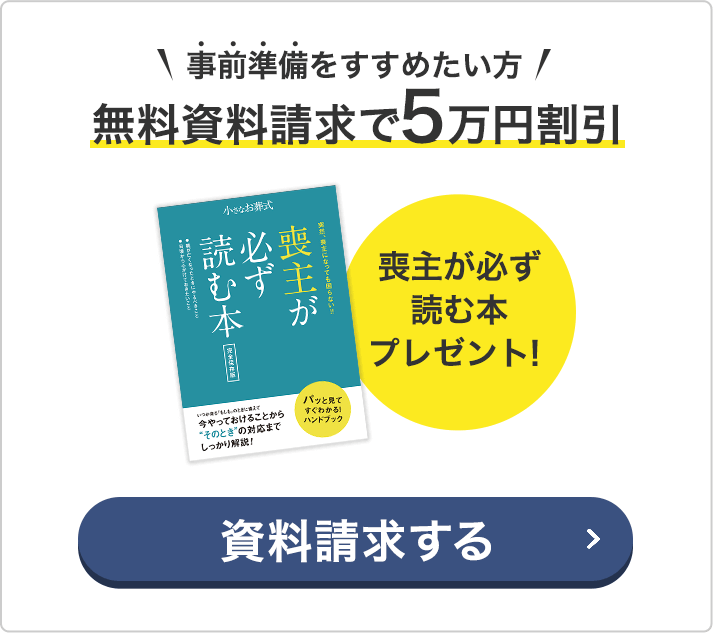
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
この記事では、喪中のクリスマスの過ごし方や、喪中期間中の各イベントのマナーについて解説してきました。仏教や神道の慣習である喪中が、キリスト教のお祝いであるクリスマスにおいて、日本でどのように過ごすべきなのか疑問に思っていた方も多いのではないでしょうか。
また、喪中期間中のさまざまな行事のマナーには、多くの取り決めがあり、驚いた方もいらっしゃることでしょう。
しかし、故人を偲んで、遺族の悲しみを和らげるために喪中があることをご理解いただければ、なぜ喪中期間中の過ごし方にさまざまな決まりがあるのか、お分かりいただきやすいと思います。
とても悲しいことですが、死は必ず訪れます。そんな時に小さなお葬式は、遺されたご遺族の方々を親身になってお支えさせていただきます。ぜひ大切な方のご葬儀の際は小さなお葬式へご相談ください。


人が亡くなった後に行う死後処置と、死化粧などをまとめて「エンゼルケア」と呼びます。ホゥ。
































