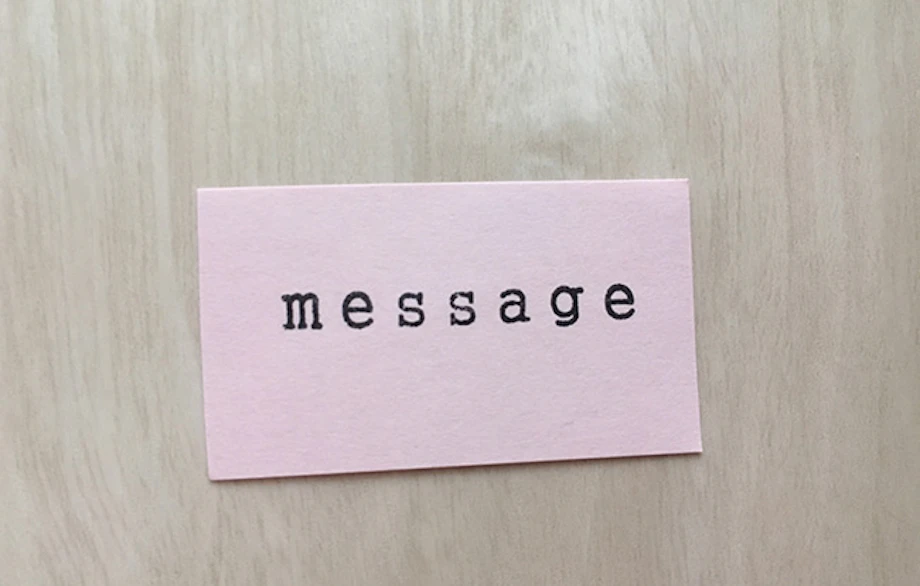訃報を受けたものの葬儀に参列できない場合、お悔やみの気持ちを伝えるための電報(弔電)を手配します。訃報を知ったときに弔電の送り方が分からず、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、弔電を送る方法について分かりやすくご紹介します。弔電の送り方や文例、送る際に気をつけたいマナーが分かる内容です。弔電を当日中に手配するときの注意点、弔電と花を一緒に送る方法についても解説します。
<この記事の要点>
・弔電の申し込みには局番なしの115に電話をかける方法とインターネット申し込みがある
・故人の呼び名は喪主と故人の続柄に合わせるのがマナー
・弔電は通夜や葬儀で読み上げられる前に届くように注意する
こんな人におすすめ
お悔やみの弔電を送りたい人
弔電の文例が知りたい人
お悔やみの電報を送る方法とは?
日常生活の中では、電報を送る機会はなかなかありません。弔電が必要な場面で手配の手順が分からず、戸惑うこともあるでしょう。
事前に弔電の申し込み方法などを知っておけば、いざというときにもスマートな対応ができます。はじめに、弔電の送り方についての基礎知識をご紹介します。
弔電の申し込み方法
弔電を申し込む方法は、主に電話とインターネットの2種類です。電話で申し込む場合は115(局番なし)にダイヤルしましょう。
電話回線の通信会社に対応する、電報サービスにつながります。115番での申し込みは、通話料自体は無料です。電報サービスによって、申し込みの受付時間が異なります。
インターネットで申し込むときには、利用したい電報サービスのWebサイトにアクセスしましょう。多くの場合、年中無休・24時間対応で受け付けられています。
いつでも利用できる利便性の高さは、インターネット申し込みの大きな魅力でしょう。なお、電報サービスによっては、利用に際して会員登録が必要です。
宛先の決め方
弔電の送付先は、葬儀を執り行う式斎場や寺社の住所です。弔電の宛先は喪主(弔電の受取人)が該当します。
弔電の宛先には、喪主の氏名をフルネームで記載しましょう。ミスなく送るには、喪主と故人のフルネームを両方記載します。式斎場の多くは、喪主や故人の氏名で葬儀を管理するからです。
喪主の氏名が分からなければ、案内があった式斎場に問い合わせましょう。確認する時間がない場合、「○○(故人の姓)家 ご遺族様」「故○○(故人の氏名)様 ご遺族様」と記載しても問題ありません。企業や団体が執り行う葬儀(社葬など)の場合、弔電の宛先は葬儀主催者や責任者、部署名を記載します。
弔電を送る方法
弔電のインターネット申し込みは、インターネットに慣れている方、しっかりと選びたい方におすすめします。
サイト内でメッセージ本文や電報台紙のデザインを確認した上で、自分のイメージに近い弔電を届けられるからです。専用フォームの手順に沿って電報台紙やオプションを選んだり、必要事項を入力したりするだけで弔電を手配できます。
電話での申し込みは、弔電の作成に慣れていない方、専門のオペレーターに相談したい方におすすめです。115(局番なし)にダイヤル後、専門のオペレーターに弔電を送りたい旨を伝えましょう。オペレーターとの相談や受け答えから、希望に沿った弔電が完成します。
弔電の費用
弔電の料金体系は、電報サービスによってさまざまです。「メッセージ(電報)料金(文字数に応じて高くなる料金)+商品料金(電報台紙など)」と設定するところもあれば、商品料金にメッセージ料金が含まれている場合もあります。予算に合った弔電の手配では、「何の料金が含まれているのか」を確認することが大切です。
電報台紙のデザインや材質、セット内容(線香・ろうそく・プリザーブドフラワーなど)によって、商品料金に大きな差があります。故人や遺族との関係性に合わせて、適した電報台紙やセット商品を選びましょう。
お悔やみの電報の文例
多くの電報サービスでは、弔電用のさまざまな定型文が用意されています。スピーディーに弔電を手配する際には、文例を利用するのも有効な手段です。
自分で文面を考えた弔電では、お悔やみの気持ちをより伝えられるでしょう。基本的な文例と合わせて、シーン別の文例とポイントをご紹介します。
基本的な弔電の文例
弔電でもっともシンプルな文面は、下記のような1行(20文字~30文字程度)の短文です。故人や遺族との関係性によっては、簡潔な弔電のほうが好まれます。
〈1行の文例〉
・○○様の悲報に接し、安らかなるご永眠につかれますようお祈り申し上げます。
・○○様のご逝去を悼み、衷心よりご冥福をお祈りいたします。
「故人との親交はあまりなかったものの、1行だけでは故人や遺族に失礼かもしれない」と感じる場合には、2行~3行(40文字~80文字程度)にまとめましょう。
弔電の基本的な構成として「お悔やみの言葉+つなぎの文(心情や故人との関係性、遺族への言葉など)+結びのあいさつ」を意識すると、2行~3行にまとまります。
〈2行~3行の文例〉
・○○様の悲報に接し、故人の在りし日を偲んでおります。
ご生前のご厚情に感謝いたしますとともに、
遠方より安らかなご永眠をお祈りいたします。
・○○様のご逝去の報に対し、謹んで哀悼の意を表します。
ご遺族様のお悲しみは計り知れないものとお察しいたします。
今はただ、○○様のご冥福をお祈り申し上げるばかりです。
親しい友人が亡くなった際の文例
親しい友人が亡くなった際に送る弔電では、故人との思い出や人柄に触れる内容を挟みましょう。故人の友人として、遺族をいたわる言葉も添えておきます。
・○○様の訃報に接し、悲しい気持ちでいっぱいです。ご生前の笑顔や楽しい会話が、今でも鮮明に思い出されます。ご遺族様のご無念のお気持ちはいかばかりかと存じますが、どうぞご自愛くださいませ。謹んでご冥福をお祈りいたします。
・幼なじみの友との突然の別れに、痛惜の念に襲われています。先日も楽しい時間を過ごしただけに、まだ信じられません。ご遺族様のご心痛をお察しいたしますとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。数多くの思い出をありがとう。衷心よりご冥福をお祈りいたします。
主人や奥様が亡くなられた場合の文例
故人が喪主(弔電の受取人)の夫の場合、弔電内での故人に対する敬称は「ご主人様」です。故人が喪主(弔電の受取人)の妻の場合、敬称として「奥様」「ご令室様」を使います。
・ご主人様の訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。ご家族様の悲しみはいかばかりかとお察ししますが、どうぞお気持ちを強くお持ちくださいませ。ご主人様のご冥福を心よりお祈りいたします。
・奥様の突然の悲報に接し、衷心よりお悔やみ申し上げます。これからもご家族で力を合わせ、この度のご不幸を乗り越えられるようお祈りいたします。生前のお姿を偲び、ご冥福をお祈り申し上げます。
実父・実母が亡くなられた場合の文例
故人が喪主(弔電の受取人)の実父の場合、故人に対する敬称は「ご尊父(そんぷ)様」「お父様」です。故人が喪主(弔電の受取人)の実母の場合には、敬称として「ご母堂(ぼどう)様」「お母様」を使います。
・ご尊父様のご逝去を悼み、衷心よりお悔やみ申し上げます。ご生前のご厚情に深く感謝を申し上げますとともに、お父様のご冥福を謹んでお祈り申し上げます。
・ご母堂様のご訃報に接し、謹んで哀悼の意を捧げます。ご生前は親子そろってお世話になりました。今はただ、ご母堂様が安らかにお眠りになりますようお祈り申し上げます。
会社関係の方が亡くなられた場合の文例
会社関係の方が亡くなられた場合、弔電の文面は簡潔にまとめましょう。会社関係の方への弔電では、「○○株式会社 △△部 □□」「○○株式会社 社員一同」と連名で送る傾向にあるからです。プライベートな内容は控えなければなりません。
また、今後の仕事上の関係に影響が出ないよう、「故人の職場関係者に対する言葉」や「葬儀に参列できないことへのお詫び」も添えましょう。
・社長様の訃報に接し、当社社員一同、惜別の念を禁じ得ません。遠方のため直接のお悔やみかなわぬ非礼をおわびいたしますとともに、衷心より社長様のご冥福をお祈りいたします。
・会長様のご逝去を悼み、衷心よりお悔やみ申し上げます。ご遺族様ならびに社員ご一同様におかれましては、ご傷心のこととお察しいたします。会長様のご功労に敬意を表しますとともに、会長様のご冥福をお祈りいたします。
お悔やみの電報を送る際のマナー
故人や遺族に失礼のないよう、弔電におけるさまざまなマナーを守らなければなりません。弔電の文面を考える際には、故人の呼び名や言葉の使い方に気をつけましょう。お通夜や葬儀・告別式で読み上げる性質上、弔電を届けるタイミングに注意する必要があります。
故人の呼び名に注意する
故人に対して文面内で使用する敬称は、喪主(弔電の受取人)と故人の続柄に合わせるのがマナーです。弔電を送る際には、喪主と故人の続柄を確認しましょう。続柄によって、以下のように敬称が異なります。
| 故人と喪主との続柄 | 故人に対して使用する敬称 |
| 喪主の実父 | ご尊父(そんぷ)様、お父様、お父上(様) |
| 喪主の実母 | ご母堂(ぼどう)様、お母様、お母上(様) |
| 喪主の夫の父 | お舅(しゅうと)様、お父様、お父上(様) |
| 喪主の夫の母 | お姑(しゅうとめ)様、お母様、お母上(様) |
| 喪主の妻の父 | ご岳父(がくふ)様、お父様、お父上(様) |
| 喪主の妻の母 | ご岳母(がくぼ)様、ご丈母(じょうぼ)様、ご外母(がいぼ)様 |
| 喪主の両親 | ご両親様、ご父母様 |
| 喪主の夫 | ご主人様、ご夫君様 |
| 喪主の妻 | ご令室様、ご令閨(れいけい)様、奥様 |
| 喪主の祖父 | お祖父(じい)様、ご祖父(そふ)様 |
| 喪主の祖母 | お祖母(ばあ)様、ご祖母(そぼ)様 |
| 喪主の息子 | ご子息(様)、ご令息(様) |
| 喪主の娘 | ご息女(様)、ご令嬢(様)、お嬢様 |
| 喪主の兄 | 兄上様、ご令兄(れいけい)様、お兄様 |
| 喪主の弟 | ご令弟(れいてい)様、弟様 |
| 喪主の姉/妹 | 浮かばれない |
| 仏教 | ご令妹(れいまい)様、妹様 |
言葉の使い方に注意する
弔電の文面では、直接的な表現(死や生死など)や忌み言葉(不幸の連続を連想させる言葉)を避けるのがマナーです。
故人が信仰していた宗教に合わせて、宗教観にそぐわない用語も避けなければなりません。故人が信仰していた宗教に関しても、事前に確認しておきましょう。弔電では使用できない、忌み言葉の代表例は下記の通りです。
| 重ね言葉 | 重ね重ね、たびたび、時々、久々、ますます、皆々様、重々、いよいよ |
| 不幸の連続を想起させる言葉 | また、再度、続いて、重ねて、繰り返し、再三再四、 |
| 音の響きが不吉な数字 | 四(音が「死」と同じため)、九(「苦」を想起させるため) |
| 不幸な言葉 | 苦しむ、大変、落ちる、消える、とんだこと |
| 仏教での忌み言葉 | 浮かばれぬ、浮かばれない、迷う、天国 |
| 神道・キリスト教の忌み言葉 | 成仏、ご冥福、供養、往生、弔う、仏、合掌 |
送るタイミングと内容に注意する
弔電は訃報を受けたらなるべく早く手配し、お通夜や葬儀・告別式で読み上げられる前に届くようにしましょう。
弔電の受取時間は式斎場ごとに差があるため、詳細について確認した上で手配しましょう。
弔電の内容では、故人のプライベートに関わる内容は避けます。故人と生前の親交が深いほど、さまざまな思い出を弔電に書きたくなるでしょう。
ただし、遺族や家族が故人の全てを知っているとは限りません。弔電の内容が思わぬトラブルを招かないよう、差し障りのない内容を記載しましょう。
お悔やみの電報は当日でも大丈夫?
やむを得ない理由から葬儀に参列できないときには、なるべく早く弔電を手配したほうが良いですが、場合によっては、葬儀の当日に訃報を知ることもあるでしょう。電報サービスや有料オプションによっては、当日中の配達も可能です。弔電を当日中に届ける方法に加えて、間に合わなかった場合の対処法について解説します。
当日でも可能
利用する電報サービスによっては、当日の手配でも当日中の配達が可能です。ただし、電報サービスごとに当日配達の期限が異なります。
当日の○時~○時までの申し込みで当日配達できたり、申し込むタイミングによっては配達の時間帯が選べたりとさまざまです。
電報サービスの中には、有料オプションとしてお急ぎ便などを利用できる場合もあります。有料オプションの内容も、「申し込みから最短○時間以内に配達」「連携斎場なら最短○時間でお届け」とサービスによって違いがあるため注意しましょう。
NTTで送る方法
NTTの電報サービス「D-MAIL」では、当日0時~19時までの申し込みで当日配達ができます。申し込み方法は、電話とインターネットの2種類です。
電話では8時~19時までの受付(年中無休)で、オペレーターが対応します。インターネット申し込みの受付時間は、24時間(年中無休)です。日本全国どこでも、同一料金で当日配達できます。
弔電をはじめとした電報サービスを展開する業者は、NTTだけではありません。大手の通信会社も、電報サービスを展開します。
スマートフォンや固定電話から115(局番なし)にダイヤルすると、契約先の電報サービスに自動でつながるでしょう。通信会社以外にも日本郵便など多くの事業者が、電報サービスを手掛けています。
郵便局のレタックスでも可能
「レタックス」とは、日本郵便が手掛ける弔電メッセージサービスです。郵便窓口などから申し込むレタックス以外に、インターネットでの24時間申し込みに対応するWebレタックスがあります。いずれも、15時30分までの差し出しで当日配達可能です(一部地域は13時30分まで)。
「レタックス」と「Webレタックス」は、選ぶ台紙や封筒によって商品料金が異なるものの、文字数による追加料金は発生しません。なお、「レタックス」よりも「Webレタックス」のほうがお得に利用できます。
お悔やみの言葉が間に合わない場合の対応
弔電の手配が間に合わない場合、無理に送る必要はありません。葬儀が終わった後に弔電を送るのは、故人や遺族に対して失礼だからです。
手配が間に合わず、弔電を送れなかったときには、弔電の代わりに後日改めて弔問します。弔問できない場合には、香典に手紙を添えて送りましょう。
香典を送る際には、現金書留を利用します。現金書留の送付でも、現金を香典袋に入れた状態で封入しましょう。
香典に添える手紙には弔意に加えて、葬儀に参列できなかったこと、弔電を送れなかったことのおわびを記します。葬儀が終わってから1週間~1か月以内には、手紙と香典を送るようにしましょう。
お悔やみの電報と花を一緒に送る方法
花をお悔やみの電報と一緒に送ると、より弔意が伝わります。ただし、花を手配する前には、遺族や家族からの了承を得ておきましょう。
弔電と花を一緒に送る方法は、主に「弔電と花をそれぞれ違うサービスで手配する方法」と「同じサービスで弔電と花を手配する方法」です。弔電と花を一緒に送る方法、花を送るタイミングをご紹介します。
弔電は通信会社を利用して送る
弔電と花をそれぞれ違うサービスで手配する場合、弔電は各種通信会社を利用して送りましょう。NTTの電報サービス「D-MAIL」以外にも、KDDIグループの「でんぽっぽ」やSoftBankグループの「ほっと電報」などがあります。佐川急便系列の「VERY CARD」や日本郵便の「レタックス」も、弔電を送れるサービスです。
電報サービスの多くは、当日配達やお急ぎ便に対応します。ただし、地域や商品によって当日配達ができないこともあるため、事前確認は欠かせません。
花は葬儀社や花屋を利用して送る
弔電を送った後、葬儀社や生花店などで花を手配します。花を手配する前に、葬儀を執り行う葬儀社や式斎場に供花について問い合わせましょう。葬儀社や式斎場の中には、供花の持ち込みを制限するところもあるからです。
供花を持ち込めない場合には、葬儀を管理する葬儀社に花の手配を依頼します。式斎場や葬儀社が供花の持ち込みに対応する場合、生花店に手配を依頼しましょう。
供花のマナーは故人が信仰していた宗教・宗派だけでなく、地域によって大きな差があります。生花店に依頼する場合には、マナーに詳しいお店に依頼したほうが無難です。
弔電と花は一緒に送ることもできる
手配する手間や時間を省くなら、弔電と花を一緒に送れるサービスを利用しましょう。電報サービスが展開する花付きの弔電、生花店が手掛ける弔電サービスがあります。弔電と花を同じサービス・お店で手配すると、同じタイミングでの配達が可能です。
電報サービスが展開する葬儀用の花は、アレンジメントや花束などさまざまな種類があります。メッセージ料金が商品料金に含まれているかどうかは、利用する電報サービスによって異なるため注意しましょう。
生花の場合には品質保持期間が短い関係から、利用するサービス地域や季節によって対応していません。
花は葬儀の2時間前には届くようにする
お通夜に合わせて花を手配する場合、通夜当日の午前中には式斎場に届くよう手配しましょう。葬儀に花を送るなら、前日までに届くように手配します。
お通夜と葬儀のいずれの場合にも、遅くとも式が始まる2時間~3時間前には届くように手配しなければなりません。
届いた花は、式を管理する葬儀社が設営します。送る花が設営に影響する性質上、花が届くタイミングによっては迷惑になりかねません。届けるタイミングに関しては、事前に葬儀社に確認しておくと安心です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
訃報を受けたものの、やむを得ない事情から葬儀に参列できない場合、弔電はお悔やみの気持ちを伝える際に役立ちます。故人や遺族に失礼がないよう、弔電を送る際にはさまざまなマナーを守りましょう。
弔電のマナーや送り方など葬儀に関するご相談なら、小さなお葬式にお任せください。24時間365日対応の専門スタッフが、さまざまな疑問にお答えします。通話料無料のお客さまサポート専用ダイヤルから、お気軽にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



香典の郵送は、現金を不祝儀袋に入れ、現金書留用の封筒でなるべく早く送ります。ホゥ。