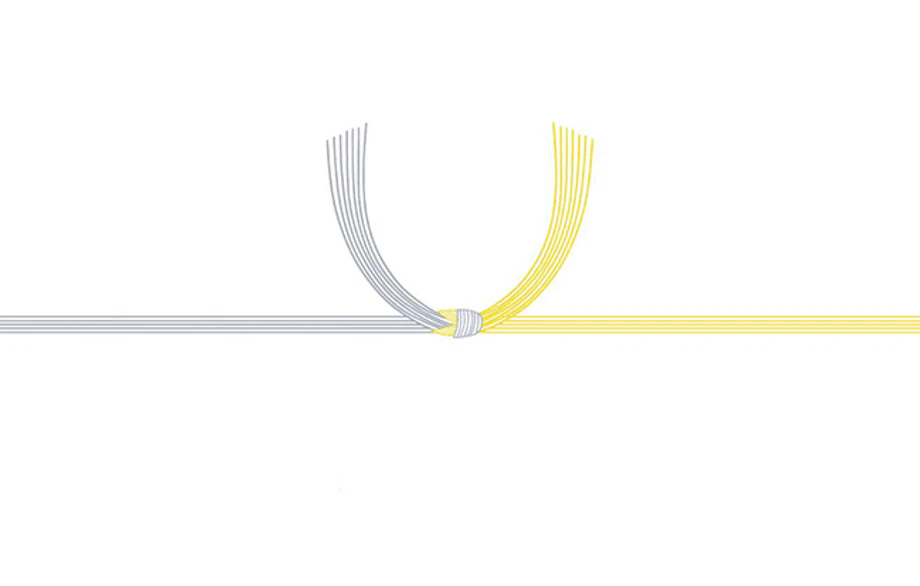香典返しは、いただいた香典のお返しとして贈るお礼です。喪主は香典をいただいた方にはお礼を返すのがマナーですが、香典返しはいつ贈るのが良いのか、金額はどの程度が適切なのか分からないという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、香典返しの正しい渡し方について解説します。即返しと後返しの違いが分かり、正しい対応の仕方が理解できるようになる内容です。
<この記事の要点>
・香典返しにはお通夜の場でお返しを渡す「即返し」と四十九日法要後に渡す「後返し」がある
・香典返しの金額は「半返し」が基本で、香典の30%~50%程度が目安
・相手が親族でも香典返しは用意する必要がある
こんな人におすすめ
香典返しの正しい渡し方を知りたい方
即返しと後返しの違いを知りたい方
家族葬で香典返しの方法を知りたい方
通夜の香典返しの正しい渡し方を解説!
通夜の香典返しは、喪主になったときに頭を悩ませる要因の一つでしょう。香典返しを送る際は、贈るタイミングや金額、相手に応じた対応など、さまざまなことに目を向ける必要があります。まずは、香典返しの基本的な渡し方についての知識を確認しましょう。
通夜の香典とは
通夜は、本来は故人と関係が深い方が集まって夜通し故人の霊魂を見守る儀式でした。近年では日が変わる前に終了する半通夜に形を変え、葬儀に出られない方の受け皿としての役割も持つようになっています。
弔問客が通夜に参列する際は、香典を持参するのがマナーです。香典は元々相互扶助の精神に則って食べ物やお供え物を贈る習慣でしたが、現在は現金を包む習慣になっています。
法要が滞りなく終了したことの報告を兼ねてお返しをする習慣が生まれ、これが香典返しとなりました。近年では香典返しも多様化しており、地域や家庭によって香典返し自体の有無や贈るタイミングなどに違いが見られます。
香典返しの渡し方
香典返しは元来忌明けの報告を兼ねていたため、四十九日法要後に贈る「後返し」が一般的でしたが、近年ではお通夜の場でお返しを渡す「即返し」も多く見られるようになりました。
後返しの場合は手渡しや郵送で、即返しの場合は香典を受け取った際に受付でお返しを渡します。
お通夜当日に参列者に贈るお礼の品というと「返礼品」を連想する方もいるかもしれませんが、香典返しと返礼品は別のものです。返礼品を用意している場合でも、香典返しは別途用意する必要があります。
返礼品は香典の有無に関係なく参列者全員に渡しますが、香典返しは香典を持参した方のみに渡すものです。ふさわしい金額や品物も異なるので、混同しないようにしましょう。
香典返しの金額
香典返しにかける金額は、「半返し」が基本とされています。半返しとはいただいた香典の30%~50%程度を意味しており、いただいた額に応じてお返しの品を変える渡し方です。
しかし、半返しをするにはいただいた額の把握と額に応じたお返しの品を用意は欠かせません。即返しする場合は、いただいた場で額をその場で確認するのは失礼にあたることに加えて、あらかじめ額に応じた品を用意するのは現実的とは言えないでしょう。そのため、いただいた額を問わず2,000円~3,000円程度の品を一律で渡すのが一般的です。
用意していた品に見合わない高額の香典をいただいた場合は、後日改めてお返しを贈って半返しになるように調整しましょう。
後返しの場合は額を確認してお返しの品を用意できます。基本に則っていただいた額の半返しの品を贈りましょう。
親族から香典を貰った場合の対応
親族の葬儀でも香典を持参するのと同様に、相手が親族でも香典返しは用意する必要があります。しかし、香典は関係が近いほど香典の額が高くなるのが一般的なため、お返しの対応に困ることもあるでしょう。
半返しの基本に従うと、5万円の香典をいただいた相手には1万5,000円~2万5,000円程度のお返しを用意しなければなりません。しかし、お礼の額としては高額過ぎると感じる方もいるでしょう。
このような場合は、半返しにこだわらずに25%程度のお返しにしてもマナー違反とは思われないでしょう。無理に高額のお返しをしようとすると先方のご好意を無下にすることにもなりかねません。
会社から香典を貰った場合の対応
会社の香典にお返しをする場合は、香典の名義によって対応が異なります。会社名義の場合はほとんどが福利厚生の一部である慶弔規定で出しているので、香典返しは不要です。
部署や数人のグループから「一同」の名義でいただいた場合は、それぞれのポケットマネーから持ち寄りで出してくれていることが多いため、お返しが必要です。
その際は、お返しの品は複数人で分けられるものを選びましょう。ことさらに高額をいただいたのでなければ、半返しにこだわらずに小分けにできる菓子折りなどで問題ありません。
会社関係の方の個人名義の場合は、個人の場合と同様に、半返しを目安にしてお返しを用意しましょう。マナーに則って対応することが大切です。
通夜と告別式両方で香典を貰った場合の対応
通夜と告別式の両方に参列する場合でも、香典を渡すのは一度にするのがマナーです。何度も香典を出すことは「不幸の重なり」を暗喩するため、避けるべきとされています。
しかし、誰もがマナーに精通しているわけではないため、同じ方から二度香典をいただくこともあるでしょう。
このようなケースでは、いただいた合計額を基準に半返しで計算するのが良いとされています。二度の香典へのお礼と相手に伝わるように「通夜と告別式にどちらもお参列いただきありがとうございました」といったお礼状を添えると良いでしょう。
香典返しを辞退する方法
会社の規則で香典返しを受け取れないこともあるでしょう。弔問客として参列して香典返しを辞退する場合は、喪主にその旨を伝える必要があります。受付で渡す際に「香典のお返しのご配慮は不要でございます」と一言添えましょう。口頭だけでは喪主に伝わらない可能性があるので、不祝儀袋の中に一筆書き添えることも大切です。
辞退する場合でも会葬御礼は受け取るのがマナーです。
香典返しの即返しとは
香典返しは本来四十九日法要後に行いますが、近年ではお通夜当日にお返しをする即返しも多く見られるようになりました。
即返しにはどのようなメリットがあって広まっていったのか、デメリットはないのかなど、気になることは多いでしょう。ここでは、即返しについて解説します。
即返しのメリット
即返しには、香典返しにかかる手間や時間を省けるメリットがあります。従来の方法でお返しをするには、いただいた方の名前と金額を全て把握して、住所なども控えて個別に対応しなければなりません。
即返しなら、参列者の大まかな人数を把握して同じ品を用意しておけば、個別に対応する作業を大きく軽減できます。渡し忘れる心配もなく、多くいただいた方に後日追加でお返しを贈るだけで済むのがメリットです。
即返しのデメリット
あらかじめ品物を用意しておく必要があるため、香典の額に応じて贈り分けができないのがデメリットです。高額の香典をいただいた相手には後日対応する必要があるため、完全に個別対応の手間を省けるわけではありません。
同じ品物を贈る都合上、相手の好みに合わせた品を用意することもできません。誰に贈っても受け入れられやすい無難な品を用意する必要があるでしょう。即返しの習慣がない地域では香典返しと認識されない可能性もあります。
香典返しの後返しとは
後返しは従来の一般的な渡し方のため、伝統的を大事にしている方にとっては馴染み深い方法なのではないでしょうか。後返しは「満中陰志」と呼ばれることもあり、香典のお礼と四十九日法要が滞りなく終了したことの告知を兼ねています。
後返しのメリット
後返しは香典の額を把握してから個別に対応できるため、相手に合わせて品物を用意できるのがメリットです。感謝の気持ちを伝えるために、一律の品を贈るよりも好みに合わせて選びたいという方に適していると言えるでしょう。
昔から行われてきた伝統的な渡し方なので、手間を惜しまず礼儀を重んじる姿勢が伝わりやすいことも長所です。
後返しのデメリット
即返しとは逆に、手間や時間がかかるのがデメリットです。法要と並行して準備を行うことが多いため、四十九日法要前後は忙しくなるでしょう。余裕がないと渡し損ねるリスクもあります。
遠方に住んでいる方には郵送することになりますが、発送料は自己負担です。加えて、後から贈る場合は葬式費用にならないため、相続税控除の対象に含まれません。経済的な負担が大きいこともデメリットとして挙げられます。
家族葬では香典返しをどうする?
近年ではさまざまな葬儀形式が見られるようになりました。親しい方のみで執り行う家族葬も増えています。
家族葬では通常の葬儀とは異なるマナーがあるので、香典返しの作法で悩んでいる方もいるのではないでしょうか。ここでは、家族葬の香典返しについて解説します。
家族葬では香典返しを辞退する
家族葬では、香典返しを辞退するのが一般的です。家族葬は遺族が負担を軽減するために選ぶことが多く、香典を辞退するケースが多く見られます。
香典を受け付けている場合でも、香典返しのやり取りを強いるのは避けた方が良いという考え方があるため、辞退するのが手堅いと言えるでしょう。
家族葬に参列する際は、家族葬を選んだ遺族の意図を察して、負担をかけないように配慮することが大切です。香典を辞退している場合は、無理に渡すことがないように注意しましょう。
会葬御礼を用意する
家族葬で喪主を務める場合は、香典を辞退していても会葬御礼は用意する必要があります。会葬御礼は葬儀へ足を運んでくれたことへのお礼なので、香典の有無とは無関係です。通常の葬儀と同様に参列者全員分を準備しましょう。
家族葬はあらかじめ参列者の数が決まっているのがメリットですが、当日に急に来られる方がいる可能性もあります。このことも想定して多めに準備しておくといざというときに慌てずに済むでしょう。
家族葬で香典返しを受け取ったら後返しをする
家族葬で香典を受け付けていない場合でも、ご厚意で香典を渡してくれる方もいるでしょう。そのようなときは、無理に断らずにありがたくいただくのがマナーです。
受け付けていないことを知らない場合もあるので一度はその旨を伝えた方が良いですが、何度も断るのは失礼になります。
香典を受け取ったら、香典返しは辞退すると伝えられていない限り香典返しは必要です。即返しの用意はないでしょうから、後日贈りましょう。
会葬御礼の選び方
会葬御礼の品はあまり高額なものを選ぶと参列者に香典返しと誤解させることや気を遣わせてしまう恐れがあるので、気持ち程度の品を選びます。500円~1,000円程度の品が一般的でしょう。
葬儀の返礼品は、後に残らない「消えもの」が基本です。お茶や菓子といった食べ物や、タオル、洗剤などの消耗品が良く選ばれます。相手が好きなものを選べるカタログギフトも人気です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
通夜の香典返しの渡し方は、即返しと後返しの2種類があります。どちらも一長一短なので、何を優先するかを考慮して渡し方を選ぶことが大切です。
贈る相手によって適切な対応は変わるので、マナーを完全に把握するのが難しいと感じる方もいるでしょう。そのようなときは、あらかじめ葬儀社に香典返しの渡し方を相談して確認しておくことをおすすめします。
小さなお葬式では遺族の想いに応えた葬儀のご提案が可能です。葬儀の前から葬儀が終わるまでしっかりサポートいたします。葬儀をお考えならぜひご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



葬儀費用が捻出できないときは「葬祭扶助」を活用することで補助金が受け取れる場合があります。ホゥ。