浄土真宗とは阿弥陀如来を信仰する仏教宗派のひとつです。臨終後はすぐに極楽浄土へ迎えられると考えられており、法事は故人の冥福を祈る場ではなく、故人をしのんで仏法に接するために営まれます。
他の宗派と異なる点がある浄土真宗では、法事を何回忌まで執り行うのか疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、浄土真宗の法事について詳しく解説します。何回忌まで営むのかという疑問をはじめ、参列者の作法や遺族の準備が分かれば、安心して法事が執り行えるでしょう。
<この記事の要点>
・浄土真宗の場合、三十三回忌を弔い上げとする場合がほとんどである
・施主や遺族はまず法事の日取りを決め、招待する人に案内はがきを送る
・法事の準備としてお供え物や、参列者へ渡す返礼品を用意しておく
こんな人におすすめ
浄土真宗の弔い上げについて知りたい方
年忌法要の種類を知りたい方
弔い上げの時期を早めたい方
浄土真宗の年忌法要について
年忌法要は故人の祥月命日に執り行う法要です。祥月命日とは、命日と同じ月・同じ日を指します。例えば、亡くなった日が1月1日であれば毎年1月1日が祥月命日です。ここでは、浄土真宗の年忌法要について解説します。
年忌法要は命日に営むのが正式
法要は命日当日に営むのが正式な作法です。ただし、どうしてもできない事情がある場合もあるでしょう。
命日が平日だと仕事をしている方や学校に通っている方は休みを取らなくてはなりません。特に、参列する親族が遠方に住んでいる場合、全員が集まるのは難しいでしょう。
したがって、集まりやすい週末に営むのが一般的です。日取りを調整する際は、命日よりも前に移動しましょう。
年忌法要の種類
主な年忌法要や時期を表にまとめました。浄土真宗も他の宗派と変わらないため、参考にしてみてください。
| 年忌法要 | 時期 | 内容 |
| 一周忌 | 亡くなってから1年後 | 遺族、親族、友人、知人が参列。 僧侶による読経の後、一同で焼香・お斎をする。 |
| 三回忌 | 亡くなってから2年後 | 遺族、親族、友人、知人が参列。 僧侶による読経の後、一同で焼香・お斎をする。 |
| 七回忌 | 亡くなってから6年後 7回目の命日 |
遺族、親族が参列。 僧侶による読経の後、一同で焼香・お斎をする。 一般的に、七回忌から法要の規模を縮小。 |
| 十三回忌 | 亡くなってから12年後 13回目の命日 |
遺族だけで供養するのが一般的。 |
| 十七回忌 | 亡くなってから16年後 17回目の命日 |
遺族だけで供養するのが一般的。 省略する場合もある。 |
| 二十三回忌 | 亡くなってから22年後 23回目の命日 |
遺族だけで供養するのが一般的。 省略する場合もある。 |
| 二十七回忌 | 亡くなってから26年後 27回目の命日 |
遺族だけで供養するのが一般的。 省略する場合もある。 |
| 三十三回忌 | 亡くなってから32年後 33回目の命日 |
遺族だけで供養するのが一般的。 仏教では、死者は全て33年目には無罪となり極楽浄土に行くといわれているため、 弔い上げとするケースが多い。 |
法要によって規模が異なる
法要の規模は時間の経過とともに変化し、比較的大きな規模で執り行うのは、初七日、四十九日、一周忌、三回忌です。
現在では一周忌以降は家族と近しい親族のみの場合も多く、規模を縮小する傾向があります。特に七回忌以降は家族以外が参列するケースはまれです。
浄土真宗の法事は何回忌まで?
年忌法要にはさまざまな種類がありますが、規模は徐々に縮小するのが一般的です。浄土真宗の法事はいつまで続ければよいのか、悩んでいる方もいるでしょう。
ここでは、浄土真宗の法事は何回忌まで営むのかという疑問について解説します。なお、法事とは法要後の会食を含む呼び方です。
浄土真宗における弔い上げ
弔い上げとは故人に対する個別の法要を終了することで、弔い上げ以降は他のご先祖様と一緒に供養します。弔い上げの時期ははっきりと決まっていません。三十三回忌や五十回忌を弔い上げとするのが一般的で、浄土真宗でも三十三回忌を弔い上げとする場合がほとんどです。
ただし、必ず三十三回忌を弔い上げとしなければならないわけではありません。弔い上げの時期は地域の慣習やお寺の意向に大きく左右され、弔い上げ自体が浄土真宗にはないとする考え方もあります。弔い上げのタイミングは、お寺と相談して決めるのがベターです。
弔い上げを早くしたいときは?
核家族化が進んだ昨今、家やお墓を引き継ぐ方がいないというケースも多いでしょう。また、高齢化という問題もあります。
多くの方が弔い上げとする三十三回忌は、故人が亡くなってから32年後です。故人を知る方がほとんどいない場合もあり、三十三回忌や五十回忌より前に弔い上げを済ませたいという方が増えています。
そのような事情がある方は、菩提寺に連絡して前倒しで弔い上げをするとよいでしょう。具体的には、十三回忌や二十三回忌で弔い上げとするケースがあります。
【浄土真宗の法事】施主や遺族の準備
浄土真宗の法事も他の宗派と同じように準備をしなければなりません。同じ浄土真宗でも地域やお寺によって異なる場合があるため、事前に周りの方やお寺に相談すると安心です。ここでは、施主や遺族がする浄土真宗の法事の準備について解説します。
スケジュールの調整
まずは法事の日取りを決めます。参列する遺族や親戚の予定を把握してから、お寺へ連絡しましょう。遺族の予定と当日お勤めをしてもらう僧侶の予定をすり合わせて、スケジュールを調整します。
お寺とお付き合いのある方
菩提寺(ぼだいじ)とは、先祖代々のお墓のあるお寺のことです。菩提寺がある場合には、菩提寺に連絡をして、読経の依頼を行いましょう。
お寺とお付き合いが無い方
菩提寺が無い場合には、知人縁故からお寺を紹介してもらう方法や、葬儀の際にお世話になったお寺に相談する方法があります。
その他最近では、インターネット上でお坊さん手配サービスを利用される方も増えています。
自宅はもちろん、手配したお坊さんのお寺での法要も行えるので、菩提寺がない方には便利です。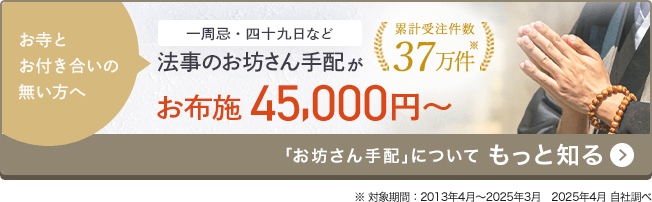
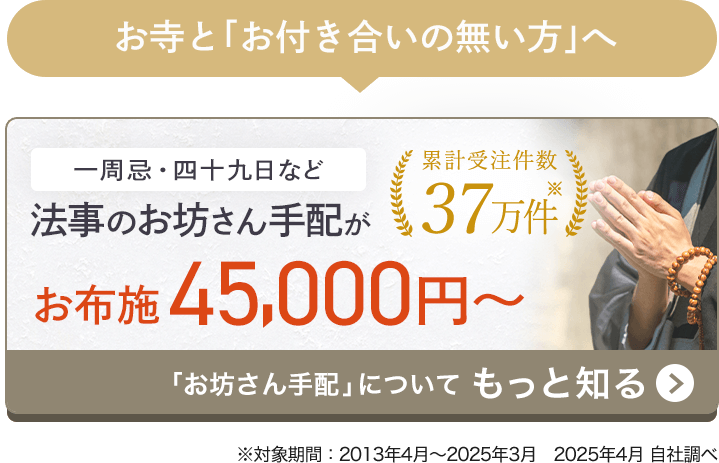
お寺の都合によっては希望日に添えない場合もあるため、1ヵ月~2週間前を目安に寺院手配の予約をすることをお勧めします。
法事をお寺で執り行う場合、必要なものは全てお寺で用意してもらえますが、自宅の場合は御本尊や掛け軸、ろうそくを用意して仏壇の飾り付けをしなければなりません。初めての法事で必要なものが分からないときは、あらかじめお寺に確認するとよいでしょう。
案内はがきの送付
招待する方に法事の日程や会場を明記した案内はがきを送ります。招待するのが身内だけでお寺の場所を知っている場合には、電話やメールによる連絡でも構いません。
また、浄土真宗では「冥福」や「供養」といった言葉を使わないようにしましょう。一般的な言葉ですが、浄土真宗の教えには背いてしまいます。
お斎の会場を予約
法要後の会食「お斎」の会場が自宅ではなくお店の場合、事前に予約しておくと安心です。参加する人数が多いと想定されるときは、会場までの移動手段がない方のために送迎してくれるお店を選ぶとよいでしょう。
料理は和食が一般的ですが、お祝い事を連想させる伊勢エビや尾頭付きの鯛は避けるのが無難です。お酒を振る舞っても構いません。
お供え物を用意する
お供え物として餅や落雁を用意します。お供えする台にも宗派ごとの決まりがあるものの、左右に同数ずつ供えるのは他の宗派も同じです。配置に関してはあまり気にしなくてもよいでしょう。自宅での法事では、線香や花、経本も必要です。
返礼品
参列者が来る場合、香典のお礼としてお渡しする返礼品の準備が欠かせません。お菓子の詰め合わせを参列者の分だけ用意しても構いませんし、カタログギフトを後で手配しても問題ないでしょう。故人が生前好んでいたものを渡すのもおすすめです。
浄土真宗の葬儀や法事における参列者の作法
浄土真宗には「臨終即往生」という考え方があり、それぞれの法要で追善供養をする習慣はありません。浄土真宗でも年忌法要を執り行いますが、作法が異なる点があるため注意しましょう。ここでは、浄土真宗における参列者の作法について解説します。
浄土真宗の通夜と葬儀
浄土真宗の通夜では、「仏説阿弥陀経」または「正信偈」を僧侶が読経します。参列した方は僧侶に合わせて合掌や礼拝をするとよいでしょう。また、他の宗派では線香を一晩中絶やさないという慣習がありますが、浄土真宗ではありません。
浄土真宗では、故人は亡くなってすぐに成仏するという考えです。したがって、葬儀では故人の冥福を祈る「引導」や「授戒」の儀式がありません。同様の考えから、納棺の際に故人に死装束を着せて旅支度をすることもなく、葬儀の後は出棺、火葬、収骨と滞りなく進めます。葬儀後に清めの塩をまくこともありません。
浄土真宗の香典
浄土真宗も他の宗派と同じく、お渡しする香典の金額は決まっていません。故人との関係性によって金額は異なり、近しい方のほうがたくさんお渡しする傾向があります。
浄土真宗には霊魂という概念がありません。他の宗派の場合、通夜や葬儀の香典の表書きは「御霊前」と記載するのが一般的ですが、浄土真宗では「御仏前」と書きます。相手の宗派が分からなければ、「御香典」と書くのが無難です。
浄土真宗の数珠の持ち方
念仏を唱える際に数取りの必要がない浄土真宗の数珠は、蓮如結びの房が特徴です。また、「浄土真宗本願寺派」と「真宗大谷派」の2つの宗派があり、それぞれ数珠の持ち方が異なります。
浄土真宗本願寺派では、数珠は二重にして合掌した手に掛け、房は下に垂らすのが作法です。一方、真宗大谷派では二重にした数珠を両手に掛け、房は上から左側に垂らします。故人がどちらの宗派か分からないときは、事前に施主や遺族に確認するとよいでしょう。
浄土真宗の焼香や線香
浄土真宗では焼香をつまんだ後に額に押しいただかず、そのまま香炉にくべるのが他の宗派と異なる点です。
回数は浄土真宗本願寺派では1回、真宗大谷派では2回と定められています。「焼香は3回」というイメージを持っている方もいるかもしれませんが、実際は宗派によって異なるため注意しましょう。
また、線香は立てて供えるのではなく「寝線香」が作法です。1本の線香を2つから3つに折って、横に寝かせて供えます。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
浄土真宗の法事は何回忌までというはっきりとした決まりはありません。三十三回忌を弔い上げとするケースが一般的ですが、遺族の事情を考えてさらに早くしたいという方は、お寺と相談しながら決めるとよいでしょう。
また、浄土真宗には他の宗派とは異なる点があるため、法事に参列する方はマナーや作法を事前に確認すると安心です。
浄土真宗だけでなく他の宗派の葬儀や法事に関する疑問や困ったことがある方は、「小さなお葬式」にご相談ください。24時間365日、専門スタッフがお答えします。


包む香典の金額は、故人・遺族との関係の深さ、年齢や社会的な立場で異なります。ホゥ。



































