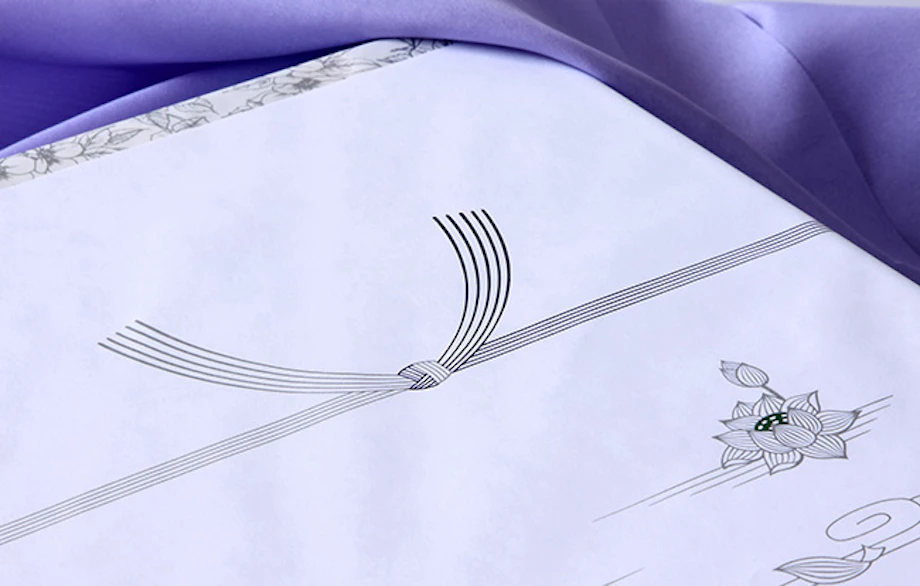粗供養とは、法事などの参列者からいただいた香典に対する返礼品のことです。一周忌などの法事では、施主は参列者にお渡しする返礼品を用意するのがマナーとなっています。
これから法事を予定している方の中には、どのようなものを用意すればよいか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、一周忌の粗供養の選び方から渡し方まで、知っておきたいマナーを解説します。定番の粗供養についても紹介しますので、何を選ぶか迷っている方はぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・粗供養は食品や消耗品などの「消えもの」を選ぶのがマナー
・掛け紙の水引は「結び切り」または「あわじ結び」のものを選ぶ
・粗供養に添える挨拶状は縦書きを基本とし、句読点を使わずに書くのがマナー
こんな人におすすめ
一周忌の「粗供養」を用意しようと考えている人
「粗供養」として何を贈ればよいか悩んでいる人
のしや挨拶状のマナーについて不安な人
一周忌とはどのような法要か?
一周忌法要は、故人が亡くなって一年が経った祥月命日に行う年忌法要です。一般的に、一周忌法要までが故人をしのんで喪に服す「喪中」とされ、一周忌を経て喪が明けます。
一周忌は年忌法要の中でも特に重要な法要とされており、遺族や親族のほか友人や知人も参列し、僧侶を招いての法要と「お斎(とき)」と呼ばれる会食を実施するのが一般的慣習です。
なお、一周忌は本来、故人が亡くなって満一年の祥月命日に行うものですが、平日に当たる場合などは日にちをずらすこともあります。その場合は、祥月命日より前の土日など、前倒しで設定するケースが多いです。
一周忌と似た言葉として「一回忌」がありますが、一回忌は故人が亡くなった当日を指します。一周忌と一回忌は別物であるため、混同しないようにしましょう。
一周忌などの法事に用意する「粗供養」とは
法事に関する言葉として「粗供養」という言葉を聞いたことがあっても、正確な意味は知らないという方も多いのではないでしょうか。
「粗供養」という言葉は地域や家庭などによって複数の解釈で使用されるため、やや紛らわしい言葉といえるでしょう。ここでは「粗供養」という言葉の意味と主な解釈を紹介します。
「粗供養」は弔問客への返礼品を指す
「粗供養」とは、供養のためにいただいた金品への返礼品、という意味の言葉です。「祖供養」の漢字で表記されることもあります。
「粗供養」という表記の場合は「粗品・つまらないもの」というニュアンスになり、「祖供養」という表記の場合は「先祖に対する供養の品へのお礼」というニュアンスになりますが、弔問客への返礼品を指す言葉であることに変わりはありません。
「粗供養」という言葉にはさまざまな解釈がある
「粗供養」という言葉は、地域によって複数の意味合いで使用されています。一つ目の解釈は、粗供養はお通夜や葬儀に来てくださった方へのお礼の品である「会葬御礼」を指すものとする考え方です。その場合、粗供養はお通夜や葬儀の当日に弔問客全員にお渡しします。
二つ目の解釈は、粗供養は「香典返し」と同義語であるとするものです。この場合、粗供養はお通夜や葬儀の当日または四十九日後に、香典をいただいた方にお渡しします。
三つ目の解釈は、粗供養は「法要の際にいただいたお供えに対する返礼品」であるというものです。この場合、粗供養は法要の際にお供えをくださった方にお渡しすることになります。
このように、「粗供養」はさまざまなニュアンスで使われる言葉です。どのようなタイミングで贈る返礼品を指すのか各々の認識が異なる場合があるので、誤解がないよう気をつける必要があるでしょう。
一周忌の粗供養はどう選ぶ?
粗供養を用意する際は、一般的な金額の目安やマナーを踏まえて選ぶ必要があります。金額が低すぎても高価すぎても望ましくありません。また、粗供養は後に残らない「消え物」が望ましいといったマナーもあるため、それらを踏まえて選ぶようにしましょう。ここでは、金額の目安と選び方のポイントについて解説します。
粗供養の金額の目安
一周忌では、香典でいただく金額の1/3~半分程度が目安といえるでしょう。粗供養は事前に用意しておく必要があるため、香典で受け取る金額を想定して準備しなくてはなりません。
故人との関係性が深いほど香典の金額が高くなるため、それに伴い粗供養の金額も高くするのが一般的です。金額の目安は、親族の場合は3,000円~1万円、友人の場合は2,000円~5,000円程度となります。
ただし、香典や粗供養に関するしきたりやマナーは地域によって異なるため、周囲の方に相談するなどして事前に確認しておくと安心です。
粗供養を選ぶポイント
一般的には食品や消耗品など、後に残らない物を贈るのがマナーです。これらは「消え物」と呼ばれ、「不幸を残さない」という考えに起因する慣習と言われています。食品であればお茶やお菓子など、実用品であればせっけんや洗剤などが定番です。
一周忌はお通夜や葬儀と比べるとマナーが厳格ではないことも多く、地域によっては「消え物」以外の品物を選ぶケースもあります。地域の風習なども踏まえて検討するとよいでしょう。
また、粗供養を選ぶ上で参列者が持ち帰りやすいという点も大切です。参列者の負担を考慮し、かさばる物や重い物は避けるようにします。
定番の粗供養3選
粗供養は「消え物」であること、かさばらないことなど、複数の条件を満たす必要があります。また、受け取った方の好みに合わないといったことがないよう、多くの方から好まれる物を選ぶことも大切です。ここでは、定番の品を紹介していきます。
日持ちのするお茶やお菓子
粗供養の定番としてまず挙げられるのが、お茶やお菓子です。お茶やお菓子は「消え物」であり持ち運びもしやすいため、どのような相手にも贈りやすいでしょう。
お茶には魔除けの意味合いもあるとされ、お茶を飲みながら故人をしのぶ、といった文化もあります。なお、お酒は慶事の贈答品のイメージを持っている方もいますので、避けたほうが無難でしょう。
お菓子については、和菓子に限らず、クッキーやマドレーヌ、バウムクーヘンなどの洋菓子も選ばれます。個別包装になっており、なるべく日持ちするものを選ぶのがポイントです。
せっけんや洗剤などの日用品
せっけんや洗剤などの日用品も人気です。せっけんや洗剤は実用的であり、後に残りません。また、「不幸や悲しみを洗い流す」という意味合いがあることも、好まれる理由となっています。香りや個性が強いものは避け、なじみのある品物を選ぶのがポイントです。
また、日用品としてはタオルやハンカチも定番です。「消え物」ではありませんが、日常生活で役に立つタオルやハンカチは多くの人に喜ばれるでしょう。白い色や落ち着いた色のデザインを選ぶようにします。
自由に選べるカタログギフト
参列者が自分の好きな物を選択できるカタログギフトも便利です。カタログギフトというとお祝い事のイメージが強いかもしれませんが、弔事用のカタログギフトも存在します。
「消え物」以外の物や通常の返礼品には望ましくないとされるお酒や肉類なども、カタログギフトであれば選択可能です。カタログギフトはかさばらず、持ち運びしやすい点でも便利です。
のし(かけ紙)・水引はどうする?
粗供養を渡す際は、品物をそのまま渡すのではなく、「かけ紙」や「水引」をつける必要があります。
弔事の場合、お祝い品の「のし」などとは作法が異なるため、混同しないようにしましょう。ここでは、「かけ紙」と「水引」の選び方、表書きの書き方について解説します。
のし(掛け紙)・水引の選び方
粗供養を渡す際には、品物に「掛け紙」を掛けます。これは慶事の際の贈り物に付ける「のし紙」にあたりますが、弔事で使用するものは掛け紙と呼ばれるものです。「のし紙」には添えられている縁起物が掛け紙にはないなど、両者は同じではありません。
品物に掛け紙をつけたら、上から「水引」という飾り紐を付けますが、最近では本物の水引を付けるのではなく、水引を印刷した掛け紙を用いるのが主流です。
水引には、さまざまな結び方や色があります。弔事の際に使用するのは、固くてほどけない「結び切り」または「あわじ結び」の水引です。
これには、「不幸を二度と繰り返さない」という意味が込められています。また、水引の色は黒白か双銀がよいとされますが、地域によっては黄白も使用可能です。
表書きの書き方
掛け紙の表書きは地域によって異なります。全国的に多く見られるのは「志」ですが、関西や中国・四国・九州などの一部地域では「粗供養」も一般的です。
水引の下部分には、贈り主の名前を書きましょう。「〇〇家」や姓のみを書くことが多いですが、フルネームを書く場合もあります。
表書きや名前は、筆か筆ペンを用いて毛筆で書くのがマナーです。お通夜や葬儀では悲しみを表す薄墨を使用するしきたりがあります。一方、四十九日以降は一周忌を含め、濃墨で問題ありません。
粗供養の渡し方は?
一周忌の粗供養は、参列者には法事の後にお渡しし、参列せず香典やお花だけをくださった方には後日届けることになります。
いずれも感謝の気持ちを込めて、失礼のない方法で渡すことが大切です。ここでは、一周忌の返礼品をお渡しするタイミングとマナーについて解説します。
法事の参列者への渡し方
粗供養は、会食が終わって参列者が帰る際に、一人ひとりにお礼の言葉とともにお渡しするのが基本です。その場で慌てることのないよう、事前に品物を袋に入れて準備しておきましょう。
ホテルやレストランなどで大人数での会食を行う場合は、一人ずつお渡しするのが難しいこともあります。
そのような場合は、あらかじめ座席に粗供養を入れた袋を置いておき、会食の終了後に持ち帰っていただくのも一案です。会場のスタッフに事前に依頼して、参列者が帰る際に渡していただくという方法もあります。
なお、当日高額な香典を受け取った場合には、当日お渡しする粗供養とは別に、後日あらためて差額程度の品を贈るのがマナーとされています。
法事に参列しなかった方への渡し方
当日の法要には参列せず、香典やお花だけを送ってくださる方もいるかもしれません。そのような場合には、法要から1ヶ月以内を目安に粗供養を届けるのがマナーです。いただいた金額などを踏まえて用意しましょう。
宅配便などで送る際には、法要が無事に済んだことを報告するとともに、香典やお供えへの感謝の気持ちを伝える挨拶状を忘れずに添えます。なお、粗供養を辞退すると言われた場合には、法事から一週間以内を目安に挨拶状のみを送りましょう。
粗供養に添える挨拶状のマナー
法要当日に粗供養を手渡しする場合も、後日届ける場合も、挨拶状を添えるのがマナーです。
業者に印刷を依頼することもできますが、手書きであればより感謝の気持ちを伝えられるでしょう。ここでは挨拶状の書き方や注意点に加え、基本的な文例を紹介します。
挨拶状の書き方
粗供養に添える挨拶状には、書き方のマナーがあります。失礼のないよう、ルールを踏まえて書くようにしましょう。
挨拶状は縦書きを基本とし、句読点を使わずに書くのがルールです。句読点を使用しないことについては、昔は毛筆で文を書く際に句読点を使わなかったことに由来するという説や、法要が滞りなく進行するという意味が込められているという説など、諸説あります。
また、「ますます」「くれぐれも」といった繰り返し言葉の使用は避けましょう。これは、不幸が「繰り返す」ことを想起させないためとされています。
挨拶状の文例
挨拶状の文面は、法事に参列いただいた場合と、参列はせずに香典やお花のみをいただいた場合で異なります。
法事に参列して香典をくださった方への挨拶状では、まずは弔問に来てくれたことへのお礼を述べ、粗供養を送る旨を伝えましょう。下記は基本的な挨拶状の例です。
謹啓
先般 亡祖父 ○○○○ 儀 一周忌法要に際しましては ご多忙のところご参列賜り厚くお礼申し上げます
心ばかりではありますがお礼の品をお送りいたします
略儀ながら書中をもちましてお礼申し上げます
敬白
法事には参列せず、香典やお花のみをくださった方への挨拶状では、まず香典やお花へのお礼を述べ、法要が無事に済んだこと、お礼の品を贈ることを伝えます。下記は一例です。
謹啓
先般 亡祖母 ○○○○ 儀 一周忌法要に際しましては ご多忙のところご鄭重なるご厚志を賜り厚くお礼申し上げます
お陰さまで 法要も滞りなく相営むことができました
ささやかではございますがお礼の品をお送りいたします
略儀ながら書中をもちましてお礼申し上げます
敬白
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
「粗供養」とは、供養のためにいただいた金品への返礼品を指す言葉です。法事の際の返礼品は一般的な目安やマナーを踏まえて、ふさわしい品を選ぶ必要があります。
返礼品としては、お茶やお菓子などの食品やせっけんや洗剤などの日用品のほか、カタログギフトなどが定番です。返礼品を渡す際には、包み方や渡し方にも注意しましょう。
小さなお葬式の「香典の後返し」オンラインストアでは、金額に応じたさまざまな返礼品を取り揃えています。返礼品をお探しの方は、ぜひご検討ください。
粗供養に関する疑問以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


御仏前は「仏となった故人の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。