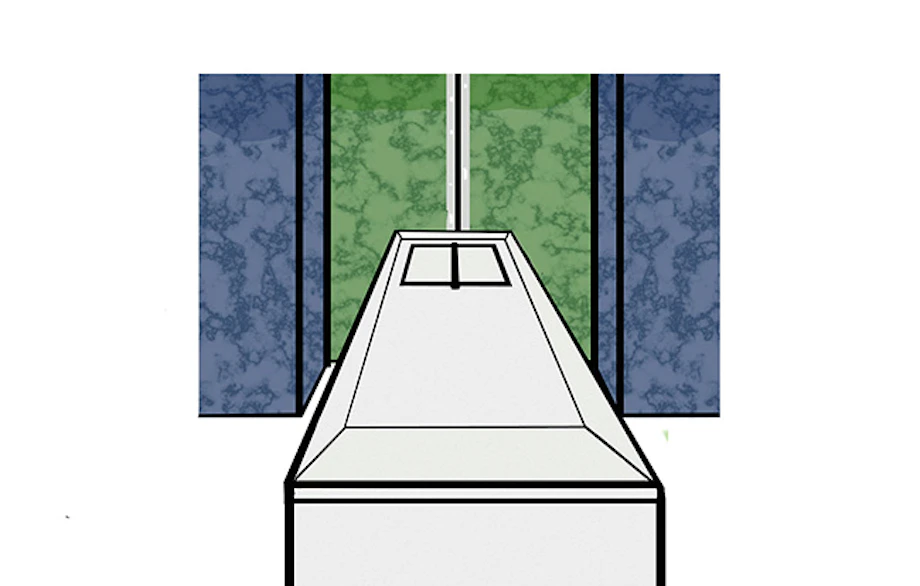日本では、火葬の際に故人が好んでいたものや思い出の品などの「副葬品」を棺に納める習慣があります。しかし、遺族が入れたいものや故人が希望したものなら何を選んでもよいというわけではありません。安全かつスムーズに火葬するためには、副葬品に関するルールを守ることが大切です。
この記事では、棺の中身に適したものや、入れてはいけないものについて詳しく解説します。また、火葬の流れや火葬中の過ごし方についても学べる内容です。
<この記事の要点>
・棺には故人の衣類や小物、手紙や写真、好んでいた食べ物や飲み物などの副葬品を納める
・金属製品や電子機器、ライターは火葬設備の故障や遺骨損傷の原因となるため、棺には入れられない
・副葬品に関するルールは火葬場ごとに異なる
こんな人におすすめ
葬儀をお考えの方
棺の中に思い出の品を入れようとお考えの方
納棺の際に入れてもいいものが何か気になる方
火葬のマナー|棺の中身は何を入れる?
棺に入れる「副葬品」は、家族の想いと弔いの気持ちを込めて、さまざまなものを入れられます。しかし火葬にあたって、棺の中身には「燃えやすいもの」を選ぶことも必要です。ここからは、棺の中身に適したものや副葬品を選ぶ際のポイントについて紹介します。
故人の洋服や着物
故人が大切にしていた衣類や着物、ユニフォームなどはメジャーな副葬品のひとつです。衣類を入れる際には、綿・絹・麻などの燃えやすい素材のものを選びます。できるだけ薄手の生地だと、燃え移りや燃え残りの心配がなく安心でしょう。
衣類以外に、生前大切にしていた帽子やハンカチなどの小物を入れる方もいます。衣料などは入れすぎるとお骨上げが難しくなるため、少量になるよう厳選しましょう。
手紙や写真
故人への思いを込めた手紙はもちろん、家族や友人などで書いた寄せ書きを準備するのもおすすめです。どうしても言えなかったことや感謝の気持ちを手紙にして棺に入れることは、遺族の心の整理にもつながります。旅行先で撮った写真や故人らしさの出ている写真を入れるのもよいでしょう。写真は存命中の人が写っていないものを選びます。
好んでいた食べ物・飲み物
生前好きだった料理やお菓子、お茶やコーヒーなどを入れる際には、容器に注意します。缶やプラスチック、瓶など燃やせない容器に入ったものは、紙皿に取り分けて入れましょう。また、他のものと同様に大量には入れられません。
たばこやお酒などの嗜好品を入れれば、故人も喜んでくれるでしょう。紙巻きたばこは問題ありませんが、電子たばこは避けます。お酒は小さな紙パックであればそのまま、ビールなどは紙コップに少しだけ注いで入れましょう。
故人が望んだもの
最近は終活のために「エンディングノート」などを準備する方も増えています。エンディングノートに副葬品の希望を書いていたり、生前に直接お願いされたものがあったりする場合は、ルールを守ったうえでできるだけ希望にそったものを準備しましょう。
そのほかにも折り鶴や御朱印帳、おいづる(巡礼で着る白衣)などは、死後の幸福の願いが込められており、故人が極楽へ行けるといわれています。もしこういったものを所持していた場合、副葬品として入れるのもおすすめです。
棺の中に入れてはいけないものとは?
お骨を汚したり火葬設備の不具合につながったりするものは、棺の中に入れられないというルールがあります。ここでは、棺の中に入れてはいけないものをまとめました。ルールに反するものを入れると、事故や公害発生にもつながるため注意しましょう。
火葬設備の故障・遺骨損傷の原因となるもの
故人が身に着けていた眼鏡や入れ歯、指輪などを一緒に棺に入れたいと思う方は少なくありません。しかし、カーボン製品・ガラス製品・金属製品は、火葬設備の故障や遺骨損傷の原因になります。これらは棺ではなく、骨壺の中に納めましょう。
趣味で愛用していた釣り竿やゴルフクラブ、スマートフォンや音楽プレイヤーなどの電子機器を入れるのもルール違反です。特に、スプレー缶やライター、電池などは炉内爆発の危険があるため注意しましょう。
火葬時間延長・不完全燃焼の原因となるもの
灰が多く出るもの・水分含有量が多い物は燃焼に時間がかかったり、不完全燃焼の原因になったりします。そのため、分厚い本や辞書、フォトアルバムなど厚みがあるものは副葬品に適していません。布団やぬいぐるみも同じ理由で避けた方がよいでしょう。メロンやスイカなど水分が多く大きなものを入れたい場合は、少量に切り分けて入れます。
公害発生の原因となるもの
バッグや靴などのビニール製品は、燃やすと公害発生の原因となるため許可されていません。CD、DVD、ゴルフボールも燃やすと有害物質が出ることから、多くの火葬場で禁止されています。また、化学合成繊維を含む衣類や、発泡スチロール製品の枕は燃やせない素材です。
生前使用していた杖を入れる方もいますが、アルミ製のものは避けます。総木製の杖であれば一緒に納められる火葬場もあるため、確認するとよいでしょう。
違法なもの
「三途の川を渡るのに冥銭として6文必要である」という言い伝えから、昔は故人にお金を持たせたり、棺に入れたりする風習がありました。しかし現在の日本では、紙幣や硬貨を燃やすことは法律で禁止されています。古いお金でも燃やすと違法になるため避けましょう。6文銭を印刷した紙や、木で作ったお金を用意している火葬場もあります。
縁起が悪いとされるもの
昔から存命中の人の写真を火葬すると、「死者と一緒に彼岸に立つことになり、あの世に連れていかれる」という言い伝えから縁起が悪いとされています。そのため、生きている人の写った写真を入れるのはマナー違反です。写真は故人の周囲から端っこまで、存命中の方が写り込んでいないかどうかをチェックしたうえで選びましょう。
棺の中身に関する注意点
機械や金属などの燃えないものやかさばるもの、水分が多いものは棺に入れられないというのが基本的なルールです。そのほかにも、自治体や火葬場ごとに細かいルールが異なります。ペースメーカーなど事前申告が必要なものもあるため、注意点を見てみましょう。
火葬場によってルールが異なる
「棺の中身に適しているか」の判断は、火葬場によって違いがあります。都道府県をまたぐとルールが変わるケースも多く、よその土地で経験したことと違いがあり戸惑うかもしれません。大切なのは、ルールを守り故人をあたたかくお見送りすることです。利用する火葬場ごとのルールを確認したうえで、想いを込めた副葬品を準備しましょう。
ペースメーカーなどは事前申告が必要
故人が心臓にペースメーカーを入れている場合、そのまま火葬すると炉内爆発を起こす危険性があります。そのため、多くの火葬場では事前申請が必要です。事故が起こると、故人の遺体が損傷するだけでなく、火葬設備が破損したり火葬場の職員が負傷したりと大きな問題につながります。
事前申告をすれば、ペースメーカーが入ったまま火葬できるケースがほとんどです。しかし、ペースメーカーを摘出してからでないと火葬できない地域もあるため、忘れずに事前確認しましょう。
どうしても入れたいものは写真や絵にする
ルール上は棺の中に入れられないが、故人が愛用していたものや遺族がどうしても棺に入れたいと希望するものがあるかもしれません。副葬品にできないものは、写真を撮って納めるのもひとつの方法です。
すぐに写真を用意できない場合は、絵に描いて入れるのもよいでしょう。遺族で一緒に描いたり子どもを交えて描いてみたりすれば、故人の思い出を振り返りながら心を癒すひとときにもなります
火葬の流れと遺族の過ごし方について
故人を看取った医師から発行された死亡証明書とともに死亡届を自治体に提出すると、火葬許可が下ります。遺族は、火葬許可が下りた証明書として受け取る「死体火葬許可証」を火葬場に持参しなければなりません。近年では、これらの手続きを葬儀社が代行してくれるケースが増えましたが、一連の流れを覚えておくとよいでしょう。
ここからは、火葬の流れや火葬中の遺族の過ごし方について紹介します。
火葬受付からお骨上げまでの流れ
火葬をするには、火葬場への予約が必要です。葬儀社に代行を依頼するケースが多いですが、代行してもらえない場合は個人で電話または直接窓口にて予約しましょう。
火葬場へは予約時間の15~20分前を目安に、余裕を持って到着します。死体火葬許可証を職員に渡し受付が終わったら、告別室にて故人と最後のお別れの時間です。地域によっても異なりますが、このタイミングで副葬品を納めることが多いでしょう。お別れと僧侶による読経や焼香を終えたら、火葬が始まります。
火葬後は、収骨室にてお骨を骨壺へ納めます。これをお骨上げといい、故人と縁の深かった親族から順番に、足元から上半身に向かって収骨するのが一般的です。お骨上げの作法は地域差が大きいため、係員の指示に従いましょう。
火葬中の遺族の過ごし方
故人の体格や年齢、棺に入れた副葬品の量によっても異なりますが、火葬時間は1時間程度が目安です。その間、遺族および親族は火葬場に併設してある控え室で待機します。
控え室では故人の思い出話をしたり、お茶菓子やお弁当を食べたりしながらゆっくりと過ごしましょう。また、火葬中に精進落としをおこない、お酒がふるまわれる地域もあります。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
副葬品は、故人を想いながら選ぶ重要なものです。大切な人の棺にはたくさんの副葬品を入れたいと考える方もいるでしょう。しかし安全かつスムーズに火葬を終えるためにも、火葬場で定められたルールをしっかりと守ったうえで、棺の中身を決めることが大切です。
副葬品に関して「何を入れればよいか」と悩む方も少なくありません。火葬や副葬品について、困ったことや分からないことがあればぜひ「小さなお葬式」へご相談ください。「小さなお葬式」では365日24時間、葬儀全般に精通したスタッフがさまざまな疑問や不安の解消をサポートいたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。