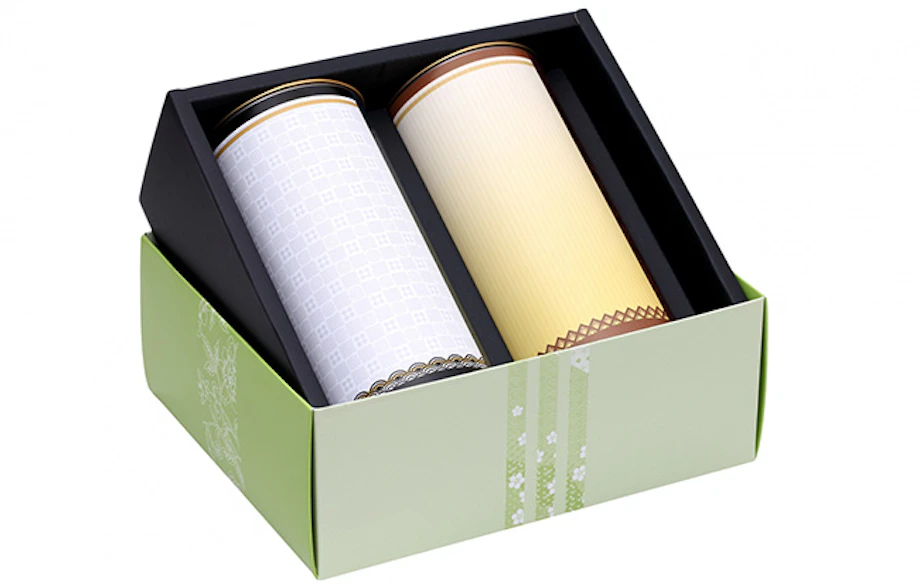香典返しの値段はいくらが望ましいのか、金額の決め方に困ってしまう方は多いのではないでしょうか。また、いざ値段のめどがついても、それに適した品物にはどのようなものがあるのか、選ぶときの基準についても迷うことは少なくありません。
そこで今回は、香典返しの値段の決め方について解説します。値段の考え方をチェックしたうえで、それに合った品物の選び方もしっかりと押さえておきましょう。
<この記事の要点>
・香典返しの相場は、いただいた香典の半額から3分の1程度が目安
・香典返しには消えものと呼ばれる、食べ物や洗剤などが選ばれている
・肉や魚などの四つ足生臭ものやお祝い事で贈られる昆布や鰹節を送るのはマナー違反
こんな人におすすめ
香典返しの基礎知識を知りたい方
香典返しの値段の決め方を知りたい方
値段別に見る香典返しの品物の選び方を知りたい方
値段を考える前にチェック!香典返しの基本
通夜や葬儀で香典をいただいた際には、どのようにお返しすればよいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。そのため、まずは前もって香典返しにおける基礎知識を整理しておくことが重要です。
香典返しとは
香典は、通夜や葬儀で参列者が用意する金銭です。また、香典だけでなくお供え物や供花を出すこともあります。喪主・施主側はこれら頂いた金品に対してお礼をしなければなりません。これが香典返しです。
香典返しは、現金ではなくお礼の品を選ぶことで対応します。故人を一緒に送ってもらった感謝の気持ちや、支援いただいたおかげでしっかりと供養することができましたという報告・挨拶の意を示すことといった重要な役割を担うものです。
香典返しは、頂いた香典の額を考えて値段を決めます。関係性によって香典の金額は異なるため、それぞれに見合った対応をしなければなりません。
四十九日を済ませた後に贈る
後日返しの香典返しは、四十九日を終えた後に通夜や葬儀の参列者に贈ります。直接手渡したり、宅配便で送ったりなど方法はさまざまです。
一方で香典返しのタイミングは忌明け後に限定することなく変わってきています。当日返しというかたちで、葬儀の当日に渡すパターンも最近は珍しくありません。この場合は頂いた香典の額にかかわらず、一律の金額の香典返しを渡します。
当日返しの場合、香典を多めに包んでもらった方には、後日あらためて別の返礼品を追加で渡すなどの対処が必要になることに注意しましょう。
香典返しの値段の決め方
香典返しにはさまざまなパターンがあります。当日返し、後日返しだけでなく、頂いた香典の金額によっても対処が変わるので注意しましょう。ここでは香典返しの品物の値段の決め方について解説します。
香典返しの値段は「半返し」or「3分の1返し」
値段を決める際に知っておきたいのは、「半返し」「3分の1返し」という考え方です。半返しは、頂いた香典の半分の金額に相当する品をお返しします。特に関東でよく見られる文化です。これには、昔の葬儀費用が香典の半分くらいにあたり、残った半分の金額をお返しとして贈るというしきたりがあったためともいわれています。
3分の1返しは、頂いた香典の3分の1の金額を目安にお返しをすることです。これは、関西でよく見られます。
どちらを基準とするかは地域柄や親戚との取り決め、香典を包んでくれた方との関係性の影響もあり、一概にどちらとはいえません。そのため香典返しの値段を決める際には、葬儀社に相談したり、親戚にヒアリングしたりして判断するとよいでしょう。
半返しが望ましいケース
地域によって差や違いはありますが、葬儀費用を賄った後に香典の半分が残ることが多かったという背景が色濃い場合には、半返しが一般的な考え方といえるでしょう。
半返しの場合、5,000円の香典には、2,000円~3,000円程度の品を用意します。一般的な考え方にのっとって香典返しを贈りたい場合は、半返しを選択しておけば基本的に失礼にはありません。
3分の1返しが望ましいケース
3分の1返しの場合は半返しよりも香典返しの値段が低くなるため、「失礼にあたるのでは」と考えてしまう方も多いかもしれません。
しかし、値段を少なくすることに、納得できる理由がある場合もあります。例えば、世帯主や一家の大黒柱的存在にあたる家族が亡くなったときのパターンです。
このとき半返しすると香典返しの値段が高くなり、大黒柱を失って困っているにもかかわらず遺族の負担は増えてしまいます。こういったときは参列者から配慮や支援の意味も込めて香典を頂くことも多いため、あえて3分の1にとどめるという考え方で用意しましょう。
また、亡くなった方と関係性の深い友人や職場関係者からも高額な香典を頂くことは珍しくありません。例えば5万円もの香典をいただけば、半返しにすると2万5,000円もの値段の品を用意する必要が出てきてしまい、遺族の負担が増えてしまいます。
このときも香典返しは、3分の1~4分の1の値段に設定されることがあるのが特徴です。ちなみに高額な香典の場合は、参列者自ら返礼品の受け取りを辞退されることも少なくありません。
具体的にはいくら?香典返しの値段の目安
半返し・3分の1返しといった考え方にのっとって値段を考えた場合、具体的には2,000円~3,000円ほどの値段が目安としてあげられるでしょう。
香典の額は5,000円だったり1万円だったりなど関係性によって変わってきます。そのため値段の考え方や品物の決め方に困ったときはパターン別に、複数の種類の香典返しを選んでおくことが望ましいでしょう。
値段別に見る香典返しの品物の選び方
香典返しに相応しい品物にはさまざまなものがあります。香典返し選びでは値段がひとつの基準になりますが、値段別にどのようなものが選ばれているかを見てみましょう。選ぶときの基準や注意点なども整理します。
2,000円~3,000円の値段
2000円~3000円の香典返しは、同じ品を渡す当日渡しのケースにおいて目安となる値段です。下記のような、お菓子、お茶、海苔などの食品類がよく選ばれます。
・焼き菓子
・海苔
・お茶
・ジュース
・洗剤
・調味料
・カタログギフト
弔事の贈り物は、悲しい出来事を後に残さないという考え方に基づいて、「消えもの」が選ばれる傾向にあります。食品は食べてしまえば後に残らないため、香典返しとしては最適といえるでしょう。洗剤なども使えば無くなるため、消えものの一種です。
3,000円~4,000円の値段
3,000円~4,000円目安の値段で香典返しを選ぶときも、同じように消えもののギフトを選ぶのが一般的です。3,000円~4,000円程度になると、お菓子とタオルの詰め合わせや立派な木の化粧箱に入った煎茶のギフトセットなど、金額的に選択肢も多くなります。先方の選ぶ楽しみも増えることから、カタログギフトを選んでもよいでしょう。
お菓子の詰め合わせセットは、2,000円~3,000円の予算に比べて個数が増え、重厚感のあるしっかりとしたイメージを出せます。また、個数はそこまで多くなくても高級菓子や高級茶葉なども選びやすくなるため、選択肢は広がるでしょう。
香典返しで注意したい避けるべき品物とは
香典返しの品物選びにおいても、マナーには十分注意したいところです。値段的に問題がないからと安易に選ぶと、ふさわしくないものを贈ってしまい、結果としてイメージを悪くしてしまうことが考えられます。ここでは、弔事の贈り物としてふさわしくないものを確認しましょう。
お酒・昆布・かつお節
食品類にあたるため間違って贈ってしまいそうなものですが、香典返しとしてお酒や昆布、かつお節は避けるべきと捉えておきましょう。これらは縁起の良い出来事をイメージさせます。亡くなった方を供養するという場においては好ましくないと考えられるためです。
四つ足生臭もの
肉や魚などの「四つ足生臭もの」と言われるものも、香典返しでは控えましょう。亡くなった人の四十九日を迎えるまで、肉や魚を使わない精進料理を食べて過ごす習慣が仏教にはあるためとされます。また、肉や魚は基本的に生ものであるため日持ちせず、贈られても困ってしまうケースが多いというのが理由です。
しかし、肉や魚が加工されて少し含まれている程度の食品なら、そこまで過剰に気にする必要はないでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
香典返しの値段を考える際には、半返しや3分の1返しの文化を覚えておくと役に立ちます。頂いた香典の額を考慮しながら、感謝の心を示すのにふさわしい値段を決めることが大切です。その際には、予算内で選べるものには何があるのか、事前にチェックしておきましょう。
しかし、香典返しはさまざまなパターンが想定されるため、値段決めだけでなく用意の仕方でも不安なことが生じがちです。その際は、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。経験豊富なスタッフが真心込めて最良の形を提案させていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



包む香典の金額は、故人・遺族との関係の深さ、年齢や社会的な立場で異なります。ホゥ。