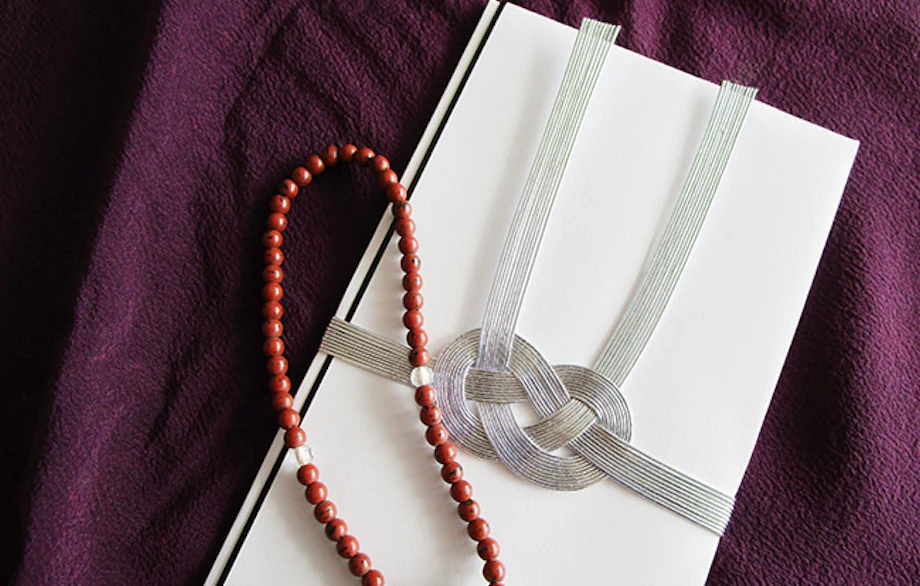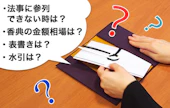故人が亡くなって12年後の命日に行う十三回忌法要ですが、「家族だけで執り行ってもよいのか」「何を用意したらよいのか」と迷うかもしれません。準備する期間は十分あるためじっくり考えて、故人のために心を込めて供養をしましょう。
この記事では、家族だけで十三回忌法要を執り行う際の準備から当日の服装、お布施や香典のマナーまで詳しく解説します。
<この記事の要点>
・参列人数などのきまりはないため、家族だけで法要を行ってもマナー違反にはあたらない
・流れや準備はほかの法要とかわらないため、日程と場所、僧侶の手配を行う
・お布施の目安は1万円~5万円程度で、これまでと同様の金額をお渡しする
こんな人におすすめ
家族だけで十三回忌法要を行いたい方
十三回忌法要の準備について知りたい方
十三回忌法要の服装について知りたい方
法要はいつまで?十三回忌は家族だけでもよい?
法要は五十回忌まであり、回数を重ねるごとに小規模になっていきます。回忌法要に「〇回忌まで〇名呼ばなければいけない」というきまりはありません。そのため、家族だけで十三回忌を行う場合もマナー違反にはなりません。
十三回忌のやり方は家族の考えによる
十三回忌は、今後どのように法要をしていくか考えるタイミングにもなるでしょう。法要のやり方は地域や家族の考え方によって異なります。ここからは、十三回忌のやり方を3つ紹介します。
家族だけで執り行う
「法要を小規模にして負担を減らしたい」という理由から、三回忌や七回忌の時点で家族だけの法要を選ぶケースもあります。
十三回忌を執り行わない
形式を重んじた法要ではなく、家族で会食をしたり手を合わせたりすることで故人を偲ぶ方法もあります。「形式よりも気持ちを大切にしたい」という思いがある方は、十三回忌法要を執り行わないという選択肢も視野に入れるとよいかもしれません。
複数の法要を一度まとめる(併修)
複数人の法要を一度にまとめて行う「併修(へいしゅう)」を選択するケースもあるでしょう。併修は先に亡くなった方の命日に合わせて、同日に法要を執り行う方法です。
近年では法要の考え方も変わってきており、「法要の準備をする負担を減らしたい」「遠方から参列者を招くのは申し訳ない」といった理由から併修を選ぶこともあるようです。
ただし、三回忌まではなるべく併修を避けるという考え方もあります。そのため、併修は家族や親戚、菩提寺と相談してからきめるとよいでしょう。
十三回忌法要を家族だけで行うときの準備
十三回忌法要は、故人が逝去してから12年後(数えで13年目)に執り行う法要です。亡くなって10年以上の年月が経っているため、遺族、家族だけで法要を営むケースも多いでしょう。ここからは、十三回忌法要を行う際の準備について紹介します。
流れは基本の法要と同じ
法要の流れはほかの法要とほとんど同じです。家族だけの十三回忌だからといって、特別な違いはありません。開催場所は七回忌までと同様に、自宅か菩薩寺のどちらかを選ぶことが多いでしょう。
十三回忌法要は、お坊さんが入場して読経をしてもらい、参列者が順番に焼香をします。その後、お坊さんの法話を聞いて終了となります。法要後はお墓参りをして会食をすることもありますが、家族だけの場合は特別な場を設けないケースも多いでしょう。
日程をきめたら参列者に連絡する
十三回忌法要は、亡くなってから満12年目の命日に行うのが理想的です。しかし、平日の場合は都合がつかない方も多いでしょう。その場合は、命日よりも前の土日祝日に執り行います。命日の後に法要を行うのはマナー違反とされています。
会食をする場合は日程調整後に食事処の予約を取りますが、家族だけの法要であれば、自宅や菩提寺でも執り行えるでしょう。日程が決まったら、これまで案内状を出していた故人の友人・知人に「家族だけで法要をする」旨を伝えます。
「どうして呼ばれないのだろう」と思われないために、趣旨の説明とねぎらいの言葉、お礼を忘れないようにしましょう。
お坊さんの手配をする
お寺とお付き合いのある方
菩提寺(ぼだいじ)とは、先祖代々のお墓のあるお寺のことです。菩提寺がある場合には、菩提寺に連絡をして、読経の依頼を行いましょう。
お寺とお付き合いが無い方
菩提寺が無い場合には、知人縁故からお寺を紹介してもらう方法や、葬儀の際にお世話になったお寺に相談する方法があります。
その他最近では、インターネット上でお坊さん手配サービスを利用される方も増えています。
自宅はもちろん、手配したお坊さんのお寺での法要も行えるので、菩提寺がない方には便利です。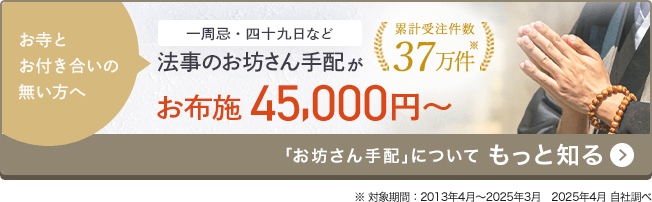
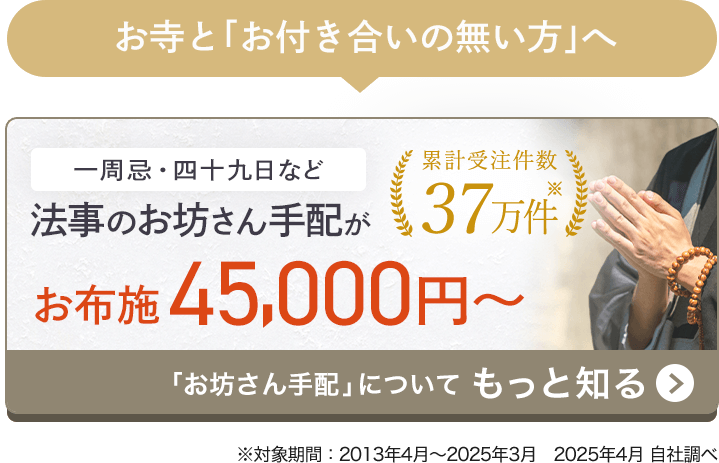
お寺の都合によっては希望日に添えない場合もあるため、1ヵ月~2週間前を目安に寺院手配の予約をすることをお勧めします。
挨拶文を考える
お坊さんの読経の後に、施主は法事に参列してくれたことへのお礼の挨拶をします。また、会食をする場合はその前後にも挨拶をする場面があるでしょう。
一般的には、会葬者へのお礼、故人についての話、日頃の感謝や今後の法事の予定について話します。家族だけの場合は、手短な挨拶にしても問題ないでしょう
十三回忌を家族だけで行うときの服装
家族だけの十三回忌法要では、葬儀などで着るような正式な喪服を着用しなくてもよいとされています。一般の参列者と、服装の格式に差をつける必要がないためです。とはいえ、考え方は人それぞれなので、形式を重んじるケースもあるでしょう。基本の服装は以下のとおりです。
| 基本の服装 | 平服や略式喪服を着用 |
| 男性 | 無地のダークスーツ、ネクタイは無地の暗めカラー、革靴・ベルトは黒を選ぶ |
| 女性 | 暗めの色のワンピース・アンサンブル、黒のストッキングとパンプスを選ぶ |
| 子ども | 制服(制服がない場合は黒っぽい服装) |
| 幼児・赤ちゃん | 淡い色合いの服でも可 |
十三回忌を家族だけで行うときのお布施と香典
家族だけの法要では、「僧侶へのお布施」や「霊前に供える香典」をどうすればよいか判断に迷う方がいるかもしれません。ここでは、お布施や香典の金額の目安について解説します。
お布施の目安
現代では、お布施はお坊さんへの感謝の気持ちを表すものという意味合いが強くなっています。宗教宗派や地域によって金額の目安は異なりますが、おおむね1万円~5万円程度包むのが一般的です。
家族だけで法要を行う場合でも、これまでと同様の金額を包みましょう。会食の場を設ける場合は、お坊さんに参加の有無を確認して、不参加であれば「御膳料」を包みます。こちらは一般的に5,000円~1万円程度が目安です。
香典の目安
家族だけの法要では、香典を用意するか迷うかもしれません。気持ちで包む場合は、故人が親の場合は1万円~5万円、故人が兄弟姉妹や祖父母の場合1万円~3万円を目安にするとよいでしょう。ただし学生であれば、無理に用意する必要はありません。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
家族だけの十三回忌は小規模な法要になり、故人を偲ぶ気持ちを家族で共有しながら過ごすことができるでしょう。以前招待していた参列者には、「家族だけで法要する」という旨を丁寧に伝えておくと安心です。
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切になります。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。


東京や一部の地域では7月、ほかの地域では8月にお盆を迎えることが多いようです。ホゥ。