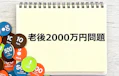退職は人生における大きな転機になりますが、老後の人生設計ができないことに不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。人生設計ができない理由には具体的な数字を意識していないことが考えられます。
豊かな老後を過ごすために必要な生活費や、支給される年金額を調べるだけでも明確な老後のビジョンを持つことができるようになります。
この記事では、老後の人生設計における基本的な考え方や、上手くできない3つの理由を解説し、老後を考える上で避けては通れない長生きリスクを軽減する方法について紹介します。
<この記事の要点>
・老後の生活について目的意識を持っていないと具体的な人生設計が立てられない
・繰り下げ受給などで年金額を増やすことで、長生きリスクを軽減できる
・医療費の増加に備えて医療保険に加入するのも長生きリスク対策の一つである
こんな人におすすめ
老後の人生設計における基本的な考え方が知りたい方
老後の人生設計ができない理由と対処法が知りたい方
長生きリスクと軽減方法について知りたい方
老後の人生設計の基本的な考え方
65歳以上になると年金を受給できるようになりますが、65歳以降に働く場合、平均給与は減少し収入が少なくなります。国税庁の調査によると男女の平均給与は20歳から50歳になるまで上昇を続け、50歳~54歳でピークを迎えます。日本では多くの場合、年功序列で給与が決まるので、50代以下の現役世代では年齢が高いほど給与が高まりやすくなります。
50歳~54歳の男女の平均給与は525万円になりますが、60歳以降になると平均給与は減少します。60歳~64歳で411万円、65歳~69歳で324万円、70歳以上では282万円です。
60歳以上の年齢になると、長く働くほど労働による収入が得られなくなる長生きリスクが発生します。長生きリスクとは、長寿であるほど生涯に必要な生活費を賄えなくなるリスクのことです。
労働による収入の低下も長生きリスクの1つであり、生活費が支払えない原因にもなります。また、毎月の収入で生活費を賄えない場合は、現役世代の貯蓄や、退職金を取り崩す形で生活費を賄うことになりますが、長生きするほど取り崩す資産が増えるので、破産のリスクが増加します。
老後の人生設計は、このような長生きリスクに対して備えることが重要です。年金などを活用して、労働による収入が低下することも考えながら老後の生活で不足する金額を準備していきましょう。
参考:令和元年分 民間給与実態統計調査 国税庁
長生きリスクには医療費の増加も
長生きリスクは労働による収入の減少だけではなく、医療費の増加も挙げられます。
65歳未満の1人当たりの年間の医療費の平均は18万8,300円ですが、65歳以上になると73万8,700円となり、70歳以上になると82万6,800円に増加するので、年齢を重ねるごとに高まっていることが分かります。
生活費だけでなく医療費の増加に対する対策も必要です。
参考:平成30年度 国民医療費の概況 厚生労働省
老後の人生設計ができない理由と対処法
老後の人生設計における基本的な考え方と現状について紹介しました。ここからは老後の人生設計ができない理由と対処法について解説します。
目的意識を持っていない
老後を過ごす際、何を目的にどのような生活がしたいのか考えていない場合は、具体的な人生設計が立てられません。例えば、定年後は労働をせずに年金だけで暮らしたい場合と、70歳まで働いて収入を得る場合では老後に必要な資金も変わってきます。
また、時間に余裕がある老後の生活の中で、新しいことを始めようと考えている場合には生活費や医療費の他にもお金が必要になることもあるでしょう。
老後の生活において、働き続けたいのか、現在の生活レベルを維持するのか、新しくなにかを始めるのか、さまざまな観点から自分が過ごしたい老後について考えることが、老後の人生設計において目的意識を持つきっかけになります。
数字を考えていない
人生設計を立てるうえで必要なのは、お金も含めた具体的な数字です。年金はいくらもらえる、老後の生活に必要な資産の目安など、具体的な数字を考えない人生設計は曖昧なものになります。
例えば、老後を過ごすために必要な毎月の費用が27万円のとき、貰える年金が20万円の場合、不足する7万円の赤字をどのように補うのか考える必要があります。
上記のように数字を意識するだけでも、人生設計がより具体的になります。正確な数字を計算するのは困難ですが、目安となる数字を意識するだけでも人生設計の質は変わります。
ノートなどにまとめていない
人生設計の内容はノートや、パソコンで作るならワードやエクセルを利用して形になるものにまとめるようにしましょう。自分の頭や、メモ帳で計算して満足するのではなく、形として残すことが重要です。
人生設計の内容をアウトプットすることによって、考えがまとまる効果が期待できます。また、人生設計の内容を共に生活する配偶者に見せることによって、考えを共有することが可能です。
また、自分の人生設計の内容をファイナンシャル・プランナー(FP)などの専門家に相談する場合も、形となる資料があると具体的なアドバイスを受けやすいでしょう。
老後の人生設計を考えるうえで必要な数字とは
老後の人生設計ができない理由に、数字を考えていないことを大きな理由として挙げました。ここでは、人生設計において意識する必要がある具体的な数字と調べる方法について解説します。
毎月の生活費
老後の生活を送るには、毎月の生活費を考える必要があります。求める生活レベルによって必要な生活費は変わるので、具体的にいくら必要になるのかは人それぞれです。
将来の生活費を考える場合、現在の生活費を正確に認識することが効率的です。現在の収支を正確に記録していない人は、家計簿を付けることから始めましょう。家計簿を付けることで、現在の毎月の生活費の総額と支出の内訳が分かります。
仮に現在の生活レベルを完全に維持するなら、支出の額は変化しないので、現在の支出がそのまま老後の生活費になります。現在の家計簿の支出で老後にはかからない費用があれば差し引き、一方で老後に発生することが予測される出費があれば足し合わせることによって老後の生活費の目安を計算できます。
また、厚生労働省の調査では高齢夫婦の平均消費支出は22万4,390円、独身の場合は13万3,146円です。実際の支出や、平均支出などのデータを参考に生活費の目安を算出しましょう。
参考:家計調査報告 家計収支編 2020年(令和2年)平均結果の概要 統計局総務省
支給される年金額
労働による収入が減少する老後の生活において、年金は重要な資金になります。年金で老後の生活費の大部分を賄うことを考えている場合は、支給される年金額の目安を知ることが重要です。
支給される年金額を調べる方法は簡単です。日本年金機構のねんきんネットを利用すれば、パソコンやスマートフォンを通して年金の加入記録や、支給される年金の目安を知ることができます。
年金手帳などに記載されている基礎年金番号があれば、ねんきんネットにログインできるようになります。支給される年金の目安は、35歳・45歳・59歳のときに封書で送られてくるねんきん定期便からも確認可能です。
参考:ねんきんネット 日本年金機構
生活費と比較した年金の不足額
毎月の生活費の目安と年金の目安が分かると、生活費と比較した年金の不足額を求められるようになります。年金が想定される生活費を下回る場合は、毎月の年金の不足額をどのように補うべきか考える必要があります。
ただし、医療費や不測の事態も考慮する必要があります。年金で生活費をギリギリ賄える状態であっても、油断はせずに余裕を持って考えるようにしましょう。
生活費の不足額を求められたことで、具体的な対策を講じることができるスタートラインに立ったといえます。求めた金額をもとに不足金額を補う方法を検討しましょう。
老後の人生設計におけるお金のシミュレーション
老後の人生設計において生活費の不足額を補ったうえで、長生きリスクを軽減できる方法を解説する前に、人生設計における具体的なお金のシミュレーションをしていきます。
65歳で退職して年金生活をすると仮定したとき、生活費が26万円で、年金の支給額が21万円のとき、生活費の不足額は5万円です。毎月5万円の赤字が続くと、年間の不足金額は60万円になります。
毎月5万円の赤字が寿命まで続いたと仮定して75~100歳まで生きた場合、年金以外に必要になる生活費の不足額を下記にまとめました。
| 年齢 | 不足額 |
| 75歳 | 600万円 |
| 80歳 | 900万円 |
| 85歳 | 1,200万円 |
| 90歳 | 1,500万円 |
| 95歳 | 1,800万円 |
| 100歳 | 2,100万円 |
このように生活費の不足額は長生きするほど大きくなる仕組みです。仮に85歳まで生きるとすれば、1,200万円の資金が必要になります。しかし、自分の寿命は現時点では分かりません。老後の人生設計を考えるうえでつまづきやすいポイントは、自分がいつまで生きるのか分からないため、正確な不足金額を計算することが困難な点があげられます。
よって、どれだけ長寿であっても生活できるように長生きリスクを軽減することが重要になります。
労働による収入も長生きするほど期待できなくなるので、労働以外の方法で考える必要があります。最後に、具体的な長生きリスクを軽減する方法を見ていきましょう。
老後の人生設計における長生きリスクを軽減する方法
老後の人生設計において長生きリスクを軽減する方法は主に3つありますので解説します。
繰り下げ受給などで年金額を増やす
老後の生活費に対して十分な年金が貰えない場合は、年金額を増やす対策が必要です。年金を増やす手段は、新たに年金に関する制度に加入することが挙げられますが、自営業、会社員、公務員などの職業によって年金を増やすために取れる手段は異なります。
共通して受給できる年金を増やせる方法には繰り下げ受給があります。繰り下げ受給とは65歳以上でまだ年金を貰う必要がない方は、年金の受給開始年齢を遅らせることによって、受給開始後の年金受給額を増やせる仕組みです。反対に65歳以前で年金を受給する場合は繰り上げ受給となり年金の受取額が減少します。
繰り下げ受給によって増加する年金の増額率は、昭和16年4月2日以降に生まれた人であれば、(65歳に達した月から繰り下げ申し出月の前月までの月数)×0.7%で求められます。2021年時点では繰り下げ受給ができる年齢の上限は70歳となっているので、増額率は最大で42%です。
年齢が上がるほど労働による収入を得るのが難しくなるので、受給年齢でも問題なく働ける場合は長生きリスクを軽減するためにも繰り下げ受給をおこなってもよいでしょう。年金の受取額を増やせば、生活費の不足額も減少します。
参考:年金の繰下げ受給 日本年金機構
医療保険や貯蓄性の高い保険への加入
長生きリスクには医療費の増加が考えられますが、医療費の増加に備えて医療保険に加入するのも対策の一つです。健康保険や、国民健康保険などの公的医療保険に加えて、民間の医療保険に加入し、医療費が高額になりやすい入院や手術に備えましょう。
また、老後の生活資金を用意する目的で保険に加入するなら、低解約返戻金型終身保険が適しています。こちらの保険は保険料を安くする代わりに途中解約における解約返戻金の額は少なく設定されていますが、保険料の払い込み期間が終わると解約返戻金が増加するため貯蓄性の高い保険です。
老後の人生設計における長生きリスクを軽減するなら、できる限り早い段階で保険の見直しもしておきましょう。
リスク性資産を保有する
リスク性資産とは購入した金額よりも価値が上下する可能性がある株、投資信託などの資産のことです。長期保有を前提に資産を保有することで、利用する予定がない貯蓄を増やす効果が期待できます。
例えば、300万円相当のリスク性資産を保有して、年間の利益が購入金額の3%であった場合、9万円の利益が発生します。追加で資産を購入した結果、資産の評価額が500万円になり、同様に3%の利益が発生すると利益も15万円に増加します。
リスク性資産であるため元本割れのリスクもありますが、短期的に売却する予定がなく、長期的に上昇することが期待される資産であれば、老後の資金準備に利用できます。
老後まで保有を続け、生活費が不足した段階で売却することで資金が用意できます。株式などの資産であれば評価額に対して決められた割合の配当が受け取れる場合があるので、配当収入で生活費の不足金額を補うことも可能です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
老後の人生設計ができない方は、老後の生活を想像し、どのような生活を送りたいのかを考えることから始めてみましょう。目的が明確になれば実現するために必要な方法も見えてきます。
具体的な方法を考える際は、老後の生活費や年金の支給額の目安を把握しましょう。労働による収入の減少や、医療費の増加などの長生きリスクを踏まえたうえで、どのように生活費の不足金額を用意し、長生きリスクを対策するかが重要になります。
まずは、ノートやエクセルを開いて、自分の思う人生設計を実際にアウトプットすることから始めてましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
老後の人生設計ができない理由は?
人生設計をする上で考えておくべき費用は?
長生きリスクとは?
長生きリスクを軽減する方法は?
私的年金制度は公的年金に上乗せし保険料を支払うと受給できる、任意で加入する年金制度です。ホゥ。