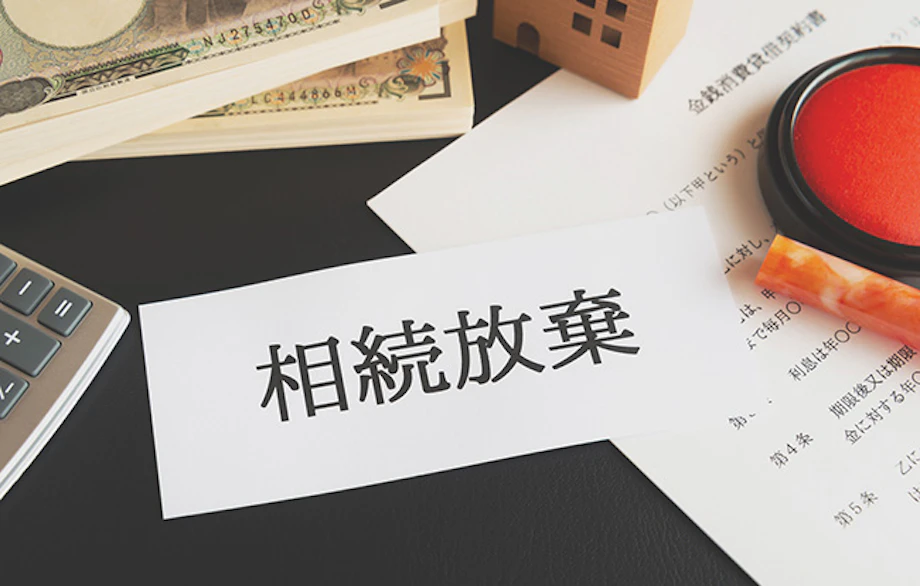お葬式も終わり、ようやく一段落付いたところで行わなくてはいけないのが相続に関する手続きです。遺産相続は「争族」といわれるほど、手間や時間がかかるものだと言えます。経験がないだけに、どのような手続きをすればよいのか分からないという人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、相続の中でも相続放棄について詳しく解説します。相続放棄と財産放棄の違いや手続きに必要な準備までご紹介しますので、読んでおくことで相続放棄のお悩みを解決できるでしょう。
<この記事の要点>
・相続放棄とは「法的に相続を放棄すること」で、マイナスの遺産も放棄することを指す
・財産放棄は相続人とみなされるため、負債があった場合は継承することになる
・相続放棄の手続きは、家庭裁判所に必要書類を提出して行う
こんな人におすすめ
遺産の相続放棄とは何かを知りたい方
相続放棄の手続き方法について知りたい方
遺産の相続放棄をするときの注意点について知りたい方
遺産の相続放棄とは
遺産の相続は、何度も経験するものではありません。分からないことや初めてのことが多く、対応に困ってしまう人も少なくありません。
遺産の相続には相続放棄という方法があります。言葉だけは知っていてもどのような手続きが必要で、どんなメリットやデメリットがあるのか知らない方も多いのではないでしょうか。遺産の相続放棄とはどのようなものかについて、詳しくご紹介します。
相続放棄とは「法的に相続を放棄すること」
相続放棄とは「法的に相続を放棄すること」を指します。相続をする人が遺産の相続を放棄するという意味で、被相続人の負債が多い場合などに利用される手続きです。
遺産の相続放棄は、相続すべき一切の財産を放棄することなので、プラスの遺産もマイナスの遺産も放棄することになります。相続を放棄することで借金を負う義務がなくなり、最初から相続人ではなかったとみなしてもらえるのです。
相続人に該当しなくなるため、代襲相続(相続人が亡くなっている場合に孫などが相続財産を受け継ぐこと)も発生しません。
財産放棄との違いは?
財産放棄は法律上認められている制度ではありません。相続放棄は民法上で認められている制度であるため、家庭裁判所へ申述しますが、財産放棄の場合は相続人全員で遺産分割協議を話し合いで行います。
相続放棄の手続きを行うと初めから相続人ではなかったとみなされ、借金などの負債は承継しません。しかし財産放棄の場合は相続人であることに変わりはないので、負債があった場合は継承することになってしまいます。
相続放棄のメリット
相続放棄の最大のメリットは、負債を引き継がなくてもよいということです。莫大な借金があったり、大きな金額の保証人になっていたりする場合には、プラスの遺産を相続しても最終的にマイナスになることがあります。負の財産の方が多い場合は、相続放棄を行うことで負債を承継する必要がありません。
また被相続人の金融機関に関する手続きなどは、相続人全員の印鑑証明などが必要です。相続放棄を行っている相続人がいれば、最初から相続人ではないとみなされるので、手続きが簡単になるというメリットもあります。
相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットは2つあります。1つ目は、相続放棄の手続きを撤回できないことです。仮に相続を放棄した後にプラスの遺産があることが分かったとしても、相続放棄を一度行ってしまうと相続権を復活させることはできません。
2つ目は、すべての財産を放棄しなければいけないということです。仮に相続人が住んでいる家が相続財産であった場合は、家を明け渡さなくてはいけなくなります。相続を放棄したことが原因で、住む家を失ってしまう可能性もあるので注意が必要です。
限定承認という方法もある
限定承認とは、マイナスの財産があった場合、相続したプラスの遺産の範囲までしか相続しないという制度です。裁判所への申述が必要で、相続人全員が限定承認を行わなくてはいけません。
単純承認と限定承認をする相続人がいることは認められませんが、限定承認と相続放棄をする相続人がいる場合は、申述が可能になります。限定承認は不動産を残すことができる、借金を負わなくてもよいなどのメリットがある制度です。
相続放棄の手続き方法
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して行います。基本的には弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが多いですが、手続きの一連の流れについて知っておくことで、準備がスムーズに行えるでしょう。
ここでは、相続放棄の手続きについて詳しく解説していきます。
相続放棄のやり方と流れ
相続放棄の流れは以下のようになっています。
1.相続人と財産の調査を行う
2.必要書類を揃える
3.管轄の家庭裁判所を確認する
4.相続放棄の申述書を作成する
5.管轄の家庭裁判所に申述書を提出する
6.家庭裁判所から送付された照会書(質問状)を返送する
7.相続放棄申述受理通知書が届く
注意が必要なのは、照会書の回答です。回答の内容によっては相続放棄が却下されてしまう可能性もあります。管轄の裁判所によって必要書類や書式が異なることがあるので、事前に調べておくとよいでしょう。
相続放棄の必要書類
相続放棄の手続きに必要な書類は、被相続人との関係性によって異なります。ここでは最も多い配偶者の場合と、子供の場合に必要な書類をご紹介します。
1.相続放棄申述書
2.被相続人の住民票除票
3.申述人(相続人)の戸籍謄本
4.800円分の収入印紙
5.定形郵便物の切手代(82円を5枚程度)
6.被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本
住民票の除票や死亡の記載されている戸籍謄本などは、手続きを行わないと入手することができません。葬儀などでバタバタしてしまう時期ではありますが、相続放棄の手続きを行うのであれば、早めに準備をしておくことも重要です。
相続放棄に必要な費用
相続放棄に必要な費用は、自分自身で手続きを行う場合と、弁護士や司法書士に依頼する場合で総額が変わってきます。
1.自分で行う場合:3,000円~5,000円程度
2.弁護士に依頼する場合:50,000円~
3.司法書士に依頼する場合:30,000円前後
弁護士や司法書士に依頼する場合には、相談料や代理手数料がかかるのが一般的です。しかし慣れない書類への記載などを考えると、専門家に依頼した方がスムーズに手続きが行える場合もあります。
相続放棄申述書の記入方法
相続放棄の手続きに必要な相続放棄申述書は、初めて目にする人の方が多いかもしれません。相続放棄申述書は2枚あり、家庭裁判所でもらうかパソコンで書式をダウンロードするか、どちらかの方法で入手します。
相続放棄申述書の1枚目は相続人の情報を記載するので、指定された内容を書けば問題ありません。2枚目は相続を放棄する理由や、相続財産の概略を記載する必要があります。放棄の理由は選択肢の中から近いものを選べば問題ありません。相続財産の概略は資産と負債に分けて記入します。
相続放棄受理証明書とは
相続放棄受理証明書とは、裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきた後に発行することができる証明書です。裁判所が正式に相続放棄を認めたという証明になります。
通知書とは異なり、証明書の場合は自分で申請をしなくてはいけません。通知書が送付されてくるときに、証明書の申請用紙が同封されているので、記入して返送しましょう。
証明書が必要になるケースは債権者への対応と、他の相続人が行う名義変更です。通知書は正式な書類ではないので、手続きが必要な場合は証明書を取得しておきましょう。
遺産の相続放棄ができるのはいつまで?
遺産の相続放棄には期限があります。葬儀や後片付けなどで忙しい時期ではありますが、期限内に手続きを行わなければいけません。相続人が多い場合には、全員の協議が必要になりますので、早めに準備を行う必要があります。
相続放棄に定められた期限はどのくらいなのか、過ぎてしまった場合はどのように対処すればよいのかを解説します。
期限は3か月
相続放棄の期限は、相続開始から3か月以内です。この期間に手続きを行わないと単純承認(資産も負債もすべて相続する)とみなされてしまうので、大きな負債があった場合は、借金の返済に追われてしまうことになります。
多くの場合は四十九日までに遺産の調査を行い、相続人が集まるタイミングで協議を行います。葬儀のときに四十九日の法要を併せて行う場合には、改めて話し合いの場を設けなくてはいけません。
3か月を過ぎてしまった場合
期限の3ヶ月を過ぎてしまいそうな場合は、管轄の家庭裁判所に申述期間伸長の申し立てを行うことで、期間を延ばすことが可能です。
遺産の調査に時間がかかったり、相続人との話し合いが難航したりすることがあります。この3か月という期限は「熟慮期間」とされているもので、遺産の相続に時間がかかることを見越して設定されているのです。
万が一3か月の期間が過ぎてしまった場合には、なぜ過ぎてしまったのかという理由を裁判所に申し立てなくてはいけません。この場合は法的な判断が難しいため、自分で行うのではなく弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
遺産の相続放棄をするときの注意点
遺産の相続放棄を行うときには、いくつかの注意点があります。被相続人に負の遺産が多い場合などでは相続放棄は有効な手段ですが、法的に認められた制度だからこそ注意点をしっかりと理解しておくことが大切です。
初めてでよく分からないという人も多いですが、自分にとってマイナスとならないためのポイントを4つご紹介します。
相続権は次の相続人に移動する
相続人が相続放棄を行うと、相続権は次の相続人に移動します。相続放棄の手続きは、最初から相続人として存在しなかったとみなされるので、次に相続人がいる場合は注意が必要です。
両親が存命で、家庭を持った息子が先に他界したケースでは、妻と子供が相続放棄をした場合、相続権は両親に移動します。仮に大きな負債がある場合などは、債権を両親が相続してしまうことになるのです。
相続権の移動は1回ではありません。自分が相続放棄をすることでどのように権利が移動するのかを、きちんと調査しておくことがポイントです。
相続放棄は被相続人の生前にはできない
相続放棄は、被相続人が生きている間は行うことができません。仮に莫大な負債があることが分かっていても、被相続人が死亡しない限り裁判所で認められないのです。
被相続人が莫大な借金を背負っていることが分かっている場合などは、生前に債務整理を行っておくなどの対処法があります。ただしこれは相続人が行うことではなく、被相続人が自分で行う手続きです。
相続放棄という手続きは、被相続人が亡くなってから行うものだということを理解しておきましょう。
相続放棄が認められないこともある
相続放棄は手続きをすれば誰でも認められるということではありません。中には申述が却下されることもあります。
1.申述の期限を過ぎている
2.勝手に処分した財産がある
3.提出書類に不備がある
4.相続人本人(もしくは代理人)が申述していない
裁判所は法的な手続きを行うため、少しでも不備があれば許可はしません。また自分たちに都合の良い財産だけを処分していたことが分かれば不正と見なされますので、注意しましょう。
相続放棄の撤回は不可
相続放棄は一度認められてしまうと、撤回はできません。負債だけかと思っていたら後日資産が発見されたという場合でも相続放棄をした以上、権利は消滅しています。
相続人以外の人間が勝手に行った場合など、詐欺や不正の可能性がある場合は別ですが、相続人が自ら行った申し立てに関しては、撤回ができることはほとんどありません。
相続放棄を考えるときには、遺産の調査を慎重に行いましょう。被相続人と疎遠になっていたり、生前の資産の状況を詳しく知らなかったりする場合は、さらに注意が必要です。
【ケース別】相続破棄と財産放棄、どちらを選ぶべき?
遺産を放棄する方法は、相続放棄と財産放棄があります。似たような名称ですが、内容が異なり、ケースによっては相続放棄をしない方が良かったということも起こりえるのです。
ここではケース別に相続放棄と財産放棄、どちらを選ぶべきなのかを解説します。双方のメリット・デメリットを知り、損のないようにしましょう。
借金がある場合
被相続人に借金がある場合は、相続放棄が適しています。資産と負債を計算し、明らかに負債の方が多い場合は相続放棄をすることで債権の相続を防ぐことができます。
親であってもどのくらいの資産があって、どの程度の負債を抱えているのかということは、生前では分かりにくいものです。銀行口座の数や生命保険の契約など、かなり細かく調査する必要があるので、時間をかけてしっかりと計算することが重要と言えます。
財産がある場合
資産から負債を引いても財産が残る場合には、単純承認(資産も負債も相続すること)が一般的です。
しかし、本当に負債がないかどうかを調べなくてはいけません。一度単純承認を行ってしまうと、仮に何年か後に負債が判明したという場合でも、相続放棄はできない決まりになっています。
相続した時点ではプラスでも、後々トラブルがあってマイナスの方が多かったと判明する事例は少なくありません。財産があると思っていても、安易に単純承認を行うことは避けた方が賢明です。
相続の内容が明確でない場合
資産や負債がいくらあるのか、保証人になっていないかなどが分からない場合は、相続放棄ではなく、限定承認が適しています。
限定承認とは負債が資産を上回った場合、資産の範囲内で相続を行うというものです。限定承認であれば、負債の方が多いと分かった場合でも、借金を背負うことはありません。
親族の知らないところで他人の保証人になっていたり、借金がかさんでいたりということも考えられます。明確な金額が分からない場合は、注意が必要です。
共有財産がある場合
被相続人との共有財産がある場合は、相続放棄を行うことは避けましょう。この場合は限定承認がおすすめです。
共同名義の不動産の場合、仮に相続放棄を行ってしまうと住む家を失ってしまったり、売却ができなかったりということにもなりかねません。限定承認は、他の相続人が単純承認できないので、親族間での話し合いが重要になります。
会社を継ぐ場合
被相続人が経営していた会社を継ぐ場合は、貸付金債権があるかどうかを確認しましょう。
相続放棄をした場合は、貸付金債権も放棄したとみなされますが、相続した場合は相続税が発生する対象です。社長として会社に貸付を行っていた場合には、返済の権利を得られます。その反面、返済された金額に対しては相続税が課されるので、金額が大きい場合には注意が必要です。
遺産の相続放棄に関するQ&A
遺産の相続放棄に関する概要はつかめているとしても、個々のケースがどのようになるのかという点は、疑問として残ることがあるでしょう。ここでは遺産の相続放棄に関するQ&Aをご紹介します。
ご自身の状況に照らし合わせて、あてはまるものがあればぜひ参考にしてください。
相続放棄したら空き家はどうなる?
相続放棄をしても、空き家に関しては相続財産管理人が決まるまでは管理義務が残ります。
両親が住んでいた家が空き家になり、相続放棄をした場合、固定資産税の支払い義務に関しては相続放棄の権利に含まれます。ただし、空き家に関するトラブルが発生した場合などは、所有者に解決の義務が発生するのです。
遠方に住んでいるなどの場合は、相続財産管理人が決まるまで専門の業者に管理を依頼するなどの対策を講じる必要があるといえるでしょう。
子どもが相続破棄したら孫は相続できないの?
子どもが相続放棄をした場合、孫が相続することはできません。孫が相続することができる代襲相続は、子どもが相続発生より前に死亡していたケースなどが当てはまります。
相続放棄をした場合は、代襲相続は認められません。相続放棄を行うことで、最初から相続人として存在しなかったということになります。そのため、孫に対しても相続の権利は発生しないのです。
甥姪が遺産相続できるケースとは?
甥や姪が遺産相続できるケースは、代襲相続の場合です。法定相続人の優先順位は
1.配偶者
2.子ども
3.両親
4.兄弟姉妹
と定められています。相続開始前に子どもや兄弟姉妹が死亡している場合は、甥や姪に代襲相続の権利が発生することがあります。
しかし2や3の法定相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続ができないので甥や姪が遺産を相続することはできません。
全員が相続放棄したらどうなる?
相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産管理人が選定され、処理を行います。相続放棄をする場合は通常資産よりも負債が多く、借金として残ってしまうことがほとんどです。
被相続人が残した借金を相続人全員が相続放棄した場合、清算時に財産が余れば債権者に配当しますが、まったく残らなかった場合は債権者の泣き寝入りということになります。
清算の結果、資産が残った場合は「国庫帰属」といい、国のものになってしまうことも押さえておきましょう。資産が残っても相続放棄をしている場合は、返還されることはありません。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
相続放棄は借金が多い場合などに有効な手段ですが、撤回ができなかったり相続権が移動したりなど、知らなかったことが原因で不利になってしまうケースもあります。
相続放棄を行う場合は、親族間でよく話し合いを行い、不利になる人間がいないことをきちんと確認する必要があります。また、資産の調査は綿密に行い、不明点が多い場合は専門家に依頼するのも確実な方法といえるでしょう。
3か月という短い期間で答えを出すのは大変かもしれませんが、情報収集を行い有意義な遺産相続となるようにしなければいけません。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
相続放棄とは?
財産放棄との違いは?
遺産の相続放棄ができるのはいつまで?
遺産の相続放棄をするときの注意点はある?
初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。ホゥ。