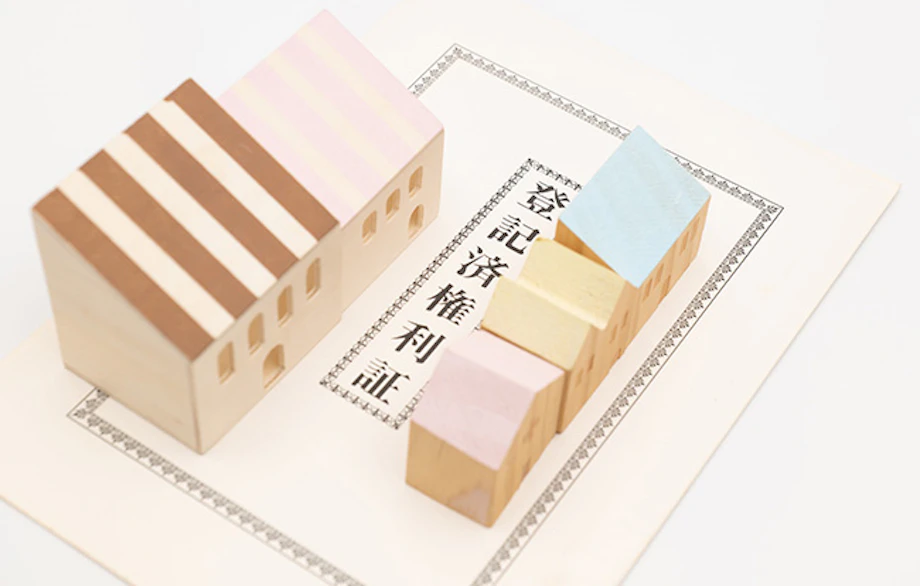亡くなったご家族が土地や建物を持っていた場合、その名義を変える相続登記が必要です。しかし、登記など行ったことがなく、何から手を付けて良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、相続登記の流れやかかる費用、自分で行うデメリットなどについて解説します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・相続登記には登記申請書、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが必要
・必要書類の取得で2万円前後、登録免許税で固定資産税評価額の1,000分の4の費用がかかる
・自分で相続登記をする場合、相続登記の完了が遅くなるなどのデメリットがある
こんな人におすすめ
相続登記とは何かを知りたい方
相続登記をするまでの流れを知りたい方
相続登記を自分で行うデメリットを知りたい方
相続登記の基本を知ろう
相続登記の流れを見る前に、相続登記の基本について知っておきましょう。なかでも期限については、2024年までに施行予定の改正法が成立していますので注意が必要です。
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方の持っていた土地や建物を相続人などの名義へと変える手続きのことです。申請は法務局へ行います。
後ほど詳しく説明しますが、亡くなった方の名義のままではその不動産の売却などができません。
そのため、存命の方へと名義を変える必要があるのです。
相続登記に期限はあるの?
2021年現在、相続登記に期限はありません。しかし、2021年4月に不動産登記法等の改正法が成立したことにより、今後2024年中までに相続登記に期限が設けられることとなっています。
なぜ、法改正を行うことになったのかについて詳しく見ていきましょう。
期限がなかったため登記を放置するケースが散見された
これまで、相続登記に期限はありませんでした。しかし、相続登記をしないと物件の売却ができないなどのリスクがあるため、価値のある不動産は早々に相続登記を済ませる場合がほとんどでしょう。
一方、それほど価値のない不動産や売却の予定がない自宅の不動産などの相続登記は、放置してしまう方が少なくないのも現状です。相続登記が放置された結果、数十年前に亡くなった故人名義のままとなっている不動産が、多数存在することとなりました。
これが、昨今問題となっている「所有者不明土地」が増加した原因の1つです。
3年以内に相続登記をすべき改正がされた
2021年4月に不動産登記法などの改正法が成立し、相続登記に新たに期限が設けられることとなりました。改正法の施行後は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をすることが義務付けられます。
改正法は、2024年4月までに施行される予定です。
所有者が不明である土地は行政などが使用したくとも誰に許可を取って良いかわからず、活用のしようがない土地となってしまいます。こうした問題がある所有者不明土地の発生を防ぐため、相続登記に期限が設けられたのです。
参考:『所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) 法務省』
相続登記を放置することのデメリットとは?
相続登記を放置するデメリットは少なくありません。ここでは、相続登記を放置するデメリットを5つ紹介します。
不動産の売却ができない
亡くなった方の名義のままでは、不動産の売却ができません。当面は売却の予定がなかったとしても、将来的に売却をする際には売却の前にまず相続登記をする必要があります。
不動産を担保に融資を受けられない
亡くなった方の名義のままでは、その不動産を担保に入れて融資を受けることはできません。不動産を担保に入れる際にはその不動産に抵当権の登記がされるのですが、故人名義の不動産にはこの抵当権を新たに付すことができないためです。
抵当権…万が一借金が返せなくなった場合にその不動産を強制的に売却し、売却で得たお金から優先的に借金の返済を受ける権利のこと
一部の相続人に勝手に売却されてしまう危険性がある
相続登記をしなければ、第三者に権利を対抗する(主張する)ことができません。
例えば、相続登記をしないまま放置していると、遺産分割協議で長男がその不動産を取得したにもかかわらず次男が自分の法定相続分だけを第三者に売却したり次男にお金を貸している人が次男の法定相続分を差し押さえたりする可能性があります。
改正後は罰則の対象となる
3年以内の相続登記が義務化される改正不動産登記法等の施行後は、期限内に登記をしないと罰則の対象となります。
罰則は、10万円以下の過料です。
長年放置すれば相続登記がより大変になる
相続登記を長年放置すると、いざ相続登記をしようとした際の手続きがより大変となります。
なぜなら、時間の経過により元々の相続人が亡くなり、関係者が増えていく可能性があるためです。
場合によっては、関係者を探し出して連絡を取るだけでもひと苦労でしょう。
相続登記は、放置することで手続きが楽になることはほとんどありません。年月の経過とともに相続登記に必要な労力も増えてしまうことが大半です。
相続登記をするまでの流れを徹底解説
相続登記をするには、次のステップを踏む必要があります。1つずつ確認していきましょう。
相続の状況を確認する
相続登記の前段階として、まずは相続の状況を確認する必要があります。確認する事項は、次のとおりです。
・遺言書の有無を確認する
相続が起きたらまず、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書の有無により、この先で行うべき手続きが大きく異なってくるためです。
・相続人を確認する
亡くなった方の相続人は誰なのかについても、早期に確認しておきましょう。相続人の確認は、相続登記の必要書類でもある出生から死亡までの連続した戸籍謄本などで行います。
相続人が誰なのかの判断に迷ったら、司法書士や行政書士などの専門家へ相談すると良いでしょう。
・相続財産を確認する
亡くなった方の持っていた財産についても、確認を進めましょう。財産の全体像が見えていなければ、誰が不動産を相続するのか決めづらいためです。財産の数が多い場合には、一覧表などにまとめると分かりやすくなります。
不動産については、次の資料で確認しましょう。
・市町村役場から毎年5月頃に送付される固定資産税課税明細書
・全部事項証明書(登記簿謄本)
全部事項証明書とは、その不動産につき法務局に登録されている情報が載った書類です。全部事項証明書は最寄りの法務局で誰でも取得することができ、一定の手続きを踏めばインターネットから請求することも可能です。
なお、固定資産税課税明細書はあくまでも固定資産税を賦課するための書類であり、不動産の情報が正確に記載されているとは限りません。そのため、固定資産税課税証明書だけで判断せず、全部事項証明書も確認されることをおすすめします。
不動産を相続する人を決める
相続の状態が確認できたら、不動産を誰が取得するのか決定しましょう。不動産を相続する人を決める方法には、主に次の3つのパターンがあります。
・遺言書で決める
亡くなった方が有効な遺言書をのこしており、その遺言書で不動産を取得する人が決まっていれば、原則としてその遺言に従います。
・遺産分割協議で決める
遺産分割協議とは、亡くなった方の持っていた財産を誰がもらうのかについて、相続人全員で話し合うことです。有効な遺言書がない場合には、この遺産分割協議で不動産を取得する人を決めます。
遺産分割協議の成立には、相続人全員の同意が必要です。
・調停や審判で決める
相続人同士では話し合いがまとまらない場合には、調停や審判で不動産を取得する人を決めます。
調停とは、調停委員を交えて家庭裁判所で行う話し合いのことです。調停でも決まらない場合には、裁判官が決断を下す審判手続へ移行します。
参考:『遺産分割調停 裁判所』
相続登記の必要書類を準備する
不動産を相続する人が決まったら、相続登記に必要な書類の準備をしましょう。相続登記の必要書類の詳細については、後ほど詳しく解説します。
登記を申請する
書類の準備が整ったら、法務局に相続登記を申請します。
・相続登記の申請先
相続登記の申請先は、その不動産の所在地を管轄する法務局です。
法務局は各市区町村にあるわけではなく県内に点在していますので、事前に法務局のホームページで管轄を確認してから申請しましょう。
・相続登記の申請方法
相続登記を申請する方法には、次の3つの方法があります。
・窓口へ持参して申請する
・郵送で申請する
・インターネットで申請する
このうち、インターネットは事前の設定や準備も必要となるため、一度登記を行うだけの場合にはおすすめできません。
相続登記に慣れていないのであれば、窓口へ持参しての申請が最も安心で確実でしょう。
相続登記にはどのような書類が必要?
相続登記をするには、さまざまな書類が必要です。ここでは、遺産分割協議で不動産を取得する人を決めた場合の一般的な書類を紹介します。状況によっては別の書類が必要となることもありますので、事前に管轄の法務局へ相談すると良いでしょう。
登記申請書
登記申請書は、相続登記のメインとなる書類です。作成の際には登記事項証明書をよく確認のうえ、正確に作成する必要があります。
法務局のホームページに記載例がありますので、参考にしてください。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果をまとめた書類です。相続登記をする不動産を誰が取得するのかが分かるよう、明確に記載しましょう。
相続人全員が協議内容に同意している証拠として、相続人全員が実印で捺印をします。
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押した印が実印であることの証明として添付します。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本も必要です。これは、亡くなった方の相続人を確認するために添付します。
なお、亡くなった方に子がおらず兄弟姉妹が相続人となる場合などには、亡くなった方の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も必要です。
被相続人の除票または戸籍の附票
除票と戸籍の附票は、いずれも亡くなった方の最後の住所を証明するための書類です。除票は亡くなった方が最後の住所を置いていた市区町村役場で取得する一方、戸籍の附票は最後に本籍を置いていた市区町村役場で取得します。
相続人全員の戸籍謄本
相続人が生存していることの確認として添付します。それぞれの相続人が本籍をおいている市区町村役場で取得可能です。
不動産を相続する人の住民票
不動産を取得する人の住所を正しく登記するために必要です。その相続人の住所地の市区町村役場で取得します。
不動産の評価証明書または評価通知書
相続登記をする際には、登録免許税という税金がかかります。この税金を正しく計算するために、不動産の評価証明書または評価通知書が必要です。
評価証明書や評価通知書はいずれもその不動産の所在する市区町村役場で取得でき、評価通知書は無料で発行してもらえます。
相続登記にかかる費用はどのくらい?
相続登記にかかる費用相場についても知っておきましょう。次のうち、必要書類の取得費用と登録免許税は、自分で登記をした場合にもかかる費用です。
相続登記を司法書士へ依頼した場合には、これに加えて司法書士報酬もかかります。
必要書類の取得費用
不動産登記には、さまざまな書類が必要です。これらの書類を取得する費用は、相続人の人数や相続関係、亡くなった方の転籍回数などにより異なります。
参考までに、相続人が子や配偶者の場合には5,000円から1万円程度、相続人が兄弟姉妹や甥姪である場合にはおおむね2万円前後となることが一般的です。
登録免許税
登録免許税とは、登記申請をする際に支払う必要のある税金です。相続登記の場合の登録免許税は、その不動産の固定資産税評価額の1,000分の4と定められています。
例えば登記をする不動産の固定資産税評価額が2,000万円であれば8万円、5,000万円であれば20万円です。
思いのほか高額となる場合もありますので、心づもりをしておくと良いでしょう。
参考:『No.7191 登録免許税の税額表 国税庁』
司法書士報酬
相続登記の専門家は、司法書士です。自分で登記ができない場合には、司法書士へ相続登記を依頼することになります。
自宅の土地建物のみの相続登記であれば、司法書士報酬は10万円前後となることが一般的です。
この報酬額は事務所によって異なるほか、相続関係や不動産の数などにより料金が変わることがありますので、依頼を検討している司法書士へ個別で見積もりを取ることをおすすめします。
相続登記を自分で行うデメリットとは
相続登記を司法書士へ依頼するか、自分で行うか迷われている方もいると思います。
相続登記を自分で行うメリットは、司法書士報酬がかからない点のみでしょう。一方、相続登記を自分で行う主なデメリットは、次の3点です。
時間と手間がかかる
自分で相続登記をすると、時間や手間がかかります。
申請書の書き方を調べたり必要書類を揃えたりすることに手間や時間が掛かるほか、申請書類の完成までに何度か法務局へ相談に行くことになる可能性が高いためです。
法務局も書類の取得先である市区町村役場も原則として平日の日中しか空いていませんので、時間に余裕があり平日の日中に何度も動ける方でなければ、自分で相続登記を行うことは困難と言えます。
なお、法務局への相談は原則として予約制ですので、あらかじめ予約をしてから出向くようにしましょう。
相続登記の完了が遅くなる
自分で相続登記をする場合には、慣れていない分、申請書類を揃えるまでに時間がかかります。さらに、申請後にも不備が見つかれば、法務局へ出向くなどして補正をしなければなりません。
こうした積み重ねで、司法書士へ依頼した場合と比べて登記の完了が遅くなる可能性が高いでしょう。
そのため、売却を控えているなど相続登記を急ぐ必要がある場合には、自分での登記申請はおすすめできません。
専門家のアドバイスを受ける機会を逃す
通常、司法書士へ相続登記を依頼した場合には、さまざまなアドバイスを受けることが可能です。
例えば、特に争いがない場合、亡くなった父が持っていた自宅不動産の名義を子にすべきか母にすべきかなどといった相談をしたい場合もあるでしょう。こうした相談をしたい場合には、司法書士へ依頼したほうが良いと言えます。
また、相続登記の依頼時は、すでに返し終わったローンの抵当権が残ったままとなっていたり共有者の住所が古いままであったりといった登記上の問題点にも気づいてもらう絶好の機会です。
自分で相続登記をした場合にはプロからこうしたアドバイスを受ける機会を逸する点も、デメリットの1つと言えるでしょう。
家族信託という選択肢もある
相続登記について詳しく知りたい際に、認知症についても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。
ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組成できるサービスです。資産管理にお困りの方は、お気軽にお問合せください。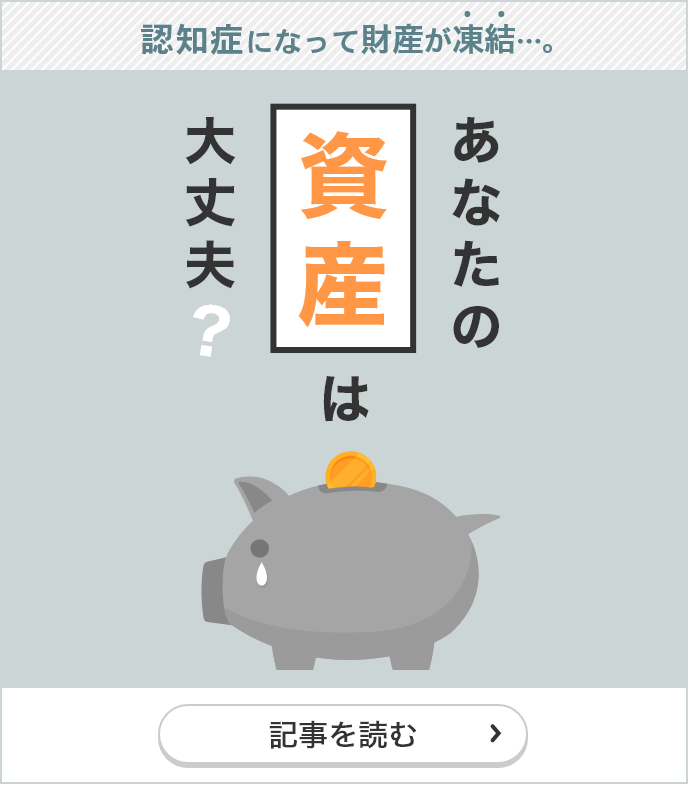
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
相続登記は、時間と手間をかければ自分で行うことも不可能ではありません。
しかし、司法書士へ依頼した場合には手間や時間を削減できるのみならず、プロのアドバイスを受ける機会を得ることにもなります。
こうしたことも踏まえ、自分で行うかプロへ依頼するか検討するようにしましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
相続登記を自分でする方法は?
相続登記を自分で行うデメリットは?
相続登記とは?
相続登記に期限はあるの?
御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。