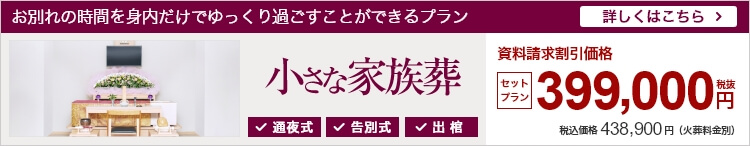既に配偶者が亡くなってしまっていても、家族に介護が必要になれば、嫁の立場ならたとえ義理の父母であっても介護をしなければならないことがあります。しかし、以前はそのような場合にも、義理の父母が亡くなった際に法定相続人でない嫁は遺産を受け取れないというケースが多くありました。
民法改正前は、遺書に指示があれば嫁であっても遺産を受け取ることができましたが、遺書がない場合は受け取る資格が得られませんでした。今回は民法改正によりできた「特別寄与料」について解説をしていきます。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・特別寄与料とは、相続人以外が無償で療養看護などをした場合に請求できる金銭のこと
・特別寄与者になるには被相続人の親族であることが条件
・相続税が発生した場合、特別寄与料の金額が決定した日の翌日から10カ月以内に申告が必要
こんな人におすすめ
特別寄与料とは何かを知りたい方
長男の嫁が特別寄与料を請求するときの注意点を知りたい方
特別寄与料の手続きを知りたい方
特別寄与料とは
民法改正によって、もともとあった「寄与分」という制度に加えて「特別寄与料」というものが設けられました。特別寄与料とはどのようなものでしょうか。
特別寄与料
特別寄与料とは、相続人以外であっても、被相続人への介護やその他労務などの貢献があった場合に、遺産の一部支払いを相続人に対して求めることができる金銭のことです。この制度は民法改正によって新たに設けられました。
介護を行った身内に対して遺産の分配を認める制度としては、以前から「寄与分」というものがありました。しかし、「寄与分」は相続人に対してのみ認められる制度のため、相続人以外が介護を積極的におこなっていたとしても、遺産の分配をすることはできませんでした。また他にも、特別縁故者の制度の活用や準委任契約、事務管理、不当利得などを主張することも可能ですが、それでは不十分と考えられていました。
そこで新たに「特別寄与料」という制度が設けられました。この制度は、相続人以外の人間が被相続人の療養看護や、被相続人財産の維持・増加に貢献したと判断された場合に、遺産分割を考慮することが目的の制度です。
特別寄与料を受け取るには
特別寄与料に関しては、相続をめぐって無用な争いが起きないようにするために、請求できる範囲は被相続人の親族までと限られています。しかし、親族であれば誰でも申請できるというものではなく、一定の要件を満たすことで申請する資格を得ることができます。
その要件というのは「被相続人に対して無償で療養看護などの労務を提供した」というものです。したがって、介護を行った際に何らかの見返りを要求していた場合は「無償」という条件から外れる可能性があります。無償でないと判断されれば、特別寄与料を要求することはできません。
「労務を提供した際、見返りはあったが利益が極端に少なかった」「療養看護する前から被相続人から生活費を受け取っていて、介護生活になってからも同様に生活費として負担してもらっていた」などの場合は労務提供の対価として認められないので、特別寄与料の請求者の範囲とみなされます。
特別寄与料の額
特別寄与料の金額については、基本的には当事者間の協議によって決められます。しかし協議で決まらない場合や、そもそも協議ができない場合は、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができると定められています。
家庭裁判所は寄与の時期、方法、程度、相続財産の額や、その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。その場合は、一般的な療養看護の日当額に日数をかけて、さらに一定の裁量割合を乗じるといった計算が行われます。
また、「特別寄与料の額は、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない」と定められています。
有効期間
相続関連のトラブルが長期化しないように、特別寄与料の審判について比較的短期間のみの権利行使を認めるという取扱いになっています。具体的な期間として「特別寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6カ月を経過したとき、または相続開始のときから1年を経過したとき」と定められています。
特別寄与料が作られた理由とポイント
特別寄与料については、利用する前に知っておきたい条件があります。制度として設けられた背景も併せて確認しましょう。
寄与分の問題点
前述の通り、改正前でも「寄与分」というものがありましたが、これが適用できるのは相続人に限定されており、長男の嫁や孫などが介護に貢献していても遺産を受け取ることはできませんでした。改正前は、長男の嫁が療養看護などで貢献した場合、長男の寄与分として調整するというような対応が取られることもありました。
しかし、この対応では長男が先に亡くなってしまった場合、遺書によって指示がなければ長男の嫁が遺産を受け取ることができません。そこで民法が改正された2019年7月1日以降の相続については、特別寄与料の制度が設けられることになりました。
そのため、相続人以外の親族でも被相続人に対して特別な寄与をすれば、貢献に応じた特別寄与料を請求できるようになりました。
特別寄与者になる条件
特別寄与者になるためには2つの条件を満たす必要があります。まずは「被相続人の親族であるということ」という条件がありますが、これは具体的に「被相続人から見て6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族である」ということです。このとき、内縁の妻は介護をしていたとしても対象にはならないので注意が必要です。
もう1つは「被相続人に対して無償で労務を提供したことにより被相続人に対しての財産の維持または増加に影響を与えたことが証明できる」ことです。介護以外でいえば、「被相続人の行っていた事業を無償で手伝っていた」などが含まれます。
前述の通り、無償での行為に限定されるので、労務に対して謝礼金や労務の対価などを受けっている場合は特別寄与者の対象にはならないことに注意が必要です。
長男の嫁が特別寄与料を請求するときの注意点
特別寄与料を請求する際には、注意するべき点がいくつかあります。ここではその注意点について紹介していきます。特別寄与料を請求する予定がある方や可能性がある方は、こちらを参考にして準備を始めておきましょう。
期限がある
家庭裁判所に協議に代わる審判を申し立てる場合は、前述の通り請求に期限があります。その期限は、特別寄与者が相続開始を知ってから6カ月以内もしくは相続開始から1年です。しかし、当事者同士でおこなう場合、期限はありません。
相続税が発生する場合がある
特別寄与料を受け取ると、それは被相続人からの「遺贈」と同じ扱いになってしまうので、同様に相続税が発生します。申告期限は「特別寄与料の金額が決定した日の翌日から10カ月以内」と定められているので、遺産が基礎控除を超える場合は早めに申告しましょう。
なお、基礎控除とは所得税や住民税の計算をするときに、納税者の所得から一律で差し引かれる所得控除の1つです。基礎控除は他の所得控除のように個々の事情によって変わるものではなく、どのような場合でも一律に適用されるので覚えておきましょう。
証拠が必要になる
基本的には、相続人が納得して支払いを渋るようなことがなければ、証拠を提出する必要はありません。しかし、特別寄与料を請求したときに相続人が支払いに納得できなければ、寄与の証拠を提出して支払いを促す必要があります。
ここでの証拠には、介護に関わる日誌や写真、病院に付き添った際の資料、介護に要した買い物の記録、立替支出に関する出納帳などが挙げられます。したがって、義父母の介護に携わっている場合は、特別寄与料の請求があることも視野に入れて、記録を残しておくとよいでしょう。
トラブルになりやすい
相続人以外の親族が相続人へ特別寄与料を請求する場合、トラブルへ発展する可能性は十分に考えられます。いざ遺産の話になると、相続人が支払いを渋ったり金額の折り合いがつかなかったりと、様々なトラブルにつながることがあります。
トラブルを避けるためには、先ほども紹介した通り労務の証拠を取ったり、相続人へあらかじめ相談しておいたりするとよいでしょう。他にも専門家に相談しておくと、トラブルの回避につながるかもしれません。
特別寄与料の手続き
前述の通り特別寄与料はできたばかりの制度のため、手続きの仕方がわからない方もいることでしょう。ここからは、特別寄与料を受け取るための手続きについて紹介していきます。
原則は協議で決める
特別寄与料は特別寄与者と相続人が直接協議をして決めることが原則です。主に金額や相続人ごとの負担の割合など、基本的には特別寄与者と相続人の間で決めていきます。この話し合いで決められることが最も理想的です。
家庭裁判所に手続きを依頼する
協議で決まらない場合は、家庭裁判所で決めてもらう必要があります。その際、まずはどこの裁判所で手続きするかを決める必要があります。基本的には「被相続人の最期の住所」を管轄する家庭裁判所に依頼することが多いですが、相続人と相談して決めたほうがよいでしょう。
調停と審判
家庭裁判所で行う手続きには「調停」と「審判」の2種類があります。まず、調停とは裁判所のもとで当事者同士が再度話し合いを行います。審判は当事者から事情を聴き取り、証拠と照らし合わせながら特別寄与の有無や金額を決めていきます。
離婚のような場合とは異なり、特別寄与は調停を経ずに審判手続きから開始することもできます。相談者との状況を検討して決めるとよいでしょう。
専門家へ相談する
相続人の中には、特別寄与者を快く思わない人も中にはいるでしょう。その場合は親族間へのトラブルへと発展してしまい相続の問題が完結してもその後の親戚付き合いや関係性に大きな影響が出てしまう場合が多くあります。
そんなときに有効なのは、第三者に入ってもらい冷静に判断をしてもらうことです。特に弁護士のような専門家に依頼・相談することで、手続きの正しい進め方や資料の作成・準備、さらには相続人との関係についてのアドバイスをしてもらうこともできます。相続人との関係が拗れる可能性が少なくなるため、おすすめです。
他にも、代理人として相続人と協議を行ってもらうことも可能です。特別寄与料に限らず、相続の問題は専門的な知識を要求されることが多くあるので、早めに弁護士などの専門家に依頼して話を進めていくことが重要です。
家族信託という選択肢もある
相続について詳しく知りたい際に、認知症による口座の凍結などについても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。
ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組成できるサービスです。資産管理にお困りの方は、お気軽にお問合せください。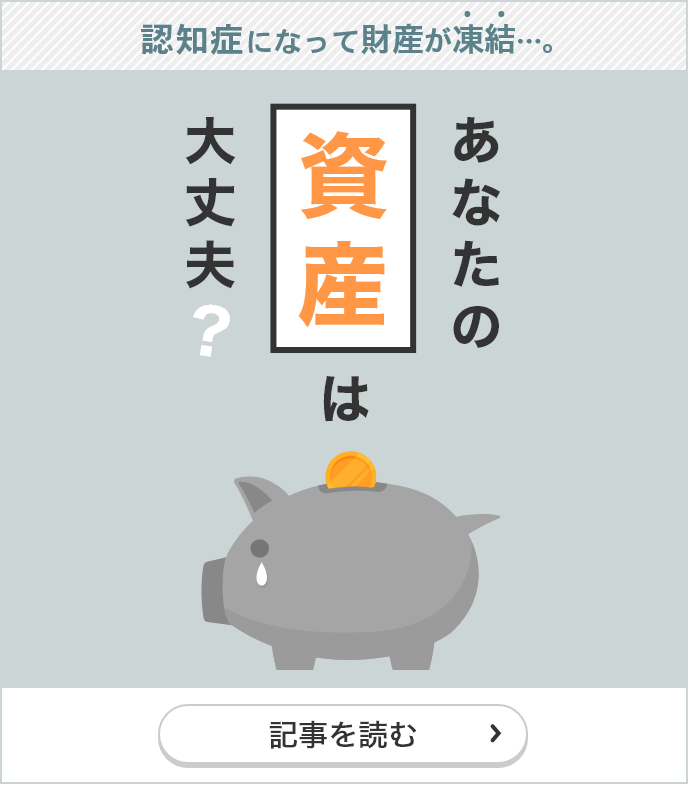
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
今回は、特別寄与料について解説しました。血がつながっていなくても、被相続人のために療養介護を行ってきた長男の嫁や孫は遺産を受け取る権利が十分にあるでしょう。特別寄与料はそのような方が損をしないために設けられた制度になので、しっかりと把握して利用することが重要です。
しかし、手続きには期間があるので、早めに専門家へ依頼をして手続きを正しく進める必要があります。相続人との関係が悪くならないようにアドバイスをもらいながら、円滑に相続を進めていきましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
特別寄与料とは?
特別寄与料を受け取る条件は?
長男の嫁が特別寄与料を請求するときの注意点は?
特別寄与料を受け取るための手続き方法は?
四十九日法要は、故人が亡くなってから48日目に執り行います。ホゥ。