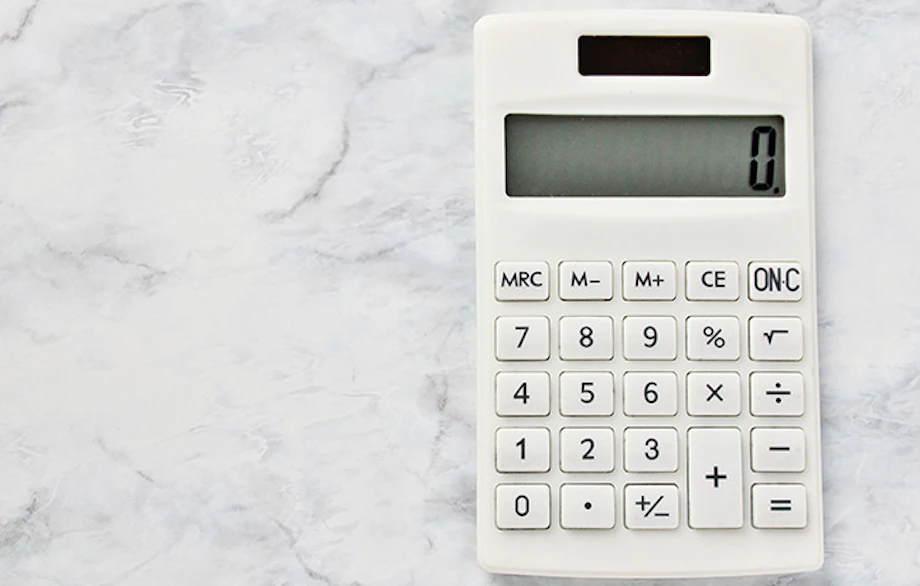昨今、経済的な負担が大きいことや核家族の増加が原因で、お墓の管理まで手が回らないという方もいるでしょう。そんな方におすすめな供養の方法として、合祀墓(ごうしぼ)というものがあります。
しかし、合祀墓のことを詳しく知る方はそう多くはないでしょう。合祀墓の具体的な供養方法がわかると、遺骨をいざ合祀墓に移すときにスムーズかつトラブルなく進行できるでしょう。
この記事では、合祀墓の費用や種類、長所や短所について解説します。現在、合祀墓について疑問を抱えている方はぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・合祀墓とは、不特定多数の方の遺骨を一ヵ所に統合して埋葬するお墓のこと
・合祀墓に必要な費用は3万円~30万円程度
・合祀墓には、自然を感じながら参拝できる「野外型」と天候を気にせず参拝できる「室内型」がある
こんな人におすすめ
合祀墓について知りたい方
合祀墓の費用や種類を知りたい方
合祀墓の長所や短所を知りたい方
合祀墓とは
合祀墓とは、不特定多数の方の遺骨を一ヵ所に統合し埋葬するお墓のことを指します。お墓の形は、寺院や霊園によって多種多様なものが存在します。別称として「合葬墓」や「合同墓」とも呼ばれています。
遺骨を骨壷から取り出して、複数人の遺骨を1つに統合するタイミングには種類があります。遺骨を最初から合祀墓1箇所にする方法もあれば、所定の時間は永代供養墓などで供養して、その後1箇所に統合する方法もあります。
合祀墓を選ぶ理由
合祀墓は、よく目にする個別のお墓とは違い、不特定多数の方の遺骨が一緒に統合されています。個別のお墓ではなく、合祀墓を選ぶことには何かしらの理由があるでしょう。
合祀墓が選ばれている一般的な理由を知る中で、自身の家庭環境に即した理由も見つかるかもしれません。ここからは合祀墓を選ぶ理由を1つひとつ解説します。
継承者がいないから
お墓の継承者がいないことが理由で合祀墓を選ぶ方も一定数います。継承者のいないお墓や所定の時間管理がされていないお墓、維持費が支払われていないお墓は「無縁墓」として扱われ、それと同時に遺骨も無縁仏として扱われてしまいます。
昨今、少子化などが影響して、無縁墓や無縁仏はどんどん増加しています。継承者のいないお墓の管理を任せるために、遺骨を合祀墓へと移動させる方も多くなっています。
維持費を支払えないから
お墓の維持費は決して安くなく、毎年支払うとなるととても大きな出費になります。また、新しくお墓を建立する場合は、その維持費に対してさらに100万円~300万円の費用を支払わなければいけません。そのため「お墓に対して多額の費用を払いたくない」と考える方もいるでしょう。
しかし、合祀墓であれば毎年支払う維持費がなくなるので、経済的にも余裕が出てきます。このような理由から、合祀墓を選ぶ方が増えています。
お墓の維持が面倒だと感じている
一昔前までは「自分の家系で代々受け継がれてきたお墓を管理するのは、子孫や後継者として当然だ」という考え方が一般的でした。
しかし、昨今その考え方は薄れていき、それに伴いお墓を管理しなければいけないという責任感も薄れているでしょう。管理する責任を感じていないのに、半永久的にお墓を管理し続けるのは楽ではありません。
合祀墓に遺骨を移動してしまえば、自分で管理することがなくなるため精神的にも体力的にも楽になるでしょう。
子孫に負担をかけたくない
お墓の運営や管理、維持はそう簡単なことではありません。そのため、お墓の継承は自分の代で終わらせて、後継者には負担をかけさせたくないと考える方は少なくありません。その要望を叶えるために遺骨を合祀墓に移動させる方が多いようです。
合祀墓に参拝する方法
合祀墓の参拝方法は個別のお墓と同じで、お墓の前に立ち手を合わせてお参りをします。ただし、不特定多数の方の遺骨が納められているため、参拝する部分や線香、お供え物を備える場所は共同です。
注意点として、霊園や寺院によっては線香やお供え物を備えることが禁止されていることが一般的です。そこで、霊園や寺院などがどういった方針であるかを事前に確認しておきましょう。
寺院の住職や霊園の管理者が「施餓鬼法要」や「彼岸法要」を行う場所もあります。宗教によっては「永代経法要」や「報恩講法要」「御会式」などが行われたり、檀家や信徒が集まって同時に供養したりする場合もあるようです。
合祀墓の費用
合祀墓に遺骨を納めるときにかかる費用は3万円~30万円ほどです。一方で、個別で供養するお墓の費用は150万円ほどが目安です。両者を比較すると、合祀墓は手が出しやすい金額といえるでしょう。
合祀墓にかかる費用の内訳は以下の通りです。
・永代供養料
・納骨料
・彫刻料
永代供養料とは、管理者に遺骨を未来永劫供養してもらうことにかかる費用です。また、納骨料は遺骨を納めるときの手数料で、彫刻料は墓誌に故人の名前を刻むときにかかる費用です。
戒名を授けられたり、所定の期間で個別に供養してもらったりする場合は追加で費用がかかります。参考として、所定の期間、個別で供養してもらうときにかかる費用の目安は50万円ほどになります。
追加で費用がかかる理由は、遺骨が1つひとつ丁寧に供養されるためです。なお、個別で供養してもらう場合の具体的な期間は、年忌法要が行われる13年や33年に設定されることが一般的です。
永代供養料に関しては地域や霊園等によって金額の幅が大きく変動するので、自身のところはどのくらいの価格帯かを確認しておくことが重要です。
合祀墓の種類
合祀墓にはさまざまな種類があるため、どの合祀墓を選べばよいのか迷う方もいるでしょう。ここからは、合祀墓の種類を1つひとつ解説します。
野外型
野外型はその名の通り、屋外に建てられた合祀墓のことです。代表的な例として、以下のようなものがあります。
| ・慰霊碑型 |
| 慰霊碑型とは、納骨されている場所の直上に、石碑や仏像等のモニュメントが建てられているお墓のことです。 |
| ・樹木葬型 |
| 樹木葬型とは、墓標が石ではなく樹木でできているお墓のことを指します。墓石の代わりに樹木を植え、その下に遺骨を納骨する方法を取ります。 |
野外型はどの型も草木などに囲まれているため、自然を感じながら参拝できます。短所としては、雨や風の日には参拝がしにくいところです。
室内型
室内型の合祀墓は、交通の便が充実している場所に建立していることが一般的です。例として、以下のようなものがあります。
| ・納骨堂型 |
| 納骨堂のように屋内が堂になっており、そこへ不特定多数の方の遺骨が統合され納められています。 |
| ・個別集合型 |
| サイズの大きな墓標の周りに個別で供養できる空間があり、そこへ各々の遺骨が納められます。個別で所定の期間供養された遺骨は、その後は統合され、まとめて供養するところへと移されます。 |
| ・区画型 |
| コインロッカーのように仕切られた空間に遺骨が納められます。コインロッカータイプの他にもボタンで操作できる種類もあり、地域によってさまざまです。 |
上記の例は全て室内に設置されているので、雨や強風の日でも参拝することが可能です。親族の中に足が悪い方がいる場合は、屋内型にすることをおすすめします。
合祀墓の長所
合祀墓を選ぶ長所は以下の通りです。
・継承者を必要としない
・費用を抑えられる
ここからは1つひとつ解説します。
継承者を必要としない
合祀墓は継承者を必要としないため、継承者がいない場合でも供養をしてもらえることが長所として挙げられます。加えて、寺院の住職等が供養をし続けているので、無縁墓になる心配もありません。
昨今、少子高齢化に伴い継承者がいなくなる家庭が多いですが、合祀墓にすることでその悩みが解決できた方も少なくはないでしょう。
費用を抑えられる
合祀墓の長所として最も多く挙げられているものが費用を抑えられるということです。合祀墓は永代使用料がかからないうえに、新しくお墓を建立する費用もかかりません。
一般的なお墓にかかる費用が合計して200万円前後なのに対し、合祀墓にかかる費用は3万円~10万円ほどです。
昨今では経済的な面で不安を抱えている方が増えているため、この点は大きな長所となるでしょう。
合祀墓の短所
合祀墓には長所がある一方で、以下のように短所も存在します。
・2度と遺骨を取り出せなくなる
・他の人と一緒に埋葬される
短所を理解しておくことで、後々のトラブルを回避できるでしょう。1つひとつ解説します。
2度と遺骨を取り出せなくなる
一度合祀墓に遺骨を納めたのはいいが、気が変わり普通のお墓に戻したくなったと考える方もいるかと思います。しかし、合祀墓は不特定多数の遺骨と合わせて埋葬するため、一度納めてしまうと2度と取り出せなくなる可能性が高いでしょう。
とはいえ、個別で供養されている期間内であれば、管理人に頼んで取り出してもらうことができるかもしれません。その場合は相談してみるとよいでしょう。
他の人と一緒に埋葬される
不特定多数の方の遺骨と一緒に埋葬されるため、ご先祖様のことをより強く思うなら個別のお墓に納めてあげたいという方もいるでしょう。そのような方にとっては、合祀墓に遺骨を納めること自体に抵抗を感じているかもしれません。そこで、親族間で話し合ってから合祀墓に納めるようにしましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
昨今、経済的な負担や核家族の増加が原因で、故人の遺骨を合祀墓に移す家庭が増えてきています。合祀墓とは、不特定多数の遺骨を統合して納骨するお墓のことを指します。費用は3万円~10万円で抑えられるため、普通のお墓に比べると安価といえるでしょう。
合祀墓の長所は、上記のように費用が抑えられることと、継承者を必要としないことです。一方で短所には、一度納骨されたら2度と取り出せない、不特定多数の方の遺骨と統合されてしまうといったものがあるでしょう。
合祀墓はご自身の家庭環境と照らし合わせて、本当に必要と思った場合に利用しましょう。お墓の扱いについては、個人で判断できないことが多いです。家族やお世話になる霊園の意見も聞く必要があるでしょう。判断に悩み、どうしたらよいかわからないときは小さなお葬式へご相談ください。専門知識をもったスタッフがご対応いたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


葬儀の挨拶では、不幸を連想させてしまう忌み言葉と重ね言葉には気をつけましょう。ホゥ。