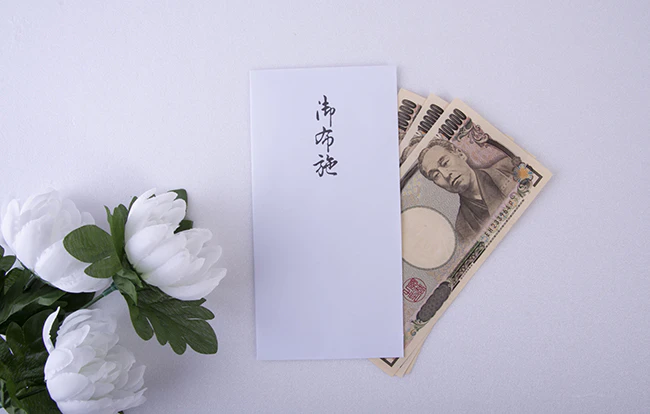墓じまいをしたあと、遺骨はどうやって供養するのでしょうか。遺骨を新しいお墓に移動することもできますが、さまざまな事情や考えから散骨を選ばれる方もいます。近年では供養の方法が多様化し、散骨での供養も徐々に増えています。この記事では墓じまいのあとの散骨や注意点について解説します。
<この記事の要点>
・散骨には、粉末状にした遺骨を海に撒く「海洋散骨」と山中で撒く「森林散骨」の2種類がある
・散骨は専門業者を介さなかったり、指定された場所以外で行うと法律に触れるため注意が必要
・散骨を行う際には、分骨や散骨費用について親族間での話し合いが大切
こんな人におすすめ
墓じまいのあとの散骨について知りたい方
墓じまいのあとの散骨の注意点を知りたい方
散骨前に確認しておくべきことを知りたい方
墓じまいのあとの散骨について
墓じまいとはお墓の引越しや撤去のことです。墓じまいをする際は、墓石を撤去するだけでなくお墓にあるご先祖様の遺骨も移動しなければいけません。
遺骨の供養方法の一つとして挙げられるのが「散骨」です。
ここからは、散骨の種類について解説します。
海洋散骨
海洋散骨は、粉末状にした遺骨を海に撒く散骨方法です。指定された海域まで船で移動し散骨をします。そのため、専門の散骨業者に依頼をして指定海域まで移動する必要があります。
海洋散骨には3つの参加形式があります。一家族が船一隻を貸し切って移動する方法、複数の家族と乗り合って散骨に参加する方法、そして散骨にかかわるすべての工程を業者に任せる方法です。
3種類の散骨方法の中から、自分たちに一番合った方法を選びましょう。専門業者を介さずに散骨した場合は罪に問われる可能性があります。条例が制定されている自治体もあるので、事前に確認して正規の方法で散骨を行う必要があります。
森林散骨
森林で散骨を行うことを「森林散骨」と呼びます。粉末状の遺骨を山の中で撒き供養をします。遺骨を海へ還す海洋散骨はイメージしやすいですが、土に遺骨を撒く森林散骨は馴染みのない方も多いかもしれません。しかしながら、どちらも故人を自然に還す散骨方法であることに変わりはありません。
海洋散骨と同様に、指定された場所以外に散骨すると法律に抵触する可能性があります。また、土や葉で撒いた遺骨を隠した場合も埋葬扱いになり、法律違反になる危険があるので注意しましょう。
森林散骨に似ている供養方法に「樹木葬」があります。樹木葬は樹木をお墓に見立てて遺骨を埋葬する方法です。そのため、遺骨を納骨しお参りできる空間が設けられます。森林散骨の場合は、お供え物や線香をあげる場所が別途設けられることはありません。
森林散骨を検討される方は、散骨と埋葬の違いをしっかりと理解することが大切です。
墓じまいのあとの散骨が選択肢に入るのはこんな方
墓じまいを検討する理由は、お墓の継承者がいなかったりお墓を維持できる人が近くに住んでいなかったりとさまざまです。生活様式の変化に伴い、現代では身近な供養方法として知られるようになってきました。しかしながら、遺骨を残すことのできない散骨を行う方はまだあまり多くないようです。
散骨が選択肢に入る方は、以下の通りです。
・墓の管理が難しい方
・自然に還してほしいと遺言がある方
・納骨費用を抑えたい方
・特定の場所に墓を作りたくない方
・お墓などの供養場所を残さない方が楽だと思っている方
このような考えをお持ちの方は、墓じまいのあとの散骨も選択肢に入るでしょう。ここからは散骨のメリットとデメリットを解説します。散骨の特徴を理解して検討するとトラブル回避につながります。
メリット
散骨を行うメリットは、故人が亡くなったあとにお墓の管理をする必要がない点です。お墓を建立したり維持したりすることは、経済的にも体力的にも負担が大きいでしょう。お墓を持つことが難しいと判断した場合は、散骨という方法を選べば納骨費用を抑えることが可能です。
また、「遺骨を自然に還してほしい」という遺言があった場合は故人の意思を尊重できる散骨を選んでもよいでしょう。
デメリット
散骨を選択した場合は遺骨が残りません。そのため、お墓参りをする場所がないことに不安を覚えたり後悔したりしてしまう可能性があります。
散骨は、遺族が気持ちに区切りをつけ故人を供養します。ただし、親族の理解を得られないまま散骨を行った場合はトラブルになる可能性があるので注意が必要です。
一度埋葬をして墓じまいのタイミングで散骨に切り替える方法や、遺骨の一部を散骨して残りを納骨したり自宅供養にしたりする方法もあります。それぞれのメリットとデメリットを理解して、親族と相談しながら納骨方法をきめることをおすすめします。
墓じまいのあとの散骨の注意点
散骨を行うタイミングは、墓じまいを行うときや納骨をするときなど人によってさまざまでしょう。散骨を行うタイミングによって手続きの方法や必要書類が変わる場合があります。
最寄りの自治体や葬儀会社、専門的業者に確認するのが賢明です。
墓じまいのあとに散骨する場合の注意点
お墓を撤去し他の場所に移動することを「墓じまい」、遺骨を移動することを「改葬」と呼びます。散骨もお墓から遺骨を移動させますが、散骨の場合は改葬に当たらないので注意が必要です。
改葬と散骨では必要となる書類も異なります。ここからは墓じまいの注意点について解説します。
許可証も不要の場合がある
散骨は、ほかの場所に遺骨を埋葬し直す通常の改葬には当てはまりません。そのため、墓じまいに必要な書類である「改葬許可証」は必要ないと考える方もいるようです。
改葬許可証は、お墓からお墓に遺骨を移動する場合に必要な書類なので改葬に当てはまらない散骨では用意する必要がありません。発行を依頼しても許可がおりないので、注意しましょう。
ただし、遺骨を分骨する場合や自宅供養を検討している場合は改葬許可証が必要になります。自治体にその旨を説明して、必ず改葬許可証を発行してもらいましょう。
自治体によって異なる対応
墓じまいあとの散骨に関する取り決めが明確ではない自治体もあります。また、散骨の定義は寺院、自治体、墓地の管理者によっても異なる場合があります。手続きが円滑に進まない可能性もあるので留意が必要です。
不安要素を一つずつ確認して、不明点を解消しながら散骨に向けての手続きを行いましょう。
散骨前の確認事項
故人の遺言に従い遺骨を自然に還したいと考えていても、親族間の考え方の違いなどから折り合いがつかない場合もあります。そのような場合は、ほかの選択肢を検討してみましょう。
ここからは散骨前に確認しておくべき項目について解説します。
分骨について
分骨は、手元供養の一つで故人の遺骨を二ヶ所以上に分けて供養することを指します。火葬場で「火葬証明書(分骨用)」という書類を発行してもらうと、遺骨を分けることができます。すでに遺骨をお墓に埋葬している場合は、墓地の管理者に分骨の意思を連絡して証明書を発行してもらいましょう。
分骨を行うことで、故人の遺言や自分たちの希望を叶えられる可能性があります。供養の選択肢が広がることが分骨のメリットです。
ただし、分骨についての考え方は地域や信仰する宗教によって異なる場合があります。遺骨の所有権を持っている親族に承諾を得ることを忘れないようにしましょう。
費用について
墓じまいのあとに散骨をする場合、散骨費用についても確認しておきましょう。お墓を新たに建てるよりは出費を抑えられますが、散骨でも船を借りたり業者に粉骨を依頼したりする費用はかかります。地域によっても価格が変動するので、事前に散骨業者から見積りをとっておきましょう。
また、住んでいる地域の近隣に散骨ができる場所があるかどうかも重要な確認事項です。自治体の条例とあわせて事前に確認することをおすすめします。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
墓じまいのあとの遺骨の供養方法の一つに散骨があります。指定の海や森林に散骨することで、遺骨を自然に還すことができる方法です。散骨の定義は曖昧な部分も多く、市町村によって散骨の条例が異なる可能性があります。
散骨を検討する場合は、まずお墓を管理している親族としっかり話し合いましょう。自治体の条例や、寺院の規定に従うことも大切です。
墓じまいあとの散骨について疑問をお持ちの方は、お気軽に小さなお葬式にご相談ください。
納骨先探しをお手伝いするサービス「OHAKO(おはこ)」では、海洋散骨や樹木葬をはじめ、永代供養などさまざまな納骨先をご提案します。納骨先をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
納骨先探しのお手伝いをするサービス「OHAKO-おはこ-」
・土地、墓石など必要な費用を全て含んだ明瞭価格
・お墓、納骨堂、樹木葬、永代供養、海洋散骨、自宅供養など様々な納骨方法から簡単に比較、検索できる
・全国の霊園、寺院、墓地の豊富な情報を集約
あなたに最適な納骨先が見つかる「OHAKO」 詳しくはこちら
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


包む香典の金額は、故人・遺族との関係の深さ、年齢や社会的な立場で異なります。ホゥ。