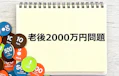昨今、日本人の平均寿命が延びて「人生100年時代」といわれています。長生きするとその分の生活費が増えるため、準備する老後資金も増やす必要があります。
退職金や年金の給付額が減っていることから、老後資金に漠然とした不安を抱えている方も少なくありません。また、人生設計において結婚や出産を予定している場合は、老後資金が必要になる前にまとまったお金が必要になります。
では、老後資金はいくら準備しておけば安心できるのでしょうか。この記事では、老後資金の具体的な金額を準備する方法とあわせて解説します。
<この記事の要点>
・平均寿命を想定して老後資産を算出すると、65歳以上の単身世帯では3,000万円以上の資金が必要
・年金の受給額は「ねんきん定期便」や「年金ネット」で確認できる
・退職金を老後資金に充てたり、財形貯蓄を活用して老後の資産を増やす
こんな人におすすめ
老後資金について知りたい方
老後資金として必要な金額を把握するポイントを知りたい方
老後資金の準備方法を知りたい方
老後資金はいくらあれば安心なのか
退職金減少や年金受給開始年齢の引き上げなどの影響により、老後の生活に不安を覚えて定年後も働き続ける方が増加しています。
定年を迎えたあとも安心して過ごすためには、具体的にいくら必要なのでしょうか。ここからは、必要となる老後資金の目安について解説します。
老後資金は3,000万円以上が目安
平均寿命を想定して総務省のデータを元に必要な老後資産を算出すると、65歳以上の単身世帯では3,000万円以上の資金が必要です。夫婦2人の世帯であれば、6,000万円以上が必要となります。
公的年金だけでは老後資金を補えない可能性が高いので、早めに自身に必要となる資金を把握して準備を始めることをおすすめします。
参考:家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)
生活レベルによって必要額は変わる
老後どのような暮らしをしたいかによって、必要となる老後資金は変化します。老後の収入や支出の状況は世帯ごとで異なるため、自身の生活水準に見合った老後資金の準備が必要です。
給与による収入がない状態で、働いていた時代と同程度の生活水準を維持するためには相応の資金が必要となります。
老後資金として必要な金額を把握するポイント
金融庁によって「老後の30年間で約2,000万円が不足する」と報告された、いわゆる「老後2,000万円問題」が話題になりましたが、自分の老後に実際に必要な資金はどのように把握すればよいのでしょうか。
ここからは、老後資金を把握するためのポイントを3つ紹介します。自分にとって必要な金額を知ることで、老後の人生設計も立てやすくなるでしょう。
年金の受給額を確認する
必要な老後資金を具体的に知るためには、まず年金の受給額を確認します。年金で老後の生活資金をどの程度まかなえるのかを把握しておきましょう。年金の受給額は、「ねんきん定期便」や「年金ネット」で確認できます。
ねんきん定期便とは、年金給付に関する情報をわかりやすく記載した通知書です。年金制度に対する国民の信頼を向上させるため発行されていて、年に1回届きます。
年金ネットは、パソコンやスマートフォンから自身の年金情報が確認できるサービスです。24時間365日閲覧可能で、最新の情報を確認することができます。
何歳まで働くのかを考える
自身が何歳まで働き続けるかによっても必要な老後資金は変化します。令和3年に「高年齢者雇用安定法」が改正されて、70歳までの就業確保が努力義務となり高齢者でも働きやすい世の中になりました。
働く期間を長く設定すれば、準備する老後資金を少なく調整することも可能です。とはいえ、年齢を重ねると働けなくなるリスクも上がるため、退職する時期や就労不能になった場合を考慮した老後資金を設定するようにしましょう。
参考:高年齢者雇用安定法
老後に送りたい生活について考える
必要になる老後資金は、老後にどのような生活を送りたいかによってパターン生活についても考えておくことが必要です。
働いていた時代と比較すると、老後の生活は大きく変わります。生活費だけでなく、健康維持や旅行などの生きがいのために使えるお金も用意する必要があるでしょう。また、人生の最期に向けて「終活」を行う方は、自身のお墓や葬儀資金も同時に用意しておくと安心です。
老後に備えて資金を準備する方法
昨今は銀行の金利が低いため、預貯金のみで数千万円単位の老後資金を準備することは難しいでしょう。給与を貯蓄したり節約に励んだりしたとしても、目標金額まで貯めきれない可能性もあります。
その場合は、貯金方法の見直しや資産運用をすることで、限られた期間でも老後資金を増やせるかもしれません。ここからは、老後に備えて資金を準備する方法を4つ紹介します。
退職金を老後資金に充てる
退職金とは、退職時に雇用主から退職者へ支給される金銭です。退職金は、勤続年数が長いほど給付金額が大きくなるので、老後資金に充てることができます。
しかし、近年は勤続年数よりも、成果によって退職金の給付金額をきめる企業が増加しています。そのため、退職金だけですべての老後資金をまかなうことは難しいのが現状です。
財形貯蓄をする
自身で老後資金の貯蓄をすることが難しい場合は、企業の財形貯蓄を活用しましょう。財形貯蓄とは国が定めた制度の一つで、給与の一部が勤務先と提携している金融機関の口座へ貯蓄されます。毎月一定額が給与から天引きされるので、計画的な貯蓄が可能です。
「一般財形」「住宅財形」「年金財形」という3種類の財形貯蓄制度があり、それぞれ目的が異なります。一般財形は、利用目的に制限はなく自由に貯蓄することが可能です。住宅財形は住宅購入やリフォームの資産形成、年金財形は老後の資産づくりを目的としています。
NISAを利用する
NISAとは、「少額投資非課税制度」という期間が定められた税制優遇制度です。通常は投資で得た収益に対して税金がかかりますが、NISAを活用すればきめられた期間内は一定の金額を非課税で受け取ることができます。
NISAを利用するには、NISA専用の口座を開設する必要があります。口座は20歳以上の人であれば1人1口座のみ開設可能です。NISAには1年で投資できる金額は総額120万円と上限設定があるため、上限の繰り越しや非課税枠の再利用はできません。また、NISAで非課税となる対象はNISA口座を通じて新規購入した金融商品に限られます。そのため、別の口座で購入した商品をNISA口座に移すことはできません。
NISAには、「つみたてNISA」や「ジュニアNISA」などいくつかの種類がありますが、2024年よりNISAの内容が一部変更されます。ジュニアNISAは廃止されることがきまっているため、口座の投資可能期間は2023年までとなっています。2024年以降は新規購入ができない点に注意しましょう。
参考:金融庁『NISAとは?』
iDeCoを利用する
iDeCoとは「個人型確定拠出年金」の通称で、掛金を自身で運用しながら資産を形成する私的年金制度です。定期預金の利息や運用益には税金がかかりますが、iDeCoで運用した場合は運用で得た収益がすべて非課税になります。
iDeCoでは60歳まで掛金を運用し、60歳以降に「年金」「一時金」「年金と一時金の組み合わせ」の3種類から受け取り方を選択します。受け取り方によっては税金がかかる可能性があるので注意しましょう。年金として受け取る場合は「公的年金等控除」が、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」が適用されます。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
自身が求める生活水準にもよりますが、一般的に安心して老後を過ごすためには単身世帯で3,000万円が必要といわれています。何歳まで働くか人生設計を立てたり年金の受給額を確認したりして、自身の老後に必要な資金を把握しておきましょう。
財形貯蓄やNISA、iDeCoなどの制度を活用することで、貯金と退職金を老後資金に充てることができます。早い段階から老後資金について考え貯蓄目標金額を把握して、安心して老後を過ごせるように準備しておきましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


葬儀費用は相続税から控除することが可能です。ホゥ。