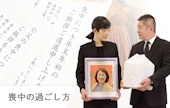喪中にはしてはいけないことがいくつかありますが、浄土真宗には他の宗派と異なる考え方があります。正しい知識を身に付けておかなければ、周りの人に失礼な印象を与えてしまうかもしれません。
この記事では、浄土真宗にはどのような考え方があるのか、喪中はどのように過ごせばよいのかについて解説します。また、一般的に喪中にはどのようなことをしてはいけないのかについても紹介します。
<この記事の要点>
・喪中とは遺族が行動を慎み喪に服す期間のことで、一般的に一周忌までの1年間を指す
・浄土真宗は亡くなった後すぐに仏になると考えられているため、喪中という考え方自体がない
・浄土真宗では、喪中はがきではなく「年賀欠礼はがき」を出す
こんな人におすすめ
浄土真宗で喪中を過ごす人
喪中に関する基礎知識を身につけたい人
マナーを守って喪中を過ごしたい人
喪中とは
「喪中はがき」は聞き馴染みのある言葉でしょう。しかし、「喪中」の正確な意味を知らない方もいるかもしれません。浄土真宗の喪中について知る前に、喪中の意味や喪中の過ごし方について理解しておきましょう。
喪中とは何か
喪中とは、近親者を亡くした遺族が故人の冥福を祈るために、行動を慎み喪に服す期間のことです。喪中の長さは故人との関係によって異なるという考え方もありますが、一般的には一周忌までの1年間とされています。
2親等までの親族が対象となるのが一般的ですが、3親等以上の場合や友人などは、故人との関係によってそれぞれが判断するものであると考えられています。
喪中の過ごし方
喪中には、お祝い事や派手な行動は控えるのがマナーです。静かに生活し、故人を亡くした悲しみを乗り越えるための期間であると考えられています。ただし、あくまでも喪中は目安にしか過ぎないという考え方もあり、喪中の過ごし方が多様化してきているのが最近の状況です。
<関連記事>
【喪中まとめ】喪中とは?喪中の期間や範囲、挨拶状の出し方、喪中の過ごし方などをすべて解説!
喪中にしてはいけないこと
一般的に、喪中にしてはいけないとされていることがいくつかあります。知らずにおこなってしまうとマナー違反になることもあるため、注意が必要です。喪中に避けたほうがよいことを4つ紹介します。
結婚式
喪中には、お祝い事はしてはいけないと考えられています。結婚式を開催する立場であれば避けたほうがよいですが、準備が進んでいる場合などには、両家で相談して行う場合もあるでしょう。
また結婚式に招待された場合には、喪中であることを伝えて欠席するのがマナーです。ただし、出席の返事を伝えた後に喪中になった場合などには、先方に相談してみましょう。
旅行
長期の旅行などのレジャーは、喪中の期間中には避けたほうがよいと考えられています。ただし、気を遣いすぎるあまりにストレスが発生することもあるため、節度を持って楽しむ分には問題ありません。
初詣などの神社参拝
神道においては、穢れとされる死を持ち込んではいけないとされています。そのため、初詣などの神社参拝は避けたほうがよいでしょう。
ただし、喪中であっても忌明けであれば神社に参拝してもよいと考えられています。神社によって考え方が異なりますので、事前に確認しておきましょう。
正月飾り・おせち・年賀状
正月飾りやおせちなどの正月のお祝いは、無事に1年を迎えることができたことを祝うため、喪中には避けたほうがよいと考えられています。
年賀状など、新年の挨拶も控えるのがマナーです。喪中はがきを送付し、喪中であるため年賀状は送れないことを伝えておきましょう。
浄土真宗の喪中とは
浄土真宗には、阿弥陀如来の救いを信じれば、誰でも亡くなったらすぐに極楽浄土に往生して仏になれるという教えがあります。そのため、故人の冥福を祈ったり、成仏を願ったりすることもなく、浄土真宗には喪中という考え方自体がありません。この点が他の仏教宗派とは大きく異なる点です。
浄土真宗の喪中の過ごし方
浄土真宗においては、故人が亡くなってから一周忌を迎えるまでの間、どう過ごせばよいのでしょうか。気をつけなくてもよい点と、気をつけたほうがよい点がありますので理解しておきましょう。
避けるべきことはない
浄土真宗には喪中という考え方がないため、特別に避けるべきことはありません。亡くなった人はすでに極楽浄土に往生して仏になっているため、遺族は普通に生活してよいとされています。結婚式への出席、旅行、正月のお祝いなども問題ありません。
他の宗教や宗派に配慮する
他の仏教宗派では喪中というものがあるため、喪中がないという浄土真宗の考え方を押し付けないように配慮したほうがよいでしょう。
また、浄土真宗としては神社に参拝してもかまいませんが、なかには喪中の期間中に参拝は控えるべきであると考えるところもあります。参拝する前に、神社に確認したほうがよいでしょう。
年賀欠礼はがきを出す
喪中がないため、浄土真宗においては喪中はがきを出す必要はありませんし、年賀状を出してもかまいません。ただし、年賀状の受け手が浄土真宗の門徒ではない場合には、非常識であると思われてしまうこともあります。
浄土真宗の教えに沿った形で受け手にも配慮するためには、喪中はがきではなく、年賀欠礼はがきを出しましょう。「喪中」という言葉を使わずに、「新年のご挨拶を失礼させていただきます」などと記載します。
<関連記事>
浄土真宗が持つ宗派の特徴は?葬儀や焼香のマナーを解説
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
浄土真宗では喪中という考えがないため、特別に避けるべきことはありません。しかし、異なる宗派の方への配慮は忘れないようにしましょう。
喪中でお悩みの方や、葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
また喪中の過ごし方について知りたい方以外にも、お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。