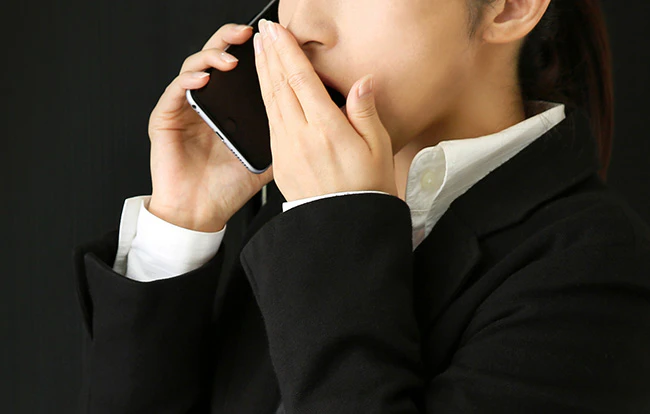夜中に病院から「危篤」の連絡を受けたら、どのように対応すればよいのでしょうか。突然のことでパニックになったり、冷静な判断ができなかったりすることも考えられます。落ち着いて行動するには、もしもの事態を想定した心構えや準備が大切です。
この記事では、夜中に病院から危篤の連絡を受けた場合の対応について詳しく解説します。夜中でも連絡を入れるべき親族や配慮する点、備えておくべきことをまとめました。
<この記事の要点>
・夜中に危篤の連絡を受けたら、気持ちを落ち着かせてから病院に向かう準備をする
・危篤の連絡に備えて、事前に携帯電話や身分証、宿泊セットなどを揃えておく
・危篤の連絡をする範囲は「三親等以内の親族」が基本で、近しい関係の方から順に電話をかける
こんな人におすすめ
夜中に病院から危篤の連絡を受けた場合の対応を知りたい方
夜中でも危篤の連絡を入れるべき親族や配慮する点を知りたい方
危篤の連絡に備えて準備するものを知りたい方
危篤とは?
危篤とは、病気やけがから回復する見込みがなく、命の危機が差し迫っていると医師が判断した状態です。家族が病院から連絡を受けたときにはすでに患者の意識がなく、いつ亡くなってもおかしくない状態に陥っているケースも多いでしょう。
危篤からすぐに亡くなる方もいますが、持ち直すこともあります。ただし、非常に危険な状態であることに変わりはないため、危篤の連絡を受けたら家族はできるだけ早く病院に駆けつけましょう。その際は、万が一の事態を想定して心構えをしておくことが大切です。
<関連記事>
危篤・臨終とは?今後の流れややるべきこととマナーについて
夜中に病院から危篤の連絡を受けた場合
夜中に病院から危篤の連絡を受けると、突然のことに慌ててしまい冷静な判断ができなくなることもあります。落ち着いて病院に駆けつけるためには、気持ちの整理と心構えが重要です。
ここからは、夜中に病院から危篤の連絡を受けた際の対応方法を紹介します。
<関連記事>
危篤と言われたら?慌てないための危篤対応ガイド
自分の気持ちを落ち着かせる
まずは、自分の気持ちを落ち着かせることを意識しましょう。突然の連絡に気が動転して慌てている状態では、運転や準備などに集中できなくなる可能性があります。
危篤になる可能性がある状態の場合は、万が一を想定して心の準備をしておきましょう。亡くなったときにするべきことを把握しておけば、病院から危篤の連絡を受けたときもスムーズに行動できます。ほかの家族が動揺していてもサポートしてあげられるでしょう。
病院へ行く支度をする
連絡を受けて気持ちが落ち着いたら、病院に行く支度をしましょう。必要なものは以下のとおりです。
・携帯電話
・携帯電話の充電器
・財布(現金・クレジットカード・身分証)
・親戚や友人の連絡先を書いたメモ
・メモ帳
・宿泊セット
危篤の連絡に備えて、あらかじめ荷物を準備しておくとよいでしょう。そのまま病院に泊まる可能性も考慮して、簡易的な宿泊セットや着替えも持参すると便利です。ほかにも、親戚や友人の連絡先をメモしておくと素早く危篤を伝えられます。
移動手段は事前に決めておくとよい
夜中に危篤の連絡を受けたときの移動手段を事前に決めておきましょう。主な移動手段は以下のとおりです。
・タクシー
・自家用車
・公共交通機関
タクシーは都心部であれば24時間利用できる会社が多く、自分で運転をしなくていい点がメリットです。自家用車はすぐに出発できますが、焦って運転すると事故のリスクが高まるため注意が必要です。
深夜バスを利用する場合は、運行状況を事前に確認しておくと安心です。ほかにも、友人や家族に送ってもらうなど、さまざまな選択肢からもっとも安全に病院に向かう方法を見つけておきましょう。
家族や親族に連絡する際のポイント
病院から危篤の連絡を受けたら、家族や親族にもその旨を連絡します。しかし「夜中に電話をしてもいいのか」と悩んだり、「連絡すべき親戚の範囲はどこまでか」と迷ったりする方も多くいるでしょう。
ここからは、夜中に家族や親族へ危篤の連絡を入れる際のポイントを解説します。
連絡する範囲は「三親等以内」
危篤の連絡をする範囲は「三親等以内」が一般的です。患者本人の「ひ孫」や「甥・姪」にまで連絡を入れると覚えておきましょう。
近しい関係にある人から順番に連絡をします。三親等に該当しなくても、最期に立ち会ってほしい友人や親戚がいる場合は連絡を入れましょう。人数が多くて連絡するのが大変な場合は、あらかじめ代表者を決めておき、その人からほかの人へ連絡を入れてもらう方法もおすすめです。
患者本人や自身の会社に連絡する場合はメールで一報入れておき、朝になってから電話をかけるとよいでしょう。
<関連記事>
親(親戚)が危篤になったときの会社への対応!連絡方法や休みの取り方とは?
基本は電話連絡で伝える
夜中でも危篤は電話で伝えるのが一般的です。特に、近しい人には早めに連絡をしましょう。メールやメッセージなどの連絡手段は避けるのが賢明です。
電話がつながらず留守電にもならないときは、メールやメッセージにて危篤の状態であることを伝えましょう。その際に、件名に危篤の連絡である旨を明記すると見てもらいやすくなります。
万が一に備えて、一緒に住んでいる家族の連絡先や、固定電話の番号を聞いておくのもおすすめです。
<関連記事>
危篤のメールをもらった時の返信方法&危篤を伝えるメールの送り方まとめ
夜中の連絡には配慮が必要
夜中でも危篤の連絡を入れるのが一般的です。そのため、電話をした際に「夜分遅くに失礼します」と一言詫びる配慮を忘れないようにしましょう。
危篤であることのほかにも、病院の住所や病室の番号など伝える項目は多くあります。そのまま口頭で伝えるよりも文面にしたほうがよいと感じたときは「のちほど詳細をメールで送ります」と伝えましょう。
また、産前産後の方や病気療養中の方など、相手の体調に大きな負荷を与えてしまうと懸念される場合は、すぐに連絡をしないと判断するのも大切です。
危篤になったときに家族ができること
病院から危篤の連絡を受けたとき、自分にできることは何かと考える方も多くいます。病院についたときに、本人の状態を見て冷静さを欠いてしまうこともあるでしょう。
ここからは、大切な方が危篤になったときに家族ができることを紹介します。
そばに寄り添う
病院に到着したら、患者本人の状態に合わせて寄り添ってあげましょう。危篤といってもその状態はさまざまで、意識が朦朧としていたり、一時的に回復して食事を欲したりするケースもあります。
たとえ意識がない状態でも、隣で見守ってあげることが大切です。医師や看護師の許可のもと、手を握ったり体をさすったりしてスキンシップをとってみましょう。
感謝の言葉を伝える
危篤の状態でも声をかけてあげるのは非常に大切です。人は衰弱していくと多くの感覚を失いますが、聴覚は比較的最後まで残っているといわれています。
たとえ意識が朦朧としていて反応がなくても、家族の言葉は届いているかもしれません。大切な方にこれまでの感謝や想いを伝えるようにしましょう。
<関連記事>
危篤状態の方に対する適切な声かけとは?家族への声かけもあわせて解説
家族間で今後について話し合う
今後の治療方針や、万が一に備えた意思決定が必要になるため、家族や親族間で話し合いをしておきましょう。納得のいく答えを出すためにも、しっかりコミュニケーションをとることが大切です。
医師や看護師にも相談して、後悔のない最期に向けて進んでいきましょう。危篤という状況は、家族も不安や緊張を抱きやすく、冷静な判断ができなくなることもあります。必要に応じてほかの家族や親族にサポートをしてもらい、ひとりで抱え込まないようにしましょう。
危篤状態からどのくらいで亡くなる?
危篤の連絡を受けてから亡くなるまで、どのくらいの時間を要するのか気になる方も多いでしょう。
ここからは、危篤状態からどのくらいで亡くなるのか解説します。
危篤から何日生きられるかは人それぞれ
危篤状態から臨終までの時間は正確に判断できず、何日生きられるのかは人によって異なります。危篤と告げられてから数分で亡くなる方もいれば、回復して一時的に安定する「小康状態」になる方もいます。
ただし、危篤と判断された以上、いつ亡くなってもおかしくはありません。危篤の連絡を受けたらすぐに病院に駆けつけて、可能な限り最期までそばにいてあげましょう。
<関連記事>
危篤状態から持ち直すことはあるの?危篤状態のときにしておくべきこと
危篤状態は何日続くのか?身内が危篤になった際の対応法
危篤状態から持ち直す確率は低い
一度危篤状態に陥った場合、持ち直す確率は低いといわれています。前述のとおり小康状態になる方はいても、完全に回復するケースは極めて低いといえるでしょう。
危篤と似た言葉の「重篤」は、生命の危機が迫っていながらも回復する確率がある状態を指します。一方で「危篤」は死が近い状態とされているため、その状況を理解して次のステップを考えましょう。
あらかじめ、医師や看護師に相談して患者の状態を知ることも大切です。疑問や不安があればその都度相談して、病状や亡くなったあとの流れを頭に入れておきましょう。
<関連記事>
重篤とはどんな意味?危篤・重体・重症との違いを解説します
亡くなってから葬儀までの流れ
ここからは、亡くなってから葬儀までの流れを詳しく解説します。万が一のときでも慌てず冷静に対応できるように、事前に死亡後の手続きを把握しておきましょう。
<関連記事>
死亡から葬儀までの流れとは?葬儀後の手続きまでを詳しく解説!
死亡診断書をもらう
医師による死亡確認がおこなわれたあと、死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は医師が患者の死亡を確認したことを証明する書類で、火葬する際に必要なので大切に保管しておきましょう。
また、亡くなった後は看護師によるエンゼルケアが施されます。エンゼルケアとは、故人の遺体をきれいな状態に整えて、感染症を予防する死後処置のことです。傷の処置や着替えなどをしたあと、遺体は病室から一時的に霊安室に移されます。
葬儀社に搬送を依頼する
息を引き取ったあとは、速やかに葬儀社に連絡して搬送を依頼しましょう。病院の霊安室は長時間使用できないため、遺体を移動させる必要があります。
このとき、家族は動揺や悲しみのなかで葬儀社を選定する必要があります。万が一のときでも慌てないように、依頼する葬儀社を決めておくと安心です。事前相談や見積もりを取り寄せて、ある程度目星をつけておくと、スムーズに手配できるでしょう。
依頼したい葬儀社が決まっていない場合は病院が紹介してくれることもありますが、病院紹介の葬儀社は割高なことが多いので注意が必要です。
<関連記事>
葬儀社を手配する際のポイントや選び方を解説!葬儀の費用相場も紹介!
葬儀の打ち合わせをする
故人の搬送が終わったら、葬儀社と葬儀の打ち合わせをします。打ち合わせの内容は以下のとおりです。
・葬儀の日程
・葬儀形式(一般葬・家族葬など)
・式場の決定
・オプションの確認
本人の希望に沿った葬儀にすることも大切ですが、予算に合ったプランを選ぶことも重要です。希望どおりの葬儀にしようとするあまり、費用が高額になってしまうこともあるでしょう。担当者と予算を確認しながら、満足のいく葬儀プランを決めていきましょう。
<関連記事>
葬儀の打ち合わせで決める内容は?形式別の費用や3つのポイントも徹底解説
お通夜・告別式を執りおこなう
一般的にお通夜は亡くなった翌日、または翌々日におこなわれます。ただし、式場や火葬場の空き状況によっては日程が大幅に変わる可能性があります。お通夜・告別式の日程が決まったら、速やかに親族や友人に連絡を入れましょう。小規模の葬儀で参列をお願いしない場合は、その旨を連絡しておきます。
火葬場では医師が発行した死亡診断書が必要です。忘れないように、事前に葬儀担当者に渡しておくのがおすすめです。
<関連記事>
お葬式のタイムスケジュールは?葬儀日程の組み方も解説
まとめ
夜中に危篤の連絡を受けたときは、速やかに病院に向かう必要があります。まずは自分の気持ちを落ち着かせて、慌てないよう心がけることが大切です。心構えができてから準備をはじめ、もっとも安全な交通手段を選んで病院に向かいましょう。
危篤の連絡は、たとえ夜中でも三親等の親族まで電話で伝えるのが一般的です。夜中でも落ち着いて行動できるように、危篤状態に陥った際の連絡方法を覚えておきましょう。
「小さなお葬式」では、危篤の連絡や葬儀に関するお問い合わせを受け付けています。お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は0120-215-618へお電話ください。

葬儀費用は相続税から控除することが可能です。ホゥ。